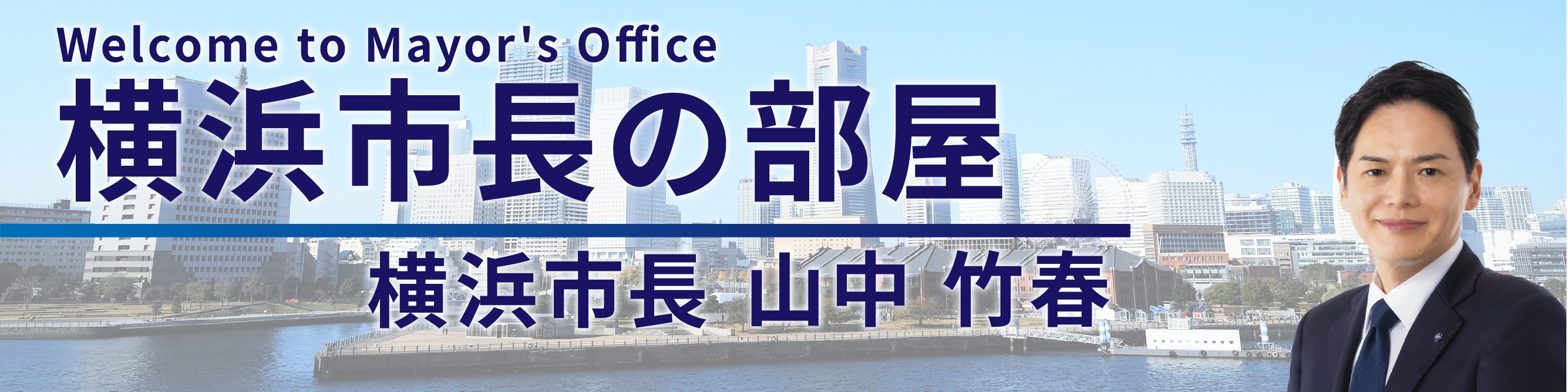ここから本文です。
- 横浜市トップページ
- 市長の部屋 横浜市長山中竹春
- 定例記者会見
- 会見記録
- 2024年度
- 市長定例記者会見(令和7年2月28日)
市長定例記者会見(令和7年2月28日)
最終更新日 2025年3月4日
令和7年2月28日(金曜日)11:00~
報告資料
- 【スライド資料】令和7年度からのシェアサイクル事業者が決定-「横浜モデル」で全国的なシェアサイクルの課題を解決-(PDF:4,012KB)
- 【記者発表】令和7年度からの横浜市全域でのシェアサイクル事業の実施に向けた協働事業の協定を締結
- 【スライド資料】親子でもっと楽しめる野毛山に! 動物園と図書館を一部リニューアルします -のげやまインクルーシブ構想-(PDF:5,695KB)
- 【記者発表】親子でもっと楽しめる野毛山に!動物園と図書館を一部リニューアルします のげやまインクルーシブ構想第1弾
- 【スライド資料】横浜市内でのはしか患者の発生について(PDF:296KB)
会見内容
1.報告
(1)令和7年度からのシェアサイクル事業者が決定
-「横浜モデル」で全国的なシェアサイクルの課題を解決-
※敬称略
政策経営局報道課長 矢野:
はい、それでは定例会見始めます。市長、お願いします。
市長:
はい、本日は3点ご報告事項がございます。まず初めに、シェアサイクルについてのご報告です。令和6年9月から12月末まで実施した公募手続きの結果、ドコモ・バイクシェアさんとOpenStreetさんの共同事業体が選ばれまして、本日協定を締結することになりました。この図が表しているんですが、共同ポート化を実現して、相互乗入の提案がございました。この共同ポート化は全国初の取組となりまして、これで固まりごとに事業者さんがバイクシェアやOpenStreetさん、その他の会社さん、いろいろあると思うんですが、シェアサイクル運行されていたのが、それからそれが相互乗入が可能になることで、市内全域でこのシェアサイクル使った移動が可能になります。これまでも本市は、便利で、手軽で、全域で、多様で、環境に配慮した、そういった理念を掲げて、このシェアサイクルを広げていきたいというふうに考えておりました。今、平均のポート数を1平方キロメートルあたり、4ポートぐらい作っていこうというふうに考えております。今回、公募を行った上で事業者さんに提案を求めた、主なポイント4つご紹介いたします。まず、本市として最も重要だったのが、交通空白地にポートを配置していただくことであります。と申しますのは、事業者さんから見ますと、どうしても便利な場所にポートを配置するインセンティブっていうのがどうしてもあるんだと思うんですが、本市としては面的に広げていきたい、そういう思いがございました。これは昨年の3月末時点でのポートのカバー図、カバーしている図なんですけども、これ横浜市の西部の一部だけをお見せしているんですが、例えば、この水色の部分が交通空白地帯でありまして、こういったところも含めてシェアサイクルが利用できるようになると、市民の皆様の移動しやすい環境の実現に一歩近づくだろうというふうに考えまして、この交通空白地へのポートの配置というものは重視いたしました。一方で、いわゆる民有地ですね、民有地にポートをどう増やしていくのかという観点も、今回の公募で求めました。シェアサイクルポートを、駐輪場の附置義務制度の中でこれまでシェアサイクルポートを含められなかったんですが、これを台数に含められるように運用基準を見直しまして、民有地におけるポートの設置というものを広げていきたいというふうに考えています。例えば、駅前、駅の近くですと場所がない、一方でニーズはあります。利用者のニーズはあります。どこを活用するのか、公有地があればいいんですけれども、ない場合が多い。民有地を活用する、活用どうすればいいか、そういった観点で、民有地ポートの整備を加速していきたい、推進していきたいというふうに考えております。3点目は、これは共同ポート化によって、相互乗入ができるようにしたほうが市民の皆様にとっては便利だろうという観点は求めました。そして、4点目は、脱炭素への環境負荷の少ない乗り物ですから、更にシェアサイクルを推進していくことによって、脱炭素化にも貢献すると思うんですが、より一層、環境に配慮した取組っていうものを提案の中で求めた次第であります。以上4点を中心に事業者提案を行ったところ、今回こちらにいらっしゃる2社さんの共同事業体、ドコモ・バイクシェアさんとOpenStreetさんの共同事業体の提案が採択されたとこういう経緯であります。本日は、ドコモ・バイクシェアの代表取締役社長の武岡様、そして、OpenStreetさんの代表取締役社長の工藤さんにお越しをいただいております。それでは、武岡さん、工藤さん、よろしくお願い申し上げます。
株式会社ドコモ・バイクシェア 武岡 代表取締役社長:
ドコモ・バイクシェア代表取締役の武岡雅則です。本日はよろしくお願いします。次のページお願いいたします。今回、ドコモ・バイクシェアとOpenStreetの共同事業体という形での公募に対しての応札、ご提案をさせていただきました。ドコモ・バイクシェアは2011年からシェアサイクル事業を開始しておりまして、その一番最初の場所がまさにこの横浜市になります。我々の創業の地でございます。そこから先ほど申しましたような、その都心のところ、中核の部分を中心に我々は事業を展開してまいりました。高利用、高コストの運用をしっかりやっていく、そのようなモデルで展開してまいりました。OpenStreetさんは2016年、遅れた形でスタートされました。OpenStreetさん、プラットフォーマーっていう形で水平分業、パートナーさんと一緒にビジネスを広げる、そのようなモデルで展開されましたので、主に郊外のほうから幅広く面的に広げるような、そのような展開をされてまいりました。日本、シェアサイクルを行ってる事業者複数ありますが、我々にしてはその中でもトップを走ってる2社でございます。次のページお願いします。その展開の戦略の違い、その結果から、主要23区、横浜市、大阪を例に示しておりますが、このように都心のところはドコモ・バイクシェアのポートの数・密度・利用が多く、郊外のところはOpenStreetさん、サービス名 HELLO CYCLINGが非常に多い形での結果としての連携、分担になっております。そして、この横浜市においては現在、都心部と中部のところはドコモ・バイクシェアが市と協定を結び、展開させていただいております。そして、北部と南部はOpenStreetさんが協定を結び、展開させていただいております。結果としてですけども、バイクシェアのユーザーは都心と中部のところでご利用できますが、北部・南部では利用ができない。HELLO CYCLINGのお客様に関して、北部・南部は利用できますが、特に都心のところにはなかなか行きづらいという結果が出ておりました。先ほど山中市長からお話しがありましたように、次の横浜市のシェアサイクルは市民に、横浜市の全てのエリアで自由にいつでも乗りたい時に使えて、返したい場所で返せる、そのような大きな方針が示されましたので、これを我々でどのようにお応えしていくかということを考えました。その際に、我々各社でも取り組めば頑張っていくっていうチャレンジもあるんですが、何よりもコストもあるんですけど、何よりこの時間がとてもかかってしまいますので、ここの部分も含めて早く市の期待に応えるためにはどのような手法が良いのかということを考えました。その中で、競合他社ですので、普段はなかなかこういうふうな、一緒に連携しましょうっていう話って起きないんですが、今回の大きな方針の下でOpenStreetさん、工藤社長とも直接お話をし、今回ポートを共同化しようと、ポートの共同化だけではなくて、運用、オペレーション、バッテリー交換、再配置というオペレーションも含めて連携しようという答えに至りました。その形での今回、提案をさせていただき、無事採択していただいた運びになりました。次のページお願い致します。共同ポートの内容ですけども、アプリでいくと例えば、これドコモ・バイクシェアのアプリのイメージですけども、普段バイクシェアのポートだけがピンとして表示されておりますが、ここにこれから共同ポートとして対象にしたポートが同じようにピンとして現れる形になります。当然、現地で行くとHELLO CYCLINGの看板が置いてる形になりますので、何らかの識別ができるような、そういう工夫はしてまいりますが、このようにお互いのポートを、お互いの利用者、ユーザーが使えるような、そういう形にシステム的にも連携をして、これをリアルタイムでポート管理、台数の管理、残りの駐輪可能な台数の管理ってのを進めていく形でやっております。システム開発も伴いますし、オペレーションの整理、非常にデリケートな部分でございますので、令和7年度の前半、夏の時期にはスタートできるような形で、今、鋭意準備を進めているところでございます。
OpenStreet株式会社 工藤 代表取締役 CEO:
ではここからは私、OpenStreet代表取締役の工藤からご説明させていただきます。よろしくお願い致します。呉越同舟という言葉がありますが、普段はドコモ・バイクシェアさん、そしてソフトバンクグループであるOpenStreetは競合としてしのぎを削ってきました。ただ、今回の横浜市さんの取組で、横浜市という同じ船に乗ることができて、先ほど武岡社長からお話があったように、市民の方の目線で見た時に最適なサービスを一緒につけるっていうのを大変嬉しく思っております。では、スライドを進めていただけますでしょうか、はい。今回、先ほど市長からお話がありましたような、交通結節点と交通空白地を連携させて、この交通不便地域を少しでも便利にしていこうというところを取り組んでまいります。先ほどドコモ様と私たち、競合同士で、同じ事業者同士が組んでるという話をしましたが、私達は更にバス会社さん、そして鉄道会社さん、すなわち同じ交通領域を行ってる会社さんとも連携をしております。ですので、バスや鉄道を置き換えるのではなく、バスや鉄道と連携をすることで、そのバス停がカバーしきれないエリアもカバーしていく、そういった考え方で今回ポートを整理してまいります。また、脱炭素の取組という話もありましたが、自転車という移動手段がエコであることは事実です。ただ、一部電動アシスト自転車として電気を使いますので、その電力そのものも脱酸素の取組をするべきと考えておりますので、今回横浜市内で設置しているメンテナンス拠点には、再生可能エネルギー由来の電力を採用しています。やっぱり、自転車のバッテリーに充電する電力も脱炭素な手段、エコな手段で発電されたものを使うという考え方になっております。では次のスライドお願いします。また、移動のサービスですので、交通の安全対策というところも、常に考える必要があります。ただ、これは一つ一つの施策で即効性の効果が出るものでありませんので、サイクルスクールや、ヘルメットの所有を普及させるような取組、こういった取組を継続的に行っていくこと、またそれを民間事業者だけではなく、横浜市様とご一緒に行うことで、市民の方にこういう対策が届いていくような取組をしていきたい、そのように考えております。はい、私からのご説明は以上となります。
市長:
はい。武岡様、工藤様、ご説明ありがとうございました。全国でシェアサイクルを導入している都市におきましては、本市もこれまでそうだったんですが、シェアサイクル事業者ごとにエリアが形成されて、事業者が異なると、そこに分断ではないですけれども、当然エリア間の移動っていうのが同じ自転車でできない。それから、ポート整備というのもなかなか進まないっていうような課題が顕在化してますし、本市も抱えておりました。こうした課題に対する解決策として、今4つ丸をお示ししております。公民連携で、こういった4つの取組を1つのパッケージとして進めていきたい。1つ目が、市内全域での公有地ポートの整備であります。ここは横浜市として、整備を加速して参ります。18区の区役所とか、歩道とか、そういったところで設置が可能なところには、順次ボートを増やしていきたいというふうに思います。そして、2番目の丸が、半分青、半分赤になっていますが、これは我々と事業者さんの協働で取り組んでいくという意味であります。駐輪場の附置義務台数にシェアサイクルポートを含められるようにしたということであります。そして、3つ目の丸がデータの利活用でよりグレードアップを目指していこうと。具体的には、これまでも移動データの分析・活用っていうのは進めてきたんですが、これをより一層強化することで、ポート配置の最適化を図っていきたいというふうに思っております。4つ目が、共同ポートによる相互乗入で、こちらに関してはこれまで説明があったとおりでございます。こういった4つの視点を持つ、横浜モデルで全国的なシェアサイクルの課題の解決に結びつけていきたいというふうに考えております。最後のスライドですが、今後全国に先駆けて課題解決に向けた横浜モデルで事業を推進して、シェアサイクルの更なる利用の促進を図ってまいりたいと思います。こちらに関する説明は以上となります。
政策経営局報道課長 矢野:
はい。それではこの件について、ご質問をお受けします。いつものお願いになりますが、ご発言の際は、マイクのスイッチのご確認をお願いいたします。では、まず幹事社からお願いします。
ラジオ日本 本田:
幹事社、ラジオ日本本田です。よろしくお願いします。4月からスタートということなんですけれども、このシェアサイクル事業における期待でありますとか、改めてお願いします。
市長:
はい。横浜市として移動しやすい街を目指しております。このたび、市として利便性が高いかつ環境に優しい、そういった移動手段としてシェアサイクルを求めました。利便性が高く、環境に優しいシェアサイクル、これを求めた結果、全国で初めて共同ポート化が実現することになりました。是非、シェアサイクルを面的に拡大し、またバッテリーも先ほど説明ございましたとおり、再生可能エネルギーを使うなどの工夫もしていただけるとのことであります。是非、より環境に配慮した移動手段の拡大を目指していきたいというふうに思います。
ラジオ日本 本田:
このシェアサイクル事業なんですけど、観光地の活性化であったりですとか、日常使いにおいてもかなり魅力を発揮するんじゃないかなというふうに思うんですけども、その点どういうユーザーにより、コミットメントしていきたいというか、その辺お聞かせください。
市長:
質問ありがとうございます。海に近いエリア、臨海部におきましてシェアサイクル見かけることは多いと思うんです。観光に来られた方の移動手段として、あるいは市民の皆様が臨海部で来られた時の移動手段として活用は進んできたというふうに思います。この活用をもっと進めてまいります。それからあとは日常使いとして、日常の移動手段として、このシェアサイクルを使ってもらえるようにしていくことです。そのためには交通空白地をはじめ、まだまだ市の中でポートが足りてないところがありますので、1平方キロメートルあたり4ポートというKPIに向かってこれから進めていければというふうに思っています。
ラジオ日本 本田:
ありがとうございます。民間と自治体がレンタサイクルとして、組むのは初めてっていうふうに伺ったんですけども、どうでしょうか、この横浜市のモデルケースとして、今後どういった成功を、築いていって地方のほうにも普及していく。
市長:
そうですね。シェアサイクルは全国的にも都市部中心に広がっているというふうに思います。ただ一方で様々な課題があるのも事実であります。今回横浜市として大方針を打ち出したことで共同事業体が応募され、そして共同ポート化が実現しました。是非市としてこうしたいんだという方針を出すことで、民間企業さんの意欲っていうものを引き出していきたいというふうに思っています。
ラジオ日本 本田:
ありがとうございます。すみません。ドコモ・バイクシェアの武岡様にお聞きしたいんですけれども、横浜市ではこういった取組を展開されていくっていうことなんですけれども、どのような思いからこの展開されていこうと思ったかお聞きしたいです。
株式会社ドコモ・バイクシェア 武岡 代表取締役社長:
はい、ご質問ありがとうございます。先ほど申しましたようには横浜市は我々事業の創業の地でもございますので、非常に思い入れが強いところでございます。とはいえど、やっぱり臨海部のところを中心に展開してきたということもあり、市民の方に日常的な使う部分ではまだまだ力が及んでないなと、そんなところも痛感しております。この中で後は日本全国の中でもやはり横浜市っていうのは居住・ビジネス・観光全てにおいても屈指の大都市になりますので、ここのところでとしっかり、より市民の方、外からいらっしゃった方もそうですけど、市民の方に本当にこの環境負荷の低いシェアサイクル、より広げていくっていうとこに尽力してまいりたいと思いますし、先ほど工藤社長から呉越同舟という言葉ありましたけども、確かに場所によっては呉越のところもありますが、しっかり今回手を取り合うことで、先ほどの何よりもスピードですね。短い時間でこの市民の方、皆さんに便利と思っていただける、そんな1交通手段になれるよう努力してまいりたいと思ってます。
ラジオ日本 本田:
もう1つ、ご質問あるんですけれども、この横浜市とのモデルを通じまして、ほかの自治体への展開というのは現時点どの辺りまでお考えでしょうか。
株式会社ドコモ・バイクシェア 武岡 代表取締役社長:
まずはこの横浜モデルのところで成果を出して明らかな変化を生み出すことが非常に重要かと思ってます。今回横浜市さんから、自治体としても本当にかなり踏み込んで、もう既に変革を始められてますし、これ横浜モデルって呼んでいただいたことはすごい我々事業者からすると、もう感動に値するぐらい素晴らしいことだと思ってまして。というのは、いかに事業者が努力しようが、ポートを増やして利便性を増すってことはできましても、特にハードの面ですね。道路の通行空間を整備したりとか、さっきの付置義務緩和もそうですし、公有地を筆頭に、いかにポートを設置しやすい環境、条例の解釈、整理をしていただくかはもうこれ自治体さんしかできないことになりますので、このハードの面とソフトの面が両方手を取って、しかもこの4月からスピード感持って変えていきましょうという宣言。これは非常に力強いものになりますので、これで明らかな成果が出てくると、他の自治体に対しても我々も説明しやすいですし。はい、参考に、まさにこれが日本の推進していくためのモデルだということでもお話しやすいかなと思ってます。期待しております。
ラジオ日本 本田:
ありがとうございます。OpenStreetの工藤様にも同じ質問になっていくんですけれども、まず、やはりこう横浜市でなぜこの取組を展開していこうと思われたかお聞かせください。
OpenStreet株式会社 工藤 代表取締役 CEO:
はい、ありがとうございます。横浜市は交通の課題、利便性という面で、かなりあらゆる要素がある街だと思っています。中心市街地や人口密集地への課題がありますし、少し住宅地のほうに行きますと、坂が多い地域であったり、少し古くなっている団地は局所的な高齢化が進んでしまっていたり、そういった日本全国にある課題を網羅的に内包している都市だと思います。ですのでこの横浜において、シェアサイクルがしっかりとしたインフラとして定着することができれば、それは日本全国の交通課題解決の基準と言いますか、見本になれるんじゃないか。そういった面で横浜市で展開する価値があると考えております。
ラジオ日本 本田:
最後になりますけども、横浜ではモデルを通じてほかの自治体への展開というのは現時点でその辺りまでお考えでしょうか。
OpenStreet株式会社 工藤 代表取締役 CEO:
ありがとうございます。基本的にお互いに話し合ってですね、考え方は完全に共通です。まず横浜で成果を出し、それを展開をしていきたい。ただ利用者の方からは横浜でやるということを発表したものに対して自分の地域でもいつ始まるんだというようなコメントは結構 SNSで見かけましたので、そういった全国の利用者の方の期待にはいずれ応えていきたいと考えております。
ラジオ日本 本田:
ありがとうございました。
政策経営局報道課長 矢野:
それでは各社いかがでしょうか。東京さん。
東京新聞 神谷:
東京新聞の神谷です。具体的に共同ポート化が始めるのは夏という表現でおっしゃっていましたけど。
株式会社ドコモ・バイクシェア 武岡 代表取締役社長:
先ほど申しましたとおり、開発であったりとか、オペレーションの整理っていうのを今鋭意やってるところになりまして、なんで具体的にもうこの日付ってとこまでまだ決定してないっていうのが事実になります。ただ資料の中では来年度、令和7年度の前半と書いてますが、夏にはきちんとご提供してスタートしていく。横浜市の全面的なバックアップがございますので、公有地のところはもう一気に展開できるんだろうと思ってます。民有地、地権者さんとポートをお借りしてる地権者さんと1ポート1ポート契約の交渉、調整をして契約変更して、ようやく例えばバイクシェアで、バイクシェア以外の自転車も停めていいですかっていう整理が進んできますので、そういう意味だと民地のほうはしっかりやりながらもスピード感を持って広げていきたいというふうに考えております。
東京新聞 神谷:
そうしますと何月何日から一斉に、という感じではないということですか。
株式会社ドコモ・バイクシェア 武岡 代表取締役社長:
はい、そうですね。展開としてはまず都心のところで、公有地は全面バックアップいただいてますので、都心のところでスタート、夏にスタートさせ、できるだけ速やかに早い段階で遅くとも年度内にはかなりの規模で全域に展開という形を進めてまいりたいと思ってます。
東京新聞 神谷:
なるほど。現在、今年度までは、この3月まではそれぞれ社会実験というスキームで、展開されてると思うんですけど、そうするとそれが4月以降も、結局そのままサービスとしてはずっと継続して使えて、順次その共同ポート化で新しいポート増えたりしていくって、そういうイメージでしょうか。
株式会社ドコモ・バイクシェア 武岡 代表取締役社長:
そうですね。4月からは共同事業体として採択いただいたという、スキームの変更はございますが、サービス、お客様の見えとしてはバイクシェアのサービスとHELLO CYCINGのサービスがそれぞれ存在していて、あるタイミングで融合して相手のポートにもお互い停められるようになるのが広がっていくというふうな見え方になると思います。
東京新聞 神谷:
なんでサービス、利用者目線としては、ずっとそのままサービスが続いていて、で、この夏には都心部から共同で。年度内にはその全域でどっちも自由に使えるみたいなのができる、できていく。年度内っていうような、そういうイメージでよろしいですか。
株式会社ドコモ・バイクシェア 武岡 代表取締役社長:
そうですね、特に民地のところは地権者さんの思い、考えもあって最後まで了承を得られないポートもあるかと思いますので、完遂はできないと思いますが、ただスピード感としては、年度内にはかなりの規模に広げていきたいというふうに考えております。
東京新聞 神谷:
現状社会実験のスキームで使ってるものは基本そのまま使えて、それでプラスで共同の、そこが共同化したり、あるいは新しいポートが増えたりってそういうイメージですかね。
株式会社ドコモ・バイクシェア 武岡 代表取締役社長:
いや、既存で持っている、バイクシェアが既に持ってるポートで、HELLO CYCINGさんはステーションって呼んでますけども、持ってるステーションのところは地権者さんにご説明をして、自社と違う自転車が停まっても良いですかっていう契約変更が必要になります。なので既存のポートの変更対象化するっていうのに時間がかかると考えております。で、逆にこれから新規に開拓するところは最初から、もう共同ポート前提でバイクシェアとHELLO CYCINGの自転車それぞれが停まりますよっていうご提案で、契約を結んでいきますので、新規ポートは最初から対象になると考えております。
東京新聞 神谷:
どちらかというと今まで既存のところが共同になるのに時間がかかる場所があるかもしれない。
株式会社ドコモ・バイクシェア 武岡 代表取締役社長:
おっしゃるとおりです。
東京新聞 神谷:
すみません、数として、すみません、どれぐらいっていうのは出てましたっけ。ポート数っていうのは。
政策経営局報道課長 矢野:
所管局からお答えします。
道路局道路政策担当理事 栗本:
道路局道路政策担当理事の栗本と申します。現時点でですね、令和7年1月時点の数でございますが、公有地ポートにつきましては現在320あります。で、民有地ポートには408あるということで、こちらは順次共同ポート化になってるんで、先ほどおしゃってた公有地ポート320個については今年度中に全て共同ポート化したいっていうふうに目指しております。
東京新聞 神谷:
令和7年度中に公有地の320は共同ポート化するってことですか。
政策経営局報道課長 矢野:
補足できますか。
道路局道路政策推進部長 村田:
道路局道路政策推進部長の村田と申します。ちょっと補足をさせていただきます。公有地ポートですね。先ほど栗本がお話ししたとおり、順次数増やしておるんですけども、いわゆるそのサービス面の共同ポート化というのは、やはり事業者様のほうのシステム開発ありますので、今年度、6年度ではなく、7年度の早期からということで、ご理解いただければと思います。
東京新聞 神谷:
7年度に、公有地は公有なので、4月、そのシステム的な準備が整い次第、夏から始められるところに入るわけですか。
株式会社ドコモ・バイクシェア 武岡 代表取締役社長:
すみません、ちょっと立場によって整理してる部分が違うので、市の立場としては公有地については、順次、安全性も確認しながら、両者で停めていいよという整理、今まさにしていただいてるので、もう進んで、了承を出したと承諾を出したというポートも増えてるというような市の認識だと思います。ただ実際に展開できるのはシステムの部分の運用が必要になりますので、システム開発を以って、先ほどの夏のタイミングから、公有地は先行して、先行していうというか、一気に全面的に。民地のとこは順次っていう形で夏以降に実際利用者の目線で行くと始まるということになります。
東京新聞 神谷:
なるほど。はい、分かりました。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。神奈川新聞さん。
神奈川新聞 武田:
神奈川新聞の武田です。ドコモさんとOpenStreetさんに伺いたいんですが、まず1点目が料金なんですが、これ共通化される形になるんでしょうか。
株式会社ドコモ・バイクシェア 武岡 代表取締役社長:
はい、料金のところはそれぞれの利用者、お客様に対してそれぞれの会社が提供していく、またアプリも残念ながら統一ってとこまではなりませんので、それぞれのサービスに契約していただいて、ただ利用できるポートが相手側のポートも対象になっていくという形になりますので、料金体系のところの統一ってのは予定はしてございません。ただ、その中で、一物二価みたいな形にはならないように、ある程度の整理、棲み分けみたいなのが必要かなとっていうのは我々としても宿題に思ってますし、市民からも全く同じ価値であれば、安いほうが良いっていうふうになると思いますので、そういうところは意識しております。
神奈川新聞 武田:
それは乗る場所では料金を統一するっていうようなイメージなるんですかね。
株式会社ドコモ・バイクシェア 武岡 代表取締役社長:
いや、そういう意味ですと現在提供してる料金体系がそのまま継続していく。まず当面はそのまま継続していくというご理解をいただければと思います。
神奈川新聞 武田:
ありがとうございました。もう1点今おっしゃっていただいたアプリのルールなんですが、例えば今ドコモさんのアプリで行くと、これでOpenStreetさんも使えるようになるのか、あるいは2個ダウンロードしなきゃいけないのかっていうのは。
株式会社ドコモ・バイクシェア 武岡 代表取締役社長:
バイクシェアのアプリで使えるのはバイクシェアの自転車だけになります。赤い自転車だけになります。HELLO CYCLINGさんのアプリ会員さんが利用できるのはハローさんの白い自転車だけになります。共通して使えるのがポートが共通で貸出返却の対象になってるということになります。
神奈川新聞 武田:
分かりました。ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
事業の詳細は所管課残しますので、後ほどご確認いただければと思いますが、その他ご質問ありますでしょうか。産経さんから。
産経新聞 橋本:
産経新聞の橋本です。よろしくお願いします。これ、公募っていうことなんですけれども、ほかの事業体とか、会社から公募ってあったんですか。
道路局道路政策担当理事 栗本:
次点でですね、もう1者ございまして、共同事業体で1者、それからもう1者、申し込んだということで、結果として今、2社が決まったということです。
産経新聞 橋本:
あと、ポート数が平均ポート密度が約4ポート、1平方キロメートル当たりということなんですけども、先ほどの話ですと今、合わせて728ですか。この平均ポート密度を達成するにはあと何ポート増やさなければいけないとかあるんですか。
道路局道路政策担当理事 栗本:
ご質問ありがとうございます。今、現時点、7年1月時点でポート密度的には2.16でございます。こちらを目標としては、平均4ポートと言ってるんですけど、地域ごとにですね、目標数値を変えておりまして、例えば都心部だと平均15を目指したいと。郊外部だと、それより低いと、それを平均にしますので、一概に今いくつという数字はなくてですね、平均すると4ポートになるということで、今、計画しているということでございます。
産経新聞 橋本:
その平均4ポートにするには、あといくつ必要なんですか。
道路局道路政策担当理事 栗本:
概算ですけど、大体あと倍。
市長:
倍じゃないですか。2点いくつっておっしゃってたので。
道路局道路政策担当理事 栗本:
700ぐらいを目標にしてる。
産経新聞 橋本:
それは、どちらのポートが増えるっていうのは、どういうふうになっていくんですか。
OpenStreet株式会社 工藤 代表取締役 CEO:
ありがとうございます。あの今時点で展開してる地域との親和性もありますので、少し分担をしながらお互いを増やしやすい場所を民間は開拓していく。で、公用地に関しては横浜市さんと連携しながらやっていきますので、ここはこっちが担当というふうに分けてやっていく段取りになっています。
産経新聞 橋本:
そうすると自転車数というのも増えるんですかね。
OpenStreet株式会社 工藤 代表取締役 CEO:
そうですね。ポートの数が増えるごとに投入できる自転車の数も増えていきますので、市民の方に使っていただく台数も増加していく予定です。
産経新聞 橋本:
今現在、何台稼働してて、この目標を達成するにはあと何台必要だっていう数字があれば教えてほしいんですけど。
OpenStreet株式会社 工藤 代表取締役 CEO:
ありがとうございます。私たちHELLO CYCLINGのほうは、他の市とも自転車乗り入れしますので、常に横浜市に何台あるっていう状態ではありません。ただ大体ステーションに停められる数の半分ぐらいの車体がありますので、今、僕らは約500箇所あって、大体2,000台から2,500台ぐらいが、今、HELLO CYCLINGの車体は横浜市内を走っています。で、これが先ほど2倍ということであれば、5,000台から6,000台ぐらいの車体を、私たちOpenStreetは横浜市内で稼働させるというところが目標に近い状況かと思います。ドコモさんは少し、ロジック変わりますね。
株式会社ドコモ・バイクシェア 武岡 代表取締役社長:
ドコモ・バイクシェアの場合は、エリアを切ってますので、横浜市は横浜市で展開しておりますので、今、概算ですと1,500台ぐらいがバイクシェアの規模になります。で、先ほど工藤社長が申しましたように、ポートが増えると収容力が増えますので、まあ適切な台数を増車していこうという形で考えております。
産経新聞 橋本:
分かりました。先ほど武岡社長さんのほうからですね、道路の通行空間の整備は自治体にしかできないっていうところで、横浜市に対する期待っていうところが話として出てきましたけど、これ、その道路の通行空間の整備とか、そのインフラ整備については、何かプランなり、お考えがおありでしょうか。
市長:
まず、これからニーズを調べてからでしょうね。もう上がってきてるニーズ、地域の住民の方とか、そういった地域から上がってきてるニーズもありますけれども、地域ごとにきめ細やかな対応が必要になろうかと思いますので、ニーズに寄り添って対応していきたいというふうに思っています。
産経新聞 橋本:
分かりました。ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他、いかがでしょう。朝日さん。
朝日新聞 小林:
朝日新聞の小林です。先ほど共同ポートの数、ありましたけれども、今、横浜市内18区で1つもポートがないところというのは存在するんでしょうか。
市長:
区の中で。
朝日新聞 小林:
区の中で。なので、何区はないとかってありますか。
市長:
ないですね。
朝日新聞 小林:
全区。あと、先ほど18区役所にポート整備ということなんですけど、区役所でポートを整備されているところと、されてないところがあるのかなという理解ですが、どうでしょうか。
道路局道路政策担当理事 栗本:
ありがとうございます。現在ですね、12の区役所で整備されてるんですが、今年度、4月末。ごめんなさい、4月から本格実施なんですけど、そこまでに18区全てに設置できるように、今調整をしているところでございます。
朝日新聞 小林:
で、4月からは18区全てで利用できるんですね。
市長:
区役所は。
朝日新聞 小林:
区役所は、ということですね。分かりました。あと、最後に、1点。先ほどアプリは別々のものを使うというふうにおっしゃっていましたが、まあ台数のポートも増えると、恐らく今まで使ってなかった方に使っていただくということも大事になってくるかなと思います。そこで市は何かこう、アプリを利用しやすいようにしたりですとか、その利用の仕方、PRみたいなところで考えていることがありましたら教えてください。
市長:
私の、あ、いいですか。
道路局道路政策担当理事 栗本:
ありがとうございます。今も、実証実験の時もやってるんですけど、広報については横浜市独自の、横浜市、広報とかありますので、そちらにPRをしていったりですね、連携してですね、今、イベント等も考えておりますので、そういったとこで利用しやすい、今、アプリこういう形になります、というのはPRをしていきたいというふうに考えております。
市長:
アプリに関してはすごく重要なところだと思うんですよね。やっぱり、そのバイク、自転車と市民の皆様のインターフェースになります。それが一気に何もかもは無理なので、今は2社独立で、今、運行してるわけなんですけれども、今後、そのアプリをどう市民の皆様の、ユーザー目線、利便性に寄せていくのかっていうところをしっかりと検討していかないといけないというふうに思っております。
政策経営局報道課長 矢野:
その他、よろしいでしょうか。それではこの件の質疑は以上となります。このままフォトセッションに移ります。どうぞ、前にお越しください。
政策経営局報道課長 矢野:
ありがとうございました。事務局、入れ替わりますので、少々お待ちください。
(2)親子でもっと楽しめる野毛山に!動物園と図書館を一部リニューアルします
-のげやまインクルーシブ構想-
政策経営局報道課長 矢野:
それでは続けて市長、お願いします。
市長:
はい、2点目は、のげやまインクルーシブ構想に関するお話です。のげやまインクルーシブ構想の中で、野毛山動物園、中央図書館、そして多目的なスペース、いろいろ、有機的に連動させて、インクルーシブなエリアとして、作っていこうということは、既にお伝えしているとおりであります。で、その中で野毛山動物園と図書館の改修の、それぞれの一部がですね、完了いたしますのでご報告をいたします。まず、のげやまインクルーシブ構想は既にお伝えしてるとおりですので割愛します。で、まず野毛山動物園のリニューアルは、主に3つに分かれておりまして、エントランスとズーペリエンタ!センター、そして、ふれあいパーク、絵本に出てくる動物たちのゾーン。まず、この2のふれあいパークゾーンに関する改修がもう終わります、というご報告です。ふれあいパークに関してはなかよし広場とか、屋内休憩棟とか、トイレ棟とか、そういったところをこの1年で改修したところであります。こちらがですね、外観で、これ今リニューアル前、現状ですね。現状で、これが今、リニューアル後で、こういったイメージであります。これ外観で、こちらが内観であります。市民の皆様が、快適に過ごせるように、特に親子連れが多いですから、親子連れが使いやすく、そして子どもが楽しくなる、そういったデザインを念頭に整備を進めてまいりました。こちら、なかよし広場でありまして、あと休憩棟に関しても今、リニューアル前ではかなりもう築年数が経っていたんですが、今回、リニューアルをいたしまして、この中には冷暖房もですね、完備できるようにいたしまして、今はそういったオープンスペースだったんですけれども、こちら屋内型の休憩棟にいたしまして、こちらで、飲み物等で休めるような環境を作っていきたいなというふうに思っています。こちら外観で、こちらが内観であります。 のげやま図書館、中央図書館に、今の野毛山の、子ども図書館を作ろうということを計画しております。まず喫茶室を全面的に改修いたしましておやこフロアを新設いたします。こちらが内観であります。もう、ほぼほぼ改修が終わりかけて、あと1か月ぐらいあれば改修が終わるというふうに聞いております。改修が終わっても、ちょっと細かい詰めがあるかと思いますので、その後に、市民の皆様方にオープンにする予定であります。基本的には、親子がゆっくり休める、そして楽しめる、喋ったりもできる。そういったスペースで作ってまいりました。また、のげやまの子ども図書館につきましては、こういったAIを活用した絵本の推薦システムを新たに導入いたしまして、絵本探しもデジタルでできるようにしたいというふうに思っております。今後の展開なんですけれども、それぞれ今、動物園では休憩棟、それから図書館のほうで喫茶室の後におやこフロアを、もうほぼほぼ完了いたしますというご報告ですが、今後、動物園のほうは、このズーペリエンタ!センター、ズーとエクスペリエンスと、エンターテイメントの造語でズーペリエンタ!センターって言ってますが、こちらの改修が本格化いたします。野毛山動物園はかなり高低差ありますし、それから階段もありますので、少しこう、まあ、昔からの動物園ですので、そういったインクルーシブな配慮っていうのが必ずしも十分ではないところがあります。ですので、高低差を考えて、制度設計して、そして動物もですね、よりいろいろ動物にも来てもらうというような制度設計を考えております。休憩棟ができて、そしてこのズーペリエンタ!センターができれば、ほぼほぼ、まだ全部ではないですけども、野毛山動物園の全面リニューアルとして市民の皆様へのご提供が一段落するかなというふうに思っております。それから図書館のほうは、今度は中央図書館の1階ですね、1階を子どもフロアとして改修したいというふうに思っております。もちろん既存の蔵書数を減らすわけにはいきませんので、それを2階以上と、1階でどういうふうに整理していくのかってのは、これから、今年1年かけて検討したいなというふうに思いますが、いずれにしてもこちらの1階全部を使ったのげやま子ども図書館と、喫茶室の跡地のおやこフロアで、1階部分を親子のためのスペース、子どものためのスペースとして蘇らせたいというふうに考えております。ズーペリエンタ!センターは令和10年度に完成予定、のげやま子ども図書館の子どもフロアは、令和8年度に完成予定を考えております。引き続き、誰もが安らげる場所になるように、準備を進めていきたいというふうに考えております。こちらに関しては以上となります。
政策経営局報道課長 矢野:
それでは、この件についてご質問お受けします。まず幹事社からお願いします。
ラジオ日本 本田:
ラジオ日本の本田です。よろしくお願いします。はい、リニューアルした施設の見どころであったり、魅力、おすすめを教えていただけますか。
市長:
そうですね。今までかなり年数が経っていた建物、動物園は年数が経っていた建物ですので、より市民の皆様に快適に過ごしていただけるようになるかなと思います。横浜の子どもが初めて来る動物園が野毛山動物園っていう方、結構多いと思うんですよ。ですので、子どもたちの記憶にも残るような、動物園の整備を引き続き進めていきたいなと思ってます。そして、中央図書館のほうは、今、新たにおやこフロアができますので、親子で読み聞かせをしたり、あるいは動き回ったり、大きな声で笑ったり泣いたり、そういったスペースになることを期待しています。
政策経営局報道課長 矢野:
はい、それでは各社いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それではこの件の質疑は終了します。事務局、入れ替わりますので、少々お待ちください。
(3)横浜市内でのはしか患者の発生について
政策経営局報道課長 矢野:
はい、それでは一般質問に入る前に、1件追加で情報提供をさせていただきます。市長、お願いします。
市長:
はい、追加で1件だけご報告させていただきます。既に皆様方には共有させていただいておりますが、横浜市内でのはしか患者の発生についてです。2月26日と27日、市内で3年ぶりに2例のはしかの患者が発生しました。で、いずれの方も海外からご帰国後に発症いたしました。ただ、調べる限り、この2例には、このお二方には関連性はないものと考えております。で、はしかは感染力が強い感染症ですので、今回の患者と同じ時間帯に公共交通機関や施設を利用された方で、利用後しばらく経ってからはしかを疑うような症状が現れた場合には事前に、まずお近くの医療機関にご連絡して、そして指示に従った上で受診をしていただきたいと思います。また、移動の際は公共交通機関のご利用は避けていただけるようお願いします。また、市民の皆様に改めてお願いです。はしかは一度かかった人や、また2回の予防接種によって、十分な免疫を持っている人っていうのは発病する心配はないと言われております。一方で感染力が強い感染症ですので、これから海外への渡航を計画している方や、あるいは、渡航先の、海外への渡航を計画している方は、渡航先の感染症の流行情報や、あるいは、はしかの予防接種歴等を今一度ご確認の上、今後必要に応じて予防接種を受けるとか、検査を受けるとか、そういったことを検討していただきたいと思います。そして海外からご帰国後に体調不良になった場合には、必ず事前に医療機関に電話連絡をしていただいた上で、指示に従って受診をお願いいたします。また、お子様には、定期予防接種の接種期間に、予防接種を検討いただきたいと、受けていただきたいというふうに思います。私からの説明は以上です。
2.その他
政策経営局報道課長 矢野:
それではこの件と合わせて一般質問をお受けします。お時間経過しておりますので、複数ご質問ありましたら、まとめて簡潔にお願いできればと思います。では、まず幹事社からお願いします。よろしいですか。では各社いかがでしょうか。毎日さん。
毎日新聞 岡:
すみません、毎日新聞岡と言います。すみません、福島第1原発の関連でちょっとお尋ねします。除染で出た土を双葉町が町内で再利用していること、再利用することを検討していますと。現状、東京ドーム11杯分の除染から出た土があるんですけども、あるようなんですが、国が県外で最終処分することになっています。それを。
市長:
その11杯分っていうのは、横浜。
毎日新聞 岡:
ううん、東京ドーム11杯分の再生利用しなきゃいけない土があると。ただ再利用を表明してる自治体はないです。その現状についてどう思うかっていうのと、横浜市として受け入れの是非について、市長としてのお考えを。
市長:
ご質問ありがとうございます。今後、様々な状況を注視しながら検討していきたいと思いますので、現時点では何とも申し上げられるものではございません。
毎日新聞 岡:
分かりました。ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。よろしいでしょうか。東京さん。
東京新聞 神谷:
東京新聞の神谷です。先週、いじめ重大事態が2件公表されまして、その内1件、中学校の事案だと、当事者、生徒、保護者側が、先生からいじめを受けていたっていう主張があったということが報告書にも書かれてました。で、教育委員会にきっとその報告書とは別にその先生に対してその事実確認をした結果、報告書にあるその生徒、保護者側の主張と、教育委員会が事実認定した事柄ってのがあまりに少なかったと思うんです。そのこともあって、保護者側が報告書に対して不満を持っているということなんですけれども、その、なぜ事実認定ってのが少なかったのか、その報告と教育委員会としての、その先生に指導する内容というのは別だってことだったんですけど、ちょっとあまりにも少なかったんじゃないかなと思いまして、その辺は保護者側が言っている事実というのを教育委員会としてどう捉えているのか、あるいはその先生の指導だけっていうのが適切だったのかっていうことの見解についてお願いします。
政策経営局報道課長 矢野:
所管局から。
市長:
まず、ご質問ありがとうございます。まず今回の専門委員会の調査結果では、初期段階での事実確認や、あるいは教職員の生徒さんの特性の理解が足りていなかったという答申をいただきました。まず教育委員会で進めている再発防止策を徹底しなければいけないというふうに思っております。そして今回、所見書がいただきましたが、こちらにつきましてまず市として真摯に受け止めるべきだというふうに考えております。
教育委員会事務局人権健康教育部長 住田:
教育委員会事務局人権健康教育部長の住田です。ただ今ご質問いただいただ件なんですけれども、基本的に今の時点では第三者が入った調査が行われておりますので、その事実をしっかり受け止めています。その上で、今市長からもお伝えしましたけど、所見書も出ておりますので、その後の対応の中で適切に判断することになるというふうには考えております。
東京新聞 神谷:
すみません、先生への聞き取りというか、教育委員会としての人事的な対応を考えたものを別途聞き取った結果、事実認定したのは各、3人の先生達、3件あったっていうようなこと、先日のレクチャーでもいただいたんですけれども、それ以外のことは今のところ教育委員会で事実認定をしていないという解釈というふうに伺ったんですが、それはどういうことですか。
教育委員会事務局人権健康教育部長 住田:
具体的には所管課のほうからお伝えすべきことだと思っておりますけれども、これ、その時もお伝えしたとおりで学校教育事務所の所管になりますけれども、事実認定につきまして、確認をして認定しているものと、まだこれからやるべきものというのがあるというふうには聞いています。
東京新聞 神谷:
それは今後その第三者委員会の調査が進んだら新たに認定をして、更にもしそれが事実であるとしたら、その先生の処分と言いますか、対応がまた変わるという意味でしょうか。
教育委員会事務局人権健康教育部長 住田:
新たな事実については、またこの後その所管のほうでしっかり聞き取りをした後に、それが処分性が高いものであるならば、弁護士等の意見も参考にしながら処分していくというふうには考えています。
東京新聞 神谷:
今その第三者の調査が行われてた先日の一旦報告書が出て、所見が出てるので、もう1回更に精査をする、そういう意味ですか。
市長:
今後、今、市の調査結果が出されて、その後、所見書が提出されました。で、その後の流れなんですけれども、今後再調査の要否を判断するために、調査委員会への諮問を行いたいと私は考えております。
東京新聞 神谷:
それは再調査をするかどうかを判断する機関。
市長:
そうです。はい。
東京新聞 神谷:
それによって再調査、更に深い調査をするかどうかが決まるっていう。
市長:
その第三者委員会。大学の有識者、臨床心理の専門家、弁護士、人権の専門家。そういった方から構成される第三者委員会におきまして、再調査の必要性、あるいはそうではない。そういった判断に従いたいと思います。
東京新聞 神谷:
もしそれで再調査がされなかった場合は、もうこの先日の報告書で調査終わりという意味になりますよね。
教育委員会事務局人権健康教育部長 住田:
はい、おっしゃるとおりです。
東京新聞 神谷:
そうすると事実認定も、そうすると事実認定としてはどうなるんですか。
教育委員会事務局人権健康教育部長 住田:
基本的にこのいじめ重大事態調査においては、子ども同士のいじめの重大事態を調査しておりますので、そこの部分の認定が変わることはない、その再調査をなければ、変えることはないというふうに思っています。で、その周辺を取り巻く、要するに先生からの文言ですとか、どういった環境的な部分も含めて、そういったものについては、調査を行って、認定をするとかっていう、この再調査を行って認定をするってことではなくて、やっぱり教育委員会自体が不適切な行為があったのか、どうなのかっていうことをしっかり判断し、その処分性についても、これは弁護士等の意見も必ず参考にしながら決めておりますけれども、そういったものをこれからもやっていくということでございます。で、更に今ガバナンスをしっかり効かせてという話が、再三出てきていると思いますが、今後についてはそういったガバナンスをしっかり効かせる意味で、法務ガバナンス室というのを作って、そういうこともしっかり連携しながら対応していくっていうことでございます。
東京新聞 神谷:
ただ今回の件に関しては、もう一通り教育委員会として事実認定はこれだっていうのは出したっていうことですよね。
教育委員会事務局人権健康教育部長 住田:
いじめの内容については出したというふうに。
東京新聞 神谷:
いじめというか、その先生からの件に関しては、直接的な対象ではないけれども、でも保護者側としてはそこに対して、まだやっぱりもう少し調査してほしいってお気持ちを持っていらっしゃるわけですよね。そのお気持ち、でも、それはいじめ重大事態調査の枠組みではない。じゃあ、どうすればいいのか。で、結局、教育委員会が調査すべきことってなるんですか。
教育委員会事務局人権健康教育部長 住田:
基本的にはそうですね、この後、はい。なので、今その一定程度、先生の不適切性について聞き取りを行った以外の部分はこの報告書の中に書かれているとすれば、それは今後また行っていくということでございます。
東京新聞 神谷:
不適切性に関してはもう調査は終了したっていう認識なんですか。
教育委員会事務局人権健康教育部長 住田:
新たな事実があるものがあれば、それをもうこの後やっていくということです。
東京新聞 神谷:
その新たな事実っていうのは報告書の中で指摘されたことってことですか。
教育委員会事務局人権健康教育部長 住田:
そういうことです。
政策経営局報道課長 矢野:
所管局残しますので、詳細のやり取りであれば後ほど。よろしいでしょうか。その他は。神奈川新聞さん。
神奈川新聞 武田:
神奈川新聞武田です。すみません、今の関連で2点伺えればと思うんですが、1つが所見書が保護者さんから出ていて、調査委員会のほうにその諮問をかける。その調査委員会っていうのは、いじめの対策の専門委員会とは別の委員会っていう建付けでよろしいんでしょうか。
市民局人権担当理事 森:
はい、市民局人権担当理事の森と申します。よろしくお願いします。ご質問ありがとうございます。教育委員会の附属機関である専門委員会とは全く別の市長の附属機関っていうことになります。
神奈川新聞 武田:
ありがとうございます。そうするとメンバーも別ってことでいいですか。
市民局人権担当理事 森:
メンバー別でございます。これ7名、先ほど市長のほうから申し上げた7名の専門家による第三者機関ということになります。
神奈川新聞 武田:
7人なんですね。はい、ありがとうございます。もう1点、今のご回答の中で、今回の専門委員会の報告書の中で、例えば1年生の担任、中学生の事案のほうで行くと、1年生の担任からこういう被害を受けたっていう保護者さんの訴えがざっと10近くぐらいあったかと思うんですけれども、先日の西部事務所のほうに伺うと、そこは言葉を濁すというか、調査したのかしてないのかっていうのは言い切らない。昨日の議会でも、そんなご回答だったのかなと思うんですが、今のやりとりで伺うと、そもそもああいう機会があったけれども、手付かずになってしまってる訴えがどうやらあるっていう理解でよろしいでしょうか。
教育委員会事務局人権健康教育部長 住田:
はい、教育委員会人権健康教育部長の住田です。新たな事実として認定されたものについて、もう一度聞き取りをするということですので、手付かずになっているか、それが訴えはあったけれども、聞いてみたけども、実はそのことについては多少の齟齬があって事実じゃなかったっていうことも中にはある、含まれるかもしれません。そういった意味合いで更にあそこに書かれているような内容をもう一度聞き取ることは考えの中には含まれています。
神奈川新聞 武田:
すみません、最後に。そうすると、市教委として重大事態の調査の前段階なんですかね、保護者さんとして訴えていた、こういう被害があったと訴えられていて把握していた内容と、報告書に出てきた内容がどうやらちょっと違うというか、プラスされてるようなイメージ。
教育委員会事務局人権健康教育部長 住田:
若干そういった部分は否めないと思います。ちょっと個別の案件になりますので、また後程お願いします。
政策経営局報道課長 矢野:
ほか、よろしいでしょうか。産経さん。
産経新聞 橋本:
産経新聞の橋本です。そうすると、その再調査することになった場合っていうのは、調査してなかったことの補足の調査だけではなくて、全体を再調査するんですか。
市民局人権担当理事 森:
ありがとうございます。えっと再調査の対象になるのは教育委員会が行った調査結果ということになります。で、基本的に報告書に書かれていることが調査結果になるので、それが基本的には対象になります。ただ、それに関して、それ以外のことですね、そういうことを調べる必要があるということであればそういったことにも多少増触れることにはなると思いますが、法律に定められている再調査っていうのは再調査ですので、最初の調査をもう一度適正に行われているか調べることになります。ちょっとあの細かい話になりますが、具体的に申しますと、新たな重要な事実が、その調査の後で出てきたですとか、あるいはあの最初に保護者と確認した事項について調査が十分に行われていなかったケース、で3点目は委員の構成、そもそも中立構成でなかったと、こういったケース。これが再調査の時の対象になります。
政策経営局報道課長 矢野:
ほか、よろしいでしょうか。では、以上で会見終了します。ありがとうございました。
このページへのお問合せ
政策経営局シティプロモーション推進室報道課
電話:045-671-3498
電話:045-671-3498
ファクス:045-662-7362
メールアドレス:ss-hodo@city.yokohama.lg.jp
ページID:651-135-349