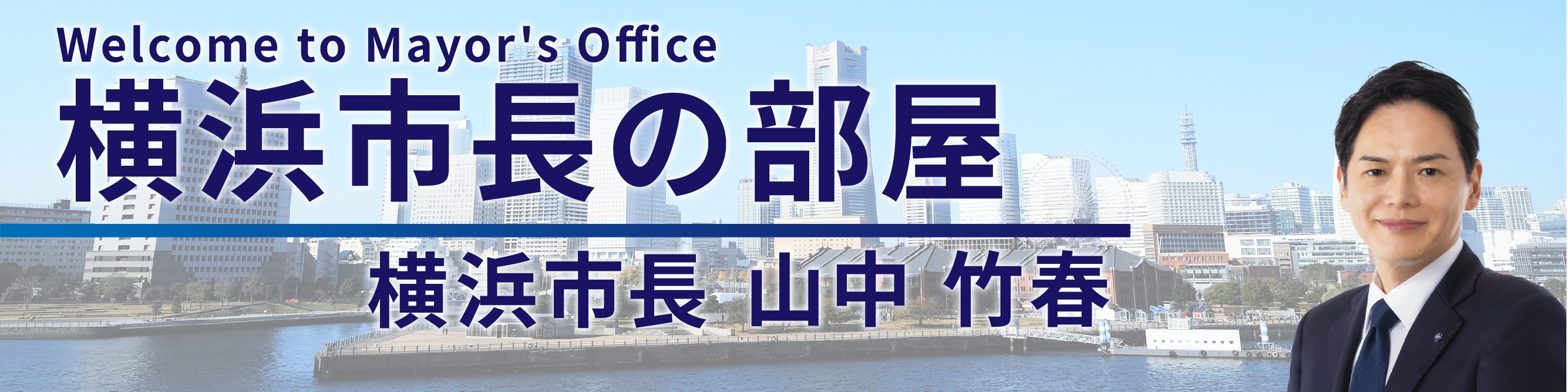ここから本文です。
- 横浜市トップページ
- 市長の部屋 横浜市長山中竹春
- 定例記者会見
- 会見記録
- 2024年度
- 市長定例記者会見(令和6年12月20日)
市長定例記者会見(令和6年12月20日)
最終更新日 2024年12月24日
令和6年12月20日(金曜日)11:00~
報告資料
- 【スライド資料】水道スマートメーターでもっと便利に ~全戸導入に向けて取組を加速します~ (PDF:553KB)
- 【記者発表】水道スマートメーターでもっと便利に 全戸導入に向けて取組を加速します
- 【スライド資料】「日本新三大夜景都市」に横浜市が選ばれました!~首都圏での選出は史上初の快挙~(PDF:2,222KB)
- 【記者発表】「日本新三大夜景都市」に横浜市が選ばれました!
- 【スライド資料】2024年 横浜10大ニュース 結果発表(PDF:1,357KB)
- 【記者発表】「2024年 横浜10大ニュース」が決定しました
会見内容
1.報告
(1)水道スマートメーターでもっと便利に
~全戸導入に向けて取組を加速します~
※敬称略
政策経営局報道課長 矢野:
はい、それでは定例会見始めます。市長、お願いします。
市長:
はい。本日、いくつかご報告事項ありまして、まず、水道スマートメーターの導入に関して、ご説明を差し上げます。水道メーターをデジタル技術を使って、より効率的にするという内容であります。スマートメーター、スマートっていうのはスマートウォッチとかスマートフォンとかデジタル技術を活用したっていう文脈で使われますけれども、このスマートメーターはですね、水道の使用量のデータを自動で取得できるようにするものであります。通常、こちらのスライドの左下のように、検針業務というものを長らく行ってきております。実際に、人が行って目視で確認をするものであります。電力、電気、ガス、水道、生活に必要なもので言われたりしますが、電気に関しては国の大号令のもと、このスマートメーターの導入っていうのが急速に進むようになりました。そして、ガスについては、電気よりは遅れているのですが、2030年頃を目途に、2030年代前半ぐらいですかね、を目途にスマートメーターが全国的に導入される、それによってガスの使用量が自動で取得できるようになる予定と聞いております。水道に関しても、スマートメーターの導入の流れが始まりつつあります。スマートメーターを導入することによって、市民の皆様に大きなメリットがあります。まず1番目、水の使用量が見える化できますので、例えば、将来的にはご自身のスマートフォンに水道使用量を1時間ごとに飛ばしてもらうとか、確認ができるようにするとか、そういったことが可能になろうかと思いますし、またそれによって、水漏れ、漏水等が早く検知できるようになろうかと思います。ここ重要だと思うのですが、一人暮らしの高齢者の見守りに役立つと思います。一人暮らしのお年寄りが数日間、水の使用量がなかった場合、そこは何か異変を察知する契機となります。こういった意味で見守りにつながるものというふうに考えております。あと、場所によっては検針員の方が、市の検針員が敷地に入らせていただいて、実際する水道メーターを測ったりしているんですが、そういったことが必要なくなります。そして、水道局本市側のメリットとしては、今、働き手不足叫ばれていますが、そういった担い手不足への対応になりますし、また、特にこの点重要でなんですが、災害対応力の強化につながります。というのは震災時にいろんなところで断水が起こると思います。この断水エリアを早期に探索して円滑な復旧作業が可能になろうかと思います。こういった市民の皆様に、そして本市行政にとりましても、大きなメリットがありますので、本市として水道スマートメーターの全戸導入に向けた取組を加速させたいと思います。これまで本市が行ってきた取組について簡単にご紹介をいたします。令和元年度からモデル実施を行いました。このスマートメーターに関して、モデル実施を行いました。これが実際のスマートメーターでありまして、ちょっとメーターなんで、どうしても大きなものになるんですけれども、これを設置して水道の使用量を自動的に取得するものであります。これですね、まず1次モデル事業では、携帯のキャリアを使っていたんですね。携帯のキャリアで結構いけたところもあったんですが、一方で通信が不安定な事例っていうのもあります。それは、皆様がスマートフォン使ってるときに感じる不安定な状況と同じかと思います。例えば、高層の建物とか、あるいはどうしても今電波が届かない場所ってあるじゃないですか。それから、あと建物の構造によっては壁で携帯の電波が遮断されるとか、あるいは弱くなってしまうとか、そういったことが起こります。それからあと、どうしても先ほどのメーターが高い、まだまだお値段が高いという事情があります。ですので、こういった課題っていうものが把握できております。そこで、今回新たに実施をいたします、モデル事業の特徴が2つあります。まず、電力は先ほどスマートメーターで、もう今、電力会社側で自動的に検針作業ができているというふうに申し上げましたが、電力会社が使っている通信ネットワークを使わせていただくと、そこに相乗りをさせていただいて、自動検針作業を実施するというのが特徴の1つ。もう1つは、これまでの規模で最大の、政令市で最大規模の約1,000戸の規模で大規模に、このスマートメーターの実証作業を進めると、この2点が特徴になります。相乗りの点なんですが、この水道メーター、先ほどのを設置して、電力のラインを、これすでに先ほど冒頭申し上げたとおり、電力に関してはスマートメーターが設置され、それをサーバーまでひくルートがもう物理的にありますので、その回線を使用させていただいて、最終的に水道局のサーバーのほうで集約するというスキームを考えております。これが今回行う予定の実験であります。スマートメーターの導入は、コストが最大の課題であります。使用が広がらないからお値段が高いっていうのはありますし、ですので、鶏、卵みたいな関係もあります。使用が広がらないから高い、高いからなかなか自治体としても導入しにくいといった、そういう関係がありますので、それは電力もそうでしたし、ガスも今そういう状況だろうと思いますが、様々なメリットがございますので、スマートメーターの全国的な普及に向けて、取組を進めてまいります。また、横浜市と大阪市と東京都の三つの都市で協力をして、スマートメーターの導入に向けて、かねてから連携はさせていただいているのですが、改めてこの3つの都市で仕様の共通化を推進しております。仕様の共通化を推進していきたいと思います。上水道は基本的に基礎自治体で行っておりますが、東京都に関しては、都が対応しております。道府県に関しては多くの場合、基礎自治体市町村で、小さい自治体はともかくとして、市町村で行っているのですが、東京都に関しては都で行っておりますので、東京都、そして横浜市、そして大阪市の3都市で連携しまして、仕様の共通化を図り、そして普及させることで、このスマートメーターの価格低減を実現して、全国的な普及につなげていきたいと考えています。今後も横浜市がリーダーシップを発揮して、このスマート検針の実用化に向けた取組を加速させてまいります。こちらに関しては以上です。
政策経営局報道課長 矢野:
はい、それではこの件についてご質問をお受けします。いつものお願いにはなりますが、ご発言の際はお手元のマイクのスイッチのご確認をお願いいたします。まず幹事社からお願いします。
NHK 岡部:
はい、幹事社のNHK 岡部です。よろしくお願いします。スマートメーターの導入について、コストが課題だというお話ありましたけれども、導入を進めることで、人を派遣しての費用に比べて将来的に削減につながるみたいなものがあるのか、あと機器が高いということでしたけど、水道料金への影響みたいなところはいかがでしょうか。
市長:
はい、ご質問ありがとうございます。まず、多くの人員の効率化、人員の作業の効率化につながると思います。これまで人が行って、それを検針、目で見て目視を行っていくという作業がなくなりますので、大きな効率化につながります。また、先ほど申し上げましたとおり、市民の皆様にとりまして、防災力の向上、見守りとか、防災力の強化など、市民の皆様にとって多くメリットがあることでありますので、是非進めなければいけないというふうに思っています。それから、コストに関してですが、コストっていうのは。
NHK 岡部:
そうですね、たくさん機器を導入して設備更新とかがあって。
市長:
そういうことで、水道料金にはね上がってくるか、関わってくるかっていうことですか。はい、現時点でスマートメーターの導入による、水道料金への影響はないものと考えております。
NHK 岡部:
分かりました。ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
それでは各社いかがでしょうか。朝日さん。
朝日新聞 良永:
朝日新聞の良永と申します。お願いします。先ほどのNHKさんの質問に関連するんですけれども、水道料金には影響はない、跳ね上がってこないというところなんですけども、市として何か交換について補助を出したりですとか、そういう形は考えていらっしゃるんでしょうか。
市長:
こちらは基本的に市の事業ですので、市として設置をしていくことになります。ですので、スマートメーターを導入していく際に、どうしても我々の市の財源を使ってしなければいけないものですから、補助金云々等はちょっと関係ないんですけれども、是非この取組進めていくべきだと思っております。
朝日新聞 良永:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。産経さん。
産経新聞 山澤:
産経新聞の山澤と申します。よろしくお願いします。横浜、東京、大阪で、仕様の共通化を推進ということでございますけども、そうすると大阪、東京でも電力のスマートメーターとの相乗りというそういう方向でやっていきたいということでしょうか。
市長:
東京はより大きな規模で携帯キャリアを使った実証実験を進めてくださってます。ですので、携帯キャリアか電力会社のラインを使ったものかの二者択一ではなくて、そこを相互補完的になろうかと思います。携帯キャリアでいけるところもかなりあります。しかしながらどうしても一部のエリア、一定のエリアが電波の状況が難しい状況にありますので、そこを埋め合わせるのがこの電力の既存のラインを活用した実証実験になります。
産経新聞 山澤:
だから、決め打ちでなく新しい選択肢として。
市長:
おっしゃるとおりです。
産経新聞 山澤:
これについても連携していくという。
市長:
はい、おっしゃるとおりです。
産経新聞 山澤:
分かりました。ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょうか。産経さん。
産経新聞 橋本:
産経新聞の橋本です。今のと重なるかもしれないんですけれども通信コストの低減についての検証っていうのはどういうことをやるんでしょうか。
市長:
通信コストの低減。スマートメーターのコスト低減ですね。スマートメーターの低減です。これが仕様が広がらない限り、需要がない限り限定生産になりますからどうしてもお高いままですので、この有用性を見いだし、そしてデータを集め、国とも交渉して、国からもできれば一定程度、大号令。そして補助金等もいただきいただければありがたいですし、そういった国との連携、都市間の連携ということでまず進めていこうと思ってます。やはり大都市がイニシアチブをとらないとこういった取組に広がらないと思いますので、そこを横浜市として率先して取り組んでいきたいと思っています。
産経新聞 橋本:
そうするとリリースに書いてある通信コストの低減っていうのは。
政策経営局報道課長 矢野:
所管局。
水道局経営部長 宮川:
水道局経営部長の宮川と申します。通信コストの低減なんですが、実は第1次モデル事業で携帯キャリアの通信コストのほうはですね、だいたい把握させていただいております。また今回東京電力さんと一緒に共同検針やることで、通信コストが比較してですね、どれぐらい低減が図れるか、こういったところもしっかり確認をしていきたいというふうに思っております。
産経新聞 橋本:
これって契約でいくらでお願いしますとかやるもんじゃないんですか。
水道局経営部長 宮川:
確かに契約でやることにはなると思うんですが、例えば今、先ほど申し上げたその規模が広がっていくというところになりますと、東京電力さんとしても、投資をするところのメリットが拡大してきますよね。そういったところで通信費については低減化を図れるというところもあるかと思います。
市長:
だから実証実験の中でコストの削減とかを見極めるものではないです。
政策経営局報道課長 矢野:
その他。
市長:
通信コストの削減を見極めるものではないです。はい。
政策経営局報道課長 矢野:
tvkさん。
テレビ神奈川 今井:
テレビ神奈川今井です。スマートメーターということで、全戸導入ということなんですけれども、いつまでに全戸に導入するとかそういったものがもし分かれば。
市長:
まずモデル事業を行いましてデータを取得いたします。ただこの間技術も日進月歩ですので技術のこれから進展もあろうかと思いますし、先ほど部長がちょっとおっしゃった通信コストの試算とかも今後、電力会社もそうですね。電力会社のほうで行っていくだろうというふうに思います。あるいは通信携帯キャリアの会社のほうで行っていくというふうに思います。ですので、データは我々は取得し、一方で、民間事業者のほうで様々な試算を今後数年間進めていきます。今のところですね、28年から順次導入を開始したいというふうに思ってます。その後は最速のスピードで全域への展開を図ってまいります。
テレビ神奈川 今井:
そうなると具体的にいつまでに全戸に導入っていうのは。
市長:
先ほどすみません繰り返しになるんですが、どうしても技術がどれだけ進歩するかとかにも依存するので、まずは今回、大きな政令市として、初めての大きな規模で実施可能性について検討したいというご報告であります。
テレビ神奈川 今井:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。神奈川新聞さん。
神奈川新聞 加地:
神奈川新聞の加地です。市民へのメリットの1つとして一人暮らしの高齢者の見守りにつながるとあったんですが、これ異変を察知して駆けつけるのは市のサービスとしてやっていくことを想定して書かれたのか、それとも民間のサービスを使ってもらうことで、想定されているのか何かイメージしていることがあれば。
市長:
そこまで具体的に決めているものではありませんが、地域に足を運んで、いろいろな方々とお話をさせていただいても、やはり高齢者の一人暮らしの方が多くなっていて見守りの体制に関するご不安の声を多くいただきます。しかしながら、地域によっては、例えば自治会の中で協力して声がけ等を行ってくださっている地域もあるんですが。それを技術の力を使って、そういった異変に関してシグナルを早く察知する、ていうことが可能になりうるのではないかというふうに思っております。そういったことが可能になれば、その後おっしゃるとおり、行政としてどういう対応をしていくのか、あるいは民間事業者さんと連携してどういう対応をしていくのか、実際に検討段階に入るかというふうに思います。
神奈川新聞 加地:
1つのツールとして持っておく。
市長:
おっしゃるとおりです。はい。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。タウンニュースさん。
タウンニュース 門馬:
タウンニュースの門馬です。よろしくお願いします。1,000戸でこれを実施するということで保土ケ谷区ではもう対象のお宅が決まっている。あと中区や西区はこれから調整ということですけれども、この現状の1,000戸の選び方とか、選択の考え方っていうのはどういったものでしょうか。
市長:
広く集合住宅とか、戸建てとかを選びたいというふうに思ってます。以上です。
タウンニュース 門馬:
分かりました。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょうか。神奈川新聞さん。
神奈川新聞 武田:
神奈川新聞の武田です。1点だけ令和元年度から第1次でやっている携帯キャリアのほうで、これで概ねどれぐらいカバーできるっていう今段階で予測っていうのがあるんでしょうか。
市長:
それは通信キャリア。
神奈川新聞 武田:
そうです。
市長:
携帯キャリアを使った通信でどれくらい出るのか。
神奈川新聞 武田:
そうですね、横浜の場合、山、坂多いと思うんですけれども、例えばどれぐらい、50%ぐらいはこれでいけるけれども、なかなかほかが難しそうだからこれを導入してみるとかっていう感覚というのはいかがでしょうか。
政策経営局報道課長 矢野:
所管局。
水道局経営部長 宮川:
はい。実際にはですね、携帯キャリアを使った通信のときも横浜市全体、面でどういう通信環境なのかというのはまだ把握していない状況ではあります。ただ横浜市全域、携帯自体はですね、かなり電波は入る状況にはなってると思うんですが。それでもやっぱり、例えば建物が込み入っているところですとか、そういったところでは通信状況がですね、良くないところもあるだろうというのがまず1つあります。もう1つはやはり今回共同検針っていうところでですね、取組をさせていただいて、別な技術も確認をさせていただくことでコストなどの比較ができるというところで、今回両方ですね。しっかり技術検証しながら、得手不得手のところ強みを生かしながら組み合わせですね、考えていきたいというふうに考えております。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょうか。
市長:
おっしゃった試算は重要ですよね。山坂が多いのでどのぐらいのカバーを携帯キャリアできるのかどうかの試算というのもきちんと進めていきたいと思います。ご指摘ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
他よろしいでしょうか。はい。それではこの件の質疑は終了します。事務局入れかわりますので少々お待ちください。
(2)「日本新三大夜景都市」に横浜市が選ばれました!
~首都圏での選出は史上初の快挙~
政策経営局報道課長 矢野:
では、続けて市長お願いします。
市長:
はい。続いてですね。もうすでにメディア等でも報道がなされておりますが、このたび日本新三大夜景都市に横浜が首都圏から初めて選ばれました。そのご報告です。こちらでありますが、こちらいただいた賞状であります。日本新三大夜景都市に選ばれたという賞状でありますが、今回横浜が首都圏で選ばれたというのは非常に嬉しいことであります。新三大夜景都市は、一般社団法人夜景観光コンベンションビューローが国内外の夜景の観光夜景観光の活性化を目指して創設した夜景ブランドであります。全国6,600名を超える夜景観光士の方がいるようでその方がですね、投票をしていただいて、集計結果から上位三つの都市を新三大夜景に認定して3年に一度改選をしているそうです。2015年から始まりまして、次が2018年。次、21年の予定だったんですけどコロナで22年の選定になりまして、22、23、24を経て25年から本市がその3年間の新三大夜景の1つに選ばれたということだそうであります。受賞理由は、ヨルノヨが評価されました。また、スパークリングトワイライトが評価いただいたようです。この夜景そのものの魅力はもちろんなんだが、夜景を生かした多種多様なコンテンツ、例えばそのイルミネーション等ですね、ヨルノヨのイルミネーションなどが評価をいただいたというふうに言われておりますし、あと都市の変化と共に変貌する夜景ってちょっと分かりにくいんですけれども、単にイルミネーションをつけるだけではなくて例えばビルとかを、ビル群とかのイルミネーションがかなり評価されているというふうに聞いております。これまで経済界と一緒にですね、地元の皆様と一緒に横浜の夜景を作るという取組を行ってきたのですが、これが改めて評価をいただきまして、大変嬉しく思っております。また最近日本経済新聞のイルミネーションのランキングでも1位に選出いただきました。様々今この横浜の夜のイルミネーションが内外に知られてきておりますので、今後も地域の皆様、経済界の皆様としっかりと連携をして、一丸となって夜の横浜の街を楽しんでいただける取組を進めていきたいというふうに考えております。こちらに関しては以上です。
政策経営局報道課長 矢野:
はい。それではこの件についてご質問をお受けします。まず、幹事社から。
NHK 岡部:
はい。お願いします。ずっと取り組んできての受賞で今まで6位だとか、三大に入らなかった。
市長:
8位とかね。
NHK 岡部:
そうですね。
市長:
はい。
NHK 岡部:
改めてその受け止めを一言いただければと思います。
市長:
はい。これまで、繰り返しになるんですが。これまで街を挙げて横浜の夜のイルミネーションへの取組を行ってきました。そのことが改めて評価されたことを嬉しく思います。今回日本新三大夜景都市なんですが、今後世界から評価される夜景作りに取り組んでいきたいというふうに思っています。
NHK 岡部:
ありがとうございます。あともう1点なんですけれども、その今回の受賞を受けて、夜の観光を、横浜は、アクセスの近さからどうしてもその日帰りでなかなか宿泊してもらえないみたいな課題もあると思うんですけれども、この夜の観光に向けて今後どんなふうに進めていきたいとお考えでしょうか。
市長:
はい、確かにどうしても東京に戻られて、戻るというか東京で宿泊される方っていうのが一定程度いらっしゃることを承知しております。ですので、夜の時間をどう楽しんでいただけるのか、ということから夜のイルミネーション作りは始まったというふうに考えて承知しておりますし、また本市としても、地元の皆様と地域の皆様と一緒にその取組進めているのですが、今後更にですね、夜の滞在時間を延長してもらえる取組が必要だと思います。花火もそうですし、食なんかもそうですし、様々な横浜の資源を使ってもっといてもらって、そして泊まってもらう。そういった取組を今後も加速させていきたいというふうに思ってます。
政策経営局報道課長 矢野:
それでは各社はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい。それではこの件の質疑は終了いたします。事務局入れ替わります。少々お待ちください。
(3)2024年 横浜10大ニュース 投票結果発表
政策経営局報道課長 矢野:
はい、それでは続けて市長お願いします。
市長:
はい。今年の横浜10大ニュースの投票結果が出ましたのでご報告させていただきます。横浜10大ニュースはですね、今年で44回目になります。市民の皆様に1年を振り返ってもらうこと、そして、市民の皆様が関心を持っていることを把握することなどを目的に行っているんですが、今回ですね、11月21日から12月12日までの3週間行わせていただきましたところ、ありがたいことに、投票人数が過去最多の約1万7,000人となりました。5年前ぐらいが4,000人ぐらいですので、多くの方に関心を持っていただいているのかなというふうに思っております。まず10大ニュースの結果の発表なんですけれども、10位から6位まではご覧のとおりであります。まず10位がプラゴミの分別について、9位がBUNTAIの開館について、8位がズーラシアでオカピの赤ちゃんが誕生したことについて、そして7位が能登半島地震の被災地支援として、本市として職員を派遣し、かつ地震防災対策強化パッケージを推進したこと、そして、みなとみらい線が開業20周年を迎えたことが選ばれています。5位がですね、地球の歩き方横浜市版の発売が選ばれました。これは先般ご報告しましたとおり、横浜市と株式会社地球の歩き方が連携をいたしまして、地球の歩き方で、初めての試みとなる、市民参加型アンケートを実施して、横浜市民の皆様の声で作った地球の歩き方になっています。多くの、もうすでにもう版も重ねて売れ行き好調で版も重ねているというふうにお聞きしておりますが、市民の皆様と、そして、有名な地球の歩き方がコラボして、こういったものができたことを大変嬉しく思っています。次に4位がゆめが丘ソラトスの開業でありました。129店舗が出店した大型商業施設の開業が選ばれています。特に、相鉄線沿線の市民の皆様がこのソラトスの開業を選ばれているのではないかなと思います。ですのでこういったですね、大型施設が沿線沿いにできたことを大変嬉しく思っております。3位が横浜市で始めました出産費用の助成並びに妊婦健診の助成が選ばれました。そして2位が帰ってきたあぶない刑事の映画の公開が選ばれました。本市の横浜フィルムコミッションのほうで撮影に関しても支援をさせていいただきまして、5月に全国公開されたこちらの映画が選ばれております。また主演のお二方には、横浜の春の恒例イベントでザ横浜パレードにも参加をしていただきました。そして第1位が横浜DeNAベイスターズの日本一でありました。98年以来、実に26年ぶりの日本一になりまして、横浜市民の皆様、ファンの皆様が歓喜に包まれたことは記憶に新しいかと思います。ベイスターズがですね、市民の皆様に愛されて、今回、日本一となったことで、今回の第1位となりました。以上が、今年の横浜10大ニュースの投票結果となります。今年もたくさんの市民の皆様に投票をいただきましたことを改めて御礼を申し上げます。こちらに関する説明は以上です。
政策経営局報道課長 矢野:
はい。それではこの件のご質問をお受けします。まず幹事社からお願いします。
NHK 岡部:
はい。お願いします。今10大ニュース発表いただきましたけれども、市長にとって思い出深かったニュースはどんなものでしょうか。
市長:
どれも印象深い出来事であったなぁというふうに感じています。ちょっとどれか1つに絞るのはなかなか難しいんですけれども、今年は過去最多となる1万7,000人もの方に投票いただいて、大変ありがたく思っております。
政策経営局報道課長 矢野:
それでは各社はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それではこの件の質疑は終了します。事務局入れかわりますので少々お待ちください。
2.その他
政策経営局報道課長 矢野:
はい。それではこれより一般質問に入ります。複数ご質問ありましたらまとめて簡潔にお願いできればと思います。ではまず幹事社からお願いします。
NHK 岡部:
はい。今月の山下ふ頭の再開発の関係なんですけれども、検討委員会のほうから答申の案がまとまって、まだ市長への提出は今後だと思うんですけれども。案がまとまりましたが、改めて受け止めだとか。あと提言の盛り込まれた内容について、このあたり取り込んでいきたいだとか、あと、まだ言えないかもしれないんですけれどもどんな場所にしていきたいのかというのを改めて、お考えいただければと思います。
市長:
はい、ご質問ありがとうございます。今回の検討委員会では6回にわたって熱心にご議論いただきました。多岐にわたる分野の方が集まっていただいて、熱心に議論をして、答申をおまとめいただいたことを大変ありがたく思っております。これから答申をいただく予定になっておりますが、山下ふ頭の優れた立地を生かして、どういうふうな開発をするべきか、その方向性に関して示していただくものというふうに期待をしております。いただいた答申案を踏まえてしっかりと横浜の財産になるような、山下ふ頭の開発を進めていきたいというふうに思っております。
政策経営局報道課長 矢野:
はい、それでは各社、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。時事通信さん。
時事通信 岩重:
時事通信の岩重といいます。先ほど横浜10大ニュースのお話もありましたが、年末なので、今年1年振り返って、市長としてこの1年、漢字一文字で表すならどうなるかっていうとこを教えていただけますか。
市長:
はい、こちらです。「想」という漢字を選ばせていただきました。「想」にはいくつかの気持ちを込めております。お正月に能登半島地震が起こりました。今なお多くの方が被災をされております。1日も早い復旧、復興への想い、こういったものを漢字に込めております。そして、26年ぶりにベイスターズが優勝いたしました。これは市民の皆様のベイスターズへの想いが成就したというふうに考えております。また、今年、日本被団協がノーベル平和賞を受賞いたしました。平和への想いを新たにした、改めて強く感じた出来事でありました。そして、この市民の皆様の期待を汲んで、この1年間、取組を進めてまいりました。市民の皆様の生活をより良いものにしていくために政策を行ってきました。そして私の任期も、もう1年を切っております。あと約8か月となっております。残された任期をしっかりと全うできるよう、私自身の想いをこの漢字の中に込めております。以上です。
時事通信 岩重:
ありがとうございます。今、任期まで1年切っているというお話ありましたが、先のこと、次にもまた選挙に出られてとか、その辺の対応については今、お話できることあれば教えてください。
市長:
1日1日、いただいた任期をですね、しっかりと全うしていくことだけを考えています。
時事通信 岩重:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。朝日さん。
朝日新聞 良永:
朝日新聞の良永と申します。2点、ご質問します。1点目が先ほどと重なってくるんですけれども、年末ということで1年の所感を教えていただきたくてですね、市長の公約の3つのゼロについても、出産費用ゼロですとか、地域交通の充実といったところでかなり達成に近づいているのかなと思うんですが。
市長:
かなり、なんですか。
朝日新聞 良永:
達成のほうに近づいているのかなと思うんですけれども、そこの所感を教えていただけますでしょうか。
市長:
はい、ご質問ありがとうございます。今年1年、全力で市民の皆様の暮らしをお支えするための取組を進めてまいりました。今年1年は特に防災と防犯への取組の重要性を感じた年であります。市民の皆様の暮らしの安全、安心。市民の皆様から安全とそして安心な暮らし、これを求める声がどんどん高まっているのを感じております。こういった声を受けて、次年度しっかりと、安全、安心な暮らし、すなわち防災や防犯への取組を加速させたいと思っております。
朝日新聞 良永:
ありがとうございます。あと2点目なんですけれども、放課後キッズクラブでの長期休み中の昼食提供についてお伺いします。先日の常任委員会でアンケート結果が出ておりまして、こちらの保護者の方から高い満足度を、かなり、8割満足ですとか、9割以上の方が時間的な負担低減したっていう話があったんですけれども、これを受けて市長の受け止めと、あと来年度に向けてどのような形で行っていくかっていうところを教えていただけますでしょうか。
市長:
はい、ご質問ありがとうございます。今回、ご利用いただいた保護者の方からは一定程度、評価するお声をいただいたというふうに感じております。今後ですね、予約のしやすさ使いやすさをですね、しっかり高めていかなければならないというふうに思っております。できる限り、昼食を事業者さんに準備していただくためには、一定程度時間があったほうがいいのですが、でも一方で、保護者の方々のニーズ、すなわち今日は使いたい、今日はやっぱりいいや、そういったことに応えるという使いやすさですね。それとのバランスをしっかり考えて、ちょっと今は早めにキャンセルしないといけないっていうような状況もありますから、これをできる限り保護者の皆様が使いやすいようにしたいなというふうに思っております。あと、更に安全、安心な取組をしっかり行った上で夏休みに関して、引き続き行っていきたいと思っておりますし、また、その他の長期の休暇に関しても、この取組を広げていきたいというふうに思っています。
朝日新聞 良永:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他、いかがでしょうか。tvkさんから。
テレビ神奈川 今井:
テレビ神奈川の今井と申します。2点、お伺いしたいんですけども、まず日産の。
市長:
日産。
テレビ神奈川 今井:
日産の経営統合の話があると思うんですが、そこをまだ正式という形ではないんですが、市の影響というか、なんかそういった、どういったことを考えているのかとお伺いしたいんです。
市長:
まだ内容に関して全然中身が分かりませんし、ホンダさんと日産さんで経営統合の話をしているという段階にとどまっておりますので、今後、統合するにせよ、しないにせよ、いろいろな内容が明らかになってくると思いますので、動向を注視したいと思います。いずれにせよ、自動車産業は、本市経済の柱の1つでありますので、本市として、しっかりと動きを注視していきたいと思います。
テレビ神奈川 今井:
ありがとうございます。もう1点あるんですけども、国際プールの件なんですけれども、先ほど常任委員会のほうで市の原案が示されましたけれども、改めてそこの受け止めについてお伺いしたいと思います。
市長:
ご質問、ありがとうございます。今回素案に関して、市民の皆様から大変多くのお声をいただきました。たくさんのご意見を踏まえて、市民の皆様のための原案の作成を進めてまいりました。横浜国際プールは横浜市民の皆様のための施設です。ですので、市民の皆様が、誰もが楽しく過ごして、そして喜んでいただける、そして、インクルーシブな視点を踏まえて、そういった拠点を作っていきたいというふうに思っています。
テレビ神奈川 今井:
ありがとうございます。その一方で、水泳団体のほうから結構まだ、存続をお願いするみたいな意見も少し残ってるんですけども、そこに対してどういう対応をしていくとか、何かお考えとかありますでしょうか。
市長:
関係団体とは所管局を通じて今後も丁寧に議論をしていくというふうに考えています。
テレビ神奈川 今井:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょうか。神奈川新聞さん。
神奈川新聞 加地:
神奈川新聞の加地です。敬老パスに関して伺っていきます。先日の常任委員会のほうで来年度に向けて、地域交通への敬老パスの適用であったり、免許返納者への無料交付だったりっていうようなことが出てきたんですけど、市長の公約の75歳以上の無料化っていうのは検討自体は続けていかれるのかっていうことと、データを分析して効果検証した結果、やらないっていう選択肢も持っていらっしゃるのかっていうのをまず、お伺いできればと思います。
市長:
はい、ご質問ありがとうございます。まず、敬老パスなんですが、できてから長らく市民の皆様に使われているものであります。これの本来の敬老パスの目的ってなんでしょう。それは敬老パスを使って外出促進をして、市民の皆様に健康になってもらう。高齢者の方に健康になってもらう。これが敬老パスの目的であります。一方、データを今回、いろいろ取らせていただいて、いろいろな課題が明らかになってきました。まず、交通空白地帯が存在します。横浜市、山坂が多いですが、交通空白地帯が見える化されました。また、敬老パスの使用状況のデータもとらせていただいて、敬老パスの地域格差が明らかになりました。ある区と、港南区と瀬谷区ですけども、30%使用状況が違う、使用率が違うっていうのは大きな課題であるというふうに思います。また、敬老パスにつきまして、健康になってもらう、外出してもらう、そして、その先にあるのはよりフレイルの方やフレイル以前の方もそうなんですけれども、介護予防効果だというふうに思っております。ただ、その介護予防効果に関して、恐らくあるだろうという仮説は既に結果としてお出ししておりますが、その仮説の、今度検証が必要だというふうに考えております。交通空白地帯があり、そして敬老パスの地域格差があり、そして、外出促進の先にある、敬老パスの本来的な、KGIって言ったらいいんですかね、そういったものがあり、こういったことが今回データを取ったことで分かってきました。行政としては、様々な施策を通じて、交通空白地帯を埋めていく努力を積極的に行います。併せて、敬老パスの地域格差、公平性の観点からも、敬老パスの地域格差を解消していくことを積極的に行ってまいります。またあわせて、その敬パスの介護予防効果に行いまして、データを取り、疫学というか、公衆衛生学的なアプローチになると思いますが、きちんと効果検証を行いたいと考えております。これらを通じまして、敬老パスの本来の目的である外出促進の取組を強力に進めていきたいというふうに思っております。なお無償化につきましては、敬老パスの本来の目的が外出促進で、無償化に関してはその手段の1つであります。目的を達成するために敬老パスの無償化も含めて、今後、様々データをとりながら検討を進めていかなければならない。今回そういった課題が明らかになったと思います。データを取ったことによって。以上です。
神奈川新聞 加地:
すみません、常任委員会の中だと、無償化にこだわらずっていう言葉だったり、無償化にとどまらずという言葉が出てきたり、ちょっと。
市長:
どこからですか。
神奈川新聞 加地:
常任委員会で、副市長の答弁が。
市長:
それは当局からですか。議員からですか。
神奈川新聞 加地:
いや、当局側です。
市長:
当局側ですか。
神奈川新聞 加地:
とどまらず、こだわらずっていう言葉が、両方でてきたなと記憶してるんですけど、今の市長のお答えだと無償化にとどまらず柔軟に制度を改善していくということで。
市長:
外出促進をしっかりと進めていくことが重要だと思います。そのために敬老パスの無償化も含めて今後データをとってしっかりと検討していきたいというふうに思っております。議会からも、敬老パスの効果に関してデータをとるようにというふうに言われております。実際、介護予防効果があれば、それは行政としてのコストの大きな減、負担減になります。ただそういったことが、敬老パスっていうのは横浜だけではなくて、全国多くの都市で導入されていますが、残念ながらその敬老パスの効果に関するデータっていうのは見当たりません。ですので漫然と敬老パス使うのではなく、きちんと今後の持続可能性を持たせるためにも検討を横浜市として率先して行っていきたいと思っています。
神奈川新聞 加地:
検証が終わった後に、本格的な議論に入ってくるという認識でよろしいですかね。
市長:
そうですね、はい。
神奈川新聞 加地:
すみません。ちょっと視点を変えてお伺いしたいんですが、5月にIC化の1年間のデータを出されたときに、利用回数にかなり隔り、年間5,000回以上使っている方などちょっと公正にしたほうがいいんじゃないかなと思うような結果が出てきたんですが、何か今後市として、制度の公平性を保つために、制度自体をちょっと変えるとか。
市長:
そのオーバーユースしている人たちに対してですか。
神奈川新聞 加地:
はい、何か対応はありますでしょうか。
健康福祉局高齢健康福祉部担当部長 青木:
はい。健康福祉局高齢健康福祉部担当部長の青木でございます。5月の常任委員会のときにかなり多数回利用されてる方がいらっしゃるということから、全体で平均で、今年間に、月に20回弱という利用なんですが、5,000回利用されてる方とかいらっしゃるということでこれを課題感としてお示しいたしました。例えばですね、この間、その辺の検討を進めていく中でですね、多数回利用がただちに悪いとか、そういう評価をするのは非常に困難であると、やはり利用目的をですね、しっかりと把握していくことが大事だということで今回検証の中にもそういった項目も入れてしっかりと研究していきたいと思っております。
神奈川新聞 加地:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。産経さん。
産経新聞 橋本:
産経新聞の橋本です。またちょっと横浜国際プールのことで恐縮なんですけども。今回素案から新たに練習用プールを作るっていうのは大きく変更されて、結果、それが一番の大きな変更点だと思うんですけども、その結果費用対効果が下がるといったことがあったりもしたんですけども、そのことについての。
市長:
効果が上がる。コストパフォーマンスが良くなるって。
産経新聞 橋本:
悪くなる。
市長:
悪くなる。
産経新聞 橋本:
悪くなるんですよね。
市長:
長期的に見たら。
産経新聞 橋本:
いやいや、素案と比較してですね。
市長:
長期的に見たら。まあいいや、すみません。
産経新聞 橋本:
まあ、いいや。
市長:
ごめんなさい。
産経新聞 橋本:
質問としては、素案から変更されたことについての、変更点についての市長の評価と感想をお願いいたします。
市長:
はい、ご質問ありがとうございます。市民のための施設ですので、インクルーシブな視点に関して、お声をいただきましたので、それをしっかりと取り入れた次第であります。はい。
産経新聞 橋本:
せっかくなんで、じゃあ費用対効果、これ原案と比べると運用費、市の年間の負担が当初の素案よりも増えるように読めたんですけど、そうじゃないんですか。
にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興部長 熊坂:
はい。ご質問ありがとうございます練習用プールを新設することのコストの増が、含めまして、6億円、整備費が増えているということは常任委員会にもご説明しました。一方で、そこから得られるトータルコストについても、今回ご説明をさせていただいておりまして、今回の議論のひとつとして、監査のところでは休館であったりとか床転換によるコストが経済性の観点から課題ではないかというふうに言われております。今回この整備、検討するに当たりまして、先ほど市長からも申し上げたとおり、施設をですね、より多くの市民の方にどう使っていただくのかというようなことをまず考え、その上で今運営をしていることを継続するよりもより多くの経済性、効率化が図れるというところでまとめさせていただいているものでございますので、素案からというよりは、結果としてこの原案でもしっかりとそういった課題があったというのは対応できているんではないかと認識しております。
産経新聞 橋本:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。タウンニュースさん。
タウンニュース 門馬:
タウンニュースの門馬です。今定例会の常任委員会の中で、図書館整備の今後の方向性が示されて、その中で、大型の図書館を今後作るという案が、方向性が示されました。この新しい大型の図書館、非常に市民の方も期待を持っている方も多くいらっしゃるので、どういう図書館にしたい、あってほしいというふうにお考えでしょうか。
市長:
はい。ご質問ありがとうございます。今回市民の皆様から多くご意見いただきましたし、市会の議員の先生方からも多くのご意見いただきました。総じて、新たな大型図書館への期待を感じています。今、時代の変化、時代の流れもあって、図書館に新たな役割が求められているというふうに思っています。図書館のニーズが大きく変わっていると思うんですよね。ですので、そういったニーズを的確にとらえながら、時代の潮流をしっかりと踏まえた図書サービスの提供、それに資するような図書館を作っていきたいというふうに思っています。
タウンニュース 門馬:
はい。ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。よろしいでしょうか。それでは定例会見以上で終了します。ありがとうございました。
このページへのお問合せ
政策経営局シティプロモーション推進室報道課
電話:045-671-3498
電話:045-671-3498
ファクス:045-662-7362
メールアドレス:ss-hodo@city.yokohama.lg.jp
ページID:479-308-752