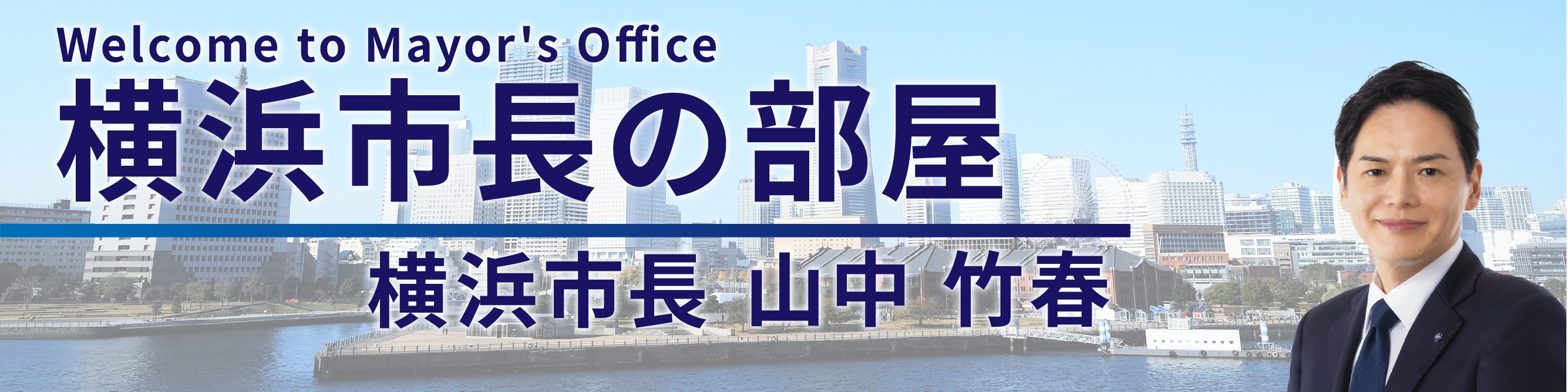ここから本文です。
- 横浜市トップページ
- 市長の部屋 横浜市長山中竹春
- 定例記者会見
- 会見記録
- 2024年度
- 市長定例記者会見(令和6年10月22日)
市長定例記者会見(令和6年10月22日)
最終更新日 2024年10月24日
令和6年10月22日(火曜日)11:00~
報告資料
会見内容
1.報告
がんの早期発見に向けた新たな取組
※敬称略
政策経営局報道課長 矢野:
それでは定例会見始めます。市長、お願いします。
市長:
はい、本日ご報告するのが、がんの早期発見に向けた新たな取組についてです。先般、65歳時点でのがん検診の無料化について、がん検診の本市で行っている、がん検診の無料化についてご報告いたしましたが、それとは別に更に4つのテーマについて、今日、ご報告したいと思います。 1つ目が、子宮頸がん検診におけるHPV検査の導入、2点目が70歳以上の方の精密検査、がん検診ではなくて、その後に続く精密検査ですね、精密検査の無料化、この2件は年明けの1月から実施をいたします。それから3点目として、がんを受けやすく、がん検診を更に受けやすくするため、検診を受けられる施設を探せるサイトを新たにオープンすることにいたしました。4点目が遺伝性乳がん卵巣がん症候群、いわゆるHBOCの検査に対して新たな助成を開始いたします。3と4の2件については、来月から開始をいたします。順にご説明をいたします。初めに、頸がん検診におけるHPV検査の導入ですが、これは欧米で推奨されている検査を全国に先駆けて、新たに本市が導入をいたします。令和7年の、来年1月からこの検査、HPV検査の単独法を開始いたします。取組としては全国初の取組となります。まずイメージなんですけれども、頸がんが発症するイメージっていうのはこういう図になろうかと思います。まず、検診対象の女性がこのグレーの部分で、その中に、子宮頸部がHPVに持続的に感染している方という人がいます。女性は一生に一度、生涯にHPVには多くの方が感染いたします。ただ、そのご本人が持っている免疫でHPVに感染したとしても、ウイルスは排除されることが多いのですが、一方で、頸部にHPVが持続的に感染している人というのが一定程度発生します。その中の一部が、子宮頸がんになると考えられています。したがって、子宮頸がんっていうのはウイルスに感染してなるがんというのが一般的なルートであります。今回ですね、この子宮頸がんの人を最初から細胞を取って見つけに行くのではなくて、まず、ウイルスに感染しているかどうか、HPVに感染しているかどうかをスクリーニングして、そこで感染しているということが分かれば、次の検査に進むという手順をとりたいと思います。従来、この紺の子宮頸がんの人を見つけるために頸部から細胞を取るんですね。取った細胞で、それを顕微鏡で見てがん細胞が混ざってるかどうかを見るっていうのが通常の細胞診です。ただ、細胞の取り方でがんがある患部って言いますけども、患部から細胞が取れれば、がん細胞見えますけれども、そうじゃない、つまりそれ以外の患部ではない正常細胞からなるところだけを取ってしまうっていうのは普通に結構あるんですね。その場合は、がん細胞が取れないので正常細胞を見てがんじゃないというふうに判断するっていうことになります。ですので、まず今回の特徴っていうのは、リスクの高い人をスクリーニングし、リスクが高いと分かればその後、細胞診を行うと、そういう二段構えの手順になります。これが欧米で行われている方法であります。今、申し上げたとおり、現在の頸がん検診ていうのは、20歳以上を対象に細胞診で行います。受診間隔は2年に1回、陰性であればその2年後にもう1回受けてもらう、また陰性であれば2年後に受けてもらうということで、2年ごとなので結構頻度としては高くなります。それに対して、新たな頸がん検診というのは30歳から60歳の方に対して、HPVの単独法を行います。これは陰性になったら次の検査は5年後です。また5年後でHPV検査、そこでも陰性であれば、次また5年後に検診を受けていただくということになります。なお、20歳から29歳、それから61歳以上に関してはこれまでどおり、細胞診で行われるものになります。頸がんのボリュームゾーンというのが30代、40代でありますので、その方々を対象にHPV検査の単独法を行うと、そういう内容になります。今言ったことを図で表したものですけれども、細胞診、従来の検査は細胞を取って、もしネガティブであれば、陰性であれば2年後にもう1回、検診を受けてもらうと、そういうスキームですが、今回導入する単独法に関しては、ポジティブであれば、その後、精密検査という意味で細胞診を行います。ネガティブであれば、先ほど申し上げたとおり、5年後まで間隔広げられるので、受診の負担が減るというメリットがあります。このHPV検診単独法の特徴なんですが、多くの受診者はネガティブになりますので、検診の間隔が2年から5年後に延びますので、負担がかなり減ると考えられます。がん検診の未受診、がん検診を受けない理由で最も多いのは、受ける時間がないからというのが理由の第1位でありまして、検診受診の負担を軽減することで受けやすくなることを期待しております。このように、検査結果がネガティブの人にとって、大部分はネガティブだと思うんですけれども、メリットがあります。それから、ポジティブになったとしても、その方々は継続的にHPVに感染をしているということで、リスクがそれ以外の方に比べると高めです。ですので、その方々に関しては1年間隔でフォローしていくことになります。したがって、HPV検査の結果に基づいてリスクの高い等考えられる人に関しては、きめ細かいフォローを行っていくっていうことで、ポジティブの人に対してもメリットがあろうかと思います。従いまして、このHPV検査単独法の本質っていうのは、一律にべたっと検診をすることから、リスクに応じてトリアージをしようっていう発想への転換であります。対象者と費用をこちらにおまとめしております。市内在住の30歳から60歳までの女性約80万人近く、本市いらっしゃるんですけれども、その方々が対象になります。それから、検査費用は2,000円となります。市内の約190か所で検診を受けることができます。この190か所に関しても、後ほどご紹介するウェブサイトで検索を行うことが可能になります。今後ですね、対象となる方に受診のご案内や検診票などを順次お送りしていく予定です。まず、12月20日に国保に加入されている30歳から60歳の女性にお送りいたします。それで、1月10日に他の健康保険、民間の会社にお勤めの方とか、あるいは公務員の共済組合とかそういった他の健康保険に加入の方には、30歳から45歳の方にまず第1弾をお送りして、46歳から60歳の方には、その後にお送りする、そういう段取りを考えております。時期を分けてお送りする予定でありますが、ご案内の到着前に受診をご希望される方については、個別に対応していきたいと思います。次にですね、これ以上がHPV検診の導入についてです。2点目は、これはがん検診一般です。市で行っておりますがん検診の、がんですので頸がんだけではなくて、肺がんとか大腸がんとか胃がんとかが、を対象になります。この2点目はですね、70歳以上の方の精密検査を無料化することにいたしました。がん検診を受けて、がんの疑いがあるかどうかという検査結果が返ってきます。がん疑い、検診で分かるのは疑いまでですので、その後がんがあるかどうかっていうのを確定する、それが精密検査です。そのための精密検査を受けてくださいというご案内がきます。横浜市は70歳以上の方を対象に、来年の1月以降に横浜市のがん検診を受診して、精密検査が必要となった方に対する精密検査の費用を助成することにいたしました。精密検査が必要となった場合の検査費用を助成して、精密検査の受診を後押しするものであります。少しイメージを大腸がんと乳がんでお話しさせていただきたいと思います。精密検査っていうものの考え方ですね。まずイメージその1として市内在住の72歳の方、国保に加入、この方は自己負担割合が2割となります。横浜市のがん検診の大腸がん検診を受診しました。便潜血で大腸がん検診を行っておりますが、検査の結果、大腸がん疑いということで便潜血検査がポジティブに出ました。その後、精密検査のために医療機関を受診することになりました。これが精密検査が大腸の内視鏡、いわゆる大腸カメラで行うことになると思うんですが、そこで、がんらしきものが見つかり、顕微鏡で見たところ、がんだったと。がんじゃなくてもいいのか。組織を採取して、病理診断を行う、ここまでが精密検査なんで、がんのこともあろうかと思いますし、がんじゃないっていうこともあろうかと思いますけども、いずれにせよ精密検査を受けたっていう行為に対して自己負担額として、この場合医療費の2割にあたる7,730円が必要になります。この部分を無料化するということであります。このような場合に申請をしていただければ、自己負担額として、病理検査、生検、細胞を採る検査、それから拡大内視鏡、染める染色、大腸内視鏡、結構ばらしていくと大変なんですけれども、どこまでが必要かっていうことをですね、医師会等とも十分に議論をいたしまして、こういった検査が精密検査として含まれうる、含まれるということを定義して、ここの部分の自己負担額を負担すると、助成すると、そういう考えであります。次の例が乳がんです。市内在住の73歳の方、国保に加入されていて、自己負担割合がこの方も2割であると。横浜市のがん検診の乳がん検診をこの方は受けられました。がん検診、マンモグラフィで行っております。通常1方向の撮影が多いのかなと思いますが、この1方向、一次検査、乳がん検診のマンモで乳がん疑いとなりました。要精密検査で医師から受診を勧められました。後日ですね、もう1回マンモグラフィを撮って、この場合今度は2方向っていうもっと精度の高い撮影になると思いますけれども、それとあと超音波検査、エコーを行って、それから切開、それでも怪しいということで、今度細胞を採って顕微鏡で見る病理診断ですね、そういったところまでが精密検査となります。考えられます。と、定義しました。そこで、この場合の自己負担額が医療費の2割ということで、17,690円となりますが、これを申請していただければ、自己負担額助成することにいたします。こういったイメージで行います。対象となりますのがですね、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、頸がんでありまして、これは横浜市が対策型の検診としてこれまで行ってきているがん検診であります。この胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、頸がんで、市が行っている検診を行って疑いになった場合、精密検査になりますが、その精密検査を助成するということであります。各がん種ごとの精密検査の種類に関してはこちらにおまとめしているとおりであります。対象になるのが、この①②③を満たす方であります。70歳以上の方になります。それから横浜市がん検診を1月1日以降に受けられた方になります。そして対象経費については、考え方については、今お話ししたとおりであります。受付も1月より開始することにいたします。以上が70歳以上のがんの精密検査の無料化に関するご説明です。3点目がですね、これはがん検診を更に受けやすくしたいという思いから検索サイトを11月1日からオープンすることにいたしました。市内にはたくさんの数千もの医療機関があります。数千もの医療機関の中でがん検診を実施しているのが1,400か所あります。しかしながら、この1,400か所で行っているがん検診もクリニックごとにバラバラです。例えば、血液だけ持ってって、血液を預かって、前立腺がんの検診だけやるところ、あるいは前立腺がんだけではなくて他にマンモグラフィがあれば、乳がん検査も行うところ、あるいは内視鏡ができるんであれば、大腸がん検診とか胃がん検診もやってくれるかもしれません。ですので、数千ものクリニックの中で、かつ1,400のがん検診実施医療機関があって、一方でやってる内容がバラバラなので、かなり医療機関の数が多い分、探すのに手間がかかったと思います。市民の皆様にとりましては。ですので、一旦市のほうでこの情報を1,400の医療機関から全て収集しました。これ結構手間はかかったんですけれども、医療局のほうでやってくれてですね、1,400の医療機関から情報を集め一元化してそれをウェブサイトにして検索をできるようにしたというものであります。こちらが実際の検索画面、スマホでの検索画面なんですが、年齢、性別をまず選択することで、受けられる検診が変わってきます。例えば、女性ですと前立腺がんは関係ないというか受けられないので、そういったチェックはできないようになるんですが、そういった性別と年齢で検診の種類が変わっていきます。それから今回ですね、各医療機関の最寄りの路線とか最寄りの駅から行っているがん検診を選べるようにいたしました。63歳で男性で胃がん検診を受けたい、そのときに、横浜線沿線沿いに住んでる、で、しかも何駅に住んでるんだけれども、とかあるいは、この区に住んでる、金沢区に住んでるんだけれども近くに無いとか、そういったところで検索をできるようにいたしました。それから、詳細な条件として、土日祝日に実施しているかどうかとか、あとこれ結構重要だったんですが、夜間に実施しているのか、会社帰りにお勤め帰りに受けられるかどうかとか、あるいはウェブ予約に対応しているかどうかとか、あとは子連れ受診とか、女性の技師さんがマンモのときにいるかとか、そういったことも含めてですね、あと車椅子の受診可能とか、そういったことも含めて1,400の医療機関から情報を収集して、今回一元化したものであります。これを使ってですね、市民の皆様の検診を、施設を探す手間が減ることを期待しております。それから、各医療サイトに行けば、医療サイトにすぐに飛べるようにしてありますので、各クリニックの情報も探せるようにしております。最後は遺伝性乳がん卵巣がん症候群、HBOCの検査の助成についてであります。がんは一般には遺伝はしません。うちはがん家系だとかいう言い方はしますが、一般にがんは後天的な環境要因。喫煙の有無とか飲酒の有無とか食生活とか、あるいは年齢、加齢によるものとか、環境要因であります。しかしながらごく一部のがんは遺伝します。代表的なものが乳がんとか卵巣がんでありまして、こちらは乳がんとか卵巣がんで生涯にですね、がんに罹患するリスクっていうものをまとめています。例えば乳がんなんかですと、生涯を通じて女性が乳がんに罹患するリスクっていうのが11%っていうふうに推計されています。ところが、このHBOCっていう遺伝子が、そういう遺伝子変異を持っているとですね、遺伝子を持っていると、これ推計なんですけども、46%から87%に跳ね上がります。ですので2人に1人から、これ推計が一定してないのは数が少ないのでHBOCに罹る方の数が少ないのでちょっと研究の症例数として少ないことが影響しているんだと思いますが、それでも2人に1人から9割近くが、罹る可能性があるという結果であります。ですので、ある研究によるとHBOCに関する遺伝子を持っていると、10人中9人ぐらいが研究では乳がんを発症していたという結果になります。ほかも卵巣がんなんかもこのHBOCの中に含められるものであります。それから若年でも発症する傾向がありますので、もし乳がんとか卵巣がんになる可能性が高いということであれば定期的にフォローアップをしていくなど、そういった予防を、予防というか対策を講じられますので、このHBOCの検査っていうものが望まれるわけであります。こちらがですね、女性の概要なんですが、親、子、きょうだいがHBOCである。そういう方を対象に遺伝カウンセリングや遺伝学的検査を受ける費用の助成を行います。カウンセリングっていうのは家系図とか書いて、遺伝専門医が家系図とか書きながらHBOCの可能性が高いかっていうのを推定していくんですよね。遺伝学的な検査というのは実際に検査をして、そういう遺伝子を持っているかどうかっていうものを見る検査なんでちょっと質が全然違うんですけれども、それぞれを助成したいというふうに思います。遺伝カウンセリングに関しては大体、いろんなクリニックでの相場っていうのが1万円ぐらいですから上限1万円を限度にして助成をしたいというふうに思います。それから遺伝学的な検査に関しては3万円を上限額にして助成を行う予定であります。今回の助成対象であるHBOCの遺伝学的な検査、こちらの下のほうですね。遺伝学的な検査を実施する市内の医療機関というのは限られています。市内ですとこちらの10病院がHBOCの対象になります。はい。以上、横浜市で行う新たながん検診に対する支援についてご説明をいたしました。以上です。
政策経営局報道課長 矢野:
はい。それではこの件についてご質問をお受けします。いつものお願いになりますけれどもご発言の際はお手元のマイクスイッチのご確認をお願いいたします。ではまず、幹事社からお願いします。
毎日新聞 岡:
幹事社毎日です。お願いします。この前の65歳のがん検診無料化も含めて、市がこのがん対策に力を入れるっていう理由、併せて新たな取組への期待感を教えてください。
市長:
はい。ご質問ありがとうございます。一般にがんは怖いっていうイメージを多くの方が持たれていると思うんですが、一方で、がんは初期の段階に見つけてその時点で手術などの治療を行えば治癒が期待できる病気であります。ですので、早期の発見ということが非常に重要になります。今回、女性、高齢者、がんのリスクが高い人などそれぞれに対して必要な早期発見の取組を支援していきたいと考えております。これまで以上にがん検診を受けやすい環境を整えることで、市民の皆様が更に安心できる環境を充実させたいと思っています。
政策経営局報道課長 矢野:
それでは各社はいかがでしょうか。東京新聞さん。
東京新聞 神谷:
東京新聞の神谷です。このHPV検査なんですけど、リリース資料とかに全国初の取組って書いてあるんですが、国の指針今年4月から変わっていて、導入している自治体既にあるのではと思うんですけれども、どういうところが全国初なんですか。
市長:
このHPV検診の方法導入するには、このHPV検査で陽性になった方のフォローアップ体制の確立が必要になります。このフォローアップ体制の確立を全市的に行えている市町村っていうのはないと思います。
東京新聞 神谷:
陽性だった場合に細胞診をやるっていう。
市長:
フォローアップを行って、1年ごとに次の検診のHPV検診の受診勧奨とか。そういったことを行っていかなきゃじゃないですか。ですので、そのフォローアップ体制っていうのがどこの市町村でも確立されてないんですね。それを本市は実は、去年からこのHPVのがん検診に関して、導入したほうが良いというふうには考えてました。というのは、世界で標準的に用いられている方法ですので、導入したほうが良いと。しかしながら、国として対策型検診として提示されていませんでした。当時は。ただ、今回対策型検診の中に導入される可能性を早くに察知してましたので、それだったら早く導入に向けて準備を進めようということで、他の市町村に先駆けて準備進めてきた経緯があります。ですので1月1日という段階で全国に先駆けて導入ができる準備ができました。
東京新聞 神谷:
単独法導入すること自体は他でもある、今年からやってるとこ。
市長:
単独法自体はあるかもしれません。ただその後のフォローアップ体制まで、つまり集団型検診として行うものですので、市全体として、それを導入しフォローアップ体制が確立されてない限り、この対策型検診、市町村の検診でHPV検査をどうやってますって言えないじゃないですか。個別のクリニックに行って、このHPV検査やってるところっていうのは神谷さんおっしゃるとおり、確かにあると思います。ただその後フォローアップを個別のクリニックでやってるかというとそれはクリニックになりますので、やってるとこでやってないとこがあるんじゃないかなと思いますが。
東京新聞 神谷:
フォローアップは何を指すんですか。
市長:
受診勧奨をしてもう1回来てもらうことです。主には。
東京新聞 神谷:
それを市としてやるっていうことで。
市長:
はい。ただ、転居なんかも発生すると思いますし、ちょっとやっぱり簡単ではないんですよね。それから特に本市の場合は対象となる方が多いので、その辺の難しさもあるんですけども。ただ準備を早くから進めていたこともありまして導入することにいたしました。
東京新聞 神谷:
そこの部分で初の取組というふうに言っているっていうことで。
市長:
全国で市町村として対策型検診として導入するのが初めてということですね。
東京新聞 神谷:
導入自体ではないんですよね。
市長:
検診としての導入だから良いんじゃないですか。導入で。個別のクリニックでやるやらないっていうのはもちろんあると思うんですけど、市町村として、この対策型検診、がん検診を行うっていうのが初めてだと思います。
東京新聞 神谷:
また細かいことは後で所管に聞きます。ありがとうございました。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょうか。神奈川新聞さん。
神奈川新聞 武田:
神奈川新聞武田です。70歳以上の方の精密検査の部分なんですが、これ例えば現状で費用の負担とか、負担に思われて精密検査を受けていない方っていうのは一定数いらっしゃるっていう形なんでしょうか。
市長:
数がどれくらいかっていうのは、十分に把握できていませんが、結構いらっしゃると思います。
神奈川新聞 武田:
ありがとうございます。そうすると一定数いるであろう精密検査を受けていない方が受けやすくなるっていう意味合いがでてくると。
市長:
そうです。はい。
神奈川新聞 武田:
分かりました、ありがとうございます。それとすみません、今の東京新聞さんの質問と重なってくるんですが、今、元々HPVの単独法のほうは導入の話があって、自治体として導入するっていうのが。
市長:
初めて。
神奈川新聞 武田:
初めてになると。各医療機関がやるケースというのはあるけれども、という。
市長:
ただ、それもそこまでないと思いますよ。かなりこのHPV検診に関しては、例えばクリニックからしますと、そこでもしポジティブに出た場合、1年ごとのフォローアップっていうことも必要になってきますし、またネガティブになると今度は5年後になってしまいますので、クリニックとしてHPV検査の単独法を導入しているところはかなり限られていると思います。ほとんどないんじゃないですか。
神奈川新聞 武田:
ありがとうございます。最後にもう1点、受診勧奨の部分なんですが、それぞれの医療機関がデータをとってマイナスであれ、プラスであるような方に1年後に勧奨するのか、あるいは5年後に勧奨するのか、これを市として全体で管理するという話ですか。
市長:
おっしゃるとおりです。そこの管理が求められるというのが本質です。
神奈川新聞 武田:
そうすると市として、管理できるから取りこぼしがなくなるというか、全体の方にちゃんと行き届くようになるよと。
市長:
はい。
神奈川新聞 武田:
分かりました。ごめんなさい、それぞれの1月からスタートする形になると思うんですけど、基本的には来年以降も続けていく。
市長:
はい。もちろんです。
神奈川新聞 武田:
予算規模としてはどれぐらいになるっていうのありますか。
市長:
HPV検診に関しては分かりますか。すみません、また後ほど。はい、すみません。
政策経営局報道課長 矢野:
その他、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それではこの件の質疑は以上で終了します。事務局、入れ替わりますので少々お待ちください。
2.その他
政策経営局報道課長 矢野:
それではこれより一般質問に入ります。複数ご質問がありましたら、まとめてご質問頂ければと思います。まず、幹事社からお願いします。
毎日新聞 岡:
幹事社、毎日です。よろしくお願いします。教育委員会の組織改革についてお伺いします。一連の不適切事案が発覚してから半年余りが経過しました。市長から見て組織は変わったというふうに見えますでしょうか。具体的な事例も含めて、教えてください。
市長:
はい。変わらなければいけないと思います。重要なのは子供たちの目線にとって考えられる、そういう教育委員会になることです。そういう対策を講じられるようになることです。徐々に方向性も見えてきております。短期間で組織改革を行えることと、短期間では難しいこととがありますが、引き続き、スピード感を持って、教育委員会が変わっていくことをしっかりと後押ししていきます。具体的には、校内ハートフルの全中学校の全校設置を行いますし、また、来年度に向けて新たな組織改編を行うことは、既に議会のほうでも報告したかと思います。組織改革の方向性について、ご報告したとおりであります。また、26万人の子供たちのデータを活用する、そういうデータサイエンス的な取組ということを通じて、クリエイティブな、教育の質を高めていくっていうクリエイティブな方向性から、それから可能であれば、いじめの予兆を見つける、サインを見つける、シグナルを見つける、そういったことも可能かどうかっていうことを、このデータから探せるか、そういったことを検討していきたいと思います。そういった改善の方向をですね、今、教育委員会のほうで作っていっているというふうに感じております。
毎日新聞 岡:
関連で、過去10年間の自死事案に関する弁護士チームの検証があったかと思うんですが、その結果を踏まえて、そこで指摘のあった数件の対応について検討状況を教えていただければと思います。
政策経営局報道課長 矢野:
所管局から。
教育委員会事務局人権健康教育部長 住田:
教育委員会事務局人健康教育部長の住田です。ただ今のご質問にお答えします。現時点でですね、重大事態調査に、もう即座に入っているというものはございませんけれども、第三者である弁護士の助言、指導を受けながら、ご家族の心情に最大限配慮して丁寧にですね、やりとりを進めている状況でございます。
毎日新聞 岡:
まだ決まっていないということですか。
教育委員会事務局人権健康教育部長 住田:
そういう丁寧に進めている状況ですので、今後、そういったこともあるかもしれない、あると思っております。
毎日新聞 岡:
これ、いつぐらいを目途にとか、そういうのはないんですか。
教育委員会事務局人権健康教育部長 住田:
公表という意味でしょうか。
毎日新聞 岡:
方針決定。
教育委員会事務局人権健康教育部長 住田:
それは進めていく中でですね、第三者等によって我々も判断していきますので、いつというのはちょっと今の時点で示せませんけれども、公表については現在は予定はしておりませんけれども、ご遺族の意向や調査内容を踏まえて判断してまいりたいというふうに思っております。
政策経営局報道課長 矢野:
はい、それでは各社いかがでしょうか。時事通信さん。
時事通信 廣野:
時事通信です。昨日発表になりました衆院選の期日前投票の状況について伺います。横浜市では前回衆院選の同時期と比べて期日前投票した人が前回に比べて4万人少なくて、割合でいうと31%減少しています。市内だと瀬谷区以外、全ての区で前回を下回っている状況なんですけども、市長の受け止めをお願いします。
市長:
はい、そうですね。4万人程度の減少になっているというふうに私も報告を受けております。今回、衆院の解散から、公示までの期間が短かったということが影響している可能性はあろうかと思います。民主主義の基盤になる選挙でありますので、市民の皆様が、個々の1票ですね、使って積極的に選挙権を行使されるようですね、切にお願いしたいと思いますし、本市としても、様々な媒体を通じて、選挙への投票というものを促していきたいと思います。
時事通信 廣野:
ありがとうございます。関連して入場整理券がまだ届いていないっていう方であったり、届いていないので選挙に行っていないっていうような人が一定数います。整理券がなくても投票はできるんですけども、まだそのことの周知が広まってないなというふうに思うんですけれども、市長、そのあたりはいかがでしょうか。
選挙管理委員会事務局選挙部長 石川:
ご質問ありがとうございます。選挙管理委員会事務局選挙部長石川です。ご質問の、投票のご案内のお知らせにつきましては、今回の選挙では、短期間の中でお届けが遅くなりお問い合わせも多数頂いております。大変ご心配ご不便をお掛けしていること、改めてお詫び申し上げます。投票のご案内につきましては、10月15、16日両日に郵便局に搬入して現在まで配達を進めているところでございまして、明日10月23日を目途に配達を完了させる予定となっております。なお、これはホームページ等でもご案内を申し上げているところですが、現在行っている期日前投票や、10月27日の投票日の投票は、投票のご案内をお持ちいただかなくても投票することができますので、お手元にまだ届いていなくてもご都合に合わせて投票に是非行っていただければと思います。選挙管理委員会としてもそうした周知を引き続き積極的に努めてまいりたいと思います。
時事通信 廣野:
ありがとうございます。以上です。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。産経新聞さん。
産経新聞 橋本:
産経新聞の橋本です。よろしくお願いします。バスケットボールBリーグの横浜ビー・コルセアーズが2026年シーズンからのホームアリーナを、横浜国際プールではなくて横浜BUNTAIに変更しましたけれども、これはもう、市も同意して行ったことなんでしょうか。
政策経営局報道課長 矢野:
所管局から。
にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興部長 熊坂:
質問ありがとうございます。スポーツ振興部長熊坂でございます。今回これにつきましては、ビー・コルセアーズ側から横浜BUNTAIをホームアリーナとして使用したいという申請があって、私ども指定管理者のほうとも確認をして問題がないということを確認できたので、私どものほうで許諾をしたという形になってます。
産経新聞 橋本:
そうすると、これ横浜国際での試合数が減るっていうことですか。
にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興部長 熊坂:
今回出たのはBプレミアの申請のことだと思います。これについては2026年からのスタートになりますので、そこからはメインアリーナをホームアリーナ、ごめんなさい、BUNTAIをホームアリーナにするということで、まだ具体的に試合数がどうだとかというところまでは詰まってませんので、今現時点ではちょっとお答えできかねます。
産経新聞 橋本:
そうすると、現在出てる横浜国際の再整備計画案でメインプールをなくす理由として、スポーツアリーナの利用者のほうがメインプールよりも利用者が多いっていうとこが1つの根拠として挙げられているんですけれども、それが数年後に変わる可能性があるという、そういうことでしょうか。
にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興部長 熊坂:
今回の国際プールの再整備につきましては、あらゆる興行に対応できるような形にしていこうということも含めて、以前から市長もご返答させていただいていますけども、より多くの市民の皆様に喜んでいただける。インクルーシブとか、そういった視点も踏まえてですね、持続可能な施設にしていこうということで検討していますので、必ずしもその方向に変わりはございません。
産経新聞 橋本:
そういう方向性はもう市長から何度も伺ってるんで理解してるんですけども、私が聞いているのは、今回そのメインプールをなくす理由として、令和4年度の利用者数がスポーツアリーナを使った人のほうがプールを使った人よりも多いと。だからなくすんだというのが1つの理由として挙げられているんですけれども、これ今あれですよね、スポーツアリーナの利用者の多くは、ビー・コルセアーズの試合を観に来た人だと聞いているんで、それが試合数が減ったらもともとプールをなくそうとしている理由がひっくり返るんじゃないかと。
市長:
橋本さん、今まだ試合数云々の話は分かんないって言ってるじゃないですか。
産経新聞 橋本:
いや、そうすると、分からないことを前提に計画案を出すというのもおかしな話ではないでしょうか。
にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興部長 熊坂:
こちらにつきましては、必ずしもビー・コルセアーズのために整備をするわけではないので、もちろんその利用者数の現状の中ではありますけれども、いろいろな興行に使えるものにしていくという中で考えてますので、ビー・コルセアーズの使用云々ということだけを捉えてこの整備計画がどうのこうのということではないと私は認識してます。
産経新聞 橋本:
それと今これBUNTAIがホームアリーナになっても支障がないっていう話があったんですけども、今回いろいろと水泳団体以外の競技団体の話を聞いてもですね、そもそも体育館の数が少ない、大会ができる施設が足りなくてですね、本来は横浜でやるべき大会を他の自治体の会場を書いているようなところは他にもあるという話を。
市長:
水泳ですか。
産経新聞 橋本:
いや、水泳以外です。水泳以外でのそういう競技団体があるという話は聞いてるんですけども、そうするとこれBUNTAIに今度ビー・コルセアーズが来た場合に、今BUNTAIを使っている競技団体には影響はないっていうことなんですか。
市長:
ビーコルの話とかとすぐにくっつけたがっていますけれども、大切なのは、より多くの市民の皆さんに使っていただける、喜んでいただける、そういう施設をつくることであります。だから、特定の団体に対してどうこうとか、あるいはBプレミアですか、ができて試合数がどうこうとかそういう話ではなくて、やっぱり市民意見の結果も踏まえてより多くの皆様に使っていただける、そこにインクルーシブな視点も踏まえて再整備をしていく、ここが肝要だと思います。
産経新聞 橋本:
すみません、ビー・コルセアーズという名前を出したのはあれだったかもしれないですけども、要はプロスポーツの興行が来ることによって、今使っている市民が出場する大会のほうが圧迫される心配は、今の話だとないっていう理解でよろしいんですか。
市長:
そういった市民の方に不便をかけるようなことっていうのは、市民の税金を使って整備するものでありますので、市民の皆様が不便にならない、できるだけの対策を講じたいと思います。
産経新聞 橋本:
分かりました。ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。神奈川新聞さん。
神奈川新聞 武田:
神奈川新聞武田です。衆院選の話に戻るんですが、すみません、他の自治体とかですと首長が応援演説に入ったりっていうケースがあるかと思いますが、市長、特に来てくださいみたいな依頼っていうのはある。
市長:
特に応援等に行く予定はございません。
神奈川新聞 武田:
今のところないっていう形ですかね。
市長:
応援等に行く予定はございません。
神奈川新聞 武田:
分かりました。ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他よろしいでしょうか。それでは以上で定例会見終了します。ありがとうございました。
このページへのお問合せ
政策経営局シティプロモーション推進室報道課
電話:045-671-3498
電話:045-671-3498
ファクス:045-662-7362
メールアドレス:ss-hodo@city.yokohama.lg.jp
ページID:378-268-662