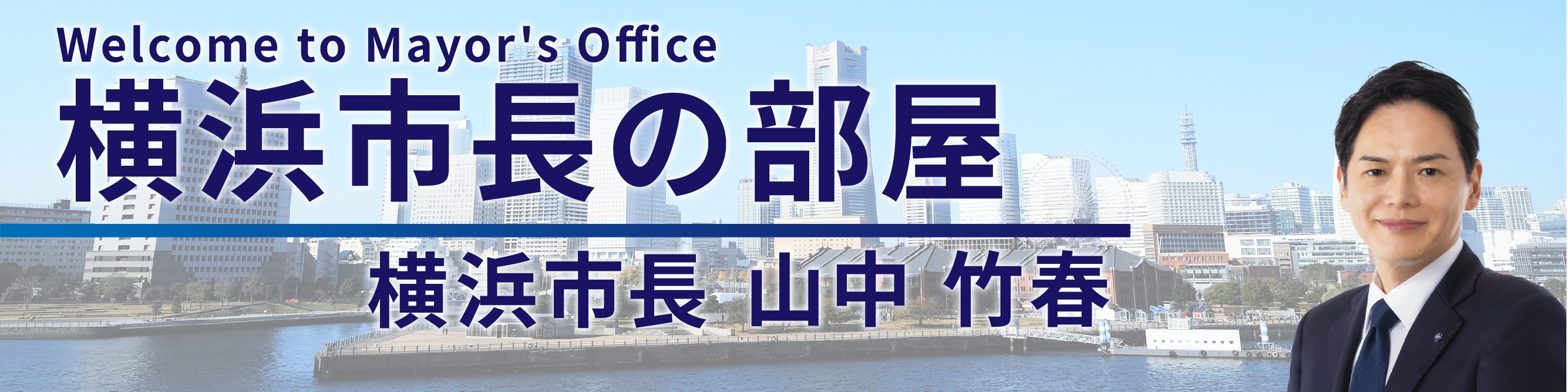ここから本文です。
- 横浜市トップページ
- 市長の部屋 横浜市長山中竹春
- 定例記者会見
- 会見記録
- 2024年度
- 市長定例記者会見(令和6年12月4日)
市長定例記者会見(令和6年12月4日)
最終更新日 2024年12月6日
令和6年12月4日(水曜日)11:00~
報告資料
会見内容
1.報告
令和7年「二十歳の市民を祝うつどい」式典テーマが決定しました!
ゲスト:令和7年二十歳の市民を祝うつどい実行委員
※敬称略
政策経営局報道課長 矢野:
はい、それでは定例会見を始めます。市長お願いします。
市長:
はい、今日は来年の二十歳の市民を祝うつどいについてご報告いたします。まず概要なんですが、令和7年の1月13日に決まりました。成人の日です。横浜アリーナ、去年と同じ場所で行います。当日はライブ配信も行います。対象者は約3万5千人になる予定であります。開催方法なんですが、令和7年の式典は2回に分けて開催します。コロナ前はずっと2回で開催しておりましたが、ここ最近は2回だったり、3回だったり、4回、5回だったり、分散開催を行っておりましたが、今回は5年ぶりに2回の開催となります。参加にあたりましては、事前申込制をとっております。対象者の皆様には、既に案内状を順次送り始めているところでありまして、案内状に記載の二次元コードからアクセスをしていただいて、事前にお申込みをいただく形式になっております。各回の式典時間と対象の区はご覧の通りであります。続いて、式典の企画に関わって、携わっていただいている実行委員会について、ご紹介をいたします。実行委員会は公募によって10名の二十歳の市民の方々で構成されています。この実行委員会は、主催者の一員として今年の5月から活動を行っていただいておりまして、概ね2週に1回程度会議をしていただいて、例えば横浜への愛着を深めるための企画の立案とか、あるいは式典当日の司会進行、二十歳の誓いなどの内容を考えていただいたり、あるいは、これから発表あります、式典テーマの考案を行っていただきました。式典テーマでありますが、令和7年の式典テーマは「はじまり」と決まりました。本日は、実行委員会から実行委員長の野本 優菜様、実行委員の佐藤 快飛様のお二方にお越しをいただいております。この式典テーマに込めた思いや、準備をしていただいている実行委員企画につきまして、お話をいただきたいというふうに思います。それでは、野本さん、佐藤さん、よろしくお願いいたします。
二十歳の市民を祝うつどい実行委員会 野本 様:
令和7年二十歳の市民を祝うつどい実行委員長の野本優菜です。
二十歳の市民を祝うつどい実行委員会 佐藤 様:
二十歳の市民を祝うつどい 実行委員の佐藤 快飛です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
二十歳の市民を祝うつどい実行委員会 野本 様:
それでは、私のほうから令和7年の式典テーマ「はじまり」に込めた思いについてお話しさせていただきます。2004年、2005年生まれの私たちは青春の最高潮といえる高校時代を、新型コロナウイルスによるパンデミックの中、過ごしてきました。制限の多い生活の中、多くの苦難や困難に立ち向かうことがありましたが、周囲の方々の支えを借りて、一歩ずつ前に進むことができました。2024年の今、コロナウイルスの影響も少しずつ少なくなり、社会全体が新たなスタートを切ったかのように思われます。そして、この年に二十歳という節目を迎える私たちも、新たな将来に向かって一歩ずつ進みたい、新たな始まりを迎えたいという思いから、このテーマに設定いたしました。それでは、次のスライドにお願いいたします。
二十歳の市民を祝うつどい実行委員会 佐藤 様:
私のほうからは、実行委員が当日の式典に向けて取り組んでいる実行委員企画について、ご説明させていただきます。私たち実行委員は、二十歳の皆さんに配布する記念冊子の数ページの作成をさせていただいております。その中で、私たちが生まれて20年間で印象に残っている横浜や日本の出来事を年表にまとめています。また別のページで、私たちが育ってきた横浜にルーツを持つ、お食事とかだったり、お店についてご紹介しているページも作成しています。この機会に、自分たちの今までの人生を振り返って、地元の横浜に、もっと好きになっていただければなと思います。また、式典の当日にアリーナで流す動画も作成しています。動画の内容は横浜で生きてきた私たちならきっと共感できるだろう、横浜あるあるというものと、もう1つ、社会に出た一人の成人の人の活躍するMV風の動画を、メッセージを込めて作っております。これから社会に出て辛いことがあっても、かけがえのない人たちと支え合って頑張っていこうっていうメッセージを込めています。最後に、二十歳の市民を祝うつどい実行委員が、同年代の方々に読んでほしいおすすめの本を厳選したものと、実行委員以外にも著名人の方々からも、おすすめの本をご紹介いただいているページも作成しています。私からのご説明は以上になります。
市長:
はい、野本さん、佐藤さん、ありがとうございました。実行委員会の皆さんの柔軟な発想力によって、新しい門出に相応しいイベントになることを期待しております。こちらに関する説明は以上となります。
政策経営局報道課長 矢野:
はい、それでは、この件のご質問をお受けします。いつものお願いになりますけど、ご質問の際はマイクのスイッチのご確認だけ、お願いいたします。では、まず幹事社からお願いします。
日経新聞 松原:
日本経済新聞の松原です。お話、どうもありがとうございました。まず市長にお伺いしたいのですが、率直にこの二十歳の皆さんにお祝いのコメントというか、皆さんに向けてコメントをお願いいたします。
市長:
はい、今回の二十歳の市民を祝うつどいにつきましては、約3万5千人もの方々がいらっしゃいますので、3万5千人もの方の新たな「はじまり」になる素晴らしいイベントになることを期待しております。二十歳を迎える皆さんは、これから自らの行動に責任を持ちつつ、自由な発想で挑戦をしてほしいと思っています。以上です。
日経新聞 松原:
ありがとうございます。もう1つ、この横浜市も少子高齢化から、多分に漏れず進んでいるわけですが、若い人に選ばれ続けるために、横浜市として何か、どのような取組を今後強化していきたいというふうにお考えでしょうか。
市長:
はい、ありがとうございます。若い人達が、それぞれが可能性を感じられる街にしていくことなんじゃないかなと思います。若い方それぞれやりたいことが様々あると思います。学業に邁進している方はそのまま学びっていうものを極めたいのかもしれませんし、それから人によっては社会、経済に関心がある方もいらっしゃると思います。他にも、ファッションとか食とか、そういったことに関心がある方もいらっしゃると思います。いろいろな関心の持ちようがあろうかと思いますが、いろいろな方面について可能性を感じられる、そういう街が素晴らしいというふうに思っています。
日経新聞 松原:
ありがとうございます。実行委員のお二人にもコメントをお願いしたいのですが、まずはこの二十歳を迎えて、何かこう挑戦してみたいことみたいなものが、ご自身の「はじまり」というか、あれば教えてください。
二十歳の市民を祝うつどい実行委員会 野本 様:
ご質問ありがとうございます。私のほうからご回答させていただきます。そうですね、二十歳を超えて挑みたいこととしましては、私自身、今、大学に通っておりまして、今月の12月で二十歳を迎えるんですけども、この1年間を通して、やはり自分自身が社会に何に貢献できるのか、社会に出るにあたって、自分がどのような形で大好きな横浜市に貢献することができるのか、この二十歳のつどいの実行委員になりましたのも、横浜市に貢献をしたい、お世話になった方に感謝を伝えたいという思いでしたので、横浜市にどのような形で貢献できるのかについて、今後1年、考えていきたいと思っております。
二十歳の市民を祝うつどい実行委員会 佐藤 様:
僕のほうから挑戦したいことということで、僕にとってはこの二十歳の市民を祝うつどいの実行委員がすごい自分の中で挑戦だなと思っていて、自分の人生の中ですごい明確な成功体験っていうのがあんまり思い当たらなくて、この機会に、一発、二十歳の市民を祝うつどいを絶対成功させて、僕の中で、僕の人生の中で、成功体験として刻みたいなと思っております。頑張ります。
日経新聞 松原:
楽しみにしてます。ありがとうございます。幹事社から以上です。
政策経営局報道課長 矢野:
それでは各社いかがでしょうか。産経新聞さん。
産経新聞 橋本:
産経新聞の橋本です。よろしくお願いします。お二人にお伺いしたいんですけれども、改めてになって恐縮なんですけれども、コロナ禍で制限の多い生活、高校生活だったということなんですけれども、どういうことが一番辛かったのかということと、それをどうやって乗り越えたのかを教えていただけますでしょうか。
二十歳の市民を祝うつどい実行委員会 野本 様:
ご質問ありがとうございます。私高校生活の頃に生徒会活動を中心に頑張らせていただいておりました。生徒会活動に入った理由としましても、高校1年生の時にちょうどコロナウイルスによって学校へ通えなくなる時期、オンラインで授業を受ける期間というものがあり、その中でやはり友達との距離があいてしまう。実際に人と会えないという体験をして、何かしら人とのつながりを持てるようなことをしたいと思い、生徒会に入りました。生徒会長に就任したんですけども、生徒会長に就任した高校二年生の時も、やはり校外に出て何かを活動する校外の地域に貢献をするといった活動ができませんでしたので、やはりその点に私は考えていたのが、地域に貢献をしたい。外に出てボランティア活動などに取り組みたいということでしたので、自分ができないこと、やりたくてもできないことというものにとてももやもやした気持ちを抱えておりました。ただ、その時に学校の先生や友人に声をかけていただいた言葉として、今できないことに悔やむのではなく、今できることに着目をして取り組んだらどうかというアドバイスをもとに、学校内の問題を解決する方向に私の生徒会の指針をチェンジして、なんとか生徒会長として誇りを持った活動をすることができました。
二十歳の市民を祝うつどい実行委員会 佐藤 様:
私が高校生の時に辛かったことは、文化祭とか体育祭とか修学旅行っていうのがもう一気になくなっちゃったことが結構辛くて、でも最後の年はちょっとずつイベントとかも回復してきてできるようになったのですけれど。どう乗り越たかっていうと、友達とせっかく、せっかくって言ったら失礼ですけど。この機会に、部活とかもちょっとお休みが増えたりしたので、いろんなところに遊びに行ったり、友達と支え合ってっていうのが一番大きかったかなと思います。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それではこの件の質疑は以上で終了します。引き続きフォトセッションに移りますのでどうぞ前のほうにお越しください。
2.その他
政策経営局報道課長 矢野:
はい、ではこれより一般質問に入ります。複数ご質問ありましたらまとめていただければと思います。ではまず幹事社からお願いします。
日経新聞 松原:
先週末にベイスターズの日本一のパレードがあったんですが、今回その経済効果ももちろんなんですけれども、市民のロイヤリティの向上であったりとか。あとは街のブランド力の向上にも大きく貢献したと思っております。今後市としてこうしたスポーツ興行、あるいはスポーツに限らず、なんかその企業との連携等をどのように進めていかれるのか。お考えがあればお聞かせください。
市長:
企業というのはスポーツ、プロポーツの企業さんということですかね。
日経新聞 松原:
はい。
市長:
ご質問ありがとうございます。まず土曜日にパレードを行いまして、1.5キロっていう、短い距離に30万もの方がお越しになられたということで、非常に横浜挙げてベイスターズの日本一をお祝いできたというふうに思います。ファンの皆様、市民の皆様と一緒に喜びを分かち合うという機会になったというふうに思いました。また、横浜市として、関係機関とも調整をして街をブルーにライトアップいたしまして。SNSなどでもかなり取り上げていただいたというふうに聞いているんですが。夜までの回遊人口っていうのもかなり増えたというふうに聞いておりますし、商店街の方々などからもですね、普段より人通りが多いと。売上にもとても良い効果得られたと。そういったお声を頂戴しております。今後もですね、プロスポーツ、横浜というのはプロスポーツチームが大変多い都市であります。いろいろなチームがですね、頑張っておられる中で、こういった優勝などそういった節目をですね、市民の皆様とお祝いをする機会を作れるっていうのはとてもいいなというふうに思います。先ほどロイヤリティという言葉出ましたけれども、やはりスポーツ、一体感を持たせてくれると思うんですよね。うちの街のチームが日本一になった。そういったことでシビックプライドっていうものも作られると思いますし。まあ、その証拠が30万人、1.5キロの沿道に30万もの方がお集まりになられたっていうことなんじゃないかなというふうに思います。
政策経営局報道課長 矢野:
はい、それでは各社いかがでしょうか。産経さん。
産経新聞 山澤:
すみません。産経新聞の山澤と申します。交通局の賃上げについて伺います。バス運転手の不足に対する対策として最大級のベースアップを行うということを発表されましたけれども、ドライバー不足の現状を今現在市長としてどういうふうに見てらっしゃるか、また賃上げをしても、人口減少が進む以上、民間との奪い合い、他業種との奪い合いとも続くわけで、なんかしら抜本的な対策も必要になっていくのではないのか。職場の魅力をどうアップしていくのか。自動運転などの新技術も必要ではないか。更にはその先には外国人を導入するみたいなことも議論になると思いますけども、市長のお考えをお願いします。
市長:
はい、ご質問ありがとうございます。まず、全国的にベアの必要性が今叫ばれていること、ベースアップの必要性が叫ばれているところですが、このバスの乗務員さんのベースアップについてもどんどん改善をしていくべきだというふうに考えております。前回、5月の募集の際だったと思いますけれど、5月だったと思いますけれども。ベースアップ、処遇の改善を行った結果ですね、多くの方の採用に結びつきました。で、今回も給与の大幅なベースアップやですね。行うことで新しい人材を確保して、市民の皆様の足を守っていきたいというふうに思っております。その他、若年層の応募者の応募を強化したいというふうに思いますし、それに向けて交通局の職員自らがこういうものなんだというリアリティのある職員PRを積極的に行っていく予定になっています。
産経新聞 山澤:
分かりました。ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょうか。朝日さん。
朝日新聞 良永:
朝日新聞の良永と申します。次の市長選についてお伺いをします。先週、後援会の設立パーティーがありまして、主催者発表で千人もの参加があったということなんですけれども、受け止めと、今お話できる範囲で今後の方針あれば教えていただきたく思います。
市長:
ご質問ありがとうございます。私の市政を応援してくださる方が後援会を作られ、またあのような会を開いていただいたことは大変ありがたく思っております。残りの任期、しっかり頑張れというメッセージだと思いますので、残された任期、一日一日しっかりと頑張りたいというふうに思います。
朝日新聞 良永:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょうか。東京さん。
東京新聞 神谷:
東京新聞の神谷です。横浜国際プールに関してなんですけれども、日本水泳連盟のほうから会長の面談の要請があったと思うんですけど、結局市長のほうは受けられないというふうに答えがあったというふうに連盟から聞いてるんですが、あんまりその答え、理由が明確ではないということだったんですけれども、それは市長として、例えば特定の利用団体とはこう全部受けないみたいな方針なのか、その辺のちょっと理由を教えていただきたいんですけれども。
市長:
所管同士、所管局と関係団体の実務レベルで話し合ってますからね。それで別にトップが話し合うっていうのもあってもいいと思いますけど、事務レベル、所管レベルで丁寧に意見交換進めていますので、それに、推移を見守っていたという次第です。
東京新聞 神谷:
これは市長として、所管レベルで話を進めていくべきことだというふうに。
市長:
丁寧に意見交換を進めているというふうに承知しておりました。
東京新聞 神谷:
先方はトップ同士でお話をしたいという要望があったと思うんですけど、それに応じていない理由っていうのは。
市長:
だから今申し上げた通りです。
東京新聞 神谷:
それはトップではなくて、所管のほうで細かいところも話し合ったほうがいいという。
市長:
丁寧に所管レベルで、事務レベル、担当者レベルですね。丁寧にお話し合いを進めていたというふうに承知しております。
東京新聞 神谷:
それは何か、先方としては、ちょっとそれでは、ちょっと納得しないところもあったようなんですけれども。
市長:
そうなんですか。でも今、丁寧に所管で意見を、進めていると思いますが。
にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課長 高梨:
はい、ご質問ありがとうございます。スポーツ振興課長高梨と申します。素案策定後にですね、市民意見募集を行っておりまして、通年スポーツフロア化に対するご意見が多かった。そういったことを踏まえると、今回の、その結果を尊重しなければいけないっていうふうに考えています。その中で面会を行って、プールの存続の要望をいただいても、実際プールを残すのは難しいという回答をしなければいけないというふうに事務局のほうでは考えています。ご要望と回答が平行線になってしまうような懸念がある状況ですので、要望いただいた団体さんのほうには面会は難しいが所管局と日本水泳連盟さんで調整をさせてほしいという形で県の水泳連盟さんにこれまでもお願いをさせていただいており、そのように調整をさせていただいていたという次第でございます。
東京新聞 神谷:
そうすると、その今の理由っていうのは、先方にもそのままお伝えはしているんですか。
にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課長 高梨:
はい、お伝えをしています。
東京新聞 神谷:
要望がされても、市としてはお答えするのが難しいということもはっきりお伝えをしているっていうこと。
にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課長 高梨:
はい、はっきりお伝えをしております。
東京新聞 神谷:
分かりました。ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょうか。神奈川新聞さん。
神奈川新聞 武田:
神奈川新聞武田です。2点お伺いします。今、朝日さんからもあった後援会の関係で、まず1点なんですが、改めて後援会が発足して、後援会の役員の方々からも、来年の市長選に向けた期待感がはっきりと示されたかと思うんですが、来年の市長選に向けた態度を、いつ頃表明されるか、時期的な、例えば年内の可能性があるのか、来年以降で考えていらっしゃるのか、その時期感的なものがあれば伺えればと思います。
市長:
はい、まず再三申し上げていますが、残された任期をしっかりやることだけを考えていると申し上げております。ですので、それに向けて今、日々頑張っているところでありますので、出馬云々等は、今、考えられる状況ではありませんので、お答えすることは特にございません。
神奈川新聞 武田:
分かりました、ありがとうございます。あともう1点、国際プールのほうですが、今、検討の案として補助プール、サブプールの横に補助プールを作るという案が出てきてるかと思うんですが、これまで再整備案で示されているものが、床を転換していく再整備と、体育館に一本化する、プールを廃止するパターンですと、床転換よりもプール廃止するほうが20億円高くなると。ただ、ランニングコストが毎年市の負担としては2.1億円ずつ安くなっていくから、回収が可能であるよ、というものが示されているかと思うんですが、改めてその仮設プールが、仮に今後できる場合のその費用部分、教えていただける範囲で伺えればと思います。
政策経営局報道課長 矢野:
所管局から。
にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課長 高梨:
はい、ご質問ありがとうございます。今、原案策定に向けていろいろ検討させていただいている最中でございます。その中でいろいろ検討している案でございまして、報告ができる時期になりましたら、ご報告させていただきたいと思いますが、現状で今、経費も含めて試算をしている最中でございます。
神奈川新聞 武田:
ありがとうございます。で、全体のその再整備費用そのものっていうものも、まだ明確にはなっていないところかと思うんですが、そのあたりも含めて原案と一緒に出すイメージなのか、あるいは案が出てきた後に揉んで原案を出すような流れなのか、その辺りも伺えればと思います。
にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課長 高梨:
はい、ありがとうございます。総整備費を出すかどうかっていうのは今後、委託、委託というか、素案ではPFIという形で言ってるんですけど、その要求水準書を作るにあたっての金額が先に出てしまうというところもありますので、そこが原案を出すときにどういうふうに出していくかっていうのは、今後検討していきたいと思います。
神奈川新聞 武田:
ありがとうございます。最後にもう1点、その市民意見を出した段階ではプール廃止するという市の方向性と、今のサブプールで行きますよ、サブプールを回収しますよっていうものが、もしかすると今、サブプールで大会を存続していくために、25mのプールもう1個作ろうという案が出てきたかと思うんですが、これも踏まえたもう一回市民意見を募るような格好になるのか、あるいはもうこれは、あの段階で市民の意見を募って、これはこれでもう原案としていくのか、今後のその議論の過程と、いつ頃原案を出していくか、早ければ12月っていう今月の4定の可能性あるかと思うんですが、その議論を含めていくのか、あるいはもう原案ボーンと出てくるのかっていう辺りのお考え伺えればと思います。
にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課長 高梨:
はい、現状ではですね、市民意見募集と団体さんからいただいた意見を踏まえて様々な検討しているという最中でございます。その意見を反映した原案を今後出していきたいと考えておりますので、市民意見募集を再度やるということは特段考えておりません。また原案に関しましては、以前にもスケジュールを出させていただきましたが、12月以降で考えているという形でございます。以上です。
神奈川新聞 武田:
分かりました。ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょうか。産経さん。
産経新聞 橋本:
産経新聞の橋本です。またプールの関係で恐縮なんですけれども、大体今の話とほぼ被るんですけれども、今回のその再整備計画案が令和3年度の包括外部監査で費用対効果の点が指摘されたことが1つの原因になってるかと思うんですけども、今回、補助プール建設とかという話が出てきてですね、包括外部監査の指摘というのは、原案に反映されるのか、それとも市長はもう再三、市民の希望が多く上がってきたものをつくることが必要だっていう点をここ何回か指摘されているんですけども、一方の費用対効果のところはどうしていくお考えなのか。もうちょっと多分、次の定例会見の前に原案出るかもしれないんで、お願いします。はい。
にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課長 高梨:
はい、ご質問ありがとうございます。財政的な費用対効果というのも、もちろん無視して新たに追加で作るということは考えられませんので、そういった部分も含めて現在いろいろな検討しているという最中でございます。全く無視するという形では考えておりません。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょうか。神奈川新聞さん。
神奈川新聞 加地:
神奈川新聞の加地です。救急医療体制の逼迫への対応についてお伺いします。逼迫防止などを目的に三重県の松阪市だったり茨城県のほうで、搬送後に、例えば擦り傷とか微熱で呼んで搬送された後に、医師によって軽症と判断された場合に、選定療養費、お金を取るという運用が始まっています。逼迫を防ぐ1つの手法だとは思うのですが、これに関する市長のお考えあればお伺いします。
市長:
はい、ご質問ありがとうございます。選定療養費という形で保険診療とは別に徴収するという方法で過剰な救急車の出動を抑えようというのが、行っている自治体の意図だというふうに承知しております、そういったことに関しては、現時点では本市では検討はしておりません。他都市のそういった動向を注視しながらですね、また本市として、そういった救急出動に馴染まない要請も確かにあるのだと思いますので、そういった要請につきましては、控えていただく旨の繰り返しの要請をしていくことを考えています。
神奈川新聞 加地:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。では以上で定例会見終了します。ありがとうございました。
このページへのお問合せ
政策経営局シティプロモーション推進室報道課
電話:045-671-3498
電話:045-671-3498
ファクス:045-662-7362
メールアドレス:ss-hodo@city.yokohama.lg.jp
ページID:477-864-026