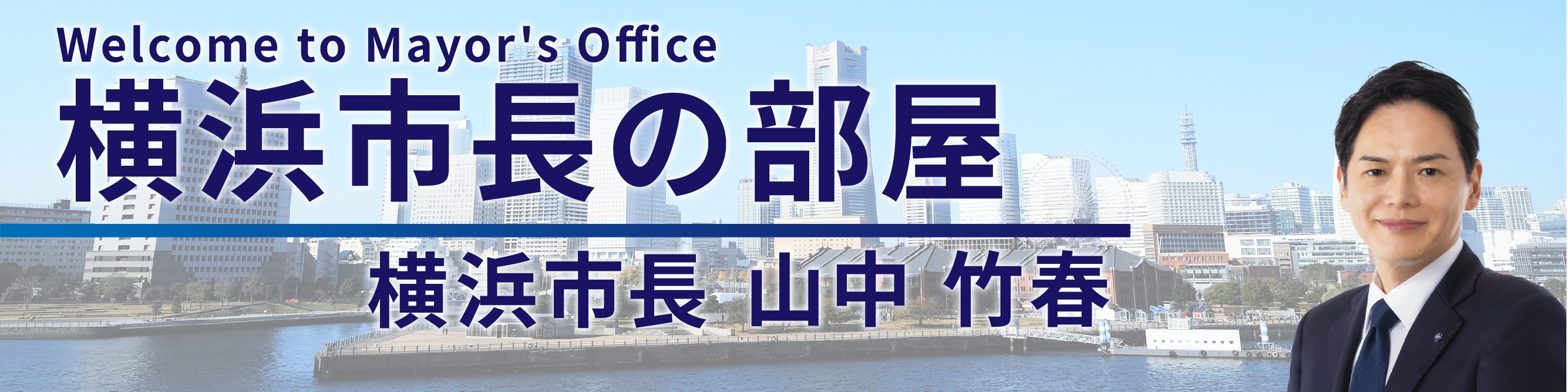ここから本文です。
- 横浜市トップページ
- 市長の部屋 横浜市長山中竹春
- 定例記者会見
- 会見記録
- 2024年度
- 市長定例記者会見(令和6年11月7日)
市長定例記者会見(令和6年11月7日)
最終更新日 2024年11月11日
令和6年11月7日(木曜日)11:00~
報告資料
- 【スライド資料】親子が楽しく絵本とふれあえる空間をつくりました! ~横浜市ゆかりの絵本作家 市原 淳氏プロデュースによるリニューアル~ (PDF:1,520KB)
- 【記者発表】~地区センターのプレイルームをリニューアル~ 親子が楽しく絵本とふれあえる空間をつくりました!
- 【スライド資料】子どものこころの変化をとらえ安心な学びの環境をつくる「横浜モデル」が始動します~横浜教育データサイエンス・ラボ発の医療×教育ビッグデータの連携~(PDF:1,875KB)
- 【記者発表】子どものこころの変化をとらえ 安心な学びの環境をつくる「横浜モデル」を始動します
会見内容
1.報告
(1)親子が楽しく絵本とふれあえる空間をつくりました!
~横浜市ゆかりの絵本作家市原 淳氏プロデュースによるリニューアル~
※敬称略
政策経営局報道課長 矢野:
それでは、定例会見始めます。2件続けてご説明させていただきます。それでは、市長お願いします。
市長:
本日、2件ご報告ございまして、最初に、地区センターのプレイルームを親子が楽しく絵本を触れ合える空間に変えましたので、リニューアルしましたので、そのご報告からです。まず、地区センターというのは、地域の皆様が気軽に利用できる、市民に身近なコミュニティ施設として本市が設置しているものであります。地区センターでスポーツ、レクリエーション、サークル活動等、そういったことを通じて相互交流を地域で深めてもらう、そういったことを目的に、市内で81館ございます。その中にプレイルームも設置しておりまして、そこで乳幼児と保護者の方々の遊びの場というものを設置しているんですが、なにぶんにも、ちょっとこう古いイメージが持たれていたりいたしましたので、こちらをリニューアルしたという次第であります。こちら、リニューアルしたプレイルーム、これ同じ場所です。こちらを、金沢地区のプレイルームをこのように改修いたしました。今回ですね、18区の27館を選びましてリニューアルいたしました。コンセプトは、親子が楽しみながら絵本と触れ合える空間をコンセプトに作って、親子が気軽に利用できる居場所として作りました。どういう内容かと言いますと、新たに絵本コーナー設置いたしました。壁紙のイラストから絵本コーナーまでを、市原淳さん、ご存知だと思うんですけれども、市原淳さんにですね、監修していただきまして、こういったリニューアルをした次第であります。それから、絵本を中央図書館の司書さんに選んでいただいて、各館に120冊の乳幼児向けの絵本セットをこのたび新たに配架することにいたしました。また、いくつかの、6館のプレイルームに関しては、子供たちの意見を聞いて、どういう色合いがいいかということを子供たちの投票で選んでいただいて、実際に色合いとかも決めております。このように、今リニューアルをして、本を読み聞かせる、そういう場所として今リニューアルをいたしましたので、今後、ボランティアの皆様、地域の皆様等と連携をした絵本の読み聞かせ会や、あるいは親子で参加できるイベント等を充実させていきたいというふうに考えております。
(2)子どものこころの変化をとらえ安心な学びの環境をつくる「横浜モデル」が始動します
~横浜教育データサイエンス・ラボ発の医療×教育ビッグデータの連携~
市長:
続きましてですね、2点目の報告が横浜教育データサイエンス・ラボに関するご報告であります。子供の心の変化を捉えて、安心な学びの環境をつくる横浜モデルを始動させたいと思います。医療と教育ビッグデータの連携が目的であります。まず、背景なんですが、本市26万人の児童生徒、小中学生でおります。その児童生徒のビッグデータを分析する、横浜教育データサイエンス・ラボを開始するというふうに先般ご報告したと思います。今年9月に第1回目を開催いたしました。より今後具体的に進めていくために、11月から市内の小学校1校、中学校1校をですね、モデル校として設置をして、よりデータサイエンス・ラボの取組を進めていく、試行していくことにいたしました。この横浜モデルとはなんですが、どういったことを考えてるかと言いますと、データで子供の心の変化を捉えていく、心の不調を軽減しようとする取組、日本で初めての取組であります。それから、26万人の児童生徒を対象に行う取組であります。リアル、学校現場ですね、それから、オンラインとバーチャル、メタバースとの3つの空間で取り組んでいき、スタディ・ナビでつないで、どこにいても同じように見守り、支援ができる仕組みを横浜から発信したいと考えております。更に具体的なイメージなんですが、このスライドで少しイメージ持っていただけるかと思うんですが、横浜市では既に1人1台端末できています。その上で、学習ダッシュボードである横浜スタディ・ナビを6月から開始しました。7月、8月お休みでしたので、9月から本格的に始動しております。学校では、学習ダッシュボードの中に、毎朝の健康観察っていうものをですね、活用して、児童生徒の健康状態の把握を開始しました。私も学校に視察に行って、朝、生徒さんたちが端末、タブレットで打ってる様子見させていただいたんですが、比較的というか、簡単にその朝の心の様子を入力してもらってました。今、市内小中学校約483校で、横浜は人数が、子供の人数多いので500万人のデータが既に集まっているんですが、イメージとしては、簡単に心の様子として5段階に分けて心の状態を報告してもらおうという内容であります。この結果、7.3パーセントのお子さんが心の様子が悪いか、あるいは少し悪いか、そういう結果となったので、これが心の不調のシグナルに、サインになるのではないかというふうに考えています。この横浜スタディ・ナビを活用して得られた教育ビッグデータをですね、専門的な知見と絡めて、今後分析を進めていきたいと思いまして、横浜市立大学の医学部と共同研究契約を締結して、今後、子供の心の不調の軽減を行う仕組みをつくっていきたいと考えております。横浜市大医学部の宮崎教授をはじめとするグループとコラボいたしまして、子供の心の不調を軽減する仕組み、その中には児童精神学の専門家等にも関わっていただければと思いますが、そういった観点から、メンタルヘルスですね、子供のメンタルヘルスを可視化する、そういう仕組みをつくっていきたいというふうに考えています。このたびのモデル校では、横浜スタディ・ナビに更にいくつかの機能を追加いたしまして、まず、子供の心の状態を捉える、心の温度計を実装することにいたしました。これはですね、このスライドの左側のほうの、これ温度計を毎日子供たちに入力してもらおうと思っています。5段階でこう入力してもらうよりも、より連続的に心の状態を捉えることができます。これ、ビジュアルアナログスケールといいまして、VASスケール、VASっていってますけれども、このVASは、医療分野で、医学の中で普通に患者さんの状態を把握するのに、例えば薬を投与したとします。で、その薬の副作用等で抑うつ状態にあるとか少しモヤモヤしてるとか、そういったことを捉えるのにもう古くから使われているものなんですけれども、このVASスケールを使いたいと思います。子供たちがこうドラッグしてですね、すごいつらい、すごい調子が悪いから、もうすごい元気いっぱいっていうところまで選んでもらって、で、それを毎朝定期的に報告してもらうことで、そのお子さんの心の変化っていうものが可視化されるようになると思います。で、これによって、シグナルをですね、掴めるようにしたいというふうに考えております。もちろん、このすごいつらい状態っていうのがずっと続いているお子さんたちっていうのは、メンタルに不調をきたしている可能性がありますので、そういったことを受けて、担任の先生や学校の先生がその生徒に接触する、より密に接触する、そういったことも可能になるというふうに思います。1人ひとりの心の状態の、1週間の変化、それから数か月単位での変化など、個々に応じた傾向を把握できるようにしたいと思っております。モデル校で。更にモデル校で子供の心の状態を月1回診断いたしまして、必要に応じて医療につなげるための心の定期検診を行いたいと思っています。これ、あくまでイメージなんですけれども、これによって、例えば中学3年生だと小学校5年生よりも少しメンタルヘルスの低下度が悪いとか良いとか、そういった傾向が得られるかもしれませんし、何よりも、この図で言う赤のところの心の状態を持っているお子さんたちっていうのはやっぱりシグナルを発しているわけですので、そういった子供たちにですね、早期に専門家に相談したりするなどの必要なケアを適切に行えるようにしたいというふうに思っています。で、三層空間に関しては、リアルとですね、こういった今説明差し上げたようなリアルでの取組と、それからオンラインにAIチャット相談を組み込みまして、児童生徒さんがチャットでやり取り、AIチャットで相談できるようにしたいというふうに考えてます。それとあと、メタバース空間でアバターを活用したバーチャル相談の仕組みもつくって、このオンラインとバーチャルに関してはまだまだちょっと思考的な段階なんですけれども、リアルだけではなくて、せっかくDX、デジタル使ってますので、オンラインとかバーチャルとか、そういったものまで踏み込んでいきたいというふうに思っています。はい。以上、概要説明したんですが、今回説明してきた内容につきましては、第2回の横浜教育データサイエンス・ラボのテーマとして、より詳しくご報告したいと思っています。11月21日に第2回のラボを行いますので、その中で、より子供の心の変化を捉えて不調を軽減する横浜モデルの開始についてご説明をしたいというふうに思っております。はい。私からの説明は以上です。
政策経営局報道課長 矢野:
はい。それでは、1件目、2件目合わせてご質問をお受けします。いつものお願いになりますけれども、ご発言の際はお手元のマイクのスイッチのご確認をお願いします。では、まず幹事社からお願いします。
テレビ神奈川 今井:
幹事社のtvkの今井です。よろしくお願いします。まず、地区センターの件でお伺いしたいんですけども、期待感と狙いをまずお願いします。
市長:
はい、ご質問ありがとうございます。明るく楽しい空間にしたいと思いました。120冊の絵本を新たに配架するなどして、壁紙等も張り替え、遊具等も入れたことで、そういった空間に近づいたのではないかというふうに思っております。多くのお子さんや保護者の方が安心して楽しんで過ごせる空間になるといいなと思ってます。
テレビ神奈川 今井:
ありがとうございます。続いて、予算の規模的なものを教えてください。
政策経営局報道課長 矢野:
所管局から。
市民局区政支援部担当部長 大澤:
市民局区政支援部担当部長の大澤と申します。よろしくお願いします。事業費ということでお答えさせていただきたいんですけれども、総事業費約7,000万円となっております。この中には絵本や玩具等の購入費も含んだ形で、というふうにお考えいただければというふうに思います。なので、単純に1館あたりの平均整備費としましては約260万円という形になります。
テレビ神奈川 今井:
ありがとうございます。今20ぐらいやってるってことなんですけど、残りの館についてはリニューアルする予定とかはありますでしょうか。
市長:
今回リニューアルした地区センターでの評判とか使い勝手とか、そういったものをお聞きしてですね、より良い場所にしていきたいと思いますので、まず今回リニューアルしたプレイルームの使い勝手を市民の皆様から実際にお聞きしたいというふうに思ってます。
テレビ神奈川 今井:
それを参考にして今後やっていくか検討するという感じですか。
市長:
もっと拡大する、していくかどうか、あるいは、今このプレイルーム、リニューアルしたんですけども、更に何か追加するかどうかとか、そういったことも検討したいと思ってます。
テレビ神奈川 今井:
ありがとうございます。続いて、横浜モデルの件でお伺いしたいんですけども、これ今回、市大と一緒にコラボしてくってことなんですけど、そこの狙いっていうのはあるんでしょうか。
市長:
はい。子供の心の不調を軽減する横浜モデルを作りたいと思っています。データから児童生徒の心の不調に早い段階で気づけるようになりたいというふうに思ってます。スタディ・ナビがあり、1台端末があり、それを子供たちに入力してもらうことによって、データを可視化することによって早く子供の心の不調に気づけるようになりたいという、そういう思いからこのトライアルを始めたいと思います。
テレビ神奈川 今井:
ありがとうございます。今、市長がおっしゃったように、早くから子供の不調を気づきたいってことなんですけども、そこにフォーカスした理由って何かあるんでしょうか。
市長:
そうですね、メンタルヘルスを向上させるっていうことは、安心な学びの環境をつくるっていうことにもつながります。適切なケアに早くつなげていくことにもつながります。是非このモデルをですね、全国初の取組となりますが、横浜市として進めていきたいというふうに思っています。
テレビ神奈川 今井:
ありがとうございます。その背景には、いじめの問題とかいろいろそういったところもあると思うんですけど、やっぱそういうところの根を早く摘み取るとか、そういったところの狙いもあるんでしょうか。
市長:
はい、そうです。
テレビ神奈川 今井:
ありがとうございます。この質問では以上です。
政策経営局報道課長矢野:
それでは各社いかがでしょうか。よろしいでしょうか。東京新聞さん。
東京新聞 神谷:
東京新聞の神谷です。この横浜モデルに関して、まずこれ、このところ、今までその500万件のデータ収集実績、この500万件っていうのはどういうことですか。
市長:
1人の子供が1日に入力したら、1回入力したら1件です。
東京新聞 神谷:
これはすみません、この5段階の健康観察はこの9月、10月に始めていたっていうことですか。
市長:
そうですね。はい、それはルーティンで行って既に開始しているものであります。また、9月、10月なので全校的に広がってるわけではないんですけれども、それでもかなりの今、入力の件数になってます。
東京新聞 神谷:
なるほど。それをモデル校ではこれから100までの値で入力するものに変えるっていうことですか。
市長:
そうです。
東京新聞 神谷:
これは他のモデル校でしかまだ、なんかシステム的にできそうな気もしますけど。
市長:
できるんですが、まず子供の心をですね、心の不安定さを早くに察知できるかどうかっていうのを時系列で追ってって、そういったことをまず見てからではないと全校展開できないかなと思います。おっしゃるとおり、システム的にはできると思うんですけれども、まずモデル校から行います。
東京新聞 神谷:
これはいつまでの予定なんですかね、試行っていうのは。
教育委員会事務局学校教育企画部長 山本:
はい。学校教育企画部長の山本でございます。11月の22日から始めてですね、3月まで実証的な実験をして、結局それがどのくらいの割合、そういったお子さんがいるのか、それを実際にじゃあどういうふうなつなぎ方ができるのかっていうことまで実証した上で、来年度に向けて少し拡大をしていきたいというふうに考えております。
東京新聞 神谷:
分かりました。ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:その他
その他、いかがでしょう。よろしいでしょうか。産経さん。
産経新聞 橋本:
産経新聞の橋本です。よろしくお願いします。プレイルームのほうなんですけども、現状でその利用者が少なくて入りづらいってことなんですけれども、今どれくらいの利用者がいて、で、これをどれくらいにしたいと考えているのか、教えてください。
政策経営局報道課長 矢野:
所管局。
市民局区政支援部担当部長大澤:
はい。利用者のほうですけれども、今回、27館整備をさせていただいております。数字としては、令和4年度で申し訳ないんですけれども、その27館の利用者で、乳幼児の利用者のほうが12万7,074人、約13万人、延べの人数になりますけれども、そういうことになります。
産経新聞 橋本:
12万いくつか。もう1回、ちょっと早口で聞こえなかった。
市民局区政支援部担当部長 大澤:
12万7,074人。はい。27館で約13万人ご利用いただいているということになっております。特段この数字をどこまで伸ばしたいという目標は正直ないところではあるんですけれども、実際この事業をやるにあたってですね、各施設でもお話を伺う中で、ご利用者さん、やはり資料にも出させていただいた古いイメージがあるだとか、あと入りづらいってイメージがあるってことはおっしゃってましたので、是非、今回もそうですけれども、明るい施設にしていきたいなっていうふうに思っております。
産経新聞 橋本:
その18区27館の選定が、乳幼児利用者数などから選定したってことなんですけども、もう少し具体的に、多いとか少ないとか、どういうところで選んだのか教えてください。
市民局区政支援部担当部長 大澤:
考え方としましては、乳幼児の人口ですね、各区の乳幼児の人口、0歳から6歳の人口ということになりますけれども、こちらと、あと地区センターの乳幼児の利用者数、あと最寄りの駅からのアクセス。利便性ですね。
産経新聞 橋本:
利用者数の多いところを選んだということですか。
市民局区政支援部担当部長 大澤:
はい、全区で、18区全てで今回整備できるようにしたいというふうに思っておりますので、そういう意味で言うと、人口だとか利用者数が多いところを抱えている区については多めに今回リニューアルしておりますし、ただ最低でも1館については各区できるように、そういった考え方でやってます。具体の施設については、先ほど申し上げましたとおり、やっぱり利便性だとか実際の利用者数の多さ、そういったことも考えながら各区のほうで決定していると、そんなような形です。
産経新聞 橋本:
すみません、あと、これ分かんないかもしれないんですけど、2館だけプレイルームがないのはなぜなんですかね。
市民局区政支援部担当部長 大澤:
はい。こちらが2館だけないんですけれども、野毛地区センターなんですが、ご存知かどうか分からないんですけど、ちぇるるの建物の中に入っていて、非常に狭いところなんですね。なので、あの地区センターを整備できるような広さがなかったというのがまず1つ。あと、新田地区センターもないという形なんですけれども、これ、廃校した小学校を活用させていただいてるんですけれども、実際、トレーニングコーナーを実は整備しておりまして、その中の一部に幼児の室内遊び場っていうこと自体は存在しております。ただ、他の施設と同様に、例えば絵本だとか玩具だとか、そういったものを設置してませんので、一応プレイルーム同様ではないということで、ないということにしております。で、当然、開館時にですね、地元ともお話をしながらこういう仕様にしているというところです。
産経新聞 橋本:
どうもありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょうか。神奈川新聞さん。
神奈川新聞 武田:
神奈川新聞武田です。横浜モデルのほうなんですが、小学校1校と中学校1校のモデル校というのはどこでどういう理由で選定されたか、伺えればと思います。
政策経営局報道課長 矢野:
所管局。
教育委員会事務局学校教育企画部長 山本:
はい。まずですね、こちらのお話については、校長先生たちの校長会のほうにもご相談させていただいて、その中でですね、まずはトライアルしていこうという学校手上げで選ばせていただいたような形でございます。実はですね、この後、保護者さんたちにもこう説明したりするので、今の段階ではちょっとお名前はあれなんですけども、そのうちまた分かってくると思います。
市長:
21日には公表する。
教育委員会事務局学校教育企画部長 山本:
そうですね。
神奈川新聞 武田:
この会ですね。分かりました。あと、すみません、もう1点、この試行実施している中で、例えば5段階で悪いっていう状況が続いてる子に対しては、今時点で、例えばこんな取組をしてるとか、こう声かけしてるというか、どんな取組なさってるのか伺えれば。
教育委員会事務局学校教育企画部長 山本:
はい。現在はですね、結局やっぱり学校の先生であるとか、あと養護教諭であるとか、あと児童支援専任であるとか、学校の中のスタッフで今までどおり対応していくような形になるんですが、なかなかやっぱり、先生方もですね、大変であって、行事が重なってたり、なかなか行き届かない部分について、今回は医療の力も借りて、オールチーム横浜で子供たちをケアしていきたいというような形になります。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょうか。神奈川新聞さん。
神奈川新聞 加地:
神奈川新聞の加地です。横浜モデルに関して追加で質問させていただきます。今回、心の不調を可視化して軽減するっていう具体の仕組みを作ろうということなんですが、こういったモデルを導入するイコールその現状に、現状の学校現場でどういう課題があるのか、例えば情報連携で目詰まりを起こしてるだとか、その医療とつなががりにくいだとか、なんかどういった課題があるのかっていうのを教えていただきたいのと、このモデル自体を実装するのがいつごろになってくるのかっていうところを教えていただきたいです。
教育委員会事務局学校教育企画 部長山本:
はい、ありがとうございます。まずはですね、現状はですね、こういったデータは、9月から5段階で始めましたので、データ自体は溜まってきて、先生方の気づきとかっていうところまではくるんですけども、じゃあ具体的にそれを誰がケアして、どういうふうに子供たちにつなげていくのかっていうところは、今までとおりの先生が対応するっていう形に今ならざるを得なくなっているのが、やはりなかなか、今、1人の先生が30人をいっぺんに見たりするような状況ですので、なかなかその目が届かなかったり、ケアが十分できなかったりっていうところが現在の課題かなというふうに考えております。そういったところをやはりきめ細かにしていくっていうことと、やっぱり早期にそういった子たちに気づいて、先生方が中心でやるんですけども、データのこういったサポートを受けて、なかなか気づかないところにサポートが届くような形にしていきたいというのが、今回の1つの狙いということになっております。で、もう1つの質問。
神奈川新聞 加地:
実際の実装が。
教育委員会事務局学校教育企画部長 山本:
そうですね。今回これをやっていくにあたっては、まずは、AI相談なんかも今考えているんですけども、どのくらいその子供たちの、その不調の子たちが割合があって、その子たちを本当に十分そういった相談機能につなげていけるのかっていうところまでしっかりとモデルを構築してから全校に広げていきたいと考えておりますので、まず3月までの間にですね、そういったところをしっかりと詰めていきながら、令和7年度はそれをもうちょっと拡充していくということで、全校展開となると、やっぱりまたもう少しその先になるかなっていうふうに考えております。
政策経営局報道課長 矢野:
その他、いかがでしょう。よろしいでしょうか。
市民局区政支援部担当部長 大澤:
すみません、先ほど利用者数のお話がありました。先程、令和4年度の数字をお出ししたんですけれども、令和5年度の数字がありますので、少し置き換えさせていただいてよろしいでしょうか。令和5年度で、今回、リニューアルした27館ですね、こちらで乳幼児の利用者数が延べ14万2,582人、はい。というふうになっております。そうですね、約14万人というふうにお考えいただければというふうに思いますので、訂正させてください。よろしくお願いします。
政策経営局報道課長 矢野:
はい、それでは、以上で2件の質疑は終了します。事務局、入れ替わりますので、少々お待ちください。
2.その他
政策経営局報道課長 矢野:
はい、それでは、これより一般質問に入ります。複数ご質問がありましたら、まとめてご質問いただければと思います。では、まず幹事社からお願いします。
テレビ神奈川 今井:
再び幹事社のtvkの今井です。ベイスターズの件でお伺いしたいと思います。26年ぶりに日本一ということで、そこへの市長の受け止めとですね、あと、市が今後、取り組むこととかですね、あと、パレードとかもやると思うんですが、そこの話とかも、もしあればお願いします。
市長:
はい、まず、26年ぶりの日本シリーズの優勝、日本一ということで、本当におめでとうございます。横浜で26年ぶりの日本一を決めてくださり、市民の皆様に歓喜をもたらしていただきました。非常に歴史的な快挙だというふうに思っています。また、今後の取組に関してなんですけど、既にブルーにライトアップすることについては記者発表しておりますが、その他に関しては。
にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興部長 熊坂:
スポーツ振興部長の熊坂でございます。よろしくお願いいたします。ご質問のあったパレードにつきましてですが、本当に申し訳ないんですけれども、現時点でちょっと皆様にお話できる内容がございません。今後、チームのほうから発表もあると思いますし、私どもにも入りましたら、また皆様方にも是非お伝えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
テレビ神奈川 今井:
ありがとうございます。もう1点お願いします。
市長:
はい。
テレビ神奈川 今井:
衆院選の件なんですけども、その投開票の当日ですね、横浜市内の当選議員のほうにですね、市長と平原副市長が一緒に訪問したと思うんですけど、そこの狙いというか、何かこう、何か理由を教えてもらえればと思います。
市長:
はい、今回、横浜市域だけの小選挙区に、すべての議員に当選確定、当確が出た後、ご訪問させていただきましたが、狙い、狙いというか理由としては、国家要望を行う際など、今後の市政運営にご協力を頂く方々になりますので、ご挨拶に伺ったという次第です。
テレビ神奈川 今井:
これは割と慣例的な話なんですか。
市長:
慣例的に行っております。
テレビ神奈川 今井:
分かりました。ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
それでは、各社いかがでしょうか。よろしいでしょうか。神奈川新聞さん。
神奈川新聞 加地:
すみません、神奈川新聞の加地です。衆院選に絡めて1問、質問させてください。今回、期日前投票の入場券の発送がかなりタイトなスケジュールだったということで遅れてしまって、序盤の期日前投票率かなり低迷していたと思います。なんかこれを受けて横浜市が、なんでしょうね、市民の方々にどう周知して投票率を促すような、何か取組をされていたのか、されていなかったのか。
市長:
ご質問ありがとうございます。解散して総選挙までの日にち、日数が短いということに関しては、我々どもでどうにかできることではありませんので、選挙管理委員会を始め、できる限りの努力はしたつもりです。期日前投票の数は、前半はおっしゃるとおり前回選挙、令和3年ですね、令和3年の前回選挙を前半は下回っていたんですが、配達が完了した23日以降は前回を上回りましたので、最終的にはトントンというか、前回とほぼ同程度の期日前投票の数となることができました。で、その間に関してですね、本市としても何か特別なことをしたというわけではないんですけれども、職員の努力で配達をできる限り早く完了することができたというふうに思っています。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょうか。時事通信さん。
時事通信 廣野:
時事通信です。首都圏で相次ぐ匿名流動型犯罪グループによる強盗事件について伺います。市内でも強盗殺人事件や強盗目的とみられる住居侵入事件が発生しています。これについて市長の受け止めを伺いたいのと、今後、県警と連携した防犯対策、何か予定してるものがあれば教えていただきたいのと、あと、今後、予算措置で、防犯対策、何か予算措置を行うお考えがあれば教えてください。
市長:
はい、何か。
政策経営局報道課長 矢野:
所管局から。
市民局地域支援部長 守屋:
はい、すみません。市民局地域支援部長の守屋と申します。よろしくお願いします。まず、防犯対策でございますが、今、地域防犯カメラの設置補助ですとか、あとは防犯灯の整備等のですね、いわゆるハード面の整備を実施をしているところでございますけれども、今年度ですね、今回の件を受けまして、今年度、自治会、町内会からご申請を頂いている、いわゆる電柱につける防犯灯につきましては、設置基準を満たしているものについては全件対応しようというように方針を変えているところでございます。従前はですね、申請がありましても、どうしても全件は対応できないという状況がありましたけれども、今回、この1件を受けましてですね、今年度についてはしっかり全件対応していきたいというふうに考えているところでございます。
市長:
防犯カメラの設置を拡大していくということと、あとLED防犯灯の整備など、ハード面の支援を積極的に行っていきたいと思ってますし、またソフト面でもですね、LINEなどを使った防犯情報の提供等は積極的に行っていきたいと思っています。
時事通信 廣野:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょうか。神奈川新聞さん。
神奈川新聞 武田:
神奈川新聞武田です。1点、まず、今みなとみらいのほうで横断歩道の封鎖をする実証実験やってるかと思うんですが、あんまり横断歩道を封鎖するっていうことがない形かと思うんですけど、将来的には撤去っていうものも見据えているというふうに伺っておるんですが、まず、そこの部分の市長の受け止めと、今後、撤去という形になると前例になっていって、他のところでもそういう形、撤去っていうものが相次いでしまうような懸念もあるのかなと思うんですが、改めてその歩行者視点であるべきところでの考え方、伺えればと思います。
市長:
はい、ご質問ありがとうございます。まず、歩行者視点に関して、歩行者の安全性を優先しながら、歩行者の利便性を高めるっていうことが重要だというふうに思います。歩行者の利便性もさることながら、安全性が担保できないところっていうのは、それは市として対応しなければいけないというふうに考えております。ですので、その原則をまず守ることが重要だと思いますので、そこはご承知おきください。で、今後の計画等については。
都市整備局都心活性化推進部担当部長 木村:
都市整備局都心活性化推進部の木村と申します。ご質問ありがとうございます。今後の計画ですけど、今回の社会実験を行っている場所は首都高速道路の出入口という特殊性のある場所になっております。ですので、今の段階では他の場所で横断歩道を撤去するという計画はございませんけれども、これからやっぱり日が経つにつれて状況も変わっていきますので、その状況を見ながら、また改めて考えていきたいと考えております。
神奈川新聞 武田:
ありがとうございます。現時点では他の場所の予定がないということで、今回のみなとみらいでやっているけやき通りのあそこについては、いつ頃目処に方向性というか、1週間は実証実験あると思うんですが、どれぐらいの目途で考えていくのか、伺えればと思います。
都市整備局都心活性化推進部担当部長 木村:
ご質問ありがとうございます。1週間実証実験を行いまして、それから交通量などのデータ解析を行っていきます。その後、アンケートも取っておりますので、そのアンケートを集約しまして、年明けぐらいにはこの県警のほうに協議に入っていきたいと思います。どうしていくかの結論は県警のほうで判断していくことになりますので、明確にいつ判断ができるかというのはちょっと申し上げられませんけども、なるべく早く解決方法が見つかるように協議を促していきたいと考えております。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。よろしいでしょうか。産経新聞さん。
産経新聞 橋本:
産経新聞の橋本です。よろしくお願いします。公園条例、改正公園条例の関係でちょっと、公園条例の関係、ちょっとお伺いしたいんですけども、市長も10月26日の日本対ニュージーランド戦、日産スタジアム見に行かれたと聞いてるんですけども、あの日もですね、喫煙所がトイレの隣にあって、もうハーフタイムとかすごいもうもうとしてて、トイレに行く人も顔をしかめているような状況だったんですけれども、あの状況っていうのは、健康増進法に違反かどうかっていうのは難しいかと思うんですけども、少なくとも屋外においても受動喫煙を防止する義務が課せられている状況で、望ましい状況ではないと思うんですけれども、今度、公園が全面禁煙になりますが、それでも市がイベントをやる場合には喫煙所の設置は可能だということで、あの状況っていうのは変わらないのか、それとも密閉式の喫煙所の設置を義務付けるとか、何か今よりは改善することを市長としては考えているのかどうかをお聞かせください。所管が検討してるのは知ってますんで。
市長:
イベントに関してですか。橋本さんがお聞きされているのは。
産経新聞 橋本:
そうですね。普段はもう公園が全面禁煙だっていうのはもう条例で決まってるじゃないですか。ただ、その例外として、市がイベントを許可した場合には喫煙所の設置を認めると書いてあるんで。で、それが今のようなオープンエアの喫煙所というか喫煙コーナーだったら、そば通るだけでもう必然的に受動喫煙してしまうので、そこをどうするのか。
市長:
ご質問ありがとうございます。そういったお声も多く頂いております。喫煙所を設置はしているんだけれども、結果的にいろいろ外に漏れ出てるので、完全な分煙になってないというお声も頂いております。一方で吸う方々のご要望もあります。大規模なイベントで完全に何もしない状態ですと、市外からも多くの方が来ますので、結果的に路上喫煙等が増えて、結果的には良くないだろうと思いますので、喫煙できるところが必要だというふうに思います。で、その喫煙できる場所を、今後どういうふうに場所を認め、そして喫煙できる形態を密閉式なのか、今までどおりオープンなのか、そこに関してはきちんと検討していかなければいけないというふうに思ってます。私個人としては、分煙、できる限りの分煙が望ましいと思っておりますので、その方向に向けて検討を進めていきたいというふうに思っています。
産経新聞 橋本:
分かりました。ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他、よろしいでしょうか。それでは、以上で定例会見終了します。ありがとうございました。
このページへのお問合せ
政策経営局シティプロモーション推進室報道課
電話:045-671-3498
電話:045-671-3498
ファクス:045-662-7362
メールアドレス:ss-hodo@city.yokohama.lg.jp
ページID:489-073-023