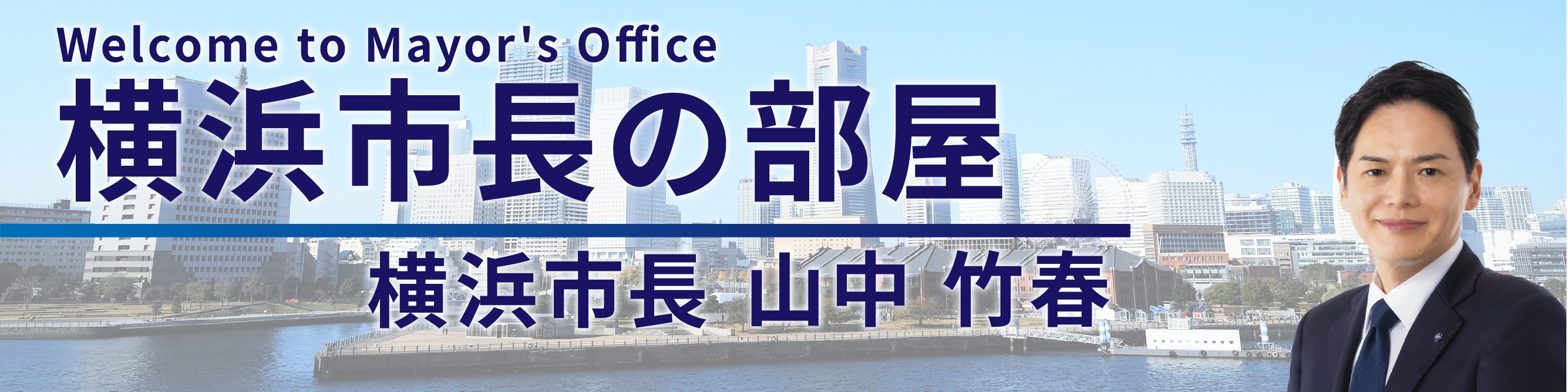ここから本文です。
- 横浜市トップページ
- 市長の部屋 横浜市長山中竹春
- 定例記者会見
- 会見記録
- 2024年度
- 市長定例記者会見(令和7年3月26日)
市長定例記者会見(令和7年3月26日)
最終更新日 2025年4月3日
令和7年3月26日(水曜日)11:00~
報告資料
- 【スライド資料】「化粧のちから」で広げる横浜市の介護予防 資生堂ジャパン株式会社と介護予防に関する連携協定を締結(PDF:1,513KB)
- 【記者発表】「化粧のちから」で広げる横浜市の介護予防 資生堂ジャパン株式会社と介護予防に関する連携協定を締結します!
会見内容
1.報告
「化粧のちから」で広げる横浜市の介護予防
資生堂ジャパン株式会社と介護予防に関する連携協定を締結
ゲスト:資生堂ジャパン株式会社 首都圏支社 支社長 菊川 佳一 様
※敬称略
政策経営局報道課長 矢野:
はい、それでは定例会見始めます。市長、お願いします。
市長:
本日ご報告させていただくのが、お化粧を通じて介護予防の取組を行うという内容であります。資生堂ジャパン様との連携であります。まず、背景なんですが、ご承知のとおり、今フレイル、あるいは要介護状態の方が増えてきております。本市では、2020年から40年までの間に約1.5倍に要介護状態の方が増えることが予想されています。また、フレイルの状態にある方がですね、コロナ禍で増えているというデータもあります。2019年と2022年度に比べて、フレイル状態にある、これ本市のデータですけれども、1.3倍に増えています。こういった中で、資生堂ジャパンさんからお化粧を通じた介護予防の取組についてご提案をいただきました。内容なんですけれども、まず、横浜市と資生堂ジャパン株式会社さんの間で連携協定を締結いたしまして、横浜市にお住まいの高齢者の方を対象に、美容教室を、年間を通じて実施することといたしました。この美容教室の目的は、ストレッチ、スキンケア、メイクなどのレッスンを通じまして、心身機能や生活の質の向上を図る、ゴールは健康寿命の延伸を目指すという内容であります。まず、次年度、令和7年度は18区におきまして、合計60回ほど開催をしていただく予定であります。教室の内容なんですけれども、資生堂ジャパンさんのスタッフに講師になっていただいて、まずストレッチを行ったり、あるいは唾液腺、唾液腺ってここですけど、唾液腺を刺激するスキンケアを行っていただきます。唾液腺は唾液の分泌、唾液腺のスキンケアで、唾液の分泌が促されます。唾液がないと舌が乾いて、咀嚼機能が落ちたりしますし、あと誤嚥性肺炎で亡くなる方も結構いらっしゃるんですけど、誤嚥性肺炎の原因にもなりかねないので、唾液を出すように訓練するっていうことは重要なんですね。そこに対するスキンケアを指導したり、あるいはご高齢の方でも簡単に続けられるメイクアップについてご指導いただける予定であります。どういう効果があるかなんですけど、これ以前に本市でも美容教室やりました。それとはこれ、別の一般的なデータなんですけれども、見方を説明いたしますと、介入っていうのは化粧ケアを実施したグループのことですね。何かを行った、医学用語です。介入を行ったっていう意味です。対照っていうのが、言葉が難しいんですけど、比較対象という意味で、何もしないというか、特に介入がないって思ってください。ですので、赤が何もしない、通常どおり。青が何か行為を行った、この場合だと化粧ケアの指導を行ったという意味であります。10月と12月なんですけれども、まず赤がですね、10月の時点で、9割ほど1日1回以上外出したっていう、まずここのデータですね。それが、この赤は特に何も介入してませんから、12月になると、寒くなることもあって、外出が40%程度まで落ちるっていう意味です。それに対して、この青が10月の時点では、これ介入前です。これが93%ぐらいなんで、だいたい3%ぐらい介入群と非介入群、青と赤で差があるんですけれども、ここはもうほぼ誤差範囲だと思います。逆に、青と赤が離れてると、それはちょっとデータとしておかしいわけで、10月の時点、まだ秋のときに、赤も青も何もしてない状態ですから、外出の割合は同じでなければならない。それが赤だと、対照群、何もしてないので時期が寒くなると外出の割合が下がる。青は、その外出の割合の低下が抑えられるっていうデータです。こういった外出機会の減少を抑制する効果に関する学術的文献もあるという内容であります。こういったデータをどんどん取っていって、こういったスキンケアとか、あるいはストレッチとかをやってどのくらいお年寄りの健康が保たれるのか、健康寿命の延伸まで測るってなるとかなり大がかりなデータで、長年フォローアップしないと測れないんですけれども、こういった比較的計測しやすいKPIって言ったらいいんですかね、評価指標で、こういった教室の効果を今後どんどん図っていきたいなというふうに思っています。本日は、資生堂ジャパン株式会社首都圏支社の支社長の菊川佳一様にお越しをいただいておりますので、お話をいただきたいと思います。菊川様、よろしくお願いいたします。
資生堂ジャパン株式会社 首都圏支社 菊川 支社長:
市長、ありがとうございます。よろしくお願いします。皆様改めまして、こんにちは。私、資生堂ジャパン株式会社営業統括本部首都圏支社の責任者やらせてもらってます、菊川と申します。よろしくお願いいたします。今、市長からお話ありまして、我々これから介護、フレイル予防について化粧品で取り組んでまいりますが、まずちょっとこちらに映させていただいてるのが、資生堂、これグループ全体になるんですけども、ミッションになります。「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD」、昔は日本語でやってたんですけども、14年ぐらいからグローバルで日本で唯一って話をしてますので英語になっていて、「美のちからでよりよい世界を」っていう大きなミッションがあります。その中で、美しく健やかな社会と地球が持続していくこと、サステナブルなことに対して貢献するということにしています。その中に、資生堂ライフクオリティービューティー活動、これは長年続けている活動なんですけども、それをしっかりと実態していって、「化粧のちから」、この言葉が今日たくさん出ますけども、通じて、ローカルSDGsの実行、地域のコミュニティ、ここがまさに横浜市様と組みたいところなんですけども、あとはあらゆる生活者の方々が自分らしい生活の実現に向けて取り組んでいくっていうことをさせていただきたいなと思ってます。下に書いてあるのがSDGsの17項目、大きい項目の中の、そこに当てはめて考えてることになります。はい、では次のページお願いします。実際ですね、その化粧、我々皆様お化粧品をね、いろんなとこで販売していって、CMとかでも綺麗なモデルさんでやってるイメージがあると思うんですが、実は我々介護というか、高齢者の方に対しての取組は長い歴史がございます。こちらに書いてあるとおり1975年にですね、岩手県になるんですけど、特別養護老人ホームで化粧のボランティアとして、まずは開始をしていきました。そこからも途切れることなく、いろんなことさせてもらったんですが、実際にこれがしっかりと科学的根拠が持てるという研究が始まったのが、1993年、鳴門山上病院。私ちょっとこれ入社していた時期なんで、まだそんな分かってなかったんですが。徳島県のほうで共同取組を看護師が発表しました。ここから本当に化粧療法、いわゆる医学療法ではなく、化粧にもそういう療法があるっていうことの研究がずっと始まってまいりました。2010年ぐらいですかね、そこでしっかりと進化をしていって、単純に化粧療法という言葉だけでなく、脳科学から入ったりとか、あとは人間工学、まさに医学のところへ入り、13年にはそのエビデンスをしっかり持っていって、化粧療法プログラムっていうものを、開発をさせていただいております。そこで資生堂ライフクオリティービューティーセミナーというものを始めて、その中に、高齢者対象の、今お話いただきましたいきいき美容教室というものを開始しております。少し中身に触れますけれども、あのいきいき美容教室。これはまさにあの認知症。今日まさに下ですごいセミナーをやられてたくさんの方いらしてましたけども、その原則っていうのは、これは資生堂が考えたわけじゃなくて、ある言葉。心地良い刺激ですとか。あとコミュニケーションをしていく、あと認知症ですから、正しいことができることを繰り返す。それと生きがいですよね。一番大事かもしれません。あとは喜び合って褒めるということ。この1、2,3,4。これに合わせてのプログラムを組んでるっていう形になっています。まず心地良いってところなんですけども、リラックスする。ハンドマッサージですとか、そういったことでこちらの講師が触れていくこと。更に気持ちを集中というのは、先ほどお話ししたスキンケア。スキンケアもやっぱり顔に集中するわけですからそこに集中していく。そこでだんだんだんだんお互いに褒め合いながらというか、うちの講師が褒めていくんですけども、コミュニケーションをとっていくと脳が活性化していくと。そこで皆さんで最後で笑顔でして。これが終了、60分になるんですけども終了したときは元気になって、メイクから少しいれていきますので、口紅を引くことによってちょっと外に出てみたい、人に会いたい、みたいなところを先ほどグラフがあったところを仕上げていくっていうことをしたいなというふうに考えています。単純に自分勝手なことだけじゃなくて、下のほうにちょっと受賞の経歴書いてあるんですけども、介護とかリハビリの商品に対しての表彰がありまして、ちょっと少し前ですけどもRE‐CARE AWRD、2018年には金賞取っており、2019年にもちょっと違う部門で金賞を取っていますので、しっかりとそのエビデンスというか、効果というところは認められてるという形になります。では、ちょっと次のページです。今私が話した内容を1分間ほど動画でお見せしたいと思いますので、よろしくお願いします。
(動画)
ありがとうございます。ではちょっと最後になります。こちら、我々ホームページというか、ずっとこれを掲げてこれを信じて活動しているんですけども、本当に美はですね、人の心、先ほどの笑顔見てもらって分かっていただけるように、豊かにしていって、生きる喜び、力を持たせることを本当に我々は信じてます。そこにフレイル。フレイル予防というところで、横浜市様と協定を結んでいただけるということは大変本当に意義があります。我々、現場でお店でやるんですけど、お店だとなかなか集まらないんですよね、どうしても。それが市というか、公共のとこでやることによってたくさんの方にこれを知っていただくことによって、いろんな社会解決、社会の課題に対して解決を一緒にやっていけるなというふうに思っております。誰もが本当に安心して、この超高齢化社会に迎える日本が1つでも我々が貢献できるように、活動して参りたいと思いますので、是非よろしくお願いします。本日はありがとうございました。
市長:
菊川様ありがとうございます。横浜市では、ポジティブエイジング、ポジティブにお歳を重ねていくそういった言葉を目標に、今後も高齢者の皆様へのご支援に取り組んでいきたいと思います。こちらに関する説明は以上です。
政策経営局報道課長 矢野:
はい。それではこの件についてご質問お受けします。いつものお願いになりますけれども、ご発言の際はお手元のマイクのスイッチのご確認をお願いいたします。ではまず幹事社からお願いします。
時事通信 廣野:
ご説明ありがとうございました。幹事社の時事通信です。今回の取組の狙いと展望について教えてください。
市長:
はい、ご質問ありがとうございます。スキンケア、お化粧といった視点から、介護予防のアプローチに取り組んでいきたいというふうに思います。先ほどご説明があったとおり、こういった資生堂ジャパンさんが化粧とか、スキンケアとか、そういったことを生業にされているわけなんですが、そういった一方で介護予防、あるいはフレイル予防、そういった取組をこれまでされてきたというふうに承知しております。ですので、我々としてはそのポジティブエイジングという言葉を目標に、お年寄りの方が前向きな気持ちで毎日を過ごせるようにしたい。そういった思いがありました。今回そういった我々の思いと資生堂ジャパンさんからのご提案の内容が合致したので、今後連携を始めさせていただきたいというふうに考えております。
時事通信 廣野:
ありがとうございます。次、支社長にも伺いたいんですけども、民間企業が介護予防に取り組む意義について教えてください。
資生堂ジャパン株式会社 首都圏支社 菊川 支社長:
ありがとうございます。介護予防に限らずなんですけども、今、お話しした、私たちも過去からやってるんですが、そもそもCSRみたいなところで、社会的な貢献で、ちょっとボランティア的な、貢献しなきゃいけないよってあったんですが、今やっぱりそこと、利益と結びつくCSVみたいな話がやっぱり進んでるんじゃないかなというふうに思います。2021年に、経産省が化粧品産業ビジョンっていうのを出したんですよ、2021年、初めて。それまで化粧品産業ってビジョンが、我々は作りますけど、産業省なくて。その中でも化粧って、弱みは、物は売るけど、綺麗になるけど、化粧って本来そうではなくて、やっぱり人々のライフクオリティバランスを良くするし、そこにも認知症の話も書いてありました。こういうことが化粧にはあるんだよっていうことをしっかりとメーカーさんアピールしなさいよ、みたいなことを弱みで書いてありました。そういうこともやっぱり含めて、我々やってきたけども、やっぱり伝わってる方が本当少ないっていうことがありますので、是非この大きい横浜市様、沢山の高齢者の方が抱えているところと取り組んで、化粧の凄さ、化粧の良さを社会で貢献できるようにしていきたいというのが、大きな意義。結果、それが恐らく事業継続につながるというふうに考えています。
時事通信 廣野:
ありがとうございます。幹事社以上です。
政策経営局報道課長 矢野:
それでは、各社いかがでしょうか。朝日さんから。
朝日新聞 良永:
朝日新聞の良永と申します。よろしくお願いいたします。2点、質問がございまして、1点目が、市民の方も結構興味のある方を多いのではないかなと思うんですけれども、この取組の周知の方法についてはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。
政策経営局報道課長 矢野:
所管局から。
健康福祉局高齢健康福祉部長 粟屋:
健康福祉局高齢健康福祉部長の粟屋と申します。よろしくお願いいたします。周知につきましては、今回、4月下旬からですね、各区役所、地域ケアプラザ、あと老人福祉センターのほうで、こちら、やっていくようになるんですけれども、4月以降、まず地域ケアプラザのほうで開催をされる予定になっております。既に4月21日が初回なので、そういったところは既にホームページに載っていて募集等を進めているところでありますので、個々に、例えばケアプラザのホームページであったり、私どものほうで発行している広報よこはまであったり、そういったものを通じて地域の方にお知らせをしていくということになっております。
朝日新聞 良永:
ありがとうございます。あともう1点なんですけれども、費用が今回、原則無料というところなんですけれども、費用負担は市のほうでするのか、それとも、資生堂さんのほうで慈善事業のような形で行っていくのか、教えていただけますでしょうか。
健康福祉局高齢健康福祉部長 粟屋:
今回はですね、いきいき美容教室自体は無償で提供していただきますので、横浜市のほうからは特に予算としての持ち出しはないということになっております。なので、横浜市は、例えば広報をするとか、場所をこういうところあるよっておつなぎするとか、そういうところをやっていくということで、費用は資生堂ジャパン様に出していただく形でございます。
朝日新聞 良永:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょうか。読売さん。
読売新聞 川崎:
読売新聞の川崎です。いずれも、菊川さんへのご質問になろうかと思うんですが、まず、こういういきいき美容教室の自治体との連携ですね、何自治体目になるんでしょうか。
資生堂ジャパン株式会社 美容戦略部 社会活動企画推進グループ 大堀 ソーシャルエリアリーダー:
資生堂ジャパン株式会社美容戦略部大堀と申します。ご質問ありがとうございます。自治体様との連携については、今、現時点で10の自治体様と連携をさせていただいております。その中にも介護美容のこともありますし、内容が違っている連携もございますけれども、今、10ということで、連携をさせていただいております。
読売新聞 川崎:
横浜市が11自治体目ということでしょうか。
資生堂ジャパン株式会社 美容戦略部 社会活動企画推進グループ 大堀 ソーシャルエリアリーダー:
はい、左様です。
読売新聞 川崎:
分かりました。一定の科学的根拠もある、画期的な良い取組だなと聞いていたんですけれども、いわゆる男性ですね、はまだまだスキンケアとか化粧っていう領域がまだ一般的ではないかなと思うんです。そういう結果の性差みたいなものっていうのはあったりするんでしょうか。
資生堂ジャパン株式会社 首都圏支社 菊川 支社長:
男性にですか。
読売新聞 川崎:
はい。
資生堂ジャパン株式会社 首都圏支社 菊川 支社長:
おっしゃるとおりですね、こちらのフレームは主にやっぱりどうしても化粧から入ってくるので、女性の方の応募がほとんどだと思うんです。男性もジェンダーレスになってきたりとか、男性の美に関することで、確かに男性化粧品市場が上がりつつはありますけど、なかなかテレビでされることほどは、実際はそんなに上がってないっていうのが事実なんですよ。我々それがやりたくて、男性にやるんですけども、確かに、むしろ我々世代の高齢者はあんまり化粧っけがなくて、若い方々は本当にメイクが当たり前のようになってきているんですけども、まず男性の方でも化粧、肌を綺麗にするのは女性も男性も関係ないし、健康には本当に欠かせないことですから、それをしっかりとアピールして、まだ結果でどうなってるって大きいデータがちょっとないような状況であります。ただ資生堂は本当に美容データはたくさん保持してますし、それを取り得る機会もたくさん持ってますから、これから積み重ねて、出せることがあるんですが、高齢者に対してですね、本当に男性をどう呼ぶかってちょっと課題の1つかなと今、言われて本当に思いました。ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他、いかがでしょうか。東京さんから。
東京新聞 神谷:
東京新聞の神谷と申します。菊川様になんですけれども、ほか10自治体と連携してるってことですけど、実際このさっきの映像とかの、このいきいき美容教室っていうのは、基本的に自治体との連携で無償で提携してるのと同じようなスキームでやってるということでしょうか。
資生堂ジャパン株式会社 美容戦略部 社会活動企画推進グループ 大堀 ソーシャルエリアリーダー:
はい、ご質問ありがとうございます。いきいき美容教室の費用ということに関しては、地方自治体の皆さんについては無料にて実施ということで統一をさせていただいております。
東京新聞 神谷:
先ほど何か、お店でやってもあまり人が来なくてみたいな。
資生堂ジャパン株式会社 首都圏支社 菊川 支社長:
お店っていうのは、私、化粧品専門店って言われてる街の化粧品屋さんをたくさん担当してるんですけれども、そこで、いわゆる化粧品買ってくれる会員様、お店のお客様ですよね。その方々を集めて公民館借りて、そこはちょっと有料にしてセミナーみたいな形、どうしてもお店がありますから。やるんですが、なかなか会員さんにかけても、たくさんの人がやっぱり一気に集まることはなかなかなくて、であればやっぱり市との協定があると、多くの方が来てくれるのかなと。ただ、それでも20人とか、普通のセミナーやるよりも、来てくれれば、特にフレイルに関しては去年辺り始めたんですけど非常に多いです。はい、どうしても商売に入ってくるのでそこから加入してお店にみたいな、ちょっとそういう方が入ってくるよりも、やっぱり無償で、そのためにってしっかりやったほうが、やっぱりさっきの話じゃないですけど、本当にサステナビリティなことになるのかなというふうに思っています。
東京新聞 神谷:
そうすると、先ほどご紹介いただいた高齢者に対する取組っていう、やっぱりこの美容教室っていうのは始まったのはいつごろ。2013年以降のいつ頃からになるんですか。
資生堂ジャパン株式会社 美容戦略部 社会活動企画推進グループ 大堀 ソーシャルエリアリーダー:
すみません、具体的な月というのはすみません、持ち合わせてなくて大変恐縮なんですけれども、2013年からスタートして今に至るというふうな形になります。
東京新聞 神谷:
なるほど、そうすると、順次自治体とやっていったり、あるいはそのお店での有料のでやっていったりっていう取組を広げていったっていうイメージですか。
資生堂ジャパン株式会社 美容戦略部 社会活動企画推進グループ 大堀 ソーシャルエリアリーダー:
いきいき美容教室、化粧療法をベースとしたこのプログラムという形で言いますと、2013年以降という形になります。その前になりますと、美容をメインとしたそのような生活者、お客様に向けたお取組ということは続けているっていうような形になります。
東京新聞 神谷:
なるほど、最後に、これ別に女性向けってわけではもちろんなくて、今回も別に男女問わずだけど、実質的にはやっぱり女性の方のほうが圧倒的に多い。
資生堂ジャパン株式会社 首都圏支社 菊川 支社長:
多いです、はい。
東京新聞 神谷:
分かりました。ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。日経さん。
日経新聞 松原:
日本経済新聞の松原と申します。先ほど純粋なCSRだけではなく、企業として利益も追求していかなければいけないというお話があったんですけれども、スキンケアは毎日のことなので、会に参加するだけじゃなくて、日々のケアも大事になってくると思うんですが、参加者の方々に例えばケアグッズの販売であったりとか、そういったとこにつなげていく取組っていうのもされているんでしょうか。
資生堂ジャパン株式会社 首都圏支社 菊川 支社長:
これ販売はですね。
資生堂ジャパン株式会社 美容戦略部 社会活動企画推進グループ 大堀 ソーシャルエリアリーダー:
ご質問ありがとうございます。いきいき美容教室の中でのお化粧品のご紹介ということには至っていないというような形になります。お近くに化粧品店であったりとか、販売いただいている店舗様がありましたら、そちらに行っていただくっていうお話はあるかもしれませんけれども、固定的にどちらに行っていただきたいというようなお話ということは、教室の中には入っておりません。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。神奈川新聞さん。
神奈川新聞 加地:
神奈川新聞の加地です。市長にお伺いします。冒頭でですね、データを取っていきたいというようなお話があったんですけども、どういう目的でデータ取るのか、どういうことにつなげていきたいのかっていうのがあれば教えてください。
市長:
ありがとうございます。この事業だけの話ではないんですけれども、市として何かコミットする、高齢者向けの施策、子供向けの施策、全てについて、データを取ってきちんと検証を進めていったほうがいいんじゃないかなという思いであります。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。よろしいでしょうか。それではこの件の質疑は以上で終了します。
このままフォトセッションに移りますのでどうぞ前のほうにお越しください。ありがとうございました。事務局入れ替わりますので、少々お待ちください。
2.その他
政策経営局報道課長 矢野:
それではこれより一般質問に入ります。複数ご質問ありましたら、まとめてお願いできればと思います。では、まず幹事社からお願いします。
時事通信 廣野:
幹事社時事通信です。GREEN×EXPOについて伺います。協会からの会場建設費の増額要請について、議会などでも答弁されてますが、正式な受け入れ表明についての流れは今後どうなるのでしょうか。
市長:
はい、ご質問ありがとうございます。昨日の予算案の議決にあたりまして、議会のほうから適切に対応するようにと、開催市として的確な対応を図るように、という内容の附帯意見もいただきました。コスト抑制に向けた不断の努力をしていただくことを前提に、今回の協会の要請をですね、受け入れることを妥当と考えまして、今後、必要な手続きを進めていきたいというふうに思っています。
時事通信 廣野:
ありがとうございます。幹事社以上です。
政策経営局報道課長 矢野:
それでは、各社いかがでしょうか。よろしいでしょうか。神奈川新聞さん。
神奈川新聞 武田:
神奈川新聞の武田です。関連して、博覧会の部分なんですが、来月、大阪万博が開幕するということで、市長は、視察の予定とかはいかがでしょうか。
市長:
現時点では、まだ何日に行くとかっていうのはないですし、公務で行くのか、それ以外で行くのかも含めて、検討中であります。
神奈川新聞 武田:
ありがとうございます。一応行く予定ではあるという感じですか。
市長:
今、検討中です。
神奈川新聞 武田:
検討中、はい、分かりました。先日3月19日、2年前の節目っていうことで博覧会協会のほうが都内でイベントを開いて、政府の出展と協会の出展、会場の一個花というか、この概要、本当に一部ですけど、発表ありました。改めて横浜市としての出展、開催自治体基本的に出展が恒例だと思いますし、県がミュージカルみたいなものをやるっていうのは、黒岩知事も発表されてますけれども、改めて横浜市としての出展の方向性ってのは現時点でいかがでしょうか。
市長:
もちろんホストシティとして出展を予定しておりますが、まだ細かい内容に関して、どういった内容に関してどういう建付けで出店するのか、そういったところを鋭意調整中ですので、詳細決まりましたらまた改めて発表したいと思います。
神奈川新聞 武田:
分かりました、ありがとうございます。それとですね、博覧会の開幕まで2年間ということで、改めてなんですけども、今後例えば認知度の向上とかちょっといろいろ課題ありますけど、2年間どうしていくかっていう部分伺えればと。
市長:
私18区回って、町内会や、あるいは公園愛護会、あるいは地域で活躍していただいてる方々向けに、説明会等も行いました。それとは別に区役所のほうでも、それぞれの区で様々な周知活動を行っております。また合わせて、駅とか公共空間でのプロモーション活動等も、今、活発化してきて、市の中では大分広がってきたかなと思っています。今後ですね、鉄道各社さんと協力をしながら、一都三県向けに、PR活動拡大させていきたいと思いますし、合わせて日本全国、それから世界各国からお客様に来ていただくためのPR活動を展開していきたいというふうに思っています。
神奈川新聞 武田:
ありがとうございます。鉄道会社の部分、JRのデスティニーキャンペーンですかね、あるかと思いますけども、例えばほかに今後の部分でこういうふうにやっていくって部分って、何か企画的なものが。
市長:
横浜の鉄道会社さん、相鉄さんとか京急さんとか東急さんとか、JRさんもありますけれどもそういった鉄道各社さんと適切に協力していきたいというふうに思っています。
神奈川新聞 武田:
ありがとうございます。もう1点、認知度のその部分で。認知度。
市長:
認知度。
神奈川新聞 武田:
認知度の部分で、大阪ですと2年前、もうちょっと前から博覧会の万博協会のほうが定期的に会見を開いたりして、出せる情報、出せない情報をいろいろあると思いますけれども、定期的に発信をして、何らかマスコミ通じて市民に知らせようみたいな取組をされてたと思うんですけれども、横浜のほうは、私も個人的にはそういう、こっちも2年前ということでそろそろそういう形で定期的な会見とかの場を設けるべきかなと思うんですけど、そのあたり市長、副会長のお立場でもありますけど。
市長:
協会のほうからどんどん発信していくこと重要だと思います。そういったフェイストゥフェイスでの会見も必要でしょうし、SNS等での発信も必要でしょうし、あとは自然に目に入るプロモーション、公共空間活用した、駅を活用した、そういったプロモーションなんかも必要だと思いますので、是非多角的なプロモーションを協会にはお願いしたいと思ってます。
神奈川新聞 武田:
分かりました。あとごめんなさい、長くなっちゃって。最後に1点だけ、市長選の部分なんですが、取材の中で8月3日投開票っていう情報をひとつ得てるんですが、そうすると7月20日告示、今日から考えると4ヶ月切っているということで、大分もう近いなっていう感じですけれども、改めて今段階での市長のお考え、伺えればと思います。
市長:
その期日に関する話ですか。
神奈川新聞 武田:
市長選に対する、はい。
市長:
私は再三申し上げているとおり、いただいた任期限られていますので、その間しっかりと政策進めることだけを考えています。
神奈川新聞 武田:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょうか、東京さん。
東京新聞 神谷:
東京新聞の神谷です。国際園芸博覧会に関して、海外出展について今どれぐらいの出展希望があって、どれぐらい目指しているのか、あるいは今後どれぐらいの国にアプローチしたいのかなどあれば教えてください。
政策経営局報道課長 矢野:
所管局から。
脱炭素・GREEN×EXPO推進局GREEN×EXPO推進部担当部長 藤村:
すみません、脱炭素・GREEN×EXPO推進局担当部長の藤村と申します。現在ですね、外務省から約130のですね、駐日大使への働きかけですとか、在外公館から各国政府への書簡発出など出展に向けた働きかけをですね、精力的に行っているところです。本市も開催都市といたしまして、海外都市とのネットワークや今年8月に横浜で開催するTICAD9を始め、COPなどの国際会議の機会も活用して、海外からの出展に向けてしっかりと働きかけを行ってまいりたいというふうに考えております。
東京新聞 神谷:
現時点で数字的には。
脱炭素・GREEN×EXPO推進局GREEN×EXPO推進部担当部長 藤村:
現時点ではですね、先日、報道などもありましたけれども、約30か国ということに聞いております。
東京新聞 神谷:
が、出展したいという表明っていうことでよろしいですかね。
脱炭素・GREEN×EXPO推進局GREEN×EXPO推進部担当部長 藤村:
ごめんなさい、ちょっとお待ちください。
政策経営局報道課長 矢野:
後ほど確認してご案内させていただきます。他よろしいですか。よろしいですか。神奈川新聞さん。
神奈川新聞 加地:
神奈川新聞加地です。議会の総合審査での市長の答弁について。
市長:
先週ですか。
神奈川新聞 加地:
先週ですね。お伺いしたいんですけども、市政運営のことを聞かれた際にですね、市民の声の中心がどこにあるのか考えながら進めてきたというお話をされてたんですけど、ここで仰っている中心っていうのはどういうことなのかっていう。
市長:
中心は中心で、中心と全体と両方把握するっていうことが、声を把握することなんじゃないかなと思いますけどね。
神奈川新聞 加地:
中心っていうのは本質的なところっていう意味ですかね。
市長:
本質的なところですね。それと様々いろいろな少数の意見とかもあるじゃないですか。だから、両方把握することが重要だと思います。本質っていうか、中心、どういったお声が大きいのか、それとあとは少数の意見も重要ですから、その意見と。ですので、統計学の概念でばらつきっていう概念がありますけれども、そういったばらつきをしっかりと踏まえて考えていくことが、市政運営上重要だという私の意図です。
神奈川新聞 加地:
大きい声というか、大多数の声と少数の声、どちらも聞いて。
市長:
両方とも重要だと思います。
神奈川新聞 加地:
ありがとうございます。その中心捉えるために、どういう聞き方といいますか。
市長:
普段からそういう意識を持ってしっかりと聞くこと、それから、やはりサンプリングも重要だと思いますので、しっかりとどういう意見の聞き方をしているのかっていうことを常に考えながら進めていくことだと思います。
神奈川新聞 加地:
ありがとうございました。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。よろしいでしょうか。それでは以上で定例会見終了します。ありがとうございました。
このページへのお問合せ
政策経営局シティプロモーション推進室報道課
電話:045-671-3498
電話:045-671-3498
ファクス:045-662-7362
メールアドレス:ss-hodo@city.yokohama.lg.jp
ページID:108-537-944