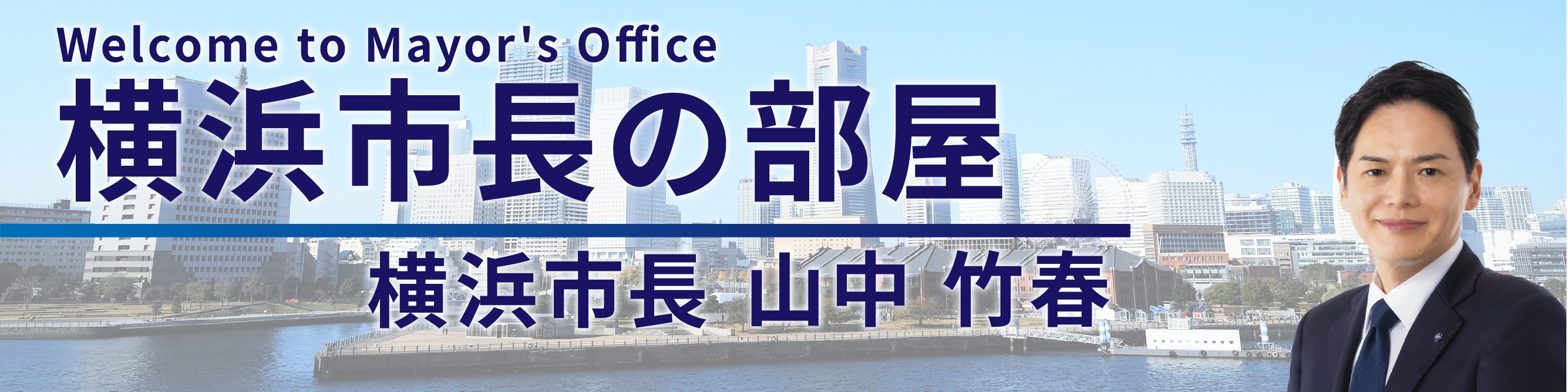ここから本文です。
- 横浜市トップページ
- 市長の部屋 横浜市長山中竹春
- 定例記者会見
- 会見記録
- 2024年度
- 市長定例記者会見(令和7年1月22日)
市長定例記者会見(令和7年1月22日)
最終更新日 2025年1月30日
令和7年1月22日(水曜日)11:00~
報告資料
- 【スライド資料】「旧根岸競馬場一等馬見所」を横浜市認定歴史的建造物に認定し保存活用します(PDF:1,096KB)
- 【記者発表】「旧根岸競馬場一等馬見所」を「横浜市認定歴史的建造物」に認定し保存活用していきます
- 【スライド資料】マルチコピー機を全区役所に設置します(PDF:542KB)
- 【記者発表】マルチコピー機を全区役所に設置します 住民票取得をもっと早く、簡単に!
会見内容
1.報告
(1)「旧根岸競馬場一等馬見所」を横浜市認定歴史的建造物に認定し保存活用します
※敬称略
政策経営局報道課長 矢野:
はい、それでは定例会見始めます。市長お願いします。
市長:
はい。まず、今日ご報告するのが、旧根岸競馬場に一等馬見所が残ってまして、それを歴史的建造物に認定したという報告であります。まず、旧根岸競馬場に関してはご存知だと思うんですけれども、そこに一等馬見所がありまして、そちらのですね、写真がフルスペックの写真であります。こちらに競馬場がありましてですね、こちらが観覧席ですね、すなわち、馬見所です。競馬場の観覧席である馬見所をですね、保存活用したいということであります。一等馬見所と二等馬見所がありまして、二等のほうは老朽化のため88年に解体をしております。こちらがフルスペックなんですけど、こちらが現存する写真ですね。こちらが実際に馬が走っている、競争している様子なんですけれども。こちら一等馬見所があって、こちらに二等馬見所があるじゃないですか。こちらの上にこの3本見えると思うんですけど、これがちょうどこれに相当しています。このチョンチョンチョンというのが、こちらのチョンチョンというか、この出っ張っているものに相当しています。ですので、こちらの観覧席が見えると思うんですけども、それがちょうどこちらの観覧席に位置しております。はい。こういう関係でありまして、慶応2年。1866年に日本初の洋式の競馬場として開設されたものであります。根岸競馬場の一等馬見所なんですが、こちらがですね、競馬場の歴史を表しておりまして、現存している、かつ日本唯一の、日本最古の競馬場ということになります。ほかはですね札幌とか、函館とか、競馬場ありまして、例えば中山競馬場というのは今でもあるじゃないですか。あれも、もともと馬見所があったんですが、今はそれは完全に取り壊した上でほかのところに観覧席を新たに作ってるんですよね。ですので、馬見所自体はないんです。ですので、馬見所が残っている唯一の競馬、競馬場の馬見所で唯一残ってるのが根岸であり、かつ最もそれが古いっていうのがこの表の意味しているところであります。ですので、ここに関して、保存活用していこうという次第であります。これ先ほどお見せした現存している馬見所の拡大図なんですが、地上7階建てになっておりまして、延べ床面積が5,000平米ということで、かなり広い建物であります。現在はちょっと建物の耐震性に課題がありますため、市民の皆様が入れる訳では、入れるようにはしてありません。今回、歴史的な建造物として認定をするっていうその枠組みなんですけれども、横浜は従来から近代建築とか、西洋館とか、古民家とか、歴史的な建造物が豊富にございます。それらの歴史的な建造物を保存し、かつ活用して多くの方に見ていただく、楽しんでいただく、そういったことで今、横浜市認定歴史的建造物という認定制度を用意しております。これに認定いたしました上で、保存活用を積極的に推進していくという枠組みであります。認定を開始したのが1988年でありまして、現在までに104件が認定されております。こういった枠組みの中で本市としてこの馬見所の保存活用を更に進めていく上で、このたび馬見所認定しますというご報告であります。認定をした理由なんですけれども、やはりなんといっても日本初の洋式競馬が開催された競馬場の観覧施設であるっていうところは大きなポイントでありますし、また、各地のモデルとなった日本発の鉄骨鉄筋コンクリート造りの競馬場建築なんですね。また、先ほど申し上げたとおり、現存する、かつ唯一の日本最古の競馬場建築ということになります。こういった認定理由を踏まえまして、耐震化をより一層進め、馬見所をですね、今後も後世に残していかなければならないというふうに考えまして、このたび、認定することにしたという次第であります。はい、こちらの報告は以上です。
政策経営局報道課長 矢野:
はい、それではこの件についてご質問をお受けします。いつものお願いになりますけれども、ご質問の際、お手元のマイクのスイッチのご確認をお願いいたします。ではまず、幹事社からお願いします。
NHK 岡部:
はい、幹事社 NHK岡部です。ご説明ありがとうございました。今回の認定なんですけれども、以前よりそういった要望もあった建物かと思うんですが、このタイミングになった理由などあればお聞かせいただきたいのと、認定することで今後のまちづくりだとか、にぎわいにどんなふうに取り組んでいくのか、お伺いできればと思います。
市長:
はい、ご質問ありがとうございます。この馬見所は、横浜市の歴史的な建造物であります。しかしながら、早急な耐震化を図った上で保存活用していくことが求められております。適切な耐震化を施した上で今後、周辺には根岸の森林公園がありますので、しっかりと一体的なまちづくりを進めていきたいという思いで、このたび認定をすることにいたしました。
政策経営局報道課長 矢野:
それでは各社いかがでしょう。朝日新聞さん。
朝日新聞 堅島:
朝日新聞の堅島です。今回の保存活用、認定によって、助成なり、補助なり、予算の面で何かメリットとかというのがあるんでしょうか。
政策経営局報道課長 矢野:
所管局。
都市整備局企画部長 松本:
はい、都市整備局企画部長の松本でございます。民間のですね、方がお持ちのものにつきましては助成金がございます。要綱に基づいて、例えば耐震改修であれば3分の2の補助、非木造、RC造ですとか、鉄骨造であれば、上限額が2,000万という補助制度を用意してございます。今回この施設は横浜市が所有してるものですので、横浜市の予算などで、今後の保存活用を図っていく予定でございます。
朝日新聞 堅島:
分かりました。もう1点が、赤レンガ倉庫とかはこの中に入るっていう部分で観光客の方とかっていうのは行ってみたくなるのがあると思うんですが、今回この現状では入れないということで、今後の展開として耐震化を施して中に入れる状態にするとかそういった見通しはあるんでしょうか。
市長:
そうすべきだと思います。そうした上で観光に来られた方が日本最古の歴史的な建造物を実感できる。そういった場所にしていきたいというふうに思ってます。
朝日新聞 堅島:
はい、ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。読売新聞さん。
読売新聞 田川:
読売新聞の田川と申します。2点教えていただければと思います。まずこの建造物に認定した日にち教えていただきたいのと、今後のスケジュール感の目途があれば、例えば何年、何年度を目指して公開ですとかその辺り教えていただければと思います。
政策経営局報道課長 矢野:
所管局。
都市整備局企画部長 松本:
はい。認定日につきましては本日でございます。令和7年1月22日が認定日となります。
政策経営局経営戦略部政策担当部長 黒田:
経営戦略部担当部長の黒田です。よろしくお願いします。今後の活用の方向性なんですけども、来年度ですね、耐震化に向けた詳細の設計等を行っていきます。それによってですね、工法とかを確定してから工事に入っていきますので、今何年度としっかり決めてはまだできてないんですけれども、今95年を迎えてまして、あと5年でこの100年を迎えますんで、そういった節目のタイミングですね、歩調を合わせるような工事の完成というのを見据えて、今後推進していきたいというふうに思っています。
読売新聞 田川:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。神奈川新聞さん。
神奈川新聞 武田:
神奈川新聞 武田です。こちらのすみません、まず認定の制度なんですが、これ市の認定歴史的建造物に認定されると国の予算とかも使えるんでしたっけ。
都市整備局企画部長 松本:
この認定制度が市の助成金が使えるということでございます。もう少しあれなんですけども、あわせて国費が使えるかどうかにつきましてもですね、今検討中でございます。
神奈川新聞 武田:
ありがとうございます。来年度設計で、ごめんなさい、100年の節目というのは2029年度になるイメージですか。
政策経営局経営戦略部政策担当部長 黒田:
はい、そうです。2029年に100周年を迎えていることになります。工事の内容によっていつ完成するかはまだ定まっておりませんけれども、そういった節目を狙ってですね、進めていきたいというところでございます。
神奈川新聞 武田:
ありがとうございます。あと最後にもう1点、先ほど朝日さんからもありましたが人が入れるようにしていくべきだというお話ありましたけれども、例えばどんなイメージ、今の形を残してその中に入ってもらうようなイメージになるのか、あるいは別のちょっと改築していくようなイメージになるのか、どんなイメージをお持ちでしょうか。
市長:
まだその辺まで、細かいところまで、例えば多少リアル感を増すために何か施すとかそういったところまではまだ詳細決まっておりませんが、まずは耐震化を施し、しっかりと当時の雰囲気を味わえる、そういった建築物として市民の皆様にお見せしたいというふうに思ってます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。産経さん。
産経新聞 橋本:
産経新聞の橋本です。よろしくお願いいたします。だいたい今までに出た質問にもちょっと重なるんですけれども、根岸森林公園と一体の活用とか周辺のまちづくりと合わせた活用っていうのはちょっとその地域のイメージをちょっと私よく分からないんで。どういうイメージなのかもう少し、森林公園と一体ってどういうふうにするのかなとか、教えていただきたいです。
市長:
位置関係が、森林公園があって、すぐ馬見所があるんですね。森林公園というのは市民の皆様の憩いの場所になっています。馬見所のあそこの観覧席に行きますとかなり高台にありますのでいろいろ風景もいいですし、森林公園も近いっていうのもありまして、そこを一体的に開発することによって、子育て世代もそうですし、様々な世代、子育て世代を含む様々な世代に楽しんでいただけるようになるのではないかというふうに思ってます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。東京新聞さん。
東京新聞 神谷:
東京新聞の神谷です。この公園に隣接で根岸住宅地区、米国の。今跡地利用も考えてらっしゃるかと思うんですけど、その辺との関連というのはまちづくりで何かあるんでしょうか。
市長:
そこも含めて、そこも視野に入れて開発はすべきだと思うんですが、何分にもまだ根岸の基地返還の時期等もまだはっきりは決まっておりませんし、その後の地権者の調整等もあるかと思います。ですので、神谷さんおっしゃるとおりそこまで含めて一体的に何か市として、できればいいんですけれども、ちょっとまだそこまではいけないかなと思います。はい。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。タウンニュースさん。
タウンニュース 門馬:
タウンニュースの門馬です。よろしくお願いします。目途として100周年を1つの節目と考えてるっていうお話ありましたけれども、この近くに馬の博物館、今休館中ですけどもあったりして。そういったこの場所が耐震する、人を入れるというだけじゃなくて、その馬事文化の1つの拠点みたいな位置づけも考えられるかなと思うんですけども、そういった文化として、この競馬場があったということを何かこう残すための戦略みたいの、今後のお考えは何かあるのでしょうか。
市長:
歴史的な建造物がありますので、そこの耐震化を推進していくことで、歴史的な建造物としての魅力を最大限引き出せる、かつ一体的なまちづくりを進めていきたいなというふうに思っています。
タウンニュース 門馬:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。よろしいでしょうか。それではこの件の質疑は以上となります。事務局入れ替えますので少々お待ちください。
(2)マルチコピー機を全区役所に設置します
矢野:
それでは続けて市長お願いします。
市長:
はい。続いてマルチコピー機を全ての区役所に設置するというご報告であります。大分コンビニで証明書を取るっていうことも、広がりつつあるんですが、ただ、依然として区役所に来られて、住民票を取られる、申請書を書いて、並んで、待って、そういった方が多いのも事実であります。そういった方々に、近くのコンビニで取れますよということを改めて知っていただくことが必要であります。一旦区役所に来て、そこでご案内をして、こんな簡単に取れるんだっていうことが分かれば、次からもし必要になられた際はお近くのコンビニで取るようになろうかと、取るようになるというふうに思います。市民の皆様の行動変容ってほどではないんですけれども、近くで時間かけずに取れるっていうことを知っていただくための、そういったことの促進として、18区にこういったコピー機を置くことにいたしました。全区役所にマルチコピー機を設置することによって、コンビニと同じもので、基本的には同じものであります。これは設置するということであります。ローソンさんと協定を結んでおりますので、その協定の中で、13区にまずローソンさんからの提供でコピー機を置きます。残りの5区に関しては、本市としてリースいたしました。これで18区にマルチコピー機を置いて、実際に戸籍なり、住民票取りに来られた方に、これをご案内して使っていただく、利便性を実感していただくという、そういった取組であります。平成6年11月から順次設置稼働しておりまして2月3日で全ての区役所で稼働いたしますので、このタイミングでご報告をいたしました。
【訂正前】平成6年11月
【訂正後】令和6年11月
マルチコピー機で実際とってみますと、意外に簡単、大分今ユーザーインターフェイスも良くなってきておりますので、意外と簡単だった、それから手数料が安くなる、そういったお声いただいておりますので、家の近くの次回はコンビニ使うよって言っていただくことが狙いであります。まず窓口よりも安くして、それからあとは手続書類の記載等は一切不要でありますし、それから閉庁時間帯もOKにしてございます。ですので、土日休日、夜間ですね。そういった時間でも、取れる。全部が取れるわけではないですけれども、住民票等ですね、とれるようになります。はい。それから書かない窓口の取組についてもこちらに今まとめているとおりでありますので、こちらについてはちょっと割愛させていただきます。「書かない」「待たない」「行かない」というデジタルの取組を今後も推進いたしまして、市民の皆様の利便性図っていきたいというふうに思っています。こちらに関しましては以上です。はい。
政策経営局報道課長 矢野:
それではこの件のご質問をお受けします。幹事社からお願いします。
NHK 岡部:
市民の方に体験してもらうための設置ということですけれども、改めて市民への呼びかけがあればお願いします。
市長:
はい。これまでは役所に行って住民票や戸籍を取る時代でありました。これからはコンビニで取れる時代です。休日も取れますし朝早くから夜遅くまで取ることができますので、その便利さを実感していただきたいと思っています。
政策経営局報道課長 矢野:
それでは各社いかがでしょうか。日経さん。
日経新聞 松原:
日本経済新聞の松原です。今地方公務員の副業の推進について注目が集まっているかと思うんですけども、現時点での市長の考えについてお聞かせください。
市長:
このマルチコピー機と別の話。
日経新聞 松原:
ごめんなさい。
政策経営局報道課長 矢野:
この後一般質問ご案内いたしますので。このマルチコピー機の件で、その他ご質問ありましたら。朝日さん。
朝日新聞 良永:
朝日新聞の吉永です。今回、マルチコピー機で実際にコンビニでの便利さとかも分かってほしいっていうきっかけ作りかと思うんですけれども、現在交付の方法の現状の内訳、区役所での交付が多いのか、それともコンビニ交付まだ少しですとか現状を教えていただけますか。
市長:
区役所の交付が多いです。だいたい3割ぐらいがコンビニ交付というふうに聞いております、本市の場合は。その割合をどんどん上げていきたいというふうに思ってます。
朝日新聞 良永:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。よろしいでしょうか。読売さん。
読売新聞 田川:
読売新聞の田川です。もし把握されていればなんですけれども、他の自治体での取組をもし把握されてたら、他の自治体と比べてどれぐらい先進的なのかっていうのが分かればちょっと教えていただければと思います。
市長:
他の自治体で、マルチコピー機を各所に置いているような、そういった市町村があるかっていう様な質問でよろしいですかね。
政策経営局報道課長 矢野:
所管局。
市民局窓口サービス部長 高橋:
市民局の窓口サービス部長高橋と申します。よろしくお願いします。他の自治体でいわゆる直営、市の直営により設置をしているっていうものについてちょっと県内のものしか現状把握できてないんですけれども、県内ですと、鎌倉市、伊勢原市、南足柄市にリースにより設置をしているというふうに伺っております。
「リースにより設置をしている」と申し上げましたが、正しくは、購入などの可能性もございます。
市長:
何台ぐらいか分かります。
市民局窓口サービス部長 高橋:
台数までは、申し訳ありません、ちょっと把握してございません。それからですね、本市と同様に株式会社ローソン様との協定で取り組んでいる自治体もございまして、そちらにつきましては福岡市、北九州市、それから東京都品川区ですね、こちらのほうで本市と同様に取り組んでいるという話を伺ってございます。以上です。
読売新聞 田川:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、この件の質疑は終了いたします。事務局入れかわりますので少々お待ちください。
2.その他
政策経営局報道課長 矢野:
はい、それではこれより一般質問に入ります。複数ご質問がありましたら、まとめてご質問いただければと思います。ではまず、幹事社からお願いします。
NHK 岡部:
はい、今月発表のあった市の人口の動態の関係なんですけれども、1月1日時点のものが4年ぶりに増加というものでしたけれども、改めて市長の受け止めをいただければと思います。
市長:
はい、ご質問ありがとうございます。今回、4年振りに人口増となりました。ご承知のとおり、人口増は社会増、転入、転出と、自然増減、死亡と出生の差で、それらのバランスで決まります。ちょっと今、データを詳しく分析しているんですが、過去20年間で社会増が最大になりました。これに関しては議会とともに行ってきた子育て政策をはじめ、そういったことが好感されている可能性もあります。今、データをちょっとまとめていますので、月曜日に、予算案発表がありますので、その際にですね、もう少しデータをお見せしたいというふうに思っています。
NHK 岡部:
まだ、今の段階ではちょっと言いづらいのかもしれないですけど、そういった取組が効果が出てきたとか、そういった手応えはいかがでしょうか。
市長:
いろいろやってきました。子育て政策含めて、いろいろな政策を行ってきました。それらが子育て世代を始め、好感されていると嬉しいですし、そういったことを確認できるような、いろいろちょっとデータ分析を進めているところであります。やはり、全世帯の全人口が増えるっていうことが、今は発表しているとおりなんですけども。その中で、例えば子育て世代がどれぐらい増えているのかとか、あるいは65歳以下を含めて生産年齢人口がどれぐらい増えているかとか、そういったことを今、調べていますので、そこを月曜日にお話しさせていただきたいというふうに思います。
NHK 岡部:
ありがとうございました。
政策経営局報道課長 矢野:
それでは各社いかがでしょうか。日経さん。
日経新聞 松原:
大変失礼いたしました、日経新聞松原です。地方公務員の副業推進についての市長のお考えをお聞かせください。
市長:
はい、現在の地方公務員法では、ご承知のとおり兼業を制限しています。それを今後ですね、地方公務員の兼業と副業の弾力化をですね、目指していくということを今、政府のほうでご発表されるんだと思いますが、こういった地方公務員が副業しやすい環境をつくるということは私は必要だというふうに思っています。もちろん、公務員の、公務員としての品位の保持とのバランスもありますし、それから職務の公正性ですよね。公務員という立場である以上、疑義が疑われる副業を行うことは当然できませんし、それらのバランスを適切に保持した上で、より働きやすい、そういった環境を作れるといいなというふうに思っています。
日経新聞 松原:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょうか。時事通信さん。
時事通信 廣野:
時事通信の廣野です。何点か伺います。まず、アメリカのトランプ大統領が就任して就任初日にパリ協定からの再離脱を指示する大統領令に署名したことへの市長の受け止めをお聞かせください。
市長:
はい、ご質問ありがとうございます。まず、パリ協定の離脱に関して、大統領令に署名をされたことは率直に申し上げて残念です。ただ、パリ協定の重要さ、今後も続きます。世界としての危機を回避するために全世界が協力をしてパリ協定に定められた基準を達成すべく、あらゆる努力をすべきであります。本市としても、大都市横浜としての脱炭素化に向けた努力を今後も続けて、しっかりと都市としての責務を果たしてまいります。
時事通信 廣野:
ありがとうございます。次に伺いたいんですけれども、今のフジテレビで横浜市の消防司令センターを舞台にしたドラマが放送中ですけれども、市長、今、ご覧になってますか。
市長:
見たと言えば見たんですけど、こないだスペシャルでちょっとだけ見ました。最初だけちょっと。その後は時間がなくて見られませんでしたけれども。
時事通信 廣野:
分かりました。そのドラマなんですけども、フジテレビと連携協定を結んで市の消防局が全面協力しているという、昨年発表がありました。タレントのトラブルをめぐってフジテレビが調査委員会を設置するなどの動きもありますが、市長の受け止めと、何か今まで市として対応した、この件で対応したことがあるのかっていうことと、今後、フジテレビに対応を求めたり、その辺り市長のお考えをお聞かせください。
市長:
はい、ご質問ありがとうございます。まず、その件については承知しておりますが、市として何か特段のアクションを起こしたということはございません。まず、今後についてですね、今、様々状況が推移していると、流動的だと思いますので、状況をしっかりと注視していきたいというふうに思っています。
時事通信 廣野:
その関連で、総務省の消防庁がPRポスターを全国の消防本部に配付予定だったのを、PRポスターの配付を延期するといった、その動きもありますが、その辺はどう受け止めてますか。
市長:
はい、本市としてもですね、横浜市消防局の業務の理解につながるものとしてですね、例えばSNS等での発信も行ってきたところでありますし、本市としても、消防局としていろいろ、市民の皆様の安全安心を守るために日々活動している、そういった姿をですね、ご理解いただきたいなと思っていたところでした。しかしながら、そういったことがあまり許容されないっていう状況になるようでありましたら、本市としても対応を考えたいと思います。
時事通信 廣野:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょうか。東京さん。
東京新聞 神谷:
東京新聞の神谷です。横浜国際プールの再整備について、昨年12月に議会の委員会のほうで原案が発表になりましたが、まだ正式には事業計画としての公表がされていないかと思います。で、どうなっているっていうのはちょっと市民の声も聞いたりするんですけれども、その発表の予定と、あと原案とおりになった場合の今後のスケジュールについて教えてください。
市長:
先日の常任委員会でいただいたご意見も踏まえて、年度内に事業計画確定する予定で良いですよね。
にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課長 高梨:
はい。
市長:
はい。スケジュール感に関してはそういうことであります。
東京新聞 神谷:
その再整備自体のスケジュールですとか、いつ頃みたいな、改めて。
にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課長 高梨:
スポーツ振興課長高梨と申します。ご質問ありがとうございます。今後ですが、原案の中でPFI事業で進めたいという形で記載させていただいてますので、計画ができた後についてはPFIの準備、またPFIの準備終わった後にですね、事業者が決まった後に、事業者が設計、また工事をしていくというスケジュール感になります。
東京新聞 神谷:
通常、原案発表の後あまり時間がかかるものっていうのは多くはないのかなと思って、何か今その原案後の取りまとめで時間がかかっているような要因があるんでしょうか。
にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課長 高梨:
特段はありませんが、12月の中旬に原案を市会のほうで発表させていただいた後にですね、年末年始ありましたので、そこで常任委員会でいただいたご意見も参考にしながら今最終的な計画を今作成している最中でございます。
東京新聞 神谷:
大幅に変わるということなんですか。
にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課長 高梨:
今のところは大幅に変わるという予定はございません。
東京新聞 神谷:
意見を盛り込んだ何か新たな、細かい計画が入ったりするっていうことですか。
にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課長 高梨:
今その辺も含めて事務局のほうで作業している最中でございます。
東京新聞 神谷:
それについても市民意見はとらないんですか。
にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課長 高梨:
取る予定はございません。
東京新聞 神谷:
分かりました。ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょうか。朝日さん。
朝日新聞 良永:
朝日新聞の良永です。市長選の日程の関連でお伺いしたいんですけれども、現状8月下旬に任期満了というところで、直近連休が重なっていたりですとかTICADがあるっていうところで日程を決めていく、スケジュールを決めていくところが難しいところかと思います。最終的な決定をされるのは選管かとは思うんですけれども、もし市長個人のお考えですとか、今の思っていることあれば教えていただけますでしょうか。
市長:
特にございません。日程に関しては選管にお尋ねください。
朝日新聞 良永:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。産経さん。
産経新聞 橋本:
産経新聞の橋本です。よろしくお願いします。2月2日からカーリング選手権、首都圏初開催のカーリング選手権がありますけれども、大会に向けての期待や抱負があれば、お聞かせ願いたいのと、あと横浜市として大会開催まであと10日間くらいあって、大会期間中とか何かやることが、大会をやるために何かやることを考えているのがあれば教えてください。
市長:
はい。昨年に横浜BUNTAIが開幕して、横浜BUNTAIがオープンになり、そこのアリーナを使って氷を張って海外の環境と同じ環境で大会をやってもらうということが可能になります。是非、本市としても、カーリングのですね、盛り上げに一翼を担えるといいなと思いますし、そういった環境がアリーナに専用の氷を張って国際カーリング大会をやるっていうのが非常にレアな環境、それが横浜市民の皆様がすぐ間近で、そのカーリングの大会を、プロの大会を見られると。そういった環境を作りたいなっていうふうに私は思っておりますので、スポーツを推進していくまち横浜の立場としても、今回のカーリング大会の開催は嬉しいことであります。
産経新聞 橋本:
何かやられる予定はあるんですか。
市長:
サイドイベントですかね。
産経新聞 橋本:
はい。
政策経営局報道課長 矢野:
所管局から。
にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課長 高梨:
スポーツ振興課長高梨と申します。ご質問ありがとうございます。今ですね、予定してるのがですね、カーリングと観光を一緒にした冊子を発行させていただいて、観戦している方々にお配りをさせていただければなという形で思っています。その他ですね、大会の中で市民の子供たちに、最後の表彰式のときにエスコートキッズっていう形で子供たちも一緒に表彰していただくみたいな取組なども予定をしております。以上です。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょうか。神奈川新聞さん。
神奈川新聞 武田:
神奈川新聞武田です。前回の抗議文の関係で2点だけ伺います。市長に。まず前回、抗議文をお読みになっていないということでしたけれども、その後、確認はされたでしょうか。
市長:
確認しました。
神奈川新聞 武田:
その上でどのようにお感じになられたかというのだけ伺えればと思います。
市長:
こちらとして疑義照会があった点を武田さんと加地さんにお尋ねしたっていうふうに解釈してます。
神奈川新聞 武田:
それが報道機関に対する圧力になったり、萎縮を招くような行為になるかっていう、その点はいかがでしょうか。
政策経営局シティプロモーション推進室報道担当部長 藤岡:
武田さん。失礼します。報道担当部長藤岡です。前回も若干触れさせていただいたかもしれませんが、抗議文というふうな表現を使われているんですけれども、我々としては記事に対して、これちょっと偏った印象を与えかねないなというふうに、我々が取材対象の当事者として感じたことについて、疑義を呈してご意見を求めた文書というふうに私たちは思っておりますので、できればそこにご回答いただければ済む話なのかなというふうには思っておりますので、武田さんなり加地さんなりご回答をいただければありがたいなというふうに今も思っております。また回答いただけておりませんので、是非ご回答いただければなというふうに思ってます。
神奈川新聞 武田:
その上で市長の報道機関に対するああいう形で出したことに対する市長のお考えというのはいかがでしょうか。
市長:
疑義があった場合に、あるいは市民に誤解を与えるような表現があった場合に、ご質問をするっていうことはあってもいいと思いますが。抗議文ではないというのが私も文章見ての印象でしたし、所管もそういうつもりで出したわけではないというふうに申してます。
神奈川新聞 武田:
そもそもその抗議文じゃないっていうご認識ってことですか。
市長:
質問の照会、疑義の照会って申し上げていると思いますが。
神奈川新聞 武田:
分かりました。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。よろしいでしょうか。それでは以上で定例会見終了します。ありがとうございました。
このページへのお問合せ
政策経営局シティプロモーション推進室報道課
電話:045-671-3498
電話:045-671-3498
ファクス:045-662-7362
メールアドレス:ss-hodo@city.yokohama.lg.jp
ページID:353-954-691