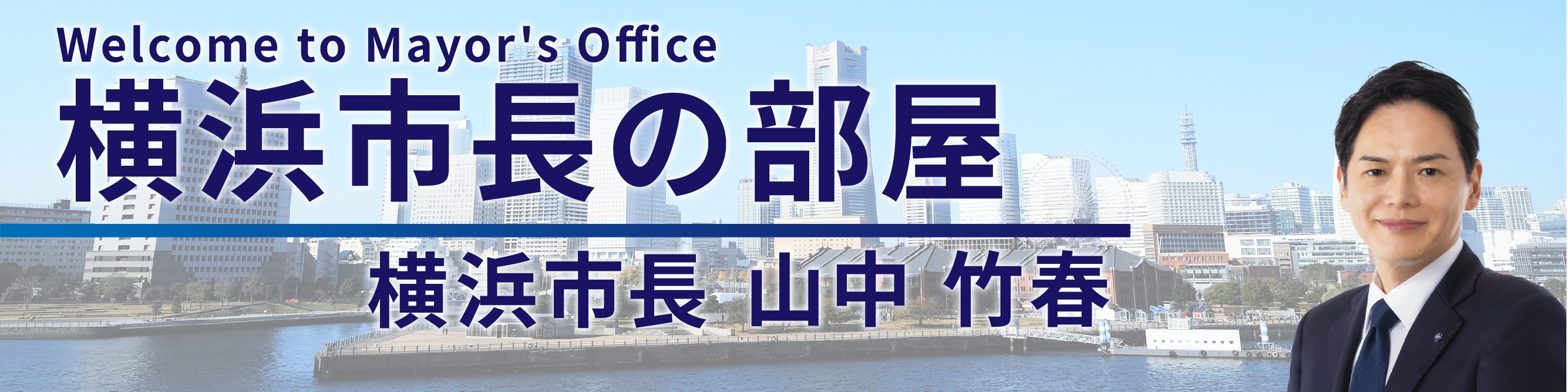ここから本文です。
- 横浜市トップページ
- 市長の部屋 横浜市長山中竹春
- 定例記者会見
- 会見記録
- 2024年度
- 市長定例記者会見(令和7年1月9日)
市長定例記者会見(令和7年1月9日)
最終更新日 2025年1月14日
令和7年1月9日(木曜日)15:00~
報告資料
会見内容
1.報告
子育て応援アプリ パマトコ
新たなコンテンツを追加しました!
※敬称略
市長:
改めまして、パマトコなんですけれども、横浜市が作ったアプリであります。子育てのための総合アプリって言っているんですけれども、そのアプリがあって、アプリにアクセスすればいろんなところに飛べるようにする、例えば、行政の役所の申請物に飛べたり、できたり、それから母子健康手帳をですね、そっからいけたり、あるいは施設を探索したりすると、言ってみたらポータルサイトならぬ、ポータルアプリを目指しています。まずはそこを入口にして、いろんなことにアクセスしてもらおうと。そういう意味で総合アプリと、全国初の総合アプリと言っています。今このパマトコなんですけれども、出産された方が区役所に来てお手続きをされて、ご案内をしていますので、0歳児は90%以上が既に登録してくださっています。登録者数が61,000人であります。今後、未就学児を対象にしたサービス、それから学齢期の方、小学校、中学校の方を対象とした、今度サービスも始めますので、今後もっともっと増えていくだろうというふうに思っております。ちなみに、出産費用の助成金、昨年から始めました。出産費用の助成金に関しましては、もうほとんどがこのパマトコ使って申請をしてくださっています。今回ですね、新たにパマトコっていうこの箱があるのでできた、初めようと思ったことを2つほどご紹介させていただきます。1つが子供の健康相談・医療相談、それからもう1つが子育て応援マガジンを新たに始めたいと思います。今日からですね、こちら始めようと思います。まず、1つ目の妊産婦・こどもの健康相談なんですが、このアプリを使ってご相談を保護者の方からご相談をしてもらうスキームです。こういったサービスっていうのは、いろいろあると思うんです、世の中に。例えば、ネットでGoogleとかYahooとか、そういったところから探してって、登録してログインして質問とかできるようなあるとは思うんですけども、そうではなくてこのパマトコっていう箱から、無料でお尋ねをしてもらえるようにしたというところがポイントだと思います。まず、子育て相談のサービスを始めようと思った背景なんですけれども、既に横浜市が行ったニーズ把握の結果に基づいております。通院するほどではないんだけれども、専門家に相談したいっていうようなケース、結構多いと思うんですよね。例えば、結構湿疹が出ちゃって困っているとか、ちょっと夜中咳が出て、毎晩毎晩咳が出て困ってるとか、なかなか寝つかないとか、そういう、医療っていうことではないかもしれないですけれども、やっぱりこの子育てに係るようなお悩みでも、医者にもちょっと聞いてみたいっていうようなケースってあると思うんです。それから、なかなかそういう相談があったとして、クリニックとかにも行きたいんだけれども、小児科にも行きたいんだけどもちょっと時間がないよという方のニーズが非常に高いということが分かりました。まず、昨年ですね、令和5年度ですね、昨年度ですね、港北区でモデル事業やったんですね。「オンライン母子保健相談事業」、名前は固いんですけれども、この中で登録664人にしていただいたんです。この中で、実際にご利用されたのが445人でした。何かお困りごとがないと相談もしないでしょうから、3分の2ぐらいが何らか相談をしていただいて、相談件数が累積で1,400件ぐらいだったんで、平均なんですけども、1人あたり3回ぐらいは質問されていると。実際の繰り返しで、繰り返しというか2回、3回質問していただいた、リピーターですよね、リピーターの方もかなりいらっしゃったので。かつ使われた方の85%が、ありがたいというご評価をいただいたので、こういった港北区でのモデル実施を踏まえまして、全区展開しようよと、全区展開するにしても、何かこういう番号が、電話かけてくださいとか、こういったURLがありますんで質問してくださいだけだとなかなか広がらないんですが、パマトコがあります。パマトコのポータルっていうところの良さを生かして、全区展開を決めたっていうのが経緯であります。主に小児科のご相談と、まだ妊娠されている方向けの産婦人科のご相談と2つできるようにしております。これパマトコに登録すると、こういったサービスを利用できるようになってます。すぐに医師が、例えばお電話に出て回答するっていうのではなくて、まずオンラインフォームから質問していただきます、さっき言った湿疹出ちゃったんですけどどうしたらいいですかとか、母乳が足りているのか足りていないのか、どうすればいいかとか、そういったご相談をしていただきます。本当に緊急の場合は、例えば#7119とかを、今後パマトコ経由でお知らせします。なかなか#7119も、今度我々が始めた事業を県のほうで引き取っていただいて、全県展開しているところでありますが、なかなかその番号もみんなが知ってるかっていうとそうでもないと思うんですよ。ただ、今度パマトコ経由で、まずアージェントなもの、緊急なものに対しては#7119にお電話ください。それ以外で、少し待てるものに対しては、かつちょっと平日のね、9時、5時とかであったらクリニックに行ける方は行って欲しいんですけども、そこまでじゃないよっていう方に対しては、待てるよっていう方に関して、医療相談を受け付けるっていう建付けにしております。大体どのくらいでリプライが返ってくるかなんですけど、これ全体の6割ぐらいについて8時間以内に回答をいただいております。これはこういったサービスがあります。サービスを利用しています。ただ、繰り返しになりますけど、パマトコっていう箱があって、基本的に全員今度、このパマトコっていう入口を利用しますので、だからこそこのサービスの利用を決めたというのが経緯であります。実際、このサービスも、これ港北区のデータなんで、かなりリアルだと思うんですけれども、全体の6割が8時間以内にご回答いただいているので、夜にメール、オンラインで質問していただければ、朝起きたときには大体もう返ってきてるかなっていうスピード感であります。はい。2つ目がですね、これがだからこどもの健康相談とあと妊産婦の健康相談、2つ新たに始めたいというふうに思います。2つ目が、横浜の子育て応援マガジンになるものを始めたいというふうに思います。新たにサイトでですね、横浜市の職員が記事を作りまして、子育て世帯向けの情報提供をしようということであります。どういった内容を伝えるかなんですけれども、まずですね、全庁的にメンバーを募りました。20代、30代の子育て中の職員が手を挙げてくれました。自ら、だったらやってみたいと、私が知ってる横浜市の良い取組とか、子育て世代向けのね、そういった取組ですごいこういうのが役に立ったんでお伝えしたいとか、そういったことを記事にしたいっていうようなことを自発的に手上げていただいて、そういったものをお伝えしたいなと思ってます。企画から原稿の作成まで職員が手がけたコンテンツとなります。この100本記事原稿を作成なんですが、制度や施設を熟知しているからこそ伝えられる、市の職員なので、しかもリアルに子育て中なので、制度や施設を熟知しているからこそ伝えられる内容がありますし、それから行政だからこそ伝えられる、正しい情報を発信できると思います。今、ネット社会でいろんな情報があります、ネット上には。ただ、行政だからこそ伝えられる正しい情報っていうものをお伝えしたいなという思いがあります。それから子育て世代のニーズに応えるテーマを取り上げることができます。こういった子育て応援マガジンが、例としてこういったいくつか挙げてますけれども、こういったものをパマトコでですね、発信して実際に横浜で子育てをされている方の様々な子育てのしやすさの向上につながるといいなと思っているところです。はい。これにあわせてパマトコの画面もいくつかリニューアルしているところであります。こちらに関する報告以上となります。
政策経営局報道課長 矢野:
はい、それではこの件についてご質問をお受けします。いつものお願いになりますけれども、ご発言の際はお手元のスイッチのご確認をお願いいたします。では、まず幹事社からお願いします。
日経新聞 松原:
はい、日本経済新聞の松原です。今回、この2つの機能を追加したねらいについて、改めてご説明お願いします。
市長:
はい、ありがとうございます。先ほどの私の説明の中でも何度か申し上げましたが、まず本市として、パマトコっていうポータルのアプリを持っている強みを最大限に生かしたいなと思いました。それとあと、ニーズ調査でお困りになられている方がいる。ただ、なかなか日中忙しかったりしてクリニックとかに行く時間もない、それから夜中で困ったりしている場合ですね、そういった場合にご相談をしてできるだけ早く回答をいただけるようにする、そういった医療サービスを始めたいと思いましたし、実際に始めてみて、高評価で使い勝手も良いということでしたので、全市展開をすることにした次第であります。今後ですね、パマトコをより使いやすく、より便利にしていくためにこういったツールをどんどん増やしていきたいというふうに思っています。はい。
政策経営局報道課長 矢野:
それでは各社いかがでしょうか。産経さん。
産経新聞 橋本:
産経新聞の橋本です。よろしくお願いします。まず最初に、登録者数61,342人ということなんですけれども、9割が0歳児ということなんですけれども。
市長:
9割が0歳児?
産経新聞 橋本:
0歳児の9割。すみません。
市長:
0歳児の9割が登録している、はい。
産経新聞 橋本:
これ、0歳児から15歳までが対象なんですか。
市長:
今後はそうしたいと思っています。
産経新聞 橋本:
現段階では。
市長:
一応今もそうなんですが、例えば、施設検索とかイベント検索とかは子育て世代だったらだったら皆さん使いやすいと思うんですよね。 ただ、その他のこういった出産費用の手続きを役所に来なくてもできるようになるとか、あるいは今回導入した医療相談とかそういったことは未就学児が対象になりがちだと思いますので、今後、学齢期のお子さんたち向けにすぐーると連携した取組なんかもですね、 始めたいなと思っています、はい。
産経新聞 橋本:
後ででもいいんですけれども、61,342人の年齢別の内訳みたいなのを。
市長:
あとですみません、所管からお伝えいたします。はい、ありがとうございます。
産経新聞 橋本:
それとですね、いつでも相談のほうなんですけれども、これ医師や助産師などの専門家から回答するっていうことなんですけども、これ専門家をどうやって集めてるのかと。
市長:
これはこういったサービスがありますので、そこの業者さんとプロポーザルですかね。ポーザルで契約をしております。
産経新聞 橋本:
費用はいくらぐらいかかったんですか。
市長:
その業者さんに払う、そこに関してはちょっと。
政策経営局報道課長 矢野:
所管局から。
市長:
所管局。細かい話であったらいろいろ内訳があるんだったら、終わった後でもいいですけど。
こども青少年局こども福祉保健部担当部長 柴山:
はい、こども青少年局こども福祉保健部担当部長の柴山と申します。ご質問ありがとうございます。一応、オンラインの健康相談ということでですね、契約をしていまして、大体税込みですね、5千万弱というふうな形で、はい、契約をさせていただいております。
産経新聞 橋本:
年間でってことですかね。
こども青少年局こども福祉保健部担当部長 柴山:
今回は準備作業もございましたので、一応、今年度いっぱい、3月までという。
産経新聞 橋本:
3月まで。いつから3月までなんですか。
こども青少年局こども福祉保健部担当部長 柴山:
実際に稼働し始めるのは、1月から、今日からっていう形になりますが、今年度いっぱい、3月までという形になりますけど、様々コンテンツの構築とか、そういった部分もございましたので。
市長:
そうなんですね。
こども青少年局こども福祉保健部担当部長 柴山:
契約してからは、はい。
市長:
インフラ、このサイトとパマトコの連携とか、そういったところに対する設計費用もありますので、それは1回限りじゃないですか。だから、今後4月以降ランニングしてるかどうかを、この1月、3月でまず全市でパイロット的にやって、更に改良点があったら、そういったことを加えてですね、できる限り私は全市展開したいなと思ってます。はい、継続的に。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。よろしいでしょうか。それではこの件の質疑は以上で終了します。事務局入れ替わりますので少々お待ちください。
2.その他
政策経営局報道課長 矢野:
はい、では引き続き一般質問に入ります。複数ご質問ありましたら、まとめて簡潔にお願いいたします。ではまず、幹事社からお願いします。
日経新聞 松原:
日本経済新聞の松原です。
市長:
はい。
日経新聞 松原:
今回、2025年に入って初めての会見ということなので、2025年に向けての抱負を一言いただければと思います。
市長:
抱負ですか、はい。今年、これまでもそうだったんですけれども、今年も人にやさしいまちを目指した総合的な取組を進めていきたいとふうに思います。あらゆる世代が安心して暮らせる、そういう横浜をつくるために、取組を総合的に展開してまいりたいと思います。はい。
政策経営局報道課長 矢野:
それでは各社いかがでしょうか。朝日新聞さん。
朝日新聞 良永:
朝日新聞の良永と申します。1点お伺いします。先日、東京都のほうで無痛分娩の費用の助成をする方針を固めたという報道があったんですけれども、一方で隣県との地域格差というところも指摘されているところで、それについて横浜市の市長としてのお考えをお聞かせ願います。
市長:
はい、ご質問ありがとうございます。まだ東京都のその件は情報としては承知しておりますが、詳細が明らかになっていないので、東京都の取組へのコメントは差し控えさせていただきますが、確かに現状として格差があることは事実であります。格差をどうやって解消していくのかに関しては、これはもう税収、地域性もありますので、こちらとしてはですね、できる限り様々な、パマトコなんかもそうですし、夏休み中の学童の昼食提供なんかもそうですし、やっぱり本市の強みを生かした取組をしっかりと引き続き進めていきたいなと思っております。また、無痛分娩そのものに関して言えば、国におきまして出産費用の保険適用が今、議論進められているところだと思いますので、その議論を注視してきたいなと思ってます。
朝日新聞 良永:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。時事通信さん。
時事通信 廣野:
時事通信の廣野です。昨年決定した、25年度の与党税制大綱で年収の壁が103万円から123万円へ引き上げられる方針が明記された件で、市の減収見込み額と市長の受け止めを教えてください。
市長:
はい、ご質問ありがとうございます。今、税制の影響については、粗い試算に留りますが、十数億円だというふうに見込んでおります。ただ、令和8年度からとされていますので、令和7年度の市税収入には影響はありませんが、現時点での令和8年度以降の試算としては12億円を見込んでいるところなんですが、ただいろいろ条件とかにも依存すると思いますので、今後国の動向を注視して、国における議論を注視して、税制額、税への影響等も計算をですね、精緻化していきたいと思っています。
時事通信 廣野:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。NHKさん。
NHK 岡部:
すみません、今の関連なんですけれども、前回だと1,200億でしたか、金額が違う。
市長:
フルフルに。
財政局主税部長 永森:
財政局主税部長 永森と申します。よろしくお願いします。前回の1,200億円の試算ということですが、こちら基礎控除と言われる、ほぼ市民税を納めている方全員が対象となるというところでしたので、影響額が大きかったんですが、今回のものは給与所得控除の最低保障額を引き上げるということで、どちらかというと部分的というか、一部の方に影響が留まるものですから、そのような額になっております。
NHK 岡部:
前回、市長はかなり大きな金額ですと、影響は大きいですというふうにおっしゃっていたとも思うんですけど、今大分規模感変わりましたけれども、それについては。
市長:
まだ国における見直しの議論がまだオンゴーイングですよね。ですので、その議論の動向を注視していく必要があるというふうに思っております。いずれにしてもですね、壁を引き上げることは大切なことであります。それに対して、地方行政として、できることをですね、その結果になり、その後のできることをですね、しっかりとやっていきたいと思います。
NHK 岡部:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。神奈川新聞さん。
神奈川新聞 武田:
神奈川新聞の武田です。ちょっとすみません、長くなりますが。改めて今年8月に市長選があるということで横浜市政に検証するような報道というのは増えていくと思うんですが、改めて、メディアの批判的な報道というものもあるかと思いますけれども、それに対してどのように向き合っていくかを伺えればと思います。
市長:
批判的な報道であっても、好意的な報道であっても、それはメディアのほうのご判断というか、メディアが書いていることですので、向き合うも何も、我々がどうこう言う話ではないと思いますが。いただいたご指摘に対して、内容に関して言ってることは、それはそうだよなっていうことに関してきちんと市のほうで受け止めて、それを市政に反映していくということは重要だと思います。
神奈川新聞 武田:
ありがとうございます。続いて、神奈川新聞のほうに昨年の11月以降、国際プールの再整備と山下ふ頭の再開発の関係だったりで、4本の記事に対して横浜市から抗議文を受け取っています。これについてまず、市長、抗議文の存在は把握されてますか。
政策経営局シティプロモーション推進室報道担当部長 藤岡:
これについては事務局である報道担当部長の私から、藤岡からお答えをさせていただきます。昨年の11月以来ですね、国際プールの関係の記事に関して、やや読者の方が誤解をしてしまうんじゃないかというような表現が見受けられたというものがありましたので、それについて申入れをさせていただきました。
神奈川新聞 武田:
ありがとうございます。報道課のほうにはお話を伺っているので、改めて市長、抗議文の存在、把握されてましたか。
市長:
知りません。
神奈川新聞 武田:
全く知らなかったと。
市長:
はい。
神奈川新聞 武田:
全く知らないとなると、市の職員ないし幹部の方が独断で報道機関に対して抗議文を送ったっていうことになりますが、それでよろしいですか。
市長:
でも、だってあれでしょ。内容に関して疑義があったからそこに関して、説明を求めたっていうことで。ごめんなさい、全て会社全体で共有する必要が必ずしもないんじゃないですか。
政策経営局シティプロモーション推進室報道担当部長 藤岡:
武田さん、抗議文に関してはこういう論調で新聞が書かれている、記事が書かれているけれども、これどうですかということで所管部署とも確認をしながら文章を作ってお出ししている状況でありますので、例えば私が独断でやってるとかそういう話ではないんじゃないでしょうか。
神奈川新聞 武田:
改めて伺うんですが、組織のトップとして、行政機関が報道機関に抗議文出すっていうのはそうそう頻発することじゃないと思うんですが、それを預かり知らないところでやられてたっていうところに対しては市長、今どのようにお感じですか。
市長:
いや、内容はちょっと何を質問したいのか分かんないですけど、聞いて、そちらその取材内容なのか、書きぶりなのか分かんないですけど、そこに関して疑義があって、それ自体は別に正常なプロセスだと思うんですよ。
神奈川新聞 武田:
はい。
市長:
ちょっと中身知らないですけどね。だから、そこに関して、良いとか、悪いとかって、私が言うものでもないですし、所管とか報道担当とかと、武田さんがしっかり話し合ってくれれば済む話なんじゃないですか。それを何か会社全体の、会社というか、市役所全体の話としてどうなんだっていうことを今おっしゃってるんですけど、ちょっと違うんじゃ。今、だから、仲良くしてくれる、仲良くっていうか、議論してくれればいいんじゃないですか。
神奈川新聞 武田:
一般論として、これまでも記事書いて、当然、指摘を受けたりということは、これは健全なやりとりだと思うんですけど。
市長:
うん、そうそう、それでいいんじゃないですか、それで質問をやりとりして。いいんじゃないですか、それで。
神奈川新聞 武田:
続けてなんですが、この抗議文の内容の中で市民に誤解を与えない、公平性を担保した記事を求めるっていう文言が入ってます。これ4通とも、4件の記事に対し、4通ともその文言が入っていまして、ここで言う公平性を求めるというような抗議文の締め方になってるんですけれども、この公平性というものは、何を意図されているか。
市長:
それは、書いた人、出した人に聞いてくださいよ。
政策経営局シティプロモーション推進室報道担当部長 藤岡:
個別の事情になりますから、それはすみません、別の場でもう1回やりましょう。ここは市長会見の場ですから。
神奈川新聞 武田:
今、市長にしかお伺いできないので、改めてここで伺います。今回の抗議文がやはり事実関係の誤認ですと当然我々も指摘を受けて訂正文を出さなきゃいけないとか、それは然るべき対応しなきゃいけない。これももちろん我々も、人間なので、必ず間違うので、やらなきゃいけない。それは当然指摘として受け止めなきゃいけない。そのやりとりもありますし、論調の部分でやりとりもある。それは当然だと思うんですけれども、今回、抗議文という形で、文書でしっかり出ている。行政の文書として出ている形で、事実誤認を指摘するものではなくて、読者に偏った印象を与えるとか、一方的な視点を印象付けるっていうような指摘になっています。
市長:
個別の内容に関する記事と、それに対するやりとりなんで、担当者、神奈川新聞の担当だから武田さんとか加地さんなんでしょうけど。そこと所管局の間で議論して、喧嘩しないでやりとりすればいいんじゃないですか。
政策経営局報道課長 矢野:
武田さん、内容を承知していないと申し上げているので、もしこの話が続くようであれば、また別途、報道担当のほうとやらせていただければと思いますけれども。
神奈川新聞 武田:
今のちょっと質問の続きになっちゃうんですが、市の意図と異なるというか、市の見解とはちょっと違うよっていうものに対する報道に対して、印象論で抗議する、こういう印象を与えかねないっていう、事実誤認じゃない抗議っていうのは行政の文書として適切でしょうか。
市長:
ですから、個別の話になると思いますので、それを役所全体の方針とか、姿勢と絡めるっていう話ではなくて、まず事実関係に関して個別の案件なんで、個別の所管部局と担当者同士で議論をしてくださいって先程から申し上げているんですが、それを行政全体の姿勢とかって、それでちょっと私自身は内容を承知してないので、ちょっとお答えしかねますし、ちょっと違うんじゃないかというのが今、雑感なんですが。
神奈川新聞 武田:
文章自体が、ごめんなさい、ここだけにします。市として出してるものなんで、やっぱりその市のトップは市長なので、好き勝手当然できないと思うんですね、行政の職員の方が。
市長:
いや、全部の文章を僕が管理しているわけではないですよね。御社はどうですか。もちろん全部出すものを社長さんが全て1枚1枚把握してますか。
神奈川新聞 武田:
うちはそうじゃないです。それはもちろんです。特に今回特殊な文章なのでそういう聞き方をしてるんですけど、全く把握していないという。
市長:
個別の案件なんで、ちょっとどういう内容なのかに関しては。そういうご指摘があることは、今回、今日承りましたけれども、先程来、言っていますようにちょっと終わった後、改めて話していただけませんか。その結果の報告については、また私も聞きますし、はい。喧嘩しないで。
神奈川新聞 武田:
ごめんなさい、喧嘩したくてやってるわけではなくて。あくまで市の姿勢を問うって意味で。
市長:
だから、そこまで話なのかどうか、分からないですけどね。
神奈川新聞 武田:
最後に、この文書の、抗議文を出すっていうのが、今いろんな政府しかり、地方の自治体しかり、メディアと、こう関係性というのはずっと変化していて、たくさんの抗議文というもの自体が報道の萎縮を招くような、圧力と取れるようなものにも捉えられかねないと思うんですけれども、この点については市長、いかにお感じですか。
市長:
一般論として、報道の自由というか、表現の自由は保たれるべきだと思いますが。
神奈川新聞 武田:
それに対する圧力っていうふうに捉えられかねないと思うんですけれども。
市長:
だから、そこに関しては事実関係分かりませんって言ってますよね。
神奈川新聞 武田:
その事実関係って。
市長:
そこに関しては武田さんご意見がそうだっていうのは、今、武田さんが何度も繰り返し同じ質問をされているので分かりましたけれども、だから、これ会見が終わった後、されたらどうですかと。
政策経営局報道課長 矢野:
武田さん、じゃあそろそろ。繰り返しになっているので。
神奈川新聞 武田:
じゃあちょっと話題変えて、去年の暮なんですが、いわゆる年頭恒例のインタビューをうちとして申し込みました。これは結果的に実現しなかったんですけれども、インタビューを最終的に受けないと判断したのは市長でしょうか。
市長:
いえ、知りません。そうなの。
政策経営局シティプロモーション推進室報道担当部長 藤岡:
武田さん、そのインタビューの話も我々事務局が調整してますから、こちらからお答えしますけれども、最初に事実としてお伝えするのは我々からは日程をご提示をしました。1番その経過をご理解されてるのは武田さんかと思います。それも個別の調整の話ですから、この場ではなくて、市長会見の場ではなくて、我々と別途やりましょう。
神奈川新聞 武田:
この場で伺ってるのは、市長にこういう形で聞けるのがちょっとチャンスなので伺っているんですけれども、あくまでも我々、市長にインタビューを申し込んでいて、それを市長じゃない方が勝手に判断してるっていう。
市長:
日程調整は事務方に任せています。
神奈川新聞 武田:
日程調整はもちろんだと思うんですけれども、最終的に受ける受けないっていう部分。受けようと思えば受けられる。
政策経営局シティプロモーション推進室報道担当部長 藤岡:
すみません、武田さん、日程は我々から提示しましたよね。その事を言ってます。
神奈川新聞 武田:
もちろんです。そこを細かく言ったら12月の10日っていう日程を提示いただいているですけれども、異様に早いっていう部分、常任委員会がまだ迫っていたので、今後の市政の重要な課題がそこで議論されて、ないしは決定されていくという場でもあるので、その後が良いというのは要望として伝えてます。もう1点は、やっぱり掲載が1月以降になるので、1か月弱のブランクがあるっていう部分もあって、それは受けかねるという回答はしています。改めて通常であれば最終週に日程調整されてくると思うんですが、そこでは我々インタビュー実現していないというのは事実としてあります。その受ける受けないっていう最終判断は市長がされたのか、あるいは市長ではない方がしているのか。
市長:
私は日程調整はしていません。
神奈川新聞 武田:
もちろんです、日程調整は。
市長:
決まった日程に関して、この日程でやりますということを直前に報道課や所管局から報告を受けて決めた、その各社決められた日程に関して私のほうでご対応をさせていただいているというのが経緯全部。私が知ってる全体像です。
神奈川新聞 武田:
一般論になりますけれども市長がインタビューを受ける、我々が要望するというのは行政がどういうふうに統治されているのか、何をしているのか、トップが何を考えてるのかっていうものを、読者さん、市民に知らせる機会になるということで取材の機会がなくなってしまうと。
市長:
日程調整はしてるんですよね。もう日程を合わなかったということなんですか。
政策経営局シティプロモーション推進室報道担当部長 藤岡:
お断わりをいただいたという結果になってます。こちらから提示した日程はお断りってなってると。もちろん12月にこの新春インタビューを実施していますので、御社がお断りになった日程でインタビューをしているところもあります。
神奈川新聞 武田:
それは把握しています。我々としてはあくまでも12月の先程お伝えした通り、下旬の部分を求めて通常通りですね、一般通りの日程を希望、ちょっとこの日程の部分はそういうご回答なので一般論なんですけれども、市長がそのインタビュー、ご本人なので我々のインタビューを受けてないっていうご認識は当然おありかと思うんですけれども。
市長:
神奈川さんの受けてませんでしたっけ。そっか。どこの会社を受けているか、これだけ多くやっているのであれば10個20個あって、1個1個事務方のほうで調整してもらって、それでそこに関して私が聞かれたことをお答えしているということなので。はい。
神奈川新聞 武田:
分かりました。特に強くあそこを受けてないなっていうご認識があったわけではない。
市長:
私はどこの会社を受ける受けないかは私自身は、その事務調整ですから。日程調整が出来上がったものを今、報告を受けて私が対応させていただいてるっていうのが、それ新春だけじゃなくて、周年も全部そうですし、私が対応させていただいているインタビューの調整です。
神奈川新聞 武田:
もちろん調整はそうだと思うんですね、事務方がやるんでしょうが。市長がインタビュー受けるご本人なのでここを受けてないなとか、ご認識が。
政策経営局報道課長 矢野:
繰り返しになっているので質問は端的に。
神奈川新聞 武田:
お忙しいからあんまり覚えてないっていう。
市長:
どこを受けたか、数日前に例えば二、三日前に今日、明日、明後日何がありますよっていうのは受けますよ。事務方から。だけどそれ以上のことは、事務方のほうに、事務方のほうとまた喧嘩しないで調整してくれればいいんじゃないですか。
神奈川新聞 武田:
決して喧嘩したくてやってるわけではなくて、あくまでもインタビュー受ける受けないは先程のようなその知る権利というものを広く捉えれば侵害する行為になると。
市長:
マスコミのメディアのご質問等にはお答えすべきだと思いますし、メディアが記事を書いてそこに関して私からどうこう申し上げたってことは、就任以来1回もないですし。ですので皆さんが事務方と調整をして、いただいたインタビューの機会に私は答え、そして普段こういった定例会見とか、あるいは日々のスピーチの中で皆さんがどういうふうなことを書かれたとしても、こちらとしては皆さんが皆さんの取材や判断の中で書かれていることですから、そこに関して私がどうこう申し上げるということはないです。
政策経営局報道課長 矢野:
武田さん繰り返しになっているのでそのあたりでよろしいですか。
神奈川新聞 武田:
分かりました。もう1点先ほどちょっとこれお答えいただけないかもしれませんけど、抗議文とインタビューを実施しないという関係はありそうですか。市長にお伺いしたいんですけれども。
市長:
いや、だから知らないので。
政策経営局シティプロモーション推進室報道担当部長 藤岡:
先ほどから市長認識していないということでお答えしてますので。
神奈川新聞 武田:
分かりました。一旦最後にするんですが、改めて我々のメディアの役割っていうのが今非常にずっと問われていると思うんですけれども、行政を監視したり、あるいは政策をチェックしたりっていうものが我々付託されているのであって、我々もそれを意識して日々動いているつもりですし、どうしても懐疑的な視点に立って批判的な視点に立って権力を見てかなきゃいけないっていうふうに我々は思ってるんですね。そこの部分メディアの役割というものは民主主義の中でのメディアの役割というものを市長は。
市長:
おっしゃる通りじゃないですか。それがメディアの役割の1つ、それだけじゃないでしょうけど、メディアの役割だと思いますけどね。だからそれ以上それに関して私から何か正しいとか正しくないとかっていうこともないんですけど。おっしゃる通りだと思います。
神奈川新聞 武田:
分かりました。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。神奈川新聞さん。
神奈川新聞 加地:
神奈川新聞の加地です。関連してお伺いします。冒頭、こちらからですね、批判的な記事に関してどう向き合うのかという質問をさせてもらって、市長からは、メディアの判断だと。どう書くのもメディアの判断だから、どう向き合うのもっていうお答えがありました。一方11月から弊社、1か月に4通、公平性を担保してほしいっていう抗議文を受け取っていて、市長は預かり知らないところで、それをやられてるということで。
市長:
その内容次第なんじゃないですか。その内容に関して、何でも書いていいってわけでもないですよね。
神奈川新聞 加地:
はい。
市長:
だからその内容に関して、例えば事実誤認とかもたまにはあるっておっしゃってたじゃないですか、武田さんが。だからその内容に関して個別の話なので、所管と丁寧に話し合われたらどうですかっていうのは先程から言っているわけで、だから仲良くって言ったんですけどね。
神奈川新聞 加地:
はい。こちらが受け取った抗議文は市長確認していただいて。
市長:
所管との話ですから、別に私がその内容を見てどうこう言うこともないですし。取材内容に関する話なのかな、出したのが。
政策経営局シティプロモーション推進室報道担当部長 藤岡:
記事の内容です。
市長:
記事の内容に関して、そこを腹詰めてバックヤードで話せばいいんじゃないですか。それだったら。その行政の話とか、市長の会見とかで、市としてどうなんだっていう話にまで広げるんじゃなくて、まずメディアの役割は役割として、もちろん、こちらは承知しておりますので、書いたものに関して何か言われたから気に入らないとかじゃなくて、ちゃんと事実内容に関して、腹割って、腹は割らなくてもいいですけど、膝詰めて話せばいいじゃないですか。だからそれ以上のことはちょっと私も個別の内容なので。
神奈川新聞 武田:
もちろん我々も別に。
市長:
いいですか、この話は。
政策経営局報道課長 矢野:
繰り返しで長くなっているので、この件のご質問が続くようであれば後ほど別途伺わせていただきますので。
神奈川新聞 武田:
ちょっと1個の部分は訂正させていただきたいんですけれども、あくまでも我々受け取ったから今この場でいきなりぶつけているわけではなくて、当然藤岡さん始め、話は伺ってます。どういうことを考えていらっしゃるのか。我々どういうことを意図しているのかっていうのは口頭でやりとりしてます。その上で市長に聞ければっていうのはここしかないのでやっぱり重ねてになりますけれども、行政が出す文書を、当然逐一全部チェックしろなんていうふうには思わないですし、その必要もないと思うんですけれども。メディアに対する抗議文というものは非常に重たいと思っております。やっぱり報道の萎縮につながりかねない。こういうことを書くとまた言われるな、いろんな抗議を受けるなっていうふうに思ったときに、やっぱり報道の自由というものは守られるべきものがどうしてもそうじゃなくなってしまいかねない、そういうふうに受け取れるわけですね、抗議文というのは。その抗議文を出す重みっていうものを十分認識しているからこそ市長に問うてる。
市長:
先程来からお答えしてる内容と変わらないです。
政策経営局報道課長 矢野:
その他、他のご質問ありますか。よろしいですか。では各社いかがでしょう。よろしいでしょうか。それでは以上で定例会見終了します。ありがとうございました。
このページへのお問合せ
政策経営局シティプロモーション推進室報道課
電話:045-671-3498
電話:045-671-3498
ファクス:045-662-7362
メールアドレス:ss-hodo@city.yokohama.lg.jp
ページID:714-396-570