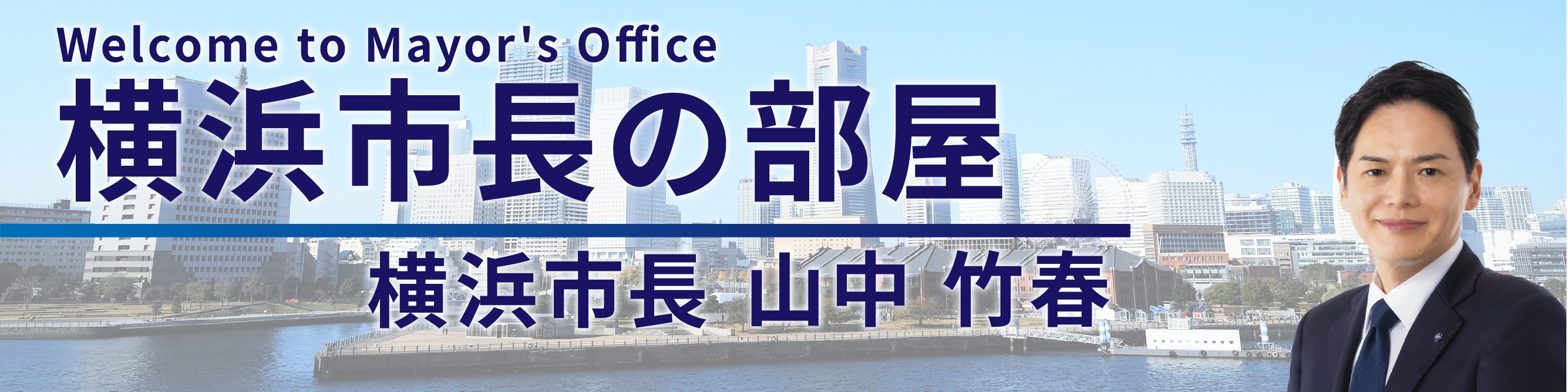ここから本文です。
- 横浜市トップページ
- 市長の部屋 横浜市長山中竹春
- 定例記者会見
- 会見記録
- 2024年度
- 市長定例記者会見(令和7年2月13日)
市長定例記者会見(令和7年2月13日)
最終更新日 2025年2月17日
令和7年2月13日(木曜日)11:00~
報告資料
- 【スライド資料】循環型社会への加速に向けた日本初「地区の資源循環の可視化」を開始(PDF:1,191KB)
- 【記者発表】循環型社会への加速に向けた日本初 「地区の資源循環の可視化」を開始!
- 【スライド資料】「令和7年度横浜開港記念式典・記念コンサート」市民のみなさま1,000名をご招待(PDF:307KB)
- 【記者発表】令和7年6月2日 横浜開港記念式典・記念コンサートに抽選で1000名様をご招待します
会見内容
1.報告
(1)循環型社会への加速に向けた日本初「地区の資源循環の可視化」を開始
※敬称略
政策経営局報道課長 矢野:
はい、それでは定例会見始めます。 市長お願いします。
市長:
はい、今日はですね、循環型社会への移行が今叫ばれておりますが、そこに向けてですね、日本で初めて、地区の資源循環の可視化に取り組むという内容であります。まず、資源循環を取り巻く世界的な状況なんですが、ご承知のとおりですね、資源の消費量っていうのがどんどんどんどん加速してきています。2060年までに、70年比で5.2倍にまで達する可能性が示唆されています。そういった資源の消費量が増大することによって、気候災害が激甚化したり、あるいは生物多様性の損失が加速化したり、様々なことが懸念されます。こういった事態を受けて、今欧州のほうではこういった取組がですね、欧州以外に比べて早く動いているというふうに思いますが、例えば、新車を作る時もですね、再生材の最低含有率として25%、4分の1を使わなければいけないっていうようなことを義務化しています。こういったことで、リサイクル社会っていうものを実現していこうと、野心的なことがどんどん今、実際に実行に移されています。我が国としても、資源循環分野の競争力を強化させ、そして循環型社会を実現していくための取組が求められているところかと思います。これは日本政府が定める循環型社会形成推進基本計画の中にある図なんですけれども、こういったインがあって、アウトがあるという、資源を採取して、消費をしてですね、その後廃棄をしていくっていう物質フローの全体像なんですけれども、循環社会を実現していく上で難しいことっていうのは、この流れをいかに見える化して、数字で測るようにして、定量化して、その定量化された数字を基に管理していくのか、運営していくのかっていうところが難しいということであります。これをどうやって数字で測っていくようにするか。例えば、資源循環を可視化するとしたらですね、こういった様々な項目があって、地区内の経済活動でこれらの項目が使われるとします。それぞれのものに応じて、野菜だったら野菜、肉だったら肉とか、食べ物もそうですし、そのほかもですね、資源として様々なものを使っているプラスチックとか、ガラスとか使ってるわけなんですけども、これらが地区内でインとして入り、そして経済活動で商業施設で使われたり、あるいはそうですね、ものづくりに使われたり、そしてアウトプットとして出て行って、そのアウトプットとして出て行ったもののうち、一定割合がまたリサイクルに回っていくという関係になります。だからこれを分解して数字で測っていけるようにするっていうことが、循環社会に向けて、どのくらい進んでいるのかの指標になるわけです。サーキュラー、循環のですね、インフロー率と、サーキュラー、循環のアウトフロー率っていう概念がありまして、投入される資源の総量がこれだけだとして、その中でどれだけ使用済み製品からリサイクルされた原材料を使っているか、あるいは、自然由来の原材料を使っているか、この割合が高ければ高いほど、インで使っている資源に関して、資源の循環率が高いので、環境に優しい社会に貢献しているっていうことになります。あとサーキュラーアウトフロー率はその逆で、使用されて排出される資源っていうのがあるわけですが、その中で回収されたり、あるいはリサイクルされたり、どのくらいしているのかっていうことであります。こういう循環率の指標を作って、測って、計算して、それを基に管理していく。循環社会の到達の程度を管理していくことが必要なんですが、課題は把握をどうやってするのかと。これができないと、サーキュラーエコノミーの進捗が評価できないということになりますので、これの評価ということは国際的な課題であります。国際的にはごく一部の都市でこういったものの流れや定量指標を用いた評価が始まりつつあります。例えば、アムステルダムは循環社会の中で世界トップの都市だと思いますが、アムステルダムやモントリオール市などごく一部であります。日本はこういったことをまだ実行できていません、どこの都市も。そういった背景がある中で、横浜市として今回、このサーキュラーのインフロー率とかアウトフロー率の測定を開始すると、そこに乗り出すという内容であります。これまで、みなとみらい地区は今、国の脱炭素先行地域に指定されておりますが、サーキュラーシティ・プロジェクトを23年の3月から実施してきました。最初はスモールスタートでありましたが、今いろいろ準備も整ってきて、この地区におられる事業者の方々との協力も進んできましたので、これから本格的に加速させていきたいと思います。24年度に実証実験を行ってきた、このペットボトルの「ボトルtoボトル」、ペットボトルから回収して、その資源を取り出して、また次のペットボトルを作るっていう「ボトルtoボトル」の水平リサイクルがですね、24年実証実験やってきたんですが、25年の1月から地区の23の施設が連携して本格的な取組を開始したところであります。今回、地区内における資源の流れを可視化する、そして測る、測定する取組を開始しますと。この施設がですね、施設というよりは、例えばランドマークタワーまるごとなので、あそこにたくさんの商業施設始め、事業者さんも入っているじゃないですか、かなり莫大な数の。そこが全て、ランドマークタワーとして協力していただけるっていう意味であります。ですので、例えば、パシフィコ、ごめんなさい、MARK ISなんかもかなり多くの商業施設入っておられますし、あるいは飲食店なんかもあります。そういったところで、例えば食物の残渣とか、あるいは原材料とか、そういったことも把握して、例えばその飲食店におけるサーキュラー率がですね、出ます、原理的には出ますので、それを例えばMARK ISとか、横浜のランドマークタワーとかそういったところで測れれば、この地区全体におけるサーキュラー率、循環率が推計できるだろうというふうに考えております。目的はサーキュラーエコノミーを評価する指標を確立して、そしてその指標を使って、具体的なアクションを検討する土台を今後整備していきたいというふうに思っています。可視化し、データを作っていくっていう仕組みづくりですね、はい。これによって、サーキュラーエコノミーを推進して、今後の温室効果ガスの排出量削減に寄与していきたいというふうに思っております。例えば、サーキュラーのインフロー率が、これイメージなんで数字は、すみません、適当ですけれども、例えば5.8%でした、アウトフローのほうは43.5%でしたとか、そういった数字ができるようになれば、進捗管理が今度できるようになるということであります。はい、以上となります。この取組をですね、進めることで循環社会への移行を加速させていきたいというふうに考えております。
政策経営局報道課長 矢野:
はい、それではこの件についてご質問を受けします。いつものお願いになりますけれども、ご質問の際、お手元のマイクのスイッチのオンとオフのご確認をお願いいたします。では、まず幹事社からお願いします。
ラジオ日本 本田:
幹事社のラジオ日本 本田です。よろしくお願いします。まず、資源循環の可視化というところで、横浜市の中でもみなとみらい地区で実施しようと思われた理由を教えていただきたいです。
市長:
はい、ご質問ありがとうございます。脱炭素先行地域として今様々な取組を行っております。その中で事業者さんとの関係が、こういったことに向かっていく事業者さんとの協力関係ができているという点は大きいと思います。
ラジオ日本 本田:
ありがとうございます。追加なんですけども、改めてこの資源循環の、この可視化の取組への期待であったりですとか、今後これが良いモデル化になっていけばっていう、そういった思いも含めてお聞かせいただければと思います。
市長:
はい。ご質問ありがとうございます。今回の取組は、地区内の資源の循環を見える化する日本初のチャレンジであります。横浜から循環社会の実現を推進していきたいというふうに考えております。是非このプロジェクトですね、最初スタートさせて、今後ですね、事業者さんを増やしていくとか、そういったことも必要だと思うんですが、是非地区全体で測る難しさっていうのが、なんとなんとなく想像できると思うんですよ。だけど、こういったことが定量化できない限り、循環社会の移行の程度が管理できないので、是非チャレンジしていきたいというふうに思っています。
ラジオ日本 本田:
もし現時点で考えている範囲といいますか、この可視化の取組が非常にこう思わしい結果と言いますが、良い形だったというふうになれば、今後の展開というところにいくと、今、市長考えていらっしゃることとかあれば教えてもらえればと。
市長:
はい。市内の多くの地域への展開だというふうに思います。今後アジアでナンバーワンの循環社会を推進する都市になっていきたいというふうに思いますので、まあ、それに向けた第一歩だというふうに思います。
ラジオ日本 本田:
ありがとうございました。
政策経営局報道課長 矢野:
それでは各社いかがでしょうか。朝日新聞さん。
朝日新聞 良永:
朝日新聞の良永と申します。今回の可視化の対象、経済活動かと思うんですけれども。市民の方からこの可視化の様子を見てもらって、どのように感じてほしいですとかあれば教えてください。
市長:
はい。どのようなものが使われて、その中に、再生材がどれくらい入っているかとか、そういった情報。それからあとは廃棄物が次の製品にどれくらい使われているのか。そういった情報っていうのは、これまで市民の皆様にも、もちろん提供できておりませんでした。そういった情報が提供することによって、循環社会の具体的なイメージを持っていただけるんじゃないかなと思うんですよね。やはり、もったいないだけではなくてきちんと循環させる。 それによって、温室効果ガスの削減に寄与していく。そういったことをですね、このプロジェクトから伝えていきたいというふうに思っています。
政策経営局報道課長 矢野
その他、いかがでしょうか。日経さん。
日経新聞 松原:
日本経済新聞の松原です。いくつか教えていただきたいんですが、まずその具体的な手法というか、なんかその計測、その測定するその装置みたいなものを、例えば市が補助して各施設に入れるのか、それともなんというか、事業者が本当に多分たくさんあるので、なんか申告制になるのか、なんかどういう形で測定するのかって教えていただけますか。
脱炭素・GREEN×EXPO推進局脱炭素社会移行推進部長 岡崎:
脱炭素・GREEN×EXPO推進局脱炭素移行推進部長の岡崎です。今言われた質問なんですけど、後者にあたりまして、実際に事業者様のほうからすべて申告していただく。そういうスタイルをとっております。
日経新聞 松原:
これって何かそういうもう測定するような、なんか装置みたいなものを企業さんが導入しているんですか。それともなんていうか、仕入れたものだったり、ゴミとかも多分計測しないと分からないですよね。
脱炭素・GREEN×EXPO推進局脱炭素社会移行推進部長 岡崎:
事業者様はマニフェスト等出してますんで、自然と測定する、従来からやっている部分というのも多くございますんで、その辺は出してもらうと。また新たに追加でインのところなんですけど、入ってくるところもできる業者さんには今後協力してもらって、精度をどんどん上げていきたいと思っております。できる限りのところはとっていただいて、申告制としております。
日経新聞 松原:
ありがとうございます。加えてなんですが、この例えば実際のこの数値みたいなものを、どこか、施設内とかそういうところに表示して、市民の方にも分かるようにされていくんですか。
市長:
地区全体としてその数字を出すことになります。その数字をどうやって共有していくのかっていうことについて、これから考えたいと思います。
日経新聞 松原:
最後にもう1点、サーキュラリティ率っていうこのイメージ図のところで、中長期的に例えばその目標、可視化する以上、何かを目標とする数値みたいなものがあれば教えてください。
市長:
例えばインフロー率の循環率を何パーセントまで引き上げるとか、そういうことですか。
日経新聞 松原:
はい。
市長:
そこまではまだ。今何パーセントなのかっていうところがまだ分かりませんので、それを見てから検討したいなというふうに思っています。
日経新聞 松原:
分かりました。以上です。ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他、いかがでしょう。読売さん。
読売新聞 川崎:
読売新聞の川崎と申します。そもそも論、この事業いつから始まるんでしょうか。
市長:
まず測定。これから開始してですね。今年、年内には公表したいというふうに思っています。
読売新聞 川崎:
ありがとうございます。えっと。このサーキュラリティ率。
市長:
循環率ですね、はい。
読売新聞 川崎:
循環率。これ、市民の方はどういった媒体とか方法で確認することができるんでしょうか。
脱炭素・GREEN×EXPO推進局脱炭素社会移行推進部長 岡崎:
横浜市のホームページのところで、全体なんですけど、全体の数値っていうのは日々更新していきたいと。月ごとになるかどうかはまだ決まっておりませんが、更新していきたいと考えているところです。
読売新聞 川崎:
すみません、最後に1点。みなとみらいのかなり多くの施設さんがご協力、既にいただいているところだと思います。ただ、他にも企業さんもたくさんあって、現時点でのカバー率というか、みなとみらいの何パーセントぐらいを反映している数字なんでしょうか。
市長:
延床面積で、だいたい4分の1くらいにあたります。これらの今、事業者さんで。
読売新聞 川崎:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは以上でこの件終了します。事務局入れ替わります。少々お待ちください。
(2)「令和7年度横浜開港記念式典・記念コンサート」 市民のみなさま 1,000名をご招待
政策経営局報道課長 矢野:
それでは市長、続けてお願いします。
市長:
はい、続けて令和7年度の横浜開港記念式典・記念コンサートについてのお知らせです。令和7年度の横浜開港記念式典・記念コンサートに市民の皆様、1,000名をご招待いたします。今年も6月2日の開港記念日に開港記念式典とコンサートを開催する予定でありますが、会場、横浜のみなとみらいホールとなります。この式典は港の歴史と先人の業績に敬意を表して、これからの横浜の発展を願う場として毎年開催しているものであります。また、記念コンサートでは、「おかあさんといっしょ」の歌のお兄さんを10年ほど務められていた、歌手で俳優の横山だいすけさんをお招きする予定であります。地元横浜を中心に活動されている横浜少年少女合唱団の皆様ともですね、共演予定されておりますので、多くの市民の方々に応募いただければというふうに思います。本日から申込みを受け付けておりますので、沢山のご応募お待ちいたします。以上です。
政策経営局報道課長 矢野:
はい、それではこの件ついてご質問を受けします。まず幹事社からお願いします。
ラジオ日本 本田:
幹事社、ラジオ日本本田です。よろしくお願いします。改めてこの開港記念式典・記念コンサートに関する思いと言いますか、期待感、見どころを教えていただければと思います。
市長:
はい。この開港記念式典は先ほど申し上げましたが、横浜港の歴史と先人の業績に敬意を表するもので、市民の皆様と一緒にですね、6月2日にお祝いをするというセレモニーであります。また今回の記念コンサートは歌のお兄さんとして、お子さんとか子育て世代の方々に、多くの方々に親しまれている横山さんをお招きいたしますので、是非ご期待いただければというふうに思います。
ラジオ日本 本田:
ありがとうございました。
政策経営局報道課長 矢野:
それでは各社、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、この件の質疑は終了します。事務局入れ替わります。少々お待ちください。
2.その他
政策経営局報道課長 矢野:
それでは、これより一般質問に入ります。複数、ご質問がありましたら、まとめてお願いいたします。ではまず、幹事社からお願いします。
政策経営局報道課長 矢野:
それでは、各社いかがでしょうか。産経さん。
産経新聞 橋本:
産経新聞の橋本です。よろしくお願いします。カーリングの日本選手権が終了しましたけれども、首都圏初のカーリング日本選手権開催ということで、その感想と、あと来年度以降の日本選手権とか、あとは2029年の女子世界選手権の横浜開催に向けての展望とかお願いします。
市長:
はい、ご質問ありがとうございます。これまで氷を張る関係上、首都圏から距離のあるところで開催されていた試合が、今回、首都圏初の開催として実現いたしました。小学生の観戦招待とか、あるいは先行チケットの販売等で、市民の皆様にカーリングというスポーツの迫力や魅力を感じる機会ができたことを嬉しく思っています。また、カーリング協会から横浜市の開催協力を高く評価していただきましたので、その点、光栄に思います。是非、どこで例えば、次の大会を開催するかは、それは日本カーリング協会様のご判断となりますが、来年どうするのかっていうのは、日本カーリング協会のご判断となりますが、本市としては来年度も是非横浜BUNTAIでの開催を目指してですね、誘致をしていきたいなというふうに思っています。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。東京さん。
東京新聞 神谷:
東京新聞の神谷です。今年になって出ている、横浜市が神奈川新聞さんに文書を出したという件なんですけど、ちょっと事実関係で確認させてもらいたいんですけれども、市長、今年始めの会見の段階では、その文書については知らないというようなことを仰っていましたが、実際に存在を知ったのはいつになられるでしょうか。
政策経営局シティプロモーション推進室報道担当部長 藤岡:
報道担当部長の藤岡でございます。市長に文書を報告したのは、前々回の定例会見でこの話題が出た後に、ご報告をしております。
東京新聞 神谷:
それまでは全く市長に報告もなく。市長もご存知なかったということでよろしいですか。その11月、1番初めに11月の20日付の誌面に対して、その日のうちに出されていると思うんですけれども、それ弊社で、こちらでも文章を拝見すると、課長と部長の決裁のみで出されていると思うんですが、この判断っていうのは、市長は適切だったというふうに思われているんでしょうか。
市長:
所管レベルの、所管と担当記者さんのやり取りだというふうに承知してます。
東京新聞 神谷:
内容についても、その公平性を、報道機関に対して公平性を担保した記事を求めるというようなことを、市から要求のようなことを書かれていますけれども、こうした内容についても特に問題はないというふうにお考えでよろしいですか。
市長:
市民の皆様に誤解を与えるとか、あるいは事実の、内容の正確性についてこちらからお伝えするということはあるというふうに思います。
東京新聞 神谷:
前回の定例会見で、これは抗議文ではないかという指摘に対して、抗議ではというふうに仰っていましたけど、その認識も変わりないですか。
市長:
今、申し上げたとおりであります。事実、内容の正確性とか、市民に誤解を与えかねない内容に関する点について、ご指摘をさせていただいたというふうに、文面を見て思っています。
東京新聞 神谷:
今後も同じようなことがあった場合には、こうした文章を出していくということでしょうか。
政策経営局シティプロモーション推進室報道担当部長 藤岡:
状況によると思いますけれども、やはり例えば、事実に誤りがあるんじゃないかとか、この我々に取材をしていただいたにも関わらず、なぜこう書いていただいてないのかとか、そういったようなご指摘とか、こう書かれてしまうと、市民、読者の方は誤解されるんじゃないかなっていうようなことは、ご指摘させていただくことはあるかな、そうしたことが起きればあるかもしれないなというふうには考えています。
東京新聞 神谷:
それはなんていうか、行政としてというよりも一取材対象としてみたいなお考えということなんでしょうか。
政策経営局シティプロモーション推進室報道担当部長 藤岡:
そうですね、前回もそのようにお答えはさせていただいていますけども、やはり取材対象として、我々当事者にもなりますので、公的機関うんぬんというよりは、取材対象として、そういうことを申していくことっていうことはあるのかなというふうに思います、はい。
東京新聞 神谷:
例えば、個人の方の取材対象の方ともまた意味合いは違うので、公的機関が報道機関に対して、こうしたことを言うっていうのは意味合いが違うのではないかと思うんですけれども、その点はどうお考えなんですか。
政策経営局シティプロモーション推進室報道担当部長 藤岡:
公的機関であるがゆえに、そういった意見を言ってはいけないってなってしまうと、そういうご主張であれば、少し私は違和感を感じてしまうんですね。やっぱり、今回我々が出した文章の中には、このように読まれてしまう懸念っていうものをご指摘させていただいたつもりですから、そういう意味では我々に対して、このような取材がありました、でも誌面ではこのように書かれました、こうだとすると、我々の主張っていうのは、全く伝えていただいていないので、そこには見え方として偏ったものが発生しかねないなというふうな思いを持って、紙で出させていただいていますので、はい、そういう考えになります。
東京新聞 神谷:
報道機関も一権力とも言われますけれども、公的機関というのもある意味で1つの権力的なものにもなるとも思うんですが、それが一取材対象として出したというのは、やはりちょっと少し、ちょっと違うんじゃないかなというふうに思うんですけれども、それをやっぱり正しい、市としては正しい主張をしたというふうなお考えでよろしいんですか。
政策経営局シティプロモーション推進室報道担当部長 藤岡:
ご見解としては、承りましたけれども。私どもの考え方としては、公的機関であるがゆえに、では何も意見が言えないってなってしまうと、それはまた少し違和感を感じざるを得ないですね。違和感を覚えますね、はい。
東京新聞 神谷:
それは報道が間違っているわけではなくても、それは報道機関はどういう報道内容にするかに対しての意見は、市として。
市長:
内容の公平性じゃないですか。
東京新聞 神谷:
公平でないと市が判断した場合には意見は今後も伝えていく、市であっても伝えていくべきであるというふうにお考えですか。
政策経営局シティプロモーション推進室報道担当部長 藤岡:
市が判断した場合には、と仰ったので、そこには先ほど仰ったような、公的機関としてとか、行政機関としてっていう部分と、その当時者としてという部分で少し、やはりニュアンスが違うのかな、というふうには感じますが。
東京新聞 神谷:
今回はこれ、当事者としてであるということですか。
政策経営局シティプロモーション推進室報道担当部長 藤岡:
そうです。
東京新聞 神谷:
公的機関として客観的に考えた時に、やはりその、ある意味でこうした文章を出すというのは一圧力になるんじゃないかという考えもあると思うんですけれども。
政策経営局シティプロモーション推進室報道担当部長 藤岡:
今回、神奈川新聞さんがその後の報道、誌面でもそのようにお書きになられていたので、そのように受け止めたということは我々も承知してますし、そのように認識せざるを得ないのかなというふうには思いますが、我々の行為としては、全くそのような意図がありませんので、そこはご理解いただきたいなというふうに思います。
東京新聞 神谷:
それは、圧力をかける意図はないということですね。
政策経営局シティプロモーション推進室報道担当部長 藤岡:
全くないですね。
東京新聞 神谷:
でもそれに対しては、報道機関として圧力だというふうに考える、受け止める。そのことに対しては、今どういうふうに捉えられているんですか。
政策経営局シティプロモーション推進室報道担当部長 藤岡:
現実問題、そのようにお受け止めになって、誌面を通じて主張されましたので、その事実に関しては、我々も、あっそういう考えもあるんだなというふうには、今は受け止めております。
東京新聞 神谷:
と言ってその文書を出した行為については間違っていたというふうな認識じゃないということですか。
政策経営局シティプロモーション推進室報道担当部長 藤岡:
仰るとおりです。
東京新聞 神谷:
分かりました。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょうか。神奈川新聞さん。
神奈川新聞 武田:
神奈川新聞武田です。今の部分でまず1点。ちょっと誤解をされているんだとしたら、訂正したいなと思うんですが、公的機関として言ってはいけないと言われると違和感を覚えるというのは、そのとおりだと思うんですけど、我々全くそういうことは言っていないですし、誌面でも書いてません。ので、そういうふうな受け止め方をされているんだとしたら、それは事実誤認だと思います。ここで訂正させていただきたいと思います。で、もう1点、今、圧力と受け止めたという我々の主張に対しても、そういう考え方もあるというお言葉がありましたけれども、あまりにもその権力に対して無自覚というか、権力側としてもう少し自覚的であるべきなのかなと思うんですが。こういう考え方一切なかったっていうのは市長もそういう形でお考えですか。
市長:
市民の皆様に誤解を与える、あるいは事実の正確性に関して指摘をさせていただいたというふうに所管からは報告を受けています。
神奈川新聞 武田:
所管の報告がそうだと思うんですけれども、一連の行為を見て、短期間で4回文書を出してくるっていうのは、通常、そのナチュラルなコミュニケーションの中で、この記事はどうなんだっていうのは当然あって然るべきだと思いますし、むしろ我々もそう言っていただきたいと思います。この記事はこういうことを、誤解を与えかねないよっていうふうに思うんであれば、そういう形でコミュニケーションをとって、これまでもとってきたつもりではあるんですけれども、それを飛び越えて文書でどんどん来たっていうのは明らかに圧力と受け止めてもおかしくないことだと思うんですけれども、それに対しては一切そういうふうに考える可能性なかったということなんでしょうか。
市長:
ちょっと話が飛躍しすぎだというふうに思います。今、所管と武田さんたちのコミュニケーションがされてるって言ってましたけども。そこはうまくいってないっていうことだと思いますので、そこに関して何度か言っても、武田さんたちは、まぁ対応されなかったっていうふうに承知してますので、そういった観点から紙の対応をされたというふうに考えていますが。それに対して回答があったんですか。
政策経営局シティプロモーション推進室報道担当部長 藤岡:
回答はいただいておりません。
市長:
紙に関して。1回も。
政策経営局シティプロモーション推進室報道担当部長 藤岡:
はい。
神奈川新聞 武田:
分かりました。そうすると、市の見解としては我々とコミュニケーションを取っていたけれども、話を聞いてくれないから文章出したっていう、そういう理解でよろしいですか。
政策経営局シティプロモーション推進室報道担当部長 藤岡:
紙にする以前の段階ではやはり口頭でやりとりはあったと。いつ何のやり取りをしたかというのは記録にも取っておりませんので、それは分かりませんけれども、やはり特に単純な事実誤認に関しては、すぐそこで解決する問題だと思うんですけれども。こういった、なんていうんですかね、誤解を与えかねないんじゃないですかというような内容に関しては、なかなか、その場で、やり取りで、何かが伝わっているなという実感は、我々はなかったですね。
神奈川新聞 武田:
分かりました。重ねてになるんですが、我々も事実誤認をしているつもりはなくて、事実に基づいて報じてきたつもりですし、そういう見られ方をする行政の進め方にも当然課題感があると思います。我々の伝え方も拙い部分があったかもしれないですし、そこは是正していかなきゃいけないと思うんですが。そのコミュニケーションの中で難しいから文書を連打するっていうのはやはり圧力になりますので、我々としてはそう受け止めると思いますので、是非それは今後是正していただきたいなというふうに思っています。以上です。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。よろしいでしょうか。tvkさん。
テレビ神奈川 今井:
テレビ神奈川の今井です。すみません。保育園バスの送迎の関係でお伺いしたいんですけども、首都圏で、川崎とか横浜のほうで送迎バスの運航会社が来月契約打ち切りするような動きがありますけども、現時点で市のほうで把握しているものがあれば教えて欲しいです。
政策経営局報道課長 矢野:
所管局から。
こども青少年局保育・教育部長 片山:
保育・教育部長の片山です。現在我々のほうで把握している状況ということなんですが。事業者さんとあと幼稚園の協会のほうとも連絡取り合ってまして、現状としましては、18社程度にそういう来年厳しいですよという話が来てまして、ただ、丁寧に事業者のほうは対応しているというふうに聞いておりまして、残り、5、6社ぐらいがちょっとまだ決まっていませんが、代替の事業者ですとか、あるいは直接雇用にするとか、様々な手を打ってですね、対応に影響がないようにしているというふうには聞いておるところでございます。
テレビ神奈川 今井:
それは、来月一杯で打ち切るっていうことになるんですか。
こども青少年局保育・教育部長 片山:
いえ、そこら辺が、打ち切りがあるかもしれないし、そうじゃないかもしれないしなんですけど、いずれにしても影響がないようにしていきたいということで、事業者さんも対応していると聞いているんですが、あくまでこれ民民の話ですので、お困りであれば我々も相談のりますが、基本はそういう状況を今注視していると、そういう状況にあります。
テレビ神奈川 今井:
市のほうで、何か対応とか何かされるってことは、今のところはないんですか。
こども青少年局保育・教育部長 片山:
現時点では情報収集していてということで、まあ幼稚園の所管って県ということもありますので、県とも少し情報取り合いながらというふうには思っております。
テレビ神奈川 今井:
ありがとうございます。改めて市長に伺いたいんですけど、こういった事態って結構非常事態というか、お子様にとっても、家族にとっても大変なことだと思うんですけど、改めてそこに対するコメントをいただけますか。
市長:
はい。園バスの運行に支障が生じますと多くの方がお困りになられます。是非市としてもしっかり情報収集して、対応を考えていきたいというふうに思っています。
テレビ神奈川 今井:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがしょう。よろしいでしょうか。それでは以上で会見終了します。ありがとうございました。
このページへのお問合せ
政策経営局シティプロモーション推進室報道課
電話:045-671-3498
電話:045-671-3498
ファクス:045-662-7362
メールアドレス:ss-hodo@city.yokohama.lg.jp
ページID:892-158-829