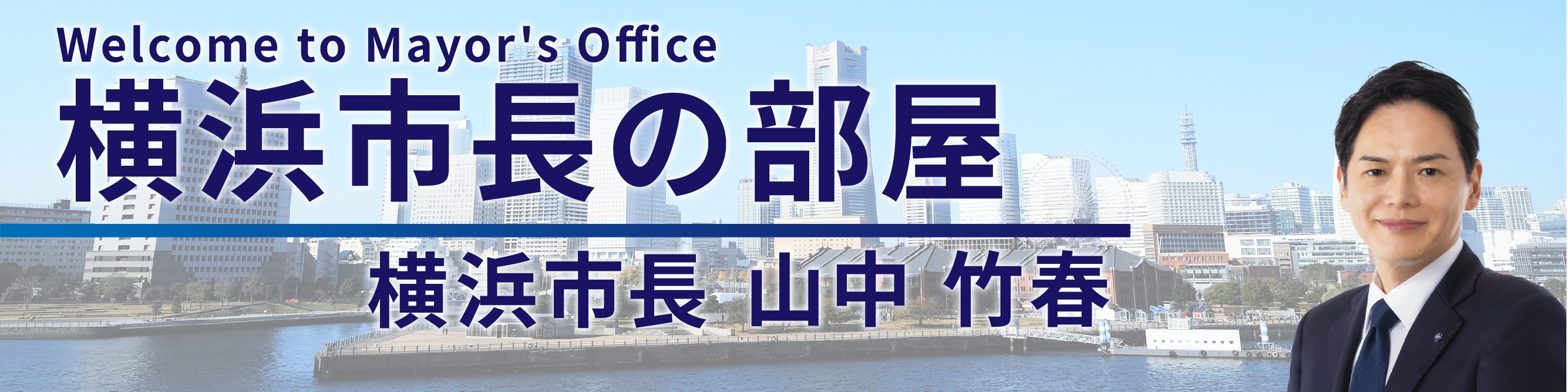ここから本文です。
- 横浜市トップページ
- 市長の部屋 横浜市長山中竹春
- 定例記者会見
- 会見記録
- 2024年度
- 市長定例記者会見(令和7年1月27日)
市長定例記者会見(令和7年1月27日)
最終更新日 2025年1月29日
令和7年1月27日(月曜日)14:00~
報告資料
会見内容
1.報告
令和7年度 横浜市予算案について
※敬称略
政策経営局報道課長 矢野:
それではこれより、令和7年度横浜市予算案に関する会見を始めます。市長、お願いします。
市長:
それでは、本市の令和7年度予算案について発表させていただきます。25年度、令和7年度の年というのは現行の中期計画の最終年度ということになります。資料の次ページから、2ページ、3ぺージ、4ぺージっていうのは、22年度、3年度、4年度のこれまでの中期計画に沿った取組についてまとめさせていただいておりますので、後ほどご覧いただければというふうに思います。これらのことを、議会とともに行ってまいりました。5ページ目をご覧下さい。本市の人口の推移ですね、推移を示したグラフであります。まずオレンジの線が、自然増減で死亡と出生の差を表しています。緑が社会増減で転入と転出の差であります。この緑とオレンジの差引の結果、すなわちプラスの社会増がマイナスの自然減を打ち消して、トータルとして人口増に転じたという結果であります。特に、社会増減については、過去20年間で最大のプラス幅になりました。その主たる要因がですね、20代から40代の社会増減が、これも過去20年間で最大のプラスになっておりまして、ここが全体の社会増減に大きくプラスに作用し、更に自然減も打ち消して、人口増に転じたというのがこのグラフの解釈になろうかと思います。こちらは生産年齢人口、すなわち15歳から64歳の推移でありまして、このコロナ以前から長らく減少傾向にあることが見て取れるんですが、本市の生産年齢人口、3年間連続して対前年比で増になっています。特にですね、この生産年齢人口の増加が影響していると思いますが、25年度の予算で見込まれる本市の税収に関しても大きく増えることになりました。それでは予算案、具体的に発表してまいります。これらの項目について、1から6までの項目について、順にご説明させていただきます。ここ数年、取り組んでまいりました本市の施策の効果が好循環として現れ始めているというふうに感じてます。次年度は、現行の中期計画の最終年度としての施策を展開しなければいけませんし、また、今後の横浜の発展につながるような施策を展開しなければいけないと考えています。そのためにも、引き続いて、データに基づいた施策の質の向上、並びに施策の創造と転換を推し進めていきたいと考えております。そしてその上で、人にやさしいまち、出かけたくなるまち、世界を魅了するまちを目指してまいります。9ページ目をご覧下さい。まず、防災対策の推進からお話しをさせてください。10ページ目でありますが、横浜市は令和7年度から5年間かけて約960億円を投じて、集中的に地震対策に取り組んでまいります。5年後の到達目標を個別に設定して管理をしていきたいと考えております。目標を立てている項目っていうのは結構あるんですが、そのうちの一部を抜粋して、こちらのスライドのほうにお示ししております。令和7年度は、工事に向けた設計作業などの下準備も多く含まれますが、本格的に地震対策をスタートさせる年としていきます。12ページご覧ください。まず、木造密集地域、通称木密と呼んでいますが、木密地域を対象に感震ブレーカーの全額補助を開始いたします。現在、木密地域っていうのは火災が広がりやすい地域として定義されておりますが、その木密地域における感震ブレーカーの設置されている割合っていうものを調べたところ、31%なんですね。これを80%にまで5年後、引き上げたいと思います。本市の規模感、世帯数を考えますと、50%を上げるっていうのはかなり大きな話になりますが、しっかりと火災対策として、地震による火災対策として進めていきたいと思います。また、新たにですね、高齢者世帯や障害者世帯を対象に、家具転倒を防止する器具の全額補助を開始したいと思います。現在、57%という設置割合ですので、これをですね、これまでも補助は行ってきました。きましたが、なかなかもうこれ以上伸びてないっていうところが長年続いてるんですね。これをもう一押しするために全額補助にし、かつお金を配るだけではダメなので、しっかりとアプローチをしていきたいというふうに思っています。これによって、これも規模感結構ありますが、80%という数字を目指しております。また、木造住宅の耐震化の促進が必要であります。そのためにもですね、補助金を拡大して旧耐震の建築物の除去を促していきたいと思っています。旧耐震の建築物の除去。また、1981年から2000年ですかね、81年から2000年の間の地区の建物っていうのが、いわゆるグレーゾーン住宅になっていますので、この20年間の間にできたいわゆるグレーゾーン住宅に対して、新たな耐震補助を開始したいというふうに思っています。13ページご覧ください。続いて、市民の皆様からの要請が高かった、避難環境の充実を図ってまいります。まず、ハード面といたしまして、小中学校のトイレの洋式化を進めます。小中学校のトイレがですね、本市、学校数ご承知のとおり多いので、全部で3万のお手洗い、便器があるんですね。3万器があります、約。そのうち、88%が洋式化されています。残りの12%っていうのがなかなか、これまでもちょっとずつはやってきたんですが、これ残りの3,000器をですね、一気に進めたいというふうに思っております。これによって、100%近い、ほぼ100%の洋式化を目指したいと思います。小中学校というのは、普段の子ども達の環境でもありますが、いざという時の避難所になりますので、そこで例えば足が悪い方に和式を使ってもらうっていうのは、それは避難環境としては改善すべきだと思いますので、しっかりと取り組んでまいります。それから、公園トイレの洋式化も着実に進めたいと思います。現在、公園のトイレが全部で1,900、2,000近くあります。本市の公園のお手洗いっていうのが、2,000器近くございまして、そのうちの75%に公園は留まっています。小中学校はまあ9割弱、88%って言いましたが、公園は75%に留まっていますので、この約2,000のうちの残りの25%ですから、500器ほどですかね、500器ほどの洋式化を一気に進めたいというふうに思っています。そして、市民の皆様からも要請の高かった、あるいは議会からも度々指摘していただきましたが、小中学校の体育館空調の整備を一気に進めます。まず、体育館がある小中学校というのが500ほどになります。正確な数字は、後ほど所管にお聞きいただければと思いますが、約500あるんですね。令和5年度、昨年度で500分の90が空調ついてました。逆に言うと、まあ400以上は付いてません。今年度は、一気に20増やしました。20増やして110程の空調設置数にしたんですが、それでも500分の110です。なので、約400近くが残っています。これを残り、5年間で一気に空調を設置したいというふうに思っています。今、気候変動もあり、夏は非常に暑いです。そして冬は寒くなります。そういう時に体育館で避難生活を送られる場合、空調が整っていないことにはやはり始まりませんので、空調環境をしっかりして避難生活送れるように、そういったことを整備していきたいというふうに思っております。また、14ページご覧ください。避難環境の充実に向けたソフト面の対策として、まず備蓄の飲食料、備蓄している飲食料なんですが、現在、1日2食を1日分なんですね。これを、国からの支援等も72時間が目安になってますので、3食3日分に確保したいというふうに思ってます。更に、流通備蓄という取組を活用して、民間企業さんと連携しながら、流通備蓄の取組を一気に進めたいというふうに思っております。また、これまで備蓄していなかった品目もありますが、市民の皆様のご意見や能登半島での職員の経験から、新たに備蓄を開始するものも多数あります。例えば、プライバシー確保のためのパーティション、少し横になるためのコット、あるいは介護食としての流動食とか、あるいは刻み食なども備蓄を開始いたします。また、全国で初めてTKBユニットの導入を行うことにいたしました。トイレ、キッチン、ベッドの頭文字をとってTKBユニットって言ってますが、そういった概念が今、入り込んできていると思うんですが、これをいち早く自治体全体として取り入れ、このTKBユニットの導入を開始したいというふうに思っています。15ページをご覧ください。医療的ケア児の支援では、特に特別支援学校に非常用のポータル電源を整備いたします。また、社会福祉施設等で避難される方も多数いらっしゃいますので、非常用電源の確保や、災害時マンホールトイレの整備を支援いたします。16ページご覧ください。上瀬谷地区にEXPOの開催後、本市初の広域防災拠点を整備すると何度かお伝えしてきました。具体的なイメージを初めてお話しいたします。まず、今、本市で備蓄庫っていうのがかなり小さいものも含めて12庫あるんですね。そんなにそれぞれは、ほとんどが大きいものではありません。13番目の備蓄庫を作る予定であります。本市としてもかなり大がかりな面積の備蓄庫を、上瀬谷に整備いたします。更にですね、従来の流通拠点をバイパス化して、いざ被災して避難生活となった場合、多くの物資が外から、本市外から支援たくさん来ます。物をですね、これまでのルートですと、例えば、スライド見ていただきたいんですけれども、国から県の一時拠点、それから市の、例えばパシフィコとかですね、その後、市の受入拠点で民間の倉庫とかにそれぞれ分配して、その後各避難所に、地域防災拠点のほうに配送するっていうそういうルート、ロジが一応なってるんです。しかしながら、もう煩雑ですので、いったん上瀬谷の地域防災拠点にワンストップで集めることができれば、この上瀬谷で例えば、荷捌き等を行って配送のロジを組んで、地域防災拠点に届けることが可能になると考えております。推計を行ったところ、既存の拠点をバイパス化して、上瀬谷でワンストップで送ることで、物資の到着時間が約7時間以上短縮する見込みと考えられております。また、物だけではなくて、人もたくさん、本市に来ていただけることになります。自衛隊もそうですし、警察もそうですし、消防もそうですし、医療、DMATなんかもそうだと思います。ボランティアの方なんかもそうだと思います。こういった方がですね、従来ですと、今場所がないので市外のサービスエリア、高速とかのサービスエリアに集まっていただいて、そこから例えば三ツ沢とか、新横とかに行って、そこで拠点にして各お近くの地域防災拠点に、例えば消防、消火に行くとか、そういう今ルートになっています。これを一旦、上瀬谷の防災拠点をセンターにして、そこから人をですね、派遣できるとより効率的だというふうに考えてます。例えば、設置が可能になれば、応援部隊の到着が約2時間以上短縮する見込みでありますので、特に消防面に関してはかなりの家屋の消失数の減少につながるというふうに考えております。この上瀬谷の防災拠点は、東名高速道路に隣接しています。立地条件を大いに生かして、市の防災の拠点としていきたいと考えております。18ページご覧ください。その他ですね、緊急輸送路に指定されている道路があるんですが、この緊急輸送路が何らかの事情で遮断されてしまった場合には、かなり大きなダメージを受けることになります。というか、必要な人や物が運べないということになりますので、非常に問題になります。緊急輸送路に指定されている沿道で崖とか電柱があるところへの対応っていうのが喫緊の課題であるというふうに思いまして、まず沿道の崖の崩落を防ぐ対策、それで車がそれ以上いけなくなってしまうとか、あるいは電柱が倒れてしまってそれ以上車が行けなくなってしまうとか、そういったことに対応していくための対策をとりたいというふうに思います。また、災害が起こった場合、給水、水というのが非常に大きな課題になります。被災地で水を求めて多くの長蛇の列をなしている、そういう姿っていうのはできる限りなくさなければいけません。そこで、避難所や病院など、水のインフラが特に重要なところ、避難所や病院など、水インフラが特に必要とされる場所の強化を行いたいと思います。具体的には、上下水道管の耐震化を行います。また、併せて、耐震給水栓を設置することによって、発災の直後からその場所で給水が可能になる、できる限り可能になる、そういう仕組みを整えたいというふうに思っております。これ地震防災対策の最後のスライドでありますが、これは地震というよりは、都市型の水害に対する大切な対策となります。今、気候変動です。気候変動によって1時間当たりの降雨量が従来の予想よりも多くなってきていることが、客観的に明らかになっています。しかしながら、本市を含め、従来の降雨量に対応した対策となっています。そこで、時間当たり降雨量が増えているっていうことを前提に、大規模な雨の際の貯留管を整備したいというふうに思っています。この貯留管の具体的な写真がちっちゃいんですけれども、こちらの左のほうの下にある、大きいんです、大きいし長いんですけれども、そこの貯留管を整備することで、必要なときに使えるようにしたいというふうに思ってますが、これ非常に大規模な工事ものになりますので、リスクの優先順位を考えて、計画的に整備をしていく必要があります。そこで、こういったことを行いました。まず、浸水の想定、浸水のしやすさですね、それをまず、リスクを考えまして、浸水想定の1点、2点、3点、4点を考え、更に、いざ浸水した場合の影響度っていうのをリスク化しました。浸水しやすいし、かつ、いざ一旦浸水した場合に被害が大きいと思われる252地区を同定しまして、そこにつながる雨水幹線を整備するという計画であります。このシミュレーションはですね、もう結構数年かけて実は行ってきました。今回初めて公表させていただくんですが、公表をすることになりましたが、普通の自治体は下水道だけを考えて、例えば浸水しやすさとか考えてると思うんですよね。そうではなくて、下水道ももちろん水漏れの原因ではあるんですが、水路とか道路の側溝とか、あまりこう考え出すと非常にきりがないというか、そういったところも実は都市にはたくさんあります。浸水しやすさを考えるとき、あるいは浸水の影響度を考えるときっていうのはどうしても、これ役所の都合だったと思うんですけれども、下水道だけを考えてきました。それではまずいだろうっていうことを、下水道局のほうからの発案で、ただその分大変だったんですけど、水路とか道路側溝なども完全に見える化した上で、データ化した上で、今回ですね、精緻なシミュレーションを行いまして、かなり確度が高い252地区を同定し、対策を行うものであります。その結果ですね、全部で44万以上の排水施設が対象になって、その中からリスクが高いところ同定したと。特に、これは影響が大きいところをピックアップして、水道の分野での事前防災っていう、これは全国初の取組だと思いますが、この対策を開始、事前防災の対策を開始したいというふうに思っております。地震以外にも、今風水害が高まっておりますので、こういった対策を行ってまいりたいと思います。続いて、子育て支援についてお話をさせてください。まず、21ページ目をご覧ください。今回の中期計画で、これまで行ってきた子育て施策をまとめております。次年度は特に、スライドの中の青の部分ですね、この青の部分でくくりました預けやすさを実現するための施策に着手してまいります。22ページをご覧ください。預けやすいまちを推進していくために、全国で初めてとなる、短時間に特化した認証制度の新設に向けて取組を開始します。今、託児所がいろんなとこで設置されていることが増えてきていると思うんですよね、これ民間ベースで、例えばちょっとイベントがあるとか、例えば私が前職のときに学会に参加しているときとかも、そういった託児所っていうのが設置されることが普通になってきました。ニーズはいろいろな側面で非常に高いというふうに思います。仕事の間、ちょっと預かってて欲しい、急に医者に行かなければいけない、歯医者に行かなければいけない、あるいはいろいろな諸手続きのためにどうしても預かってほしい、そういったこともあると思いますし、あるいは心身が疲れてリフレッシュしたいっていうようなことを思われるケースも多いと思います。ニーズが多様で大きい分、行政としても支援をしていきたいと思います。しかし、それを支援しようとするとですね、実はそういう預かりに対する基準がありません。今、民間ベースでやっているものはプロの保育士さんを配置して、プロの保育士さんに預かってもらう、数時間。民間として行っておられるんだと思いますが、行政としてそういったニーズにお応えしようと思いますと、やはり預けやすさもそうですが安心をつくらなければいけません。預けやすさと安心を両立できる、そういった預けやすいまちを創っていくための取組をこのたび開始いたします。こういった取組はですね、例えば保育なんかでも、本市、横浜保育室で作ってます。この横浜保育室っていうのは児童福祉法に定められた保育所ではありませんけれども、横浜市として独自に基準を設けて、例えば保育環境などが満たされれば、市として認定をし、運営経費の助成などを行っている、そういう認可外の保育施設のことであります。ですので、基準がないからニーズが高いにも手を出さないっていうことではなくて、やはり市民の皆様の安心をつくり、そして預けやすさを創っていくために、基準がないなら、何かこう基準を作って安心を担保しながら預けやすさを創れないか、そういう思いからこの事業を開始したいというふうに思います。希望するときに活用することができる自治体初の短時間預かりサービスの創設に向けて、モデル事業を開始いたします。例えばですね、どこにそういった預かり場所を作るかっていう一例なんですけれども、商業施設とか集客施設での短時間預かりっていうのが考えられると思います。これを常設できないかっていうことですね。例えば集客施設商業施設でそういった短時間預かりのところが、常設。もちろんデパートとかの開いている時間になろうかと思いますけれども、そういったものができれば非常に使いやすくなると思うんですね。ただ、現状調査が必要です。それから基準に照らし合わせた現行どういう基準があるのかっていうものを考えて整理をする必要があろうかと思います。併せて枠組みを検討していく必要があります。これらをですね次年度しっかりと進めたいと思います。そういった常設型の取組とは別に、非常設というか、非常設でいいんですかね。常設に対して非常設の取組を進めていきたいと思います。こちらは基準に関しては、前者よりは緩めになろうかと思いますが、例えばイベント時の短時間預かりをしていただける方に対して、民間ベースでやっていただける方に関して実施の補助を行ったり、あるいはこどもが楽しめる体験プログラム付きの一時預かり事業を開始できないかなというふうに思っております。はい、24ページご覧ください。そういった一時預かりの更なる使いやすさの拡充として、土日祝日に預かる仕組み、あるいは日中、日中もそうなんですけども土日祝日に預かる。あるいは、夜宿泊の預かりですね、オーバーナイトで預かれる。そういった仕組みを作りたいというふうに思ってます。ニーズ調査も含めてなんですが、例えばお子さんを見られる人が誰もいない夜。状況っていうのは例えば急な出張が入ってしまった。あるいは近くに親御さんもいない、そういったときで困られている方の声っていうのは聞きます。ですので、それなりの体制が必要になりますけれども、そういったことが可能かも含めて検討していきたいというふうに思いますし、また手続きがですね、預けるまでの手続きっていうのが煩雑になっているところもありますので、そういったところもきちんと改善していきたいというふうに思います。こういったことは既存資源を活用して多様なニーズに応えるための新たな取組を開始したいというふうに思っています。例えばこの右上にあるように、夜間宿泊も含めて24時間365日対応をするところとか、この左上にあるように、定員割れしている保育施設のスペースを活用するとか、左下にあるように市庁舎内で土日祝預かりできるかどうか。右下にあるように、利用の事前面談のオンライン化ができるかどうか。こういったことにも、チャレンジしていきたいと思います。役所として、預かりに対しては十分やっているというふうには、本市だけではないんですけれども、行政として預かりに対してどこまでできているか。やってるかやってないかって言ったらやってなくはないんだけれども、使いにくいし、私も自分の経験で、結局使えなかったことのほうが圧倒的に多いですし。またそもそも知らないっていう方は非常に多いんですよね。ですので、使いにくいっていうことに関しては、以前に比べて預けやすくなったかっていう市民の感覚、市民のご意見を指標にして進めていきたいと思います。やはり市民がどう思ってるかっていうことが重要ですので、以前に比べたら圧倒的に預けやすくなったって言っていただけることがKPIになるかというふうに思います。また、そもそも知らないっていう方は、本市としての周知不足でありますので、パマトコなどを使ってですね、しっかりと伝える。そういったサービスがあるんだと、支援をしているんだっていうことをお伝えしていきたいというふうに思います。預けやすいまちを目指して取組を進めてまいります。26ページをご覧ください。パマトコについては、今は乳幼児期の手続き等でお使いいただいておりますが、小学生にまで利用を拡大していくために、様々なできることを付加しようと思っています。まず、学童のオンラインでの利用申込の手続きを開始します。特に学童、民間学童の方にもですね、一応オンラインでの対応等をお願いすることになろうかと思いますが、そういったことを丁寧に進めさせていただいて、学童のオンラインでの利用申込の手続きをできるように進めます。併せてお子さんが学童に行ったときにね、来たら来たで、そこがeメールとかショートメールとかで連絡あると親御さんにとっても安心度が増すと思います。ちゃんと学童行ったな、放課後預かりに行ったなっていうことが分かると良いと思いますので、そういったメール連絡も可能にしたいと思います。また、小中学生にすぐーるでの取組が始まっていまして、すぐーるを導入したことで、紙のプリントを学校からご家庭に配布するっていう機会が大分なくなったと思います。学校からご家庭に紙のプリントで連絡するっていうことが大分減って、保護者の方々に確実に伝わるようになってきていると思います。一方で、逆。家庭から学校。家庭から学校にデジタルで提出できる。そういうルートも拡大したいと思っています。学校から家庭はかなり進みました。ですので、家庭から学校へのデジタル化っていうものを進めたいと思ってます。例えば学校の提出書類いろいろあると思います。それを書いて子どもに持たせて行くってなると、やっぱりいろいろな忘れ物も出てくると思いますし、教員の手間も増えると思いますので、あとは何よりも書く手間が保護者ありますので、そういったことをデジタル化でできる限り減らしていきたいなというふうに思ってます。こういったところですぐーるとパマトコの連携を始めたいというふうに思います。27ページをご覧ください。小学生の夏休み期間中の学童での昼食提供を今年度開始しましたが、これを冬休みと春休みにも期間を拡大いたします。夏休み中はもちろん行います。それから使い勝手に関しても、より簡易にしたいと思います。キャンセルをする場合、結構前にキャンセルしておく必要があったんですよね。それは業者さんの都合があったわけなんですけども、保護者の使いやすさからしますと、やはりキャンセルっていうのは直前に生じやすいものではありますので、そういった対応が出来る限り可能になるようにしたいと思います。また小学生の朝の居場所づくりモデル事業については2校で青葉区やってますが、これを全市的に10校に拡大していきたいなと思ってます。今年度はですね、朝の居場所づくり事業を始めたんですけれども、保護者説明会を行ったのが6月とかだったんですよ。保護者の方のご意見聞いてみますと、そんな時期に言われても困ると。もう4月に入った時点でだいたい生活のスケジュール感は組んでいるので、6月からそういった預かり始めますよ、できるなりますよって言われてもやっぱり生活スタイルがあるし準備の問題もあるので、すぐには変えられませんっていうようなご意見あって、ごもっともだなと思ったんですね。ですので、これから議会に予算を承認していただく、いただけることが前提ですけれども、しっかりと4月、新年度になってからすぐにこういった取組が開始できるように準備を進めて、保護者の皆様への周知時期を早めるということですけど、そういったことで利用の拡大を図ってまいりたいと思います。28ページをご覧ください。青葉区の3つの地区で地域交通サービス「あおばGO!」を行っております。これ行政によるモデル事業を経まして、次年度は企業主体での運行をモデル実証として行います。令和8年度からですね、本格運行を目指していきたいと考えております。29ページをご覧ください。英語に関してであります。AETの増員によって、小学校の英語教育を推進していきたいというふうに思っています。AETを大幅に増員して、全ての小学校でAETによる授業が毎日、リアルないしオンラインでできるようにいたします。全国でも初めてか、初めてに近い取組であろうかと。特に本市の規模を考えますとAETの人数もそれなりに必要になりますからこの取組はかなり本市としても挑戦的なものではあるんですが、是非このAETを確保して、全小学校で英語教育推進していきたいと考えております。また、高校生の留学支援を強化したいと思います。長期留学枠。長期留学した場合の支援額が今40万なんですが、これを150万円に増額したいと思います。40万円ですとなかなか長期っていうのが難しくありますから。例えば半年とかそういった期間でもですね、是非支援をして多くの方が海外経験できるようになることを目指したいと思います。また、短期留学への支援も開始して対象人数を100人にいたします。更に本市市立高校ありますので、市立高校を対象とした長期の留学プログラムを新設します。8年度に向けて開始したいというふうに思っておりますので、今年度中に制度設計をします。特に中高一貫校あります。そういった中高一貫校での長期留学の促進なんかも視野に入れております。中高一貫校以外での留学促進も含めてしっかりと横浜の高校生の留学支援。支援していきたいと考えております。30ページをご覧ください。図書館であります。新たな大型図書館の整備に向けまして、基本構想を次年度策定いたします。また、新たに市の全域におきまして、地区センターなど身近な施設で図書の取次拠点を増やすことを取り組んでまいります。また、野毛の中央図書館で現在、喫茶部分を親子フロアとして改修中で、今年の4月にはオープンいたします。それとは別に、中央図書館の1階全部をリニューアルして子どもフロアを作りますが、その設計工事を開始いたします。26年度のオープンを目指して、この野毛山の図書館のですね、1階部分の子どもフロア化っていうことを進めてまいります。またデジタル技術を使った新たな図書サービスの導入も着手したいというふうに思います。31ページご覧ください。誰もが暮らしやすいまちづくりについてご説明をいたします。32ページなんですが、こちらのスライドは既に昨月の都市整備局や健康福祉局の常任委員会で議員の先生方や、あるいは記者の皆様方にも共有させていただいている内容であります。市内の交通空白地域なるものを見える化して、面積の大きな地域、その中の面積の大きな地域が53か所でしたっけ。53か所ほどありますので、その53か所を向こう4年間で全部解消すると。すなわちそこに地域交通を導入することによって、市内交通空白地域のうち、面積が大きな部分を全て解消するという取組であります。また、34ページご覧ください。地域交通を増やす取組を行うとともに、それに対して、敬老パスを使えるようにしたいと思います。併せて、運転免許証を返納した方に敬老パス無償交付する取組も開始いたします。36ページの上段をご覧ください。こちら36ページをご覧ください。令和7年度、次年度はですね、受動喫煙対策を更に強化していきたいというふうに思います。受動喫煙対策はようやく端緒についたばかりですので、ペースを上げていきたいと思っています。これらの取組を進めていきます。38ページご覧ください。がん対策を主にまとめております。これまでこの赤字で囲んだ部分を総合的ながん対策として行ってきた、あるいはこれから行っていく内容であります。次年度は子宮頸がん検診のHPV検査単独法の導入や、70歳以上のがん精密検査の無料化、また65歳時点のがん検診の無料化など、これを本格的に開始する年となります。併せて新しい内容といたしまして、子宮頸がん検診の無料クーポンが現在20歳対象にお配りしているんですが、頸がん検診の啓発、普及拡大も視野にですね。20歳だけではなくて、24歳まで20、21、22、23、24、20歳から24歳まで配る、そういった対象年齢を拡大いたします。併せて、小児がん患者さんの交流に関してメタバース空間を使った実証実験を今年度やってきました。患者さんご本人や保護者の方にも非常に評価をいただいておりますので、次年度はこの小児がん患者さんのメタバースによる居場所づくりを常設化したいというふうに考えております。40ページご覧ください。左上でありますが、子どもの弱視がどうやって見つけるのか。早く見つけないと、成人してから影響大きくなりますので、弱視の発見力を向上する。その目的に3歳児検診に新たに屈折検査機器による検査を導入いたします。弱視の早期の発見、並びに早期の矯正開始を可能にしたいと思います。まず、先行区で導入いたしまして、課題を抽出し、令和8年度からの全区への展開を目指します。そして、お一人様の老後を支える情報登録事業、高齢者の方のお一人様の老後を支える情報登録事業を新たに創設したいと考えております。41ページご覧ください。防犯対策を今後深めていく必要があります。まず第1弾として、地域の防犯対策への緊急補助金を行いたいと思います。約3,000程自治会町内会ございますが、自治会町内会が行う防犯パトロールに対して、あるいは防犯品を購入したりセンサーライトを整備したり、防犯講座などを開催したり、そういった公益的な取組に対して補助率90%、9割の補助額の緊急補助を開始することにいたしました。また、防犯カメラ設置費用を拡充いたしまして、設置費用の補助ですね、すみません、防犯カメラの設置費用の補助を拡充いたしまして、補助台数を180台まで拡充したいと考えております。約10年前に比べて3倍ほどの設置増につながる予定であります。42ページご覧ください。こちらは何度かもうお伝えしているの野毛山におけるインクルーシブ構想であります。野毛山動物園のリニューアルに向けて動物展示など複合施設の設計を進めてまいります。併せて中央図書館1階全部の子どもフロアの件は先に述べました。またほかの身近な公園。身近な公園の遊具の改修、更新を積極的に行っていきます。いわゆる街区公園って我々が呼んでいるものですが、身近な公園の遊具の改修や更新を今後強化していきたいと思っています。まず来年度は、本年度に比べて倍増。対象の公園を倍増させますが、させたいと思っていますが、今後もこちらの予算を強化していきたいというふうに、私は思っています。そして本牧市民公園を始め、5か所。計6か所ですね、計6か所の公園にインクルーシブ遊具を設置、進めていきたいと思っています。43ページご覧ください。今年度は新たな取組として、農業の素晴らしさを市民に身近に感じていただく取組を開始したいと思っています。特に、子育て世帯の農体験の機会が増えることを目指します。都心臨海部で農体験ができるようになる。あるいは郊外部における農体験の機会を増やす。こういった取組であります。それから横浜でいろんな各地でこれから作るものも含めて、農体験できるところがあったり増やしたりした場合に、そういった情報をですね、一元的にやっぱり取れるようにするっていうことも、子育て世帯が見て今日行こうかと、フルーツ、果物取りに行こうかとか。そういったことも可能になろうかと思いますので、農作業しに行こうかっていうことも、そういった話合いも促進されると思いますので、そういった情報を一元的に提供できる情報源を作りたいというふうに思っています。はい、44ページご覧ください。市民の声を新たに聴く手法としてデジタルプラットフォームを試行的に導入してこの間活用を行ってまいりました。令和6年度はこのデジプラを使ってですね、市民の皆様からご意見をいただいた結果、次年度の予算に市民発案の計54事業、そして予算額としては5,600万円ほどを反映することができました。次年度もですね、18区。次年度も18区の多様なニーズや課題をお聴きするために市民の声を聞く。そのためにもデジタルを活用した広聴手段を引き続き展開していきたいというふうに思っています。45ページをご覧ください。にぎわい経済の活性化の取組についてご説明をします。まず46ページ、水際線の魅力の向上を図るために歩行者空間の創出並びに道路や公園等の公共空間を活用したにぎわいづくりを本格的に進めたいというふうに思っております。臨港パークのほうからですね、ずうっと来て、約5キロの道のりというものをもっと磨き上げて、観光に訪れる方も、それから市民の皆様にも憩いを与える、そういう場所にしていきたいというふうに思います。また、そのためにも水際線のまずコンセプトプランを策定します。併せて各エリアの今課題として思っているものもありますので、各エリアの魅力の向上に取り組んでまいります。そして山下ふ頭の再開発に向けて、再開発検討委員会からの答申を踏まえて、事業計画の策定に入ります。48ページご覧ください。国内外から人を企業を投資を呼び込む循環を生み出すスタートアップエコシステムの形成に着手いたします。併せて京浜臨海部を先端技術の創出拠点として、半導体をはじめとする成長分野の企業集積に向けた基礎調査を行いたいと思っています。49ページをご覧ください。市内企業に対して、デジタル化を支援するとともに、企業での外国人の就労に関する必要な支援の研究調査を行います。併せて戦略的な回遊性の向上や、宿泊の促進策によって、にぎわいの更なる創出につながる。そういった観光消費額の増加を押し上げるようなそういった戦略的な取組を行ってまいります。50ページご覧ください。以降はグリーン社会の実現に向けた取組についてご説明いたします。まず、昨年の予算額、この分野の予算額が約80.8億円でした。それを次年度は177億円にしたいというふうに考えております。循環型社会に向けた取組や、脱炭素社会の形成に向けて、2月補正を含めてになろうかと思いますが、計177億で取組を進めていきたいというふうに考えております。52ページをご覧ください。循環型社会に向けて、こちらのスライドにあるような取組を開始していきたいというふうに思います。こういった取組を1つ1つ進めていくことによって、市民の皆様や企業の方々の意識の変化、行動変容につながることを期待しております。以降のスライドでは四角で囲んだ項目について特に内容を説明しているものであります。53ページをご覧ください。循環型社会の取組を次年度は強化いたします。実際に、循環社会というものが、いろいろなところで言われていますけれども、本格的な取組を展開しているってところが世界的に見てもそんなにあるわけではないと思うんですよね。例えばアムステルダムとかは有名なんですが、アムステルダムのレポートとかをいろいろ見てもですね、本市としてやってきている部分もあるし、できてない部分もあるし、でもこの循環型社会の取組を強化していくっていうことは、GREEN×EXPOを開催する本市としても重要なことでありますので、この循環型社会への取組を加速させます。例えば不要な衣料品を再製品化する。服から服へ、服to服と言ったらいいんですかね。繊維とかを取り出して新たな服にするとか、それはボトルtoボトルなんか有名だと思います。ペットボトルを回収して一旦必要なものを取り出して、新たなペットボトルを作り出すボトルtoボトルの取組とか。あるいは、中学校制服のリユース・リサイクルなんかもできないのかなあというふうに思っています。それから、食品ロスを削減するためのSDGsロッカーについては引き続き進めます。また、GREEN×EXPOを開催しますが、そのEXPOの建物っていうのは基本的に造って終わりではなくて、造ったものをEXPOの開催後も活用したいと思っているんですね。EXPOを開催後に作ったものを再利用していくために、建築材の再利用のあり方っていうものを、始めたいというふうに思います。いわゆる循環建築って言ったらいいんですかね。造って終わりではなくて造ったものを別のところでどう活用するのか。そもそも造るものもですね、木材等を中心に、やっぱり優しい建築物が必要だというふうに思うんですが、そういった木材も造って終わりで廃棄するのではなくて、別の用途にリユースできるような検討を開始します、はい。54ページのスライドは従来から申し上げている、この4つの柱でグリーンイノベーション、カーボンニュートラルに向けた取組を行っていくという内容であります。1つ、ちょっとですね、お伝えしておきたいのが、グリーンエネルギーパートナーシップというものを創設いたします。これはですね、家庭で太陽光発電がつくったとします。それでご家庭で消費した分をクレジット化して、そのクレジットを扱うような仕組みを作るっていうことが目的であります。クレジット化してですね、扱うような中間施設ができたとして、環境価値がつくられますので、そういったものを市内のイベントとか、あるいはGREEN×EXPOなんかも該当すると思いますが、そういった各種のイベントで、市民の皆様によってつくられた環境価値を引き続いて活用できるようにしたいというふうに思っております。また、市内の住宅の約6割を占めているのが、集合住宅であります。この集合住宅における脱炭素をどう進めていくのか、再エネをどういうふうに使って、導入していくのかっていうのは課題であります。本市を含めて、いろんな都市での課題であろうかと思います。その点を考えまして、受変電設備等の設置に対する補助制度を新たに新設したいというふうに思っています。また、全ての中小企業さんが脱炭素化に向けて動きを進めてもらうためにも、まず脱炭素取組宣言をしてですね、この間なんと3,000者が脱炭素取組宣言に手を挙げていただきました。かなり思ったよりも企業さんの反応っていうのが良かったんですけれども、その中からですね、約3,000ほど脱炭酸取組宣言に手を挙げていただきまして、そのCO2の排出量を把握できた企業さんっていうのが656件ありました。また、カーボンニュートラル設備投資に申請していただいた企業さんも237件ほどになりました。ですので、まず企業さんのCO2排出を減らすためにも企業さんの行動変容を促す、併せて、行政としてどのくらいのCO2がどこから出ているのかっていうのを細かくする必要がありますので、そんな取組がどこの都市もやってないので、本市として先駆けてそういったことをやりたいというふうに思っております。それから56ページご覧ください。大さん橋への陸電設備設置の導入促進です。電気使った船が来た場合に、ちゃんとそれ用の設備がないと、電気使った大型船が本市に来られないことになりますので、大型船舶用の陸上電力の供給設備の設置に向けて取組を開始します。また、右上にある取組は、これはちょっと私としては強調したいです。みなとみらいで、日本で初めてとなる地区内における資源循環率の可視化に取り組みます。どういうことかといいますと、ごみとか出て行ったもの、例えばごみとかペットボトルとか、MMから出てったものがあるじゃないですか。それがどのくらいリサイクルとかされて、リユースされて戻ってきたか、アウトとインを可視化して、資源循環率を指標として使えるようにしたいという思いであります。地域全体、会社でやってるところっていうのはいくつかあると思います。海外の都市を見てもレポートを読むとアムステルダムとかは一部の地区とかでやってるんですよね。一部でやってます。ただ、あれだけの地域全体で、就業人口13万人の地域全体でやってるところは世界的に見ても稀か、初めてだと思います。ですので、資源循環率ってアウトとインなので、結構難しいことはご想像いただけると思うんですけども、ただやっぱりデータで見える化して、それをもとにモニタリングしていきたい。それでこそ取組が進むと思いますので、しっかりとこの取組をやってまいります。併せて電気の公共施設のLED化を早く進めていきます。57ページご覧ください。GREEN×EXPOの開催に向けた総合的な取組としてボランティアセンターの立ち上げや市民参加プログラム、あるいは広報・共有の場を通じて、市民活動の輪の拡大に向けて支援を進めていきたいというふうに思います。また、新たなグリーン社会の形成に向けた市民の行動変容の促進として、現在、STYLE100を始めたところですが、このSTYLE100の取組を増やし、また、併せて小中学生を対象にした教育プログラム、循環社会やグリーン社会に対する教育プログラムを強化していきたいというふうに考えております。最後、データドリブンプロジェクトで、すみません、もう1時間以上お話してますので、もうそろそろ終わりにしたいと思います。59ページの上段のほうにですね、まとめてございますが、この間、データに基づく政策経営を進めてまいりました。令和6年の4月からデータ駆動型のプロジェクトを開始しております。ページの中ほどに示してございますとおり、全ての施策を対象に、まずデータ集めから始めて、分析して、データベース化して各所管部局と共有できるようにして、各施策のこれ、質が出ているかどうか、施策の質の向上を図るにはどうしたらいいか、それからそもそも各施策について、創造や転換を図ったほうがいいんじゃないか、そういったことを議論する材料として、データを基にした政策経営を進めてまいりました。現在ですね、2030年度までに減債基金に頼らないようにする、そういった財政ビジョンの目標をつくっております。財政ビジョンの中で減債基金の取り崩しによる、一時的な貯金の使用というのは、もうやめるようにする。ただその分、財源をつくるということを、財政ビジョンの中で目標として決めております。2030年度までにだいたい500億円ぐらいの財源創出を目指しているところであります。これによって、減債基金っていう、万が一のときの貯金を取り崩すことが、これまで、私の就任前まで結構常態化してたんですけども、これをなくす。30年度までの500億円という目標に向けまして、今、年間、70億、そのぐらいのペース感で恒常的な財源を捻出し続けているところであります。今、プランド、計画の額とアクチュアル、実際にこのぐらいまで財源創出ができていますと、恒常的な、一時的な財源創出ではなくて、恒常的な財源措置ですね、それが今ちょうど200億近くまで、今、進んでいますので、ちょうど今、計画に対して実際の創出額は一応予定どおりには来てます、という内容であります。はい、ちょっとこの辺はもう飛ばします。最後ですね、一般会計が令和6年度、65ページをすみません、ご覧ください。令和6年度、これ最後のスライドになりますが、令和6年度は1兆9,156億円でした。それに対して、本年度は1兆9,844億円で3.6%の増となりました。特別会計、公営企業会計を合わせたトータルも、約4%の増加となっております。これらが令和7年度の予算規模となります。はい、以上となります。以上、すみません、令和7年度予算案についてご説明差し上げました。すみません。
政策経営局報道課長 矢野:
はい、それではこれより予算案に関するご質問をお受けします。複数ご質問がありましたらまとめてお願いできればと思います。また、併せて、お手元の資料に該当するページがございましたら、併せてお知らせいただきますようお願いいたします。まず、幹事社からお願いします。
日経新聞 松原:
日本経済新聞の松原です。まず、今回の予算案について、何か一言、キャッチフレーズで、何か象徴するようなものがあれば、お聞かせください。
市長:
はい、「もっと人を惹きつけるまちへ」であります。こちらを次年度の予算のキャッチフレーズにしたいと思っています。
政策経営局報道課長 矢野:
目線欲しい方、いらっしゃればお声掛けください。よろしいでしょうか。続けてご質問あれば。
日経新聞 松原:
はい、ありがとうございます。すみません、キャッチフレーズについてもう少し詳しく、「もっと人を惹きつける」のところを何かちょっとお伺いできますでしょうか。
市長:
はい、市民の皆様からの要請が高いことについて、優先的に進めていきたいというふうに思います。地震対策、子育て支援、地域交通の拡充、それらが核となりますが、そういったことに取り組んで「人にやさしいまち」を創っていきたい、その思いからの予算であります。
日経新聞 松原:
ありがとうございます。もう1つ、今回全てのプロジェクトが非常に重大だと思うんですけれども、その中でも特にこの、肝いりというか重点化しているものがあればお聞かせください。
市長:
はい、全て大切なんですが、特にあえて挙げるとしますと、今、申し上げたとおりなんですが、地震対策、子育て支援、そして地域交通の拡充、この3つであります。
日経新聞 松原:
ありがとうございます。最後にもう1つ、今回の子育て支援のところで横浜型の預かり制度ということを作られてるかと思うんですが、非常に他の自治体でもやれていないユニークな取組になるかと思うんですけれども、こういった横浜型の預かり制度を作ることによって、どのような子育て社会というものを創っていきたいのか、描かれているのかということをお聞かせください。
市長:
はい、「人にやさしいまち」を創りたいっていうふうに思っています。それは全ての世代にとって優しいまちであります。子育て世代にとって優しい街って何なのかなって思いますと、やはりこういうゆとりがあるということだというふうに思います。ゆとりを創るための方法はいろいろあるとは思うんですが、結構、時間的なゆとり、精神的なゆとりを創りたい、そういう思いから預けの取組を開始したいというふうに思っています。
日経新聞 松原:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
それでは各社いかがでしょうか。朝日新聞さん。
朝日新聞 良永:
朝日新聞の良永と申します。まず、人口の推移について、5ページ目なんですけれども、4年ぶりに人口増に転じたということで、市長、子育て支援策に力を入れている中でのこのデータかと思うんですけれども、その背景について改めて見解を教えていただけますでしょうか。
市長:
はい、詳しい要因分析を更に進めているところではありますが、これまで、議会とやってきた様々な子育て施策が好感されているのかなというふうに感じています。これまで、横浜に来たいと思っていた人が実際に入ってきてくれる。あるいは、これまでだったら横浜から出て行かれた方々が横浜に留まっていただけると、そういった転入転出の差がですね、過去20年間で最大になったっていうことが我々としても、非常に嬉しく思っています。
朝日新聞 良永:
ありがとうございます。あと、短時間預かり認証制度について、2点お伺いしたいんですけれども、詳細は来年度検討をしていくというところで、ただ一方で、対象年齢ですとか、有資格者の配置、どうなっていくかというところ、気になるんですけれども、方向性見えていれば教えていただけますでしょうか。
市長:
はい、預けやすさというものを創りたいというふうに思っております。私自身もですね、いろいろな保護者の方とも話しましたが、やはり子育て世代の皆さんから使いたくても実際に利用できないとか、私も経験あります。それから、手続きがそもそも煩雑で分かりにくいというようなお声もいただいておりますし、あとですね、子どもを預けることに。不安感とか罪悪感があるという声が結構多いですね。そういうときに、例えば、そのご家族が日常的に利用されている商業施設とかで預けることができれば、その不安感と罪悪感のハードルって少しかもしれませんが、下がると思うんですよ。ですので、単に場所を増やすとか、例えば保育園で一応そういった制度を作っているとかだけでは駄目で、やはり預けやすさ、柔軟に預けやすくなるような整備が必要だと思うんですよね。ですので、そういった使いやすさと、安全安心あっての預かりですから、親御さんが、保護者の方が安全安心でということを担保するために、基準を作り、横浜型の認証制度を作り、その上で使いやすさを高めていくっていうことを目指していきたいと思っています。
朝日新聞 良永:
ありがとうございます。最後に1点になるんですけれども、大きく見た中で、保育士不足っていうことがずっと言われているかと思うんですけれども、担い手の確保についてはどう考えていらっしゃいますでしょうか。
市長:
はい、ご質問ありがとうございます。そういった短時間預かりで活躍していただいているプロの保育士さんも潜在的には結構いるんじゃないかなと思うんですよね。ですので、そういった方々の発掘も含めて、是非本市として預けやすいまちを目指していきたいと思っています。
朝日新聞 良永:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他、いかがでしょうか。NHKさん。
NHK 岡部:
NHK岡部です。よろしくお願いします。子育てのしやすさの点なんですけれども、先ほどの人口が増えてきて、手応えを感じているというお話ありましたけれども、これまで行ってきたことで特にこういった施策が受けているんじゃないかとか、お感じになっているもの、ありましたらお願いします。
市長:
難しい質問ですね。各施策もそれぞれ職員や議会とともにつくってきたものなので、それぞれの施策がどのぐらいインパクトを及ぼしているのかっていうのが、ちょっと定量的には評価できないので、質問に正確にお答えできないんですが、やはり横浜市として子育て支援をどんどん強化していくっていう姿勢は感じ始めていただけているんじゃないかなというふうに思っています。ですので、ただ、今、進み始めたとこですので、より一層加速するように職員と一丸となって進めていきたいと思っています。
NHK 岡部:
ありがとうございます。あと、子育て施策なんですけれども、子育て世帯がどこに住むか、ここにいるのか、ほかの自治体に行くのかっていうのを考えたときに、どうしても近場である、この東京都の自治体も選択肢に入ってくると思うんですけれども、東京都だと5,000円給付の018サポートだとか、あと保育料の無償化だとか、都内の自治体だと給食費の無償化とか、今度は無痛分娩の助成だとか、どうしても財政的な違いもあってかなりメニューみたいなところでなかなか横浜市として、差がついてるって言ったらあれかもしれないですけれども、そういったなかなか強力なライバルがいる環境だと思うんですけど、その辺りのところはどういうふうに市長は見られているんでしょうか。
市長:
はい、ご質問ありがとうございます。経済的なゆとりの部分については、今後も本市として支援を進めていきたいというふうに思います。今、おっしゃっていたの、特に経済的なゆとりの部分かと思うんですが。一方で、精神的なゆとり、あるいは時間的なゆとりを創るっていうことも必要だと思います。パマトコをつくって、出産費用の手続きっていうものが圧倒的に早く終わったことで多くの方からも評価をいただきましたし、またおむつのサブスクなんかもですね、私が預けていたときの経験からするとやっぱりサブスクっていうもので、おむつの持ち帰りがなくなる。そういった取組ですね、時間的なゆとりにつながっていると思いますし、あるいは学童の昼食提供なんかもそうですし、夏休み期間中の。また、今回始める預かりなんかも時間的にゆとりを創りたい、精神的なゆとりを創りたい、その思いからであります。経済的なゆとり、大切です。一方で、時間的なゆとりも大切だと思います。本市では両輪をですね、高めていくことで、子育て世帯から選ばれるまちを創っていきたいと思っています。
NHK 岡部:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他、いかがでしょうか。東京さん。
東京新聞 神谷:
東京新聞の神谷です。先ほどの横浜型短時間預かりの制度なんですけど、これは認証制度は、具体的に何を認証、例えばその、保育園の配置基準とかがあると思うんですけど、例えば、そこで0、1、2歳はやらないみたいなことも聞いているんですが、具体的にどういったところだったら認証するみたいなものってあるんですか。
政策経営局報道課長 矢野:
所管局から。
こども青少年局保育・教育部長 片山:
保育・教育部長の片山です。ご質問ありがとうございます。現段階では検討中ではございますけど、今のところ、例えば3時間、2時間程度の預かりを基本として、そこに対して、例えば人の配置とか面積ですとか、どの程度まで必要なのかっていうのをこれから検討するということでございます。今の保育園というのは、基本的に長時間での預かりをベースにした基準が引かれていますので、そこまで必要じゃないだろうというところで、どう考えていくかということでこれから検討しております。
東京新聞 神谷:
そうすると、例えば、商業施設などでやるっていうことですけど、その広さとして、最低限面積とかその人についても基準はあるんですか。
こども青少年局保育・教育部長 片山:
そこら辺はまさにこれから一定程度、なんでもいいというわけではなくてですね、一定程度決めていこうと思っていますが、あまり求めすぎると今度は過剰になってしまいますので、そこら辺のバランスをこれから見ていくということでございます。
東京新聞 神谷:
これはなんて言うんでしょう、各施設さんでもちょっとした、例えばプレイスペースとかあるとこいっぱいあると思うんですけど、それをなんか市の認証で、なんて言うんでしょう、何が変わるんですかね。
こども青少年局保育・教育部長 片山:
既に多分満たしているとこもある、例えばですよ、一定基準があった場合満たしている所もあれば、ない所もあると思いますので、一定のそこにラインを引いて安心してご利用いただくということを目的としております。
市長:
今、神谷さんおっしゃったプレイスペースって最近増えてると思うんですが、ただあれは、保護者の方がいて、そこで遊ばせて時間使えるようにするって、子どもと一緒に時間を使えるようにするっていうことが主眼だと思うんですよね。それに対して一定の面積、一定の保育士さん等々で預かりをできるようにしたいっていう趣旨であります。ただ今部長さんおっしゃったとおり、そういう短時間預かりの制度が国は念頭に置いていませんので、一方でそういったニーズは多様だし大きくあります。ですので、是非本市としてそこに応えていきたいというふうに思っています。
東京新聞 神谷:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょうか。神奈川新聞さん。
神奈川新聞 武田:
神奈川新聞の武田です。今の預けに関連してなんですが、改めて行政が、ここまで手厚く取り組む意義っていうものを改めて伺えればと思います。
市長:
はい。さっきの質問にも関係するんですけど、時間的なゆとりや精神的なゆとりをどうやって創り出すかっていうところに行政として踏み込んでいきたいというふうに思っております。経済的なゆとりに関して補助金という形で、各ご家庭を支援していくっていうことは大切な取組だと思います。一方で、お金だけではなく、子育てしやすいと思っていただけるためには、お金だけでは測れないものもあると思うんですよね。そういったことに行政としても人数も多いですし、重層化していますので、取り組んでいきたいという意図です。
神奈川新聞 武田:
ありがとうございます。もう1点、行政がやっていく、認証の制度でやっていく中で、万が一のアクシデントが起きた場合の責任の所在というのはどこに置く形になるんですか。
市長:
そういったことも含めてですね、ですのでどこの行政もそういったところに踏み込むことは、やはり躊躇しがちだと思うんです。ただそういった時間的なゆとりを創っていくっていうことで、預けやすさっていうものを創っていくことの必要性は、私は論を待たないというふうに思います。ですので、そこに取り組んでチャレンジしていきたいと思っています。
神奈川新聞 武田:
ありがとうございます。別の事業で、産後ケア事業は横浜市の事業で今係争中ですけれども、市の事業で委託先で起きた事故に対して今横浜市としては責任がないと言い切っているという主張をしているわけですけれども、今回のケースで市側がある程度責任を持つって言い切れるのか、そうじゃないのか。
市長:
そういった基準をまず作るっていうことじゃないですか。今いろいろな、先ほど冒頭申し上げましたけど、民間ベースでいろいろ預かりに関してやってるじゃないですか。あれを行政としてやる場合に、いろいろな基準を満たした上で安全に預けられるっていうふうに親御さんに思っていただかないといけないので、そういった基準を作っていくということになりますね。
神奈川新聞 武田:
分かりました。ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。読売さん。
読売新聞 田川:
読売新聞の田川と申します。3点質問させていただければと思います。まず1点目は、資料の50ページのデータドリブンプロジェクトについてなんですけれども、こちらが例えば市長のデータサイエンティストとしてのご経歴を生かした市長直轄プロジェクトですとか、そういう言い方ができるのかっていうところと、今年度、7年度予算に具体的にいくらの歳出、このプロジェクトによって、幾らの歳出削減を実現できたかっていう具体的な数字があれば教えてください。
市長:
分かりました。ご質問ありがとうございます。まずこちらに関しては当初から私の思いとともに行ってきております。特に歳出改革をしていく上で、各所管部局もそうですし、議員の先生方もそうですし、あるいは、実際の市民の皆様がいます。いろいろな方々と対話を促進していく上でやはり経験や勘に基づくところっていうのも重要ですが、客観的なエビデンスが必要になると常々考えておりました。ですので、こういった歳出改革に取り組んでいく上での、私自身は全国でも初めてのこういった全庁的なプロジェクトを、特に横浜市のような巨大な都市が行うっていうのは意義があるっていうことだと思いまして、私自身の思いを乗せてこのデータドリブンプロジェクトを進めてまいりました。そして現在ですね、創ってきた金額というのがこちらになります。7年度予算編成、64ページですが、7年度予算に向けて、つまりこの6年度に行った対応っていうのが全部で1,240件の事業で172億円あるんですね。この172億円は、例えば局としてこんだけ要望をしていただいたんですが、精査した結果、ちょっとこれは多すぎるでしょとか、かえってこんだけやっちゃうと税金の無駄遣いになっちゃうでしょとか、そういうものを財政局中心に各局とやりとりしてもらって、それで積み上げた金額が172億円という数字で、そのうちですね、今回のベーターベースドで、エビデンスベースドで恒常的にですね、きちんとつくり上げたのが約80億円、79億円ということになります。これを毎年今行っております。毎年80億とか70億っていう、これ恒常的な財源になります。こういったものを積み上げて今200億円近くまでこの3年間ぐらいでつくって来てる。で、これは2030年度までに、恒常財源が4、500億不足するというふうに試算されておりますので、そこに相当する金額をつくって、減債基金を取り崩さないようにするっていうことであります。ほか質問。
政策経営局データ経営部長 安住:
いいですか喋って。すみません、補足でデータ経営部長をしております安住と申します。よろしくお願いいたします。データドリブンプロジェクトにつきましては、先ほどのプレゼンテーション資料の59ページですね、59ページにございますが、左下に今回対象としております施策につきまして、5つ、6年度議論したものを7年度予算に反映しておりまして、高齢者の支援、それから文化芸術、国際ビジネス、保育・幼児教育、子育て支援、この5つで議論してまいりました。このうちですね、7年度予算で反映している、議論した結果、予算案に反映したものについては、恐れ入りますがこの予算案の係数資料となっている資料の39ページをお開きください。39ページの資料の欄外になりますが、参考とさせていただいて、大丈夫ですかね。はい。39ページの欄外、参考となっているところの米印1でございます。施策評価、事業評価に関連する財源創出額が19億円で、このうちですね、括弧書きでございますが、データドリブンプロジェクトに関連する財源創出額は17件7億円となっております。補足説明は以上でございます。
政策経営局報道課長 矢野:
続けて。
読売新聞 田川:
ありがとうございます。では理解として確認で、市長が発案したプロジェクトっていうふうに言ってよろしいか。
市長:
この、ごめんなさい、今。
読売新聞 田川:
データドリブンで。
市長:
データドリブンプロジェクト自体はそうです。はい。
読売新聞 田川:
ありがとうございます。すみません。
市長:
どの項目を議論するかとかではなくて、DDP全体はここ数年間、私としても最重要プロジェクトとして行ってきました。
読売新聞 田川:
ありがとうございます。もう1点、全く違う観点で、子育て世代への支援を大きく打ち出しているんですけれども、今回の予算で高齢者向けの施策ですとか、事業ですとか、特に力を入れたことがありましたら教えてください。
市長:
はい。ご質問ありがとうございます。まずお一人様制度、お一人様の情報登録制度を作ってですね、今後急増するお1人様、独居老人の方への支援をつくる基礎にしたいというふうに思っております。併せて、敬老パスをより使えるようにするため、敬老パスを持続可能にしつつも、より地域格差を解消していくってことも重要な高齢者支援になろうかと思いますので、その観点から地域交通の拡充に、これは多分全国初だと思いますけど、着手いたします。はい。
読売新聞 田川:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。神奈川新聞さん。
神奈川新聞 加地:
神奈川新聞の加地です。2点お伺いします。まず人口増のスライドのところなんですが。先ほど、人口増に転じた背景として子育て施策が好感持たれているというようなお話もありましたが、転入してきた方が子育て施策を評価して入ってきたような何かデータみたいな今既にお持ちなんでしょうか。
市長:
入って来る、転入されてきた方になんで横浜に来られたのかっていうデータ、アンケートとかは基本的には取れないと思いますので、今後何らかの方法で、そういった因果関係ですよね、今加地さんおっしゃってるのは。なぜ入ってきたかっていう、もっと言えばどういったところに魅力を感じたかみたいな、そういった因果関係が取れるようになるといいんですけど、基本的には今の枠組みですとそういったデータはありません。はい。
神奈川新聞 加地:
そうなるとですね、子育て施策がうけてるっていうのはどういったところから。
市長:
20代から40代が増えている、子育て世代が増えているということに基づくスピキュレーションです。
神奈川新聞 加地:
ありがとうございます。もう1点伺います。子育て施策のところで、精神的だったり時間的なゆとりの創出と、経済的な支援を両輪で進めていくお話がありましたが、経済的支援というのは国に自治体による格差がなくなるように訴えかけていくことに留まるのか、それとも横浜市として、財源創って独自の経済的支援をこれからも打っていくっていうことなのか、どちらかお考えがあれば。
市長:
はい、両方になろうかなと思います。国としてナショナルミニマムをつくっていただきたい、いろいろな事項でナショナルミニマムをつくっていただきたいっていう思いはありますので、必要と思われることに関して、引き続き要請をしてまいります。一方で、経済的な支援も必要でありますので、経済的なゆとりを創るためにも、本市としてできることをやっていきたいというふうに思っています。
神奈川新聞 加地:
分かりました。ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょうか。朝日さん。
朝日新聞 小林:
朝日新聞の小林です。預けやすいまちの関係で、今年度初めてのお預かり券というものをやられていたかと思うんですけれども、そちらの課題みたいなものを新年度に生かされているのかなというふうに思うんですが、まず今年度やられていた事業に対する市長の受け止めと、来年度以降そちらのほうはどうなるのか。
市長:
はい、ご質問ありがとうございます。まず新生児に対してお配りをいたしました。しかしながら生まれたての頃はやはり預けることにためらいがある親御さんが多いということも分かってきました。年齢を重ねる毎に、生まれてから月日が経つ毎に、データを見てもですね、お預かり券を使って預けていただいく方が増えてきているようなんですが、やはり対象とする年代っていうものは慎重に選ばなければいけないというふうに思います。また、使える場所ですね。お預かり券を使える場所っていうものを、もう1回検討しないといけないかなというふうに思います。やはり民間の活力に頼るという意味でお預かり券を行政としてここだっていうふうにある程度狭めてしまうと、それは利用の促進の妨げになりますので、その辺りが課題だったのかなというふうに思います。
朝日新聞 小林:
次年度以降は今のところは、配布というか。
市長:
そのお預かり券ですか。お預かり券は。
政策経営局報道課長 矢野:
所管局。
こども青少年局保育・教育部長 片山:
保育・教育部長の片山です。ありがとうございます。お預かり券のほうは来年度以降も続けてまいります。伸び率、ちょっとすみません、手持ちすぐ出てこないんですが、開所時から比べると先ほど市長が申し上げたように、徐々に伸びてまして、今何倍、3倍4倍みたいな感じで伸びています。私もいくつか施設回って聞いてる中では、やはりその後ろめたさみたいなところが結構預かり使うのってあるんですけど、お金で補助も入りますのでそれをきっかけに使いやすくなったという声で、結構リフレッシュで、いわゆる気分を切り替えるということで使いやすくなったという声が結構寄せられています。
朝日新聞 小林:
そうなるとその利用状況とかもこれから見ていって、こちらの新しい施策のほうにも生かされていくという理解でよろしいでしょうか。
こども青少年局保育・教育部長 片山:
そうです。データで取れてますので、それをベースに生かしていきたいというふうに思っております。
朝日新聞 小林:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。東京新聞さん。
東京新聞 神谷:
東京新聞の神谷です。防災・減災対策のところなんですけど、資料の10ページで市長の説明でも今後5か年で960億円の計画ということで。あと18ページ、これまでの5か年で180億円と比べて増えている、特に予算規模的に一番力を入れてるとか大きなものがどういうものになるんでしょうか。具体的にどういうものになるんでしょうか。
市長:
はい。今様々なことを、個別においくらかかってるか、こちらに関してはですね、今のスライドに関しては、来年度はちょっと準備の期間とかがありますので、金額的には抑えめになっています。960億に対して、100億円近くになっておりますが、次々年度ですね、次年度以降のどういう配分になっているのかも含めて、そこに関してはちょっと細かいことなるので。
政策経営局報道課長 矢野:
所管局から。
総務局危機管理室長 稲村:
総務局危機管理室長の稲村と申します。詳細はですね、まだちょっと集計中ではあるんですけれども、伸びであるのではですね、ハード系の部分。ただこれ工事とかではなくて、設計とかが多いんだと思うんですけれども、上瀬谷地区の関連事業ですとか、あとは今回、災害備蓄ですね、こちらのほう大きく拡充していくということで舵切りをしていますので、災害対策備蓄事業ですとか、あるいは補助事業を100%に切り上げた感震ブレーカ―ですとか、家具転とかですね、こういったものが効いてきてるかなと分析しております。
東京新聞 神谷:
この18ページのがけ対策も今年度もそれなりについてるかと思うんですけど、これは具体的に緊急輸送路沿道というのは、例えばどれぐらいの総延長距離とか、結構すぐに対策しなきゃいけない場所があるんでしょうか。
総務局危機管理室長 稲村:
こちらはピンポイントで件数。何件でしたっけ。4件ですね。ちょっとあの。
東京新聞 神谷:
改めてより安全のためにやるっていう、すぐに対策が必要なほどっていう、そういう意味ではないってことですか。
市長:
分かりました。何かあったときにそこの緊急輸送路がもう遮断されてしまうので、そこに対して早く対応しなければいけないということで、今すぐにどこではないんですけども、ただがけで、今、例えば豪雨とかがあって、崩れやすくなってる可能性もありますので、そういったところに今、こことここが危ない可能性があるということが分かってますので対応したいということであります。
東京新聞 神谷:
この民間所有のっていうのは、市の所有地に対してはもう既に進めているけれどもっていう意味ですか。
市長:
民地なので、こちらとして積極的に介入できないのでっていうところで、非常に重要なポイントで、今ご指摘いただいたところは重要です。
東京新聞 神谷:
それは市道脇の民有地のがけということですね。
市長:
おっしゃるとおりです。はい。
東京新聞 神谷:
分かりました。それを、これは補助じゃなくて対策工事。
市長:
こちらそうですね、はい、市としてできることを進めて、緊急輸送路が遮断されないようにするということであります。
東京新聞 神谷:
はい。分かりました。ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょうか。その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは以上で会見終了します。ありがとうございました。
このページへのお問合せ
政策経営局シティプロモーション推進室報道課
電話:045-671-3498
電話:045-671-3498
ファクス:045-662-7362
メールアドレス:ss-hodo@city.yokohama.lg.jp
ページID:192-791-480