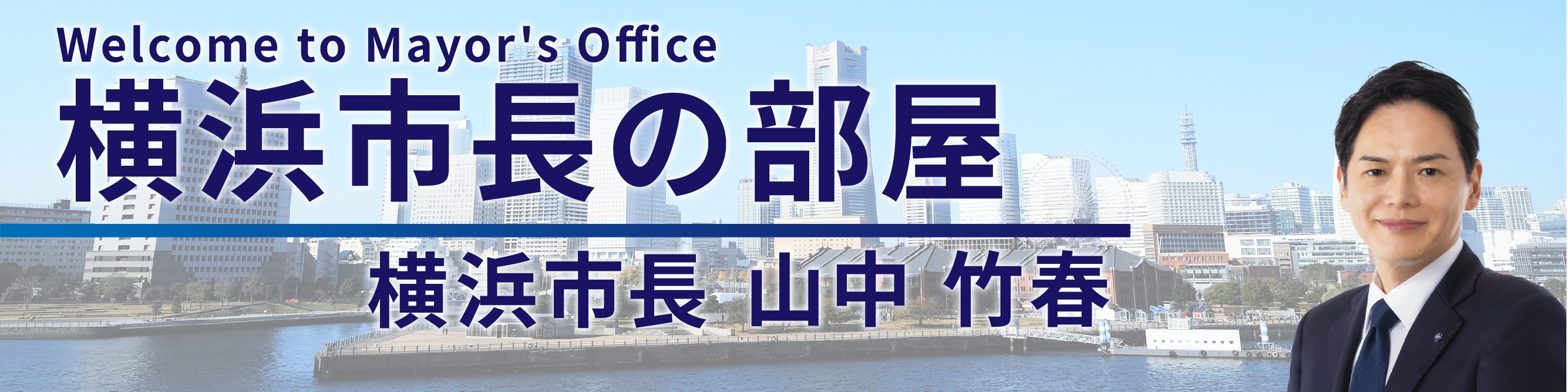ここから本文です。
- 横浜市トップページ
- 市長の部屋 横浜市長山中竹春
- 定例記者会見
- 会見記録
- 2024年度
- 市長定例記者会見(令和7年3月11日)
市長定例記者会見(令和7年3月11日)
最終更新日 2025年3月13日
令和7年3月11日(火曜日)15:00~
報告資料
- 【スライド資料】「YOKOHAMA Hack!」における交通量調査のICT化の取組について~交通量調査のICT化の実証実験結果~(PDF:5,417KB)
- 【記者発表】デジタルによる創発・共創のマッチングプラットフォーム「YOKOHAMA Hack!」「交通量調査のICT化」の実証実験を完了しました!
- 【スライド資料】『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025』との連携について(PDF:1,758KB)
- 【記者発表】『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025』との連携について
会見内容
1.報告
(1)「YOKOHAMA Hack!」における交通量調査のICT化の取組について
~交通量調査のICT化の実証実験結果~
※敬称略
政策経営局報道課長 矢野:
はい、それでは定例会見始めます。市長お願いします。
市長:
はい、報告に入る前に、一言申し上げます。本日で東日本大震災から14年となりました。改めて、犠牲となられた方々にご冥福をお祈り申し上げます。併せて、ご家族の皆様方にお悔やみを申し上げます。本市として震災の記憶を風化させずに、その経験から学び、また今後の災害対策に生かしてまいりたいと思います。それでは改めまして、報告に入らせていただきます。本日の2点、報告がございまして、1点目が交通量調査のICT化の取組についてであります。最初の1、2枚目はYOKOHAMA Hack!の話ですので、割愛させていただきます。少し背景をお話しいたしますと、交通量調査ですが、本市はですね、約2年に1回の頻度で全市的に実施をしております。目的は交通データの取得であります。課題なんですが、交通量調査、人手に頼っていますので現在、特に人手不足ということもありますし、慢性的にこの人手不足というのがありまして、なかなか人が集まりにくい。それから、煩雑かつ膨大な集計作業が必要になるっていうことが挙げられます。本市で令和5年度に行った調査ですと、こちらに書いておりますが、全部で65か所の交差点の調査に、延べ人数で362名の調査員が必要とされました。これは本市だけの事情ではなくて、全国の自治体でこうした調査が行われております。各自治体も同様な課題感を抱えているのではないかなというふうに思います。これらのニーズについて、民間企業の皆様に最新のデジタル技術を使った提案をYOKOHAMA Hack!にて提案を受け付けたところ、4社の方々から応募がありました。こちらに書いてあります、実証実験に参加していただいた企業4社であります。今回の実験の概要なのですが、このスライドが今回の発表の中でのキースライドでありますが、まず交差点にLiDARやカメラなどの観測機材を設置して、人や車の流れを撮影いたします。次に撮影した映像などのデータをAIで解析することで、交通量の調査を図るものであります。同時に、それは新しい手法による交通量調査ですので、精解と申しますか、従来型の人の目による観測も行いまして、そちらの精解として、整合性を、一致してるのかどうかっていうことを確かめるっていうのが、この実証実験の目的であります。今回の実証実験でLiDARとカメラ、それからドライブレコーダー、車に今ドラレコは標準装備されていると思いますけど、そのドラレコから得られるGPSの走行データ、この3種類の提案が4社からありましたので、それぞれについて、方向別、それから車種別の交通量の調査を行って、どれくらい精解と一致してるのかどうかっていうところを確かめたところであります。まず、LiDAR技術を用いた調査結果ですが、LiDARっていうのは特殊な機械を用いることで、無数のレーザー光を照射して、そうすると光が反射で返ってきますので、その反射光の情報をもとに対象物の位置情報を計測する技術であります。LiDARから取得した車両の位置情報をAIで解析することによって、交通量の調査を図るものであります。それからですね、それから次、カメラを用いたAIの解析技術なんですが、こちらはカメラから取得した映像データをAIで解析することで交通量を調査します。動画を貼付しましたのでご覧ください。こんな感じで調査します。撮影した動画データ内に、この走行する車両や人の動きをAIが解析している様子が分かると思います。この技術もそうですし、あとLiDARもですね、先ほどちょっと申し忘れましたが、だいたい調査精度は90%以上になっているということで、一応これは実現可能な精度が確認できたということでありました。この技術も従来の方法では得られなかった、交差点における車両の移動経路っていうものも可視化することが可能になります。今回調査した交差点では、車両の走行軌跡のデータから対向車線へのはみ出しななど、車両の異常軌跡、異常な軌跡の有無なんかも確認することができました。最後にドライブレコーダーを用いた技術なんですが、こちらはですね、三井住友海上火災保険さんから提案があったんです。それで火災保険、その保険会社と契約をしている車両のドラレコを活用するっていう提案だったんですね、会社さんから。ドライブレコーダー付き自動車保険を契約している、車両のGPS測定データから交通量を測定するっていう提案だったんですが、なかなか今の技術に対してどのくらいのサンプルサイズがあればいいのかっていうのは、技術の進歩にも依存してるんだと思います。技術が飛躍すれば、進展すれば、少ないサンプルサイズでもいけたんだろうと思いますけれども、残念ながら今回はサンプル数が精度上、十分ではなかったことから評価できなかったということになったそうです。今後の精度向上が期待されることになったので、今回は評価できなかったということであります。まとめますと、こちらがまとめであります。このようにですね、LiDARだと調査精度が95%以上、カメラですと大体90%以上、ドライブレコーダーですとまだ発展途上ということで、一応今回の実証実験の結果となりました。また、コストについてはカメラ映像のAI解析及びドライブレコーダーを用いた技術に関しては、従来の人手による調査よりも安価だったということであります。今回の実証実験では、最新のデジタル技術を用いた交通量調査手法を複数調査したわけなんですけども、検証したわけなんですけども、実証実験の結果、最新のデジタル技術を用いることで、効率化は期待できるのかなと。令和7年度、次年度から交通量調査のICT化を進めてまいります。私からの説明は以上です。
政策経営局報道課長 矢野:
はい、それではこの件についてご質問をお受けします。事業の詳細については所管局を残しますので、後ほどご確認いただければと思います。いつものお願いになりますけれども、ご発言の際はマイクのスイッチのご確認だけお願いいたします。ではまず幹事社からお願いします。
時事通信 廣野:
幹事社の時事通信です。よろしくお願いします。実証を終えての手ごたえを教えてください。
市長:
はい。こういった技術は日進月歩だというふうに思います。これまで多くの人手を要していたものが、そういった人手を省略することができるということで、大きな可能性を秘めた技術ではないかなと思います。今後こういった技術がどんどん進展して、自治体を始めですね、様々な社会で活用されることを期待しています。
時事通信 廣野:
ありがとうございます。あの7年度からICT化を進めるとのことなんですけども、導入に向けた今後の展開について教えてください。
市長:
はい。まず令和7年度は道路交通センサスと呼ばれる、全国的な交通量調査が秋頃に行われますので、この調査において活用検討しています。
時事通信 廣野:
ありがとうございます。幹事社からは以上です。
政策経営局報道課長 矢野:
それでは各社いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それではこの件の質疑は以上となります。事務局入れ替わりますので、少々お待ちください。
(2)『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025』との連携について
政策経営局報道課長 矢野:
それでは続けて市長、お願いします。
市長:
次にご報告するのはにぎわい局の取組についてであります。まずこちらは都心臨海部の音楽施設の集積で、既に記者の皆様にもお見せしているものであります。1kmないし2kmの中にかなり集積が進んでおりまして、総キャパシティが今65,000人までになっています。世界でも1、2の地区だというふうに考えております。こういった今民間のインフラが集まってきています。こういった背景が1つ。背景の2つ目は横浜市の回遊施策をこういうふうに考えてきて、こういうふうに取り組んでいきましたという話なんですが、従来ですと、コンサート会場があってコンサート会場に来てそのまま帰ってしまうっていうのが普通だと思うんですけれども、これをですね、このコンサートを行うアーティストとかいろいろなキャラクターとかあると思うんですけど。そういったいわゆるIPがかかっているものを活用して、IPコンテンツを主催者とともに作り、そして回遊をしてもらう。観光して、食事をしていただいて、街をぶらぶらしていただいて、夜も宿泊していただく。ということで、また街を面的に楽しんでもらうっていうのが回遊施策であります。こういった方策を従来から考えてきてまして、それから、様々な音楽施設が集積してきたという事情と合わせて、それから我々としてこのIPコンテンツをどんどん誘致してきたわけなんですけれども、やっぱり実績が重要になってきます。民間さんもこういったフェスティバルとかコンサートをやる上で、自治体を選ぶ。自治体はうちだけではないですので、どの自治体を選ぶかっていう観点で、実績を積んで参りました。令和5年度は6件、それから令和6年度は21件のIPコンテンツと連携をして、回遊施策の実績づくりにこれまで取り組んできた次第であります。今後ですね、今これまでの誘致実績、横浜市としてのこういった誘致実績を評価していただきまして、新しいフェスが横浜で開催されることになりまして、次のステージに進んでいきたいというふうに考えております。どういうフェスかと言いますと、CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVALという、この3日間で大体10万人ぐらいを予定されているフェスが、4月4日から4月6日まで開催していただけることになりました。主催はソニーミュージックグループを中心としたセントラル実行委員会という組織でありまして、こちらがですね、横浜を手始めに行って、今後台北やクアラルンプールで行う。そういった世界的なフェスの第1弾として横浜市を選んでいただきました。で、元々あのKアリーナと赤レンガとZeppとまあ3か所で行う予定だったんですけれども、今回この後に説明する事情から、臨港パークでの会場も加えて、計4か所で行う予定であります。こういった音楽施設が集積していること、それからこれまでの賑わい誘致の実績を評価していただいて、このCENTRALさんに横浜市を初めて選んでいただいたことっていうのがこれまでのお話です。で、これまでですね、先ほどイラストでお示しした回遊施策として、IPコンテンツを活用してコンサートや、フェスティバルに来られた方が市内を回って食べ歩きしていただいて、商品を買っていただいて、経済効果につなげるっていうことを意図していました。コンテナフォトスポットを作ったり、あるいはフォトスポットを作ったり、ライトアップをしたり、それからオリジナルステッカーキャンペーン、これ例えばですね、これかなり好評で、例えば去年なんかですと7万枚余り配れましたので、7万枚をですね、7万人か、だからそういったかなり実績がこれあるようなんですね。あわせて夜は花火を上げるとかいうこともしてまいりましたし、それから市民参加が重要ですので、多くの市民の皆様、特に小学校や中学校の方々に、中学生の方々に街中でステージやってもらうとかっていう取組もやってきました。で、こういった従来の回遊施策は今回のフェスでも行うんですけども、新たにですね、今回先ほど申し上げたように赤レンガとKアリーナとKT Zeppで行う予定だったんですが、回遊を作っていくために臨港パークを会場に加える。で、これを主催者と横浜市の共催で行って、ここ戦略的に回遊してもらう取組を今回始めたいというふうに思います。これも横浜市のこの民間の集積がですね、音楽施設の集積がやはり重要であって、そういった背景に今回のフェスティバル、フェスをですね、行うにあたり、臨港パークを会場に加えていただきました。この臨港パークで何をやるかと言いますと、Kアリーナ横浜を始めとする各会場のフェスと連携した企画を臨港パークで展開したいというふうに考えております。様々な内容につきまして、フェスの内容につきましては、今にぎわい局と主催者のほうでいろいろと詰めているところだというふうに思います。このスライドが1番重要だと思うんですけれども、重要なんですけども。これまでにぎわい局を設置しました。そして先ほどお見せした回遊施策の考え方について基づいて、来ていただいた方々に横浜を楽しんでいただいて、横浜で飲食していただいて、商品買ってもらって、経済的に効果をあげるということを目標にやってきました。そのためにまずIPコンテンツを誘致して、対民間向けの実績を作り、あわせて人流データを測るとか、消費動向を測る、宿泊動向を測る、そういった部分的にですけれども、調査分析のノウハウを積んでいきました。このIPコンテンツと連携をするのが目的ではもちろんありませんので、これを起点に、経済的にどういうふうに潤うかっていうところがやっぱり目的、重要でありますので、そのためのデータがどこの自治体、まあ自治体でこういった賑わい施策とかやってますけれども、どこの自治体もやってそれで終わりっていうのが多いと思うんですよね。そうではなくて、きちんと人流データ、消費動向、宿泊動向を測れるようにすると、で、かつ実際に回遊を面的にしてもらうための仕掛けを作るっていうことをこの2、3年間にぎわい局とともに取り組んできました。で、いろいろ人流データとか消費動向を測るっていうことも我々部分的にですけど、ノウハウを積んでいきましたので、今回面的、KT Zeppや赤レンガ、Kアリーナに加えて、臨港パークを加えて、面的に回遊してもらえるようにしましたので、これまでの測定の蓄積を踏まえて面的に定量測定をしていくことを開始したいなというふうに思っております。で、今後も検証を進めながら改善を進めながら、更なる市内経済の活性化に取り組んでまいりたいというふうに考えております。こちらに関する説明は以上です。
政策経営局報道課長 矢野:
はい、それではこの件についてご質問お受けします。まず幹事社からお願いします。
時事通信 廣野:
ご説明ありがとうございます。改めてなんですけど、民間イベントと連携する狙いを改めて教えてください。
市長:
はい。民間がいろいろノウハウを持ってきて、で、民間さんが各自治体でフェスティバルやコンサート、イベントをやって、多くのお客様に来ていただく、あるいは市民の皆様に楽しんでいただくというのは、いいことだと思うんです。ただ、あの税金を使って何かやる場合は、やはり市民に対する説明っていうものができないといけませんから、やはり突き詰めて考えた場合、賑わいを作り、経済効果をもたらすっていうところがゴールだと思うんです。で、そういった取組をこれまで準備してきたわけなんですけれども、今回、新たな次のステージに行きたいなと思って、巨大なフェスが横浜に誘致されますので、それを活用して一層エリア全体を回遊していただきながら、昼も夜も横浜を楽しんでいくイベント作りに着手して、で、その効果を測定していく、そういった取組を一層進めていきたいというふうに思ってます。
時事通信 廣野:
ありがとうございます。幹事社、以上です。
政策経営局報道課長 矢野:
それでは、各社いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、この件の質疑は終了します。事務局、入れ替わります。少々お待ちください。
2.その他
政策経営局報道課長 矢野:
それでは続いて一般質問に入ります。複数ご質問がありましたら、まとめてお願いいたします。ではまず幹事社からお願いします。
時事通信 廣野:
よろしくお願いします。GREEN×EXPOについて伺います。昨日、博覧会協会から会場建設費の増額についての要請がありました。市長の受け止めをまず教えてください。
市長:
物価高騰を理由とされておりましたが、物価高騰は協会だけでなくて、市民の皆様にも大きな影響を及ぼしていますので、引き続き、協会にはコスト削減を始めとする適切な事業管理をお願いしたいというふうに考えております。
時事通信 廣野:
ありがとうございます。昨日は要請を受けた段階だと思うんですけども、今後の展開についてのお考えを教えてください。
市長:
はい、まず今、要請の内容である物価や人件費上昇に係る算出方法、それからコストの抑制の仕方等について、協会への聞き取りによって確認をしているところであります。今後は市会にもご説明をした上で、市としての判断をしていきたいと思います。
時事通信 廣野:
分かりました。ありがとうございます。幹事社、以上です。
政策経営局報道課長 矢野:
それでは、各社いかがでしょうか。東京さん。
東京新聞 神谷:
東京新聞の神谷です。今の博覧会に関連して、今後、入場料収入で賄うとされる運営費についても、また検討が進められるということなんですけれども、入場料自体、有料入場者数を1,000万人以上っていう目標を掲げていて、実際、その人数が本当に集まるかどうか、今の大阪万博のチケット、売れ行きなんかも見ていると少し懸念もあるんですけれども、その設定とまた今後の運営費に関して見解をお願いします。
市長:
はい、運営費が決まって、そのまあ運営費に連動して、入場料金等も作られる、決まるというふうに考えています。先ほど冒頭にご指摘あった来場者数の推計につきましては、これまでの博覧会の事例に基づいて、数理的に、統計学的に算出したものであるというふうに承知しています。ですので、この1,000万人という数字は、私は横浜市としては妥当性があるものだと思っておりますので、しっかりとその来場者数が集まる、そして市民の皆様にも共感を持たれる企画内容になることを期待しております。
東京新聞 神谷:
すみません、妥当性があると思う根拠をもう少し教えてもらえますか。
市長:
過去の博覧会のデータに基づく推計であります。
東京新聞 神谷:
過去っていうのは具体的にどういったところでしょうか。
政策経営局報道課長 矢野:
所管局から。
脱炭素・GREEN×EXPO推進局担当理事 五十嵐:
GREEN×EXPO推進局の理事の五十嵐でございます。過去の博覧会、浜名湖博などの、その圏域人口などを分析した結果として算出をされたものでございます。
東京新聞 神谷:
分かりました。いろいろ時代も違うというか、状況も違うかと思うんですけれども、それの下の算出で、妥当であり、かつ集客も可能な数字だと市としては考えているということでよろしいですか。
市長:
その点は以前より、議会でも申し上げてるとおりです。
東京新聞 神谷:
分かりました。
政策経営局報道課長 矢野:
その他、いかがでしょうか。神奈川新聞さん。
神奈川新聞 武田:
神奈川新聞の武田です。今のまた関連の部分なんですけども、市長が、一応協会の副会長でもあって、横浜市のトップであり、協会側のその、役員にも名を連ねていらっしゃると。両方の立場があって難しいところだと思いますけれども。物価高騰によって100億円近く上がる。市費の負担としても26億円ですか、上がってくるという部分について、市のトップとしてのお考えと、協会のほうの副会長としてのお立場は、どういった形で役割分担してるといいますか、その、そもそもその試算を出していく中で、市長のほうもその協会の中の一員としてその試算の計算には携わってらっしゃったのか。あるいはもう昨日受けるまではあんまり携わってなかったのかっていうのは、その辺りいかがでしょうか。
市長:
はい、まず、金額については昨日お知らせいただきました。私自身としては先ほど冒頭のあの1番目の質問に答えましたとおり、市民生活にも大きな影響を及ぼしている物価高騰を理由にされていますが、苦しいのは市民の皆様ですので、しっかりと今後もコスト削減をお願いしたところであります。また、この博覧会が市民の皆様、特に地域の皆様、地元の皆様の期待が大変大きいイベントであるのは承知しておられると思いますが、今後も市民の皆様の共感を得られるような制度設計をお願いしたいというふうに思っております。
神奈川新聞 武田:
ありがとうございます。運営費の部分なんですが、あの今現状でいくと360億円で、240数億円ですか。をチケット収入で賄うっていう形で割り返すと、2,000いくらになって、平均が2,000いくらになって、一般のチケット代が試算的には3,500円って形で今示されていて、肌感として例えば5,000円よりも超えてくると、なかなか心理的ハードルが高かったりとか、いろんな、まあその感じ方あると思うんですけれども、今現在市長のお考えとして、大体どれぐらいに抑えたいとか、これぐらいでっていう、そのお考えっていうのがあれば伺えればなって思います。
市長:
いくらを高いと思うか安いと思うかっていうのは人によって違いますので、このぐらいが望ましいとかっていうのは一概に言えるものではないとは思います。運営費に関しては協会のほうで適切に算出されるというふうに思い、あっ、運営費じゃないや。チケット収入か。チケット収入に関しては、入場料に関しては今後適切に算出されるというふうに考えております。
神奈川新聞 武田:
分かりました。で、もう1点、今大阪のほうで、非常に課題となっているのがチケットの売り方。まあ向こうは並ばない万博っていう形で、完全予約制をやってたけれども、結局売れ行きがいまいちだから当日券になったっていう、ちょっと混乱してるように見えてくる状況ですけれども、横浜のほうで今例えばこういうふうにっていうものを考えてるものがあれば伺えればなと思います。
市長:
チケットをどういうふうに。
政策経営局報道課長 矢野:
所管局。
脱炭素・GREEN×EXPO推進局担当理事 五十嵐:
大阪万博の状況については、我々も承知はしているところでございますけれども、そういったことを踏まえて、協会のほうでしっかり売り方についてもご検討いただいているものだというふうに理解をしております。
神奈川新聞 武田:
市長も、もし。
市長:
はい、適切な販売方法を検討しなければいけないと思いますので、求めやすい、チケットに関しては求めやすいっていうことが大前提だと思いますので、適切な販売方法を検討していただきたいというふうに思っています。
神奈川新聞 武田:
ごめんなさい、もう1点。求めやすいっていう部分で、大阪だと今完全に電子制が最初なっていて、高齢者の方から非常に難しさがあった。で、そこら辺が求めやすさっていう部分ではなってくるかなと思いますけど、そういう辺りも、例えば紙に。
市長:
あらゆる世代に求めやすいってことが必要なのかなと思いますので、方法については今後検討されるんだと思いますけれども、適切な販売方法を望みます。
神奈川新聞 武田:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。朝日さん。
朝日新聞 良永:
朝日新聞の良永です。話題が変わるんですけれども、民間の調査で、住みたい街ランキング首都圏版で、横浜が8年連続1位を取ったということで、受け止めと、あと市長なりのなぜ選ばれたのかっていうところの推測っていうところ、教えていただければなと思います。
市長:
はい、今回8年連続で住みたい街の第1位に選ばれたことは我々どもとしても大変励みになります。特に、年代別、それからいろいろな切り口で切っても1位になっているということは大変嬉しく思っております。街自体の魅力に加えまして、子育て政策、様々な賑わいの政策、そして、公園なんかも評価していただいたようですので、そういった市の様々な政策がこういった住みたい街ランキングの1位に寄与していれば大変嬉しく思います。
朝日新聞 良永:
ありがとうございます。市の政策も寄与していればというお話だったんですけれども、今後も1位を取り続けるためには、どのような施策ですとか、市としてどうしていくべきかっていうところ、お考えがあればお願いします。
市長:
市民のニーズを第一に踏まえることだというふうに思いますね。
朝日新聞 良永:
ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。タウンニュースさん。
タウンニュース 門馬:
タウンニュースの門馬です。よろしくお願いします。先週の土曜日、指定都市市長会のシンポジウムが戸塚でありまして、その中で特別市の法制化の意義ですとか、内容を改めて市民の方に語りかけていたかと思うんですけども、今回は古川総務大臣政務官も出席されて、市長が直接問いかけるような場面もありました。あのシンポジウムを終えて、どのようなことをお感じになられたかということと、あと今までも特別市について市長自ら各区を回って、市民の方に直接説明してきたかと思うんですけども、今後特別市へ向けての機運醸成のために、どういったことが必要かということを改めてお感じになったかと、それぞれ教えください。
市長:
はい、ご質問ありがとうございます。まず今回多くの市民の皆様に参加をしていただいたことは大変ありがたいことだというふうに思いました。また今後もですね、法制化を実現して市民の選択肢を増やしていく上で、増やしていくために、いろいろな手段を使って、こういった市としてもですね、同様の機運醸成を続けていくべきだというふうに考えております。これまで地域で様々説明する機会をいただき、また今回や前回もシンポジウム等をやりまして、市民の皆様の特別市を、こういうのがあるんだというようなことを知っていただく機会はこれまでも増やしてきましたし、今後も着実に増やしていければなというふうに思っています。
タウンニュース 門馬:
はい、ありがとうございます。
政策経営局報道課長 矢野:
その他いかがでしょう。よろしいでしょうか。それでは以上で会見終了します。ありがとうございました。
このページへのお問合せ
政策経営局シティプロモーション推進室報道課
電話:045-671-3498
電話:045-671-3498
ファクス:045-662-7362
メールアドレス:ss-hodo@city.yokohama.lg.jp
ページID:791-746-659