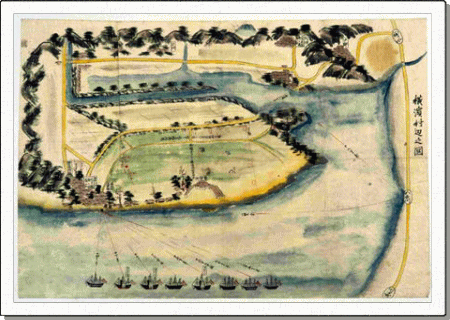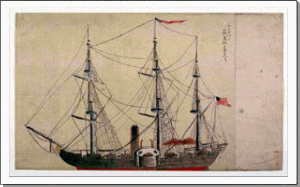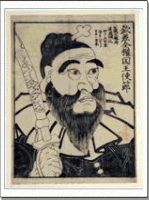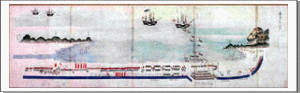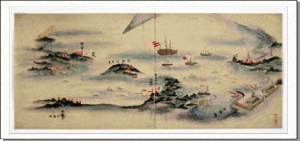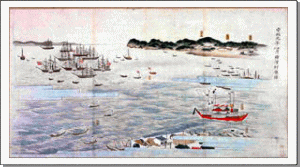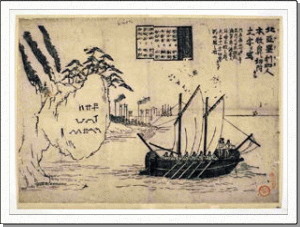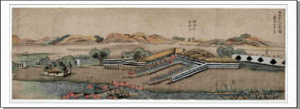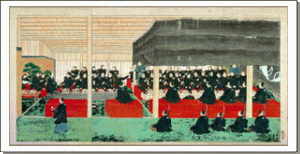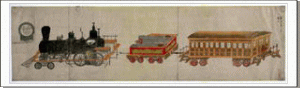ここから本文です。
横浜の歴史
最終更新日 2024年5月17日
●鎖国から開国への日々 嘉永7年、横浜村のできごと
TOP MENU 「開国」関連の画像を見る。 「開国」に関連した横浜本を読む。 嘉永7年(1854)、「開国」関連のできごとを知る。
●『横浜の歴史』(平成15年度版・中学生用)「開国」関連部分
横浜市教育委員会,2003年4月1日発行
(1)ペリーの来航
(2)国内の動揺
(3)日米和親条約
第一節 黒船の渡来
銀杏並木の美しい日本大通りと海岸通りが接する大さん橋入口近くに横浜開港資料館(旧イギリス領事館)がある。この地域は今から百数十年前、日本を世界の中に引き出させた歴史的な舞台となったところである。今、横浜村駒形とよばれた時代の姿を求めることはできない。まして、アメリカ使節の強い態度に押され、鎖国か開国かで悩んだ幕府の苦しみを知るすべはない。応接場となったこの地の近くにあった玉楠の木は、大震災のため枯れたが、若木は今もなお横浜開港資料館(外部サイト)旧館の玄関の前で茂り続けている。
(一) ペリーの来航
四隻の黒船
1853年7月8日(嘉永六年六月三日)、浦賀沖に、アメリカ東インド艦隊司令長官のペリーが率いる4隻の軍艦が現れた。浦賀奉行の早馬は「黒船現わる」の知らせをもって江戸に走った。急ぎ駆けつけた武士によって、海岸線は警備され、夜にはかがり火をたいて、黒船の動きを監視した。今までにも、外国船は姿を見せたことはあったが、今回のように艦隊を組み、砲門を開き、いつでも戦える状態で現われたことはなかった。それに加え、黒々とした蒸気船の巨体は、見る人々を圧倒してしまった。
アメリカでは19世紀にはいって工業が発達し、機械による生産が増大した。アメリカにおける産業の発達は、海外市場を求めてアジア大陸への進出を促した。しかし、アジアの中心、中国へ進出するためには、大西洋を横断し、アフリカの南端を回り、インド洋を経由しなければならず、イギリスなどと対抗するには地理的にも不利な条件であった。当時、アメリカの太平洋岸は捕鯨漁場として開かれていたこともあって、太平洋を直接横断する航路が考えられるようになった。だが、当時の船では途中で、どうしても石炭や水などの補給をしなければならなかった。太平洋岸の中継地として、日本が最良の場所であった。使節ペリーの任務は鎖国政策をとっている日本の政治を変えさせ、港を開かせることにあった。
ペリーの来航について幕府は長崎のオランダ商館長から知らされていたが鎖国政策を変えることはしなかった。実際にペリーが浦賀沖に来航しても、交渉地である長崎へ回航することを求めた。しかし、ペリーは強い態度を示し、交渉中も江戸湾の測量を行い、金沢の小柴沖まで船を進め、交渉が進展しないとみればいつでも艦隊を江戸へ直航させる構えを示して幕府の決断を迫った。
一方、幕府も戦争に備えて、急いで諸大名に対して江戸湾周辺の警備を命じた。本牧周辺を熊本藩、神奈川を平戸藩、金沢を地元の大名米倉昌寿の六浦(金沢)藩、横浜村を小倉、松代両藩がそれぞれ守りを固め、さらにその後、本牧御備場を鳥取藩、生麦・鶴見周辺を明石藩が警備することになった。このように諸大名を動員し、大規模な警備に当たったことは今までになかったことであった。
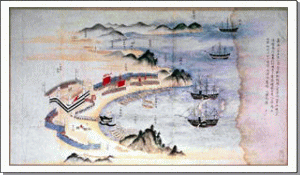
嘉永六癸丑年六月九日於相模国久里浜浦四家御固之上浦賀奉行亜墨利加国王ヨリ書簡請取ニ付異人上陸ノ図並四家御固十分一ノ写附ク近辺御台場後望見ノ図 其一
大統領の国書を受理させようとするペリーの強い態度に押された幕府は、ついに浦賀の久里浜でそれを受けることを認めた。
1853年7月14日(嘉永六年六月九日)、急いで設けられた応接所で、アメリカ大統領フィルモアの国書が、幕府の浦賀奉行に渡された。国書の内容はアメリカとの友好、貿易、石炭、食糧の補給と遭難者の保護を求めるものであった。幕府はあくまでも正式交渉地は長崎であり、浦賀は臨時の場であることを述べて、国書に関する回答はできないという態度をとった。ペリーも国書の受理が行われたことで初期の目的を達したと判断し、来年その回答を受け取りに来航することを伝えて日本を離れた。
(二)国内の動揺
広がる不安
黒船はわずか8日間の滞在であったにもかかわらず日本国内に大きな波紋を投げかけていった。諸大名は開国と攘夷との二つに分かれ、幕府はそれを統一する力さえも失っていた。
佐久間象山(松代藩家臣)は早くから横浜が防備上、地形上からすぐれた開港地であることを指摘して開国を主張し、その門下の吉田松陰は象山の勧めで停泊中の船で外国に渡ろうとして果たせず、捕えられるという事件が起こった。また、周辺の人々は、黒船の撃つ空砲の音、警戒のために鳴らす半鐘の音、あわただしい武士の動きの中で緊張の連続であった。戦争が起こるといううわさはたちまち国中に広まり、物資の買いだめ、米価の値上がりなどを招いて人々を困らせた。
その中でもいちばん苦しんだのは浦賀と東海道を結ぶ金沢道に沿った村々の人たちであり、特に保土ケ谷宿、戸塚宿の助郷になっていたため、公用の物資の運搬の仕事があった。さらに警備についている諸大名の荷物が加わり、これまでの2倍以上の負担がかけられた。そのために村では農業もできず、ついに幕府に助郷の軽減を要求した。ペリーの来航は武士たちにとっても大きな負担を与えた。平和な世が続いていたため、武士たちはあわてて武具や馬具などの購入や手入れを行うありさまであり、それらの経費がいっそう、武士たちの生活を苦しくさせていた。このような世の中の様子を町人たちは川柳や狂歌で風刺した。
(三)日米和親条約
ペリー再来
幕府が開国か鎖国かの判断が下せず苦しんでいた1854年2月13日(安政元年一月一六日)、再び七隻の艦隊を率いてペリーは来航し、江戸湾深く進み、金沢の小柴沖に停泊した。
浦賀奉行は、前回の交渉地であった浦賀沖まで回航するよう要求したが、ペリーは波が荒く、船を停泊させるには適さないことなどを理由にこれを断わった。幕府はできるだけ江戸から離れた場所で交渉しようとして浦賀、鎌倉などを提案したが、ペリーは江戸に近い場所を要求して、話し合いはまとまらなかった。ペリーは艦隊をさらに進ませ、神奈川沖や羽田沖まで移動させた。江戸の近くから黒船が見えるほど接近させたことに幕府は驚き、急いで神奈川宿の対岸、横浜村の地を提案し、妥協を図った。ペリーも、江戸に近く、陸地も広く、安全で便利な場所であることなど、満足できるところであることを認めて、この地を承認し艦隊を神奈川沖に移した。
交渉場所の話し合いが行われているときでも艦隊は神奈川沖を中心に測量を行い、海図の作成の仕事を進めていた。測量を行うボートの一隻が、本牧八王子海岸の崖(本牧市民プール付近)に接近し、白ペンキで文字を書きつけていった。このことがのちに江戸の「かわら版」に大事件として図解入りで報道された。そのため、横浜に多数の見物人が押しかけてきた。奉行は見物の禁止とともに、そのいたずら書きを消してしまった。外国人の一つ一つの行動がすべて興味と好奇心で見られていたのである。
当時の横浜は戸部、野毛浦と入り海をはさんで向かい合い、外海に面した地形で景色のすぐれた所であった。
応接地として決定された2月25日、アダムズ参謀長ほか三十名のアメリカ人がこの地を調査するために上陸した。畑地や海岸の様子を検分し、奉行の立ち合いの上で横浜村の北端、駒形という地(県庁付近)を応接地とし、確認のための杭を打ち込んだ。横浜の地に外国人が上陸した最初でもあった。
外国人の上陸を知った人々の驚きは大きかった。外国との戦争は横浜からだ、といううわさが流れた。それに加え、応接地決定の3日前がアメリカのワシントン記念日に当たっていたため、七隻の軍艦から100発以上の祝砲が撃たれた。そのごう音は江戸湾にこだまし、遠く房総の村々にまで聞こえ、事前に奉行から触書が回されていたけれども、人々に恐怖心を与えた。
応接地が決定されると、日本側も、アメリカ側も、その準備や調査のために横浜に上陸して活動を始めた。奉行も外国人との摩擦を避けるために外出禁止令を出したが、村人の生活は畑仕事や貝類の採取、漁業であったため、自然に外に出ることが多くなった。村人に対して奉行所からは外国人から物をもらってはならないという命令が出され、巡回する役人はアメリカ側が村人と仲良くするために菓子などを入れたかごを置いてあるのを見つけては焼き捨てたりしていた。やがて、外国人が危害を加えないことがわかると少しずつ恐ろしさが消え、珍しいもの見たさに人々が押しかけてくるようになった。増徳院という横浜村の寺で外国人の葬儀が行われたときは、見物人で道の両側に人垣ができたほどであった。
横浜応接所は久里浜に設けられた設備を解体し、横浜に運んで4日間で完成させたもので5棟からなるこの応接所をアメリカ側は条約館と呼んだ。
1854年3月4日(安政元年二月六日)、ペリーが再来した日から21日目に第1回の会見が行われた。日本側の全権は神奈川宿から船で到着し、アメリカ使節ペリーと兵士500名は祝砲のとどろく中を音楽隊を先頭に上陸した。会談は前回の国書の回答から始められ、4回の会談で条約の交渉は妥結し、3月31日(三月三日)に調印が行われた。これが横浜で結ばれた日米和親条約であり、一般には神奈川条約ともいわれた。
幕府は、国書に示されていた石炭、薪、水、食糧の補給、避難港の開港、遭難民の救助と人道的な取扱いについては認めたが通商に関しては認めなかった。それに関してはペリーも強く要求はしなかったが、代わりにアメリカの代表として総領事を置くことを認めさせた。条約交渉の最大の問題はどこを開港するかにあった。幕府は長崎一港を主張し、アメリカ側は長崎以外の港を要求した。交渉の結果、北海道の函館、伊豆半島の南端にある下田の2港を開くことで妥結した。幕府は、江戸から遠く離れ、しかも管理しやすい場所で日本人との接触が少ない所を選んだのである。
これで日本が長い間続けてきた鎖国政策はくずれ、世界の中に組み入れられ、新しい時代を迎えるようになったのである。
条約交渉が行われている際、ペリーはアメリカからの贈呈品としてたくさんの品を幕府側に贈った。武器、電信機、望遠鏡、柱時計、蒸気車模型一式、書籍、地図類であった。なかでも電信機と蒸気車は応接所付近に準備され、それぞれ実験をし、動かし方の指導が行われた。特に蒸気車は模型とはいいながら精巧に作られており、6歳程度の子どもを乗せて走るほどのものであった。蒸気車、炭水車、客車の3両は円形に敷かれたレールの上を人を乗せて蒸気の力で走った。この近代科学の成果は日本人にどれほどの驚きを与えたか、想像以上のものであった。
日本側はそれに対して力士を呼んで、外国人に負けないくらいの力の強い大男がいることを示し、幕府からはアメリカ大統領らに日本の伝統を誇る絹織物、陶器、塗り物などを贈った。
使節としての責任を果たしたペリーは、仕事を離れて数名の部下を連れて横浜村周辺を散策した。横浜村の名主、石川徳右衛門宅を訪れて家族の暖かい接待を受けたり、村人とも親しく交わり帰船した。4月15日(三月一八日)、およそ3か月の滞在を終えてペリーは神奈川沖を出帆して、開港される下田に向かった。
このページへのお問合せ
教育委員会事務局中央図書館調査資料課
電話:045-262-7336
電話:045-262-7336
ファクス:045-262-0054
ページID:695-574-472