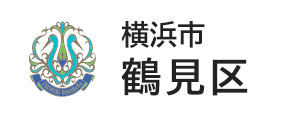ここから本文です。
第22回:鶴見が丘今昔 見返し坂
最終更新日 2024年7月9日
明治5年11月、「鶴見村の富士山の見えるところへ案内してほしい」と鶴見村名主佐久間権蔵の事務所に1人の官人が訪ねてきた。どういう人物か不明であったが、横柄なその言葉に恐れをなして、事務所にいた書記の黒川荘三が鶴見駅停車場の西側の丘陵に案内した。成願寺の墓地があったお墓山坂の中腹に至ったとき、神奈川方面から汽車の響きが聞こえてきた。官人は後ろを振り向き、汽車が鶴見駅に停車するのを見て、「ああ、この坂は汽車を見返し坂だ」と言った。お墓山の頂上や東寺尾村方面も歩いて富士山の眺められるところでは、何度も富士の雄姿を眺め、帰り道では農業のことなどを黒川荘三に尋ねた。駅に帰り着くと、縦4寸、横1寸ぐらいの奉書紙にしたためた自筆の名刺を差し出した。受け取ると、「陸軍少輔西郷従道」とあったので、いかなる人物であるかを納得した。神奈川方面から汽車が来るという知らせに、自分で切符を買い求め、改札をして線路を踏み切りホームへ登り、腰をかけるところもなく雨覆いもないホームで野立ちのまま汽車を待ち、汽車が来たので乗車された。
黒川荘三は後日佐久間権蔵と相談して、誰もが嫌がっている「お墓山坂」を西郷公が言われた「見返し坂」と命名することにし、当時の村役人にも相談したところ、大いに賛同された。しかし、呼びなれた名前を変えるということはなかなか難しいもので、村内にも通告したが、お墓山坂の旧名をとなえるものが多かった。富士山を眺めた西郷従道公は、後年東京府下荏原郡麻布広尾の新富士という丘陵を所有されて住まわれたという。西郷従道公から受け取った名刺は黒川荘三が大事にしていたが、明治43年3月31日の鶴見大火の折に類焼してしまった。
以上のようなことが、黒川荘三著の『千草』には書いてある。黒川荘三はこの由緒ある見返し坂の起源を末永く伝えることを願って、大正13年10月17日に友人の吉川兼二郎とコンクリート製の「見返し坂の碑を建てた。碑は成願寺山門の向かい側にあった吉川家の前に建てられたが、兼次郎の子孫にあたる方が昭和39年にこの地を住友生命に譲売却し、北寺尾に移転されたため、碑は鶴見・獅子ケ谷道路のバス通りから總持寺に登る坂の入口に移された。現在黒川荘三と吉川兼二郎によって建てられたコンクリート製の碑は破損したため、立派な黒御影石の碑に再建された。
旧碑の残片は新碑の後ろにひっそりとたたずんでいる旧碑の正面には「西ミ可へし坂東見返し坂」。右面には、「中坂天王院坂・□□坂・大池・熊野神社・稲荷山・諏訪坂・鎧池・民衆花壇・二本木不動・白幡神社・松蔭寺・里美義高入道墓・建功寺・仏寿禅師之墓」。左面には、「新旧国道・鶴見停車場・成願寺・子生観音・花月園・八幡山・花香園・鶴見神社・鶴見總持寺・手枕坂・安養寺・三笠園・滝坂不動・□□□・潮見橋・杉山神社・正泉寺・慶岸寺」と、当時の名勝・旧跡が記されていた。背面に刻された和歌と俳句については、鶴見歴史の会の前身である寺尾郷土史会で、郷土史研究の先鞭をつけられた故持丸輔夫氏は、「和か草も山の終葉丹飛(ついばにひ)しがれて丑(う)しと東も見かへしの坂」「東西の志るべ石あり葛乃中」と解釈され、「和歌は黒川鶴園(荘三)、句は兼本(兼次郎)であろう」と書いておられる。一方、鶴見歴史の会の初代会長大熊司氏は、「和か草も山の紅葉になりにけり西も東も見かへしの坂・鶴園」「東雲の志るべ石あり葛の花・兼本」と解釈されている。持丸氏が調査された段階(昭和40年代から50年代か)では、碑はほぼ完全な形で残されていたようだ。持丸氏が書き残されたノートに完全な形の碑の写真(コピー)も添付されている。大熊氏が解読した時点ではビル建設工事や道路整備などによって碑は破損して、その一部を残すのみとなっていたためか、持丸氏が確認している「花香園・民衆花壇・建功寺・仏寿禅師之墓」などはない。黒川荘三が書き残した『千草』の「見返し坂起源」の項には、「うららけきあきの朝日の登るらむ―くすのうら葉を見かへしの坂・鶴園」と記されている。

昔の鶴見駅

山神塔
見返し坂の碑のそばに大きな「山神塔」の碑がある。碑の背面には、「大正9年10月に鶴見耕作地組合が起工した、鶴見・御子ケ谷線の道路工事の最大難所であるお墓山の開削工事は、大雨や大風に見舞われながら十有八ケ月もかかった、県下まれにみる大工事であった。しかし、諸神の加護により1人の死者も出さなかった。この恩を永遠に忘れないために山神の加護への感謝とお墓山の供養のために山神塔が建てられた」ということが記されている。
「山神塔」は鶴見耕地整理組合によって建てられたもので、組合長は平沢権次郎、副長は佐久間権蔵、評議員には中西重蔵や持丸兵輔など当時の鶴見の有力者が名を連ねている。「山神塔」の題字を書き、最末尾に名を連ねる天野吉治は、大正児童遊園地花月園を開いた平岡広高の招きで鶴見にきた土木技師である。花月園の設備工事を請け負っていた縁で、お墓山の道路開削や鶴見駅西口から花月園への道路工事なども任されていた人物である。なお、この天野吉治の長男芳太郎は、花月園名物の子育てまんじゅうや天野式ポンプなどで財を成し、南米に渡って事業を起こすかたわらインカ文明の発掘調査をし、ペルーに天野博物館をつくった人物である。
志を砲いて1929年に南米に渡り、パナマに天野商会を開き、日本で大流行したパナマ帽などを日本に輸出したり、日本の浮世絵や絵葉書や陶磁器などを扱い成功し、百貨店へと拡大させ、チリで農場を開いたりするかたわら、古代インカ文明の発掘調査をつづけ、1964年に収集した史料を展示するために天野博物館も建てた。
芳太郎も秋田の工業学校を卒業した技術者で、南米に渡ってから、近代的装備を搭載した豪華マグロ漁船天野丸を自ら設計し、巨大な利益をあげるなど、ロマンと才覚にあふれた魅力的な人物であった。見返し坂の碑のいわれをひもといていると、遠い昔の鶴見の風景と、その風景を伝えようとした人々や鶴見で夢を紡いだ人々の姿が去来する。
大正9年には鶴見・御子ヶ谷道路も開削されて、道が東西に続き、近隣の村々との往来も便利になった。そんな喜びの気持ちもこめて、黒川荘三と吉川兼次郎は見返し坂の碑を建てたものと思われる。この碑が建てられた大正13年ごろ、見返し坂界隈には葛の葉が生い茂っていたにちがいない。当時の風景を呼び覚ますかのように、總持寺北側斜面の土手には今でも葛の葉が繁茂している。そして、見返し坂と山神塔のある場所から總持寺に通じる小さな坂は、黒川荘三が西郷従道を案内したときの情景を想わせる、踏みしだかれた落ち葉が足にやさしい小道である。
※西郷従道(1843-1902)
軍人・政治家。海軍大臣・内務大臣などを歴任。海軍大将・元帥、公爵・元老。兄は西郷隆盛
このページへのお問合せ
ページID:965-309-121