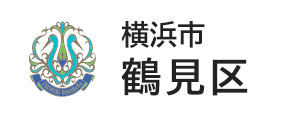ここから本文です。
第16回:三ツ池の歌碑
最終更新日 2024年7月9日

三ツ池の碑
鶴見の県立三ツ池公園北側の下の湖畔に一基の歌碑がある「千町田に引くともつきじ君が代の惠みもふかき三ツ池の水・藤原増のぶ(ふじわらますのぶ)」。三ツ池がまだ灌漑用水の溜池だった昔、水の恵みついて歌った作であろう。作者の藤原増のぶ(ふじわらますのぶ)については、その伝を詳らかにしない。裏面に「天保十四年(1843)癸卯春三月、上末吉村」の人々によって建てられたことが知られる。傍らに万葉仮名の草書体を解読した案内板がある。
上末吉村は古くは一村であったが、江戸時代の承応(1652~1654)から元禄(1688~1703)の間で上と下の二村に分かれたと伝えている。この三ツ池も上末吉村のうちで、代官が支配する天領であった。江戸日本橋から行程六里(二四キロ)西南は山つづき、東北は平地で田畑相半ばしていた。村の東北を鶴見川が流れた。鶴見川の流路の勾配がゆるく。川水を引くと、満潮時海水が逆流する恐れがあった。このため下流の村々では溜井を設けて田畑を灌漑した。

県立三ツ池公園
「武蔵風土記稿」上末吉村の条に「溜井村の西駒岡村ノ境ニアリ、広サ五尺(五丁)余コノ水ヲ引キテ所々ニ沃グ、是モ公ヨリ修造セラル」とある。この溜井は、灌漑用水だった昔の三ツ池を指したものだろう。
天保四年(1833)から七年にかけて関東地方一帯は、甚だしい凶作がつづき農民の苦悩はその極に達した。それから七年後の天保一四年になってようやく苦境を脱した上末吉村では、農民たちによって記念すべきこの歌碑が建てられた。三ツ池の水がいかに恵の水であったか、この歌碑は伝えている。
鶴見歴史の会/大熊司
鶴見区文化協会「鶴翔」より
※フォントがないため、
![]()
を、藤原増のぶ(ふじわらますのぶ)と表示しています。
このページへのお問合せ
ページID:166-590-224