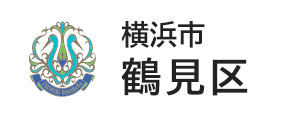ここから本文です。
第15回:鶴見地名考
最終更新日 2024年7月9日

鶴見駅周辺航空写真
私たちのまち「鶴見区」の地名の起源については諸説がある。鶴見区の都市形成には、鶴見川の恵み、水の利、舟の便の関係を切りはなしては考えられない。臨海部の埋立てによる発展もさることながら、鶴見川という恩恵があったればこその鶴見区といえるのではないだろうか。「つるみ」という地名の起源についての考察は近年になって行われたもので、その地名起源についての伝承もあまり多くはない。
幸いここに、二人の先輩の地名考があるので紹介させていただく。
椎橋好氏は、「鶴見」の地名は鶴見川によって生まれたことぐらいはすぐに分ることであろう。ツルという意味は川が海に入るために流れがヨドム状態を現わしていると思われる。というのは熊野(和歌山県)や北上川(岩手県)のトロ(瀞)と同じく、滝に落ちようとして、しばらくただよった静かな水の流れの関係だと思われる。山梨県の富士山麓の河口湖を水源とする桂川に沿う地方は、上流を南都留郡、下流を北都留郡と称しているが、ツルのような水流は猿橋附近にあり、ここを中心にこのような地名の語源になったのであろう。このような川に沿う村里は、いずれも急流の地より流れのゆるやかな地域にのみ人家が集まり、これによって部落が形成されているのが特色である。
能村潔氏の記述されたものには、「地名というものは、大抵の場合取つてつけたような口碑、伝説のたぐいに支よられて存在する。もっとも、こうした現象は、なにも一方にはじまったことではなく、日本最古の地誌ともいうべき、風土記をはじめ、その他いたるところに一種の“型”ができたというのも、そのもとをただせば、巡遊令人郡(楽器を弾く人)のその場その場の座興から発したことだったかもしれず、あながち『続日本記』に見よている和銅年間の制令「地名にはよいものを選べ」という政治的なわくから、にわかに発したものがあるように思われる。いずれにしても、このような「系諸」に、見せかけだけの新しさをこじつけようとしたゆがみが、地名の上ではそれが共有のほこりでもあったせいもあってか、常にお伽話めいた合理化を平気でやってきた。たとえば鶴見だが、江戸時代には「鶴の群が見られたので、その名をえた」と信じている向きもあるらしい。それもその一つだ。はたしてそのとおりならば「鶴代(つるしろ)」とこそ言うべきであって、「鶴見」と言ったのでは的がはずれている。といった感じがつきまとつてくる。
もっとも「鳥見」という役が、江戸にあったことはあった。しかし、これは、「鳥の監視哨」を意味していたものだから、そういうものから地名への転化は考えられぬ。また、結局はあて字に過ぎないのだが『記』『紀』に見られる「鳥見」は「外山」てあって、その背後に大きな山をもつ「前山」のことであり、古代では、そこが神をまつる所にあてられたことが多かった。
なるほど、鶴見付近一帯斜丘式の起伏がないこともないので、「とみ」または「とび」と呼んだ「外山」への連想が、一応江戸時代の地名説話の残像の上にかぶさりそうだが、言い切ってしまわないほうがよいかもしれない。
やはり飛躍し過ぎて、根拠がない。同じ地形からいうなら「とろ(瀞)み(水曜日)」から「つるみ」への変化がむしろいっそう自然でもあり、妥当であろう。その方が、地形そのものとも当てはまるからだ。
すなわち、鶴見川が大きくわん曲して、ぐっと水の流れがゆるやかになっている、ちようど「長瀞」や「瀞八丁」などの名を負う水勢に似た趣をもっているところから「とろみ」「つるみ」という民衆共感の名をかちえたのだと考えるべきだろう。
もっとも、あの煤煙に濁ったかつての工場地区が、そのはかない追憶として、昨日の背に消えた鶴のいる清浄な世界をもつことは、その当否は別として、ロマンチックな美しい詠嘆の世界を、この土地に住む人たちの上に限りなく展開してくれる。
そういう人たちのためには、鶴の羽音の幻覚が「鶴見」というこの地名が、古文書の中に現われはじめたのは、いったいいつの年代頃からであろうか、それを探ってみることとしよう。
今からおよそ九百年以前の永保年間に、鎌倉鶴ケ岡八幡宮の送進の検納に関する文書に現われはじめたもののようである。おもうに、当時この「鶴見」は鎌倉鶴ケ岡八幡宮の社領であったのであろう。中世に入って鎌倉時代以後の文献には随所に「鶴見」の地名が見られる。元弘年間(700年前)の『梅松論』によれば、同年の争乱を載せた、その中の元弘三年五月十五日の条に、「新田義貞兵を挙げ鎌倉攻めに武蔵国に駒を進めたおり、武蔵の鶴見の辺において相戦い打負けて引退く……云々」とあるが、これは上州の新田郡の豪族、新田義貞が鎌倉の北条高時を討つために、北関東の同志を率いて武蔵の国府(今の府中)に進軍し、待ちかまえていた北条軍と分倍河原で戦った。この時新田軍の背後を突くため鎌倉・神奈川・鶴見宿までやって来た北条方の別軍は、上総から大井・平間宿(川崎市)まで来た、新田方の援軍、千葉貞胤の軍と末吉(鶴見区)、小倉(川崎市)の辺で終日死斗を続けたのであるが、これが「鶴見の戦」といわれ、結局は新田軍が勝を収めたのである。その他に『吾妻鏡』の仁治二年(1242)年十一月四日の条に「秋田城介義景武蔵国鶴見別荘……云々」とあり、これにも鶴見の名が現れている。
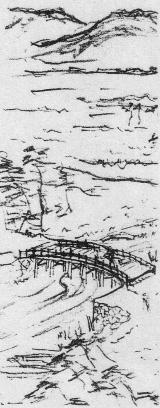
鶴見橋
これは広大な鶴見の沼沢地に目をつけ、まず大江広元以下の幹部を海月郡(久良肢)の鶴見郷や州名郷の居館を開発事業の本部に決めた記載の中にある。建武の佐竹家文書によると建武三年(1334)九月二十八日の条に「佐竹五郎義直鶴見の合戦に……云々」と討死した旨記載がある。また正平〈1636〉には「鶴見に参じ……云々」と記されている。この鶴見は御鷹頭の戸田五助、内山七兵衛などの出張区域であり、また御鷹の捉飼場と定められたこともあった。こうしたことから考えても、当時この鶴見は葦の茂っていた沼地と耕地であったことも想像にむずかしくはない。正保(1645)の頃、奥州平の城主であった内藤風虎が、鎌倉に赴く途中、この鶴見にさしかかり狩場にや鶴みて鷹の大心の句を詠んでいるが、これによっても当時の鶴見を物語る資料ともなるであろう。
徳川時代の鶴見は、東海道筋の宿駅の川崎宿と神奈川宿との間に位置した街道沿いの村で、ここは神奈川奉行のお預かりの天領であったのである。代官小林藤之助は、明治元年までここを支配していた。徳川家康が江戸入国の折、美しいいでたちでこの橋にかかると、両岸の耕地には美しい日を浴びて、おびただしい数の鶴である。しかも我が世の幸いを祝うかの如く、このめでたい吉兆に我れ知らずうちに大いに喜び、行列を控えさせて、しばし、この風情に見入るのであった。橋の名を問えば、釣海村の釣海橋と答える。それではこれからは、音同じくして字を変えよとあって、「鶴見」の文字が村にも橋にもつけられるようになった。こういう話なのである。文政七年(1824)、小笠原長保の『甲申旅日記』を見ると、鶴見村の鶴見橋を渡る。長さ二十六間といい、右の方ははるかに田の面を越えて山々が連なり、左は青海原が続き、大変景色がよい。先年詠んだ歌である。「山人ののりて渡少し鶴見橋千年もあかぬ四方の色かな」-鶴見は横浜市に編入せられて、鶴の名の昔がたりのみになろうとしているが、以前は静かな土地として、往来の人を遠い歴史に引込んだものであった。今はこの地に二つの鶴見橋が出現した。一つは国道十五号線に架せられた鉄筋コンクリート大橋、一つは旧東海道上の木橋に変るコンクリート橋、これこそ昔ながらの鶴見橋なのである。文久二年(1862)この橋詰に見張り番所が置かれた。名物「米(ヨネ)まんじゆう」というのがあるが、昔この橋のたもとで売っていたのが元祖というのである。
郷土つるみ創刊号/伊藤実「地名考・鶴見について」より
このページへのお問合せ
ページID:188-756-470