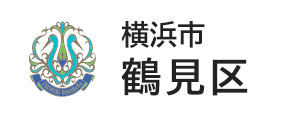ここから本文です。
第18回:常倫寺の久志本氏夫妻の像
最終更新日 2024年7月9日

常倫寺
乳母銀否の伝説で知られる駒岡の常倫寺は、天文11年(1541)涼月安清居士を元祖開基とする曹洞宗の古刹である。
永禄年間獅子ケ谷村の地頭小田切土佐守により堂宇の修復普請が行われ、瑞雲山吉祥院と号した。その後、宝永3年(1706)12月当村を久志本左京亮常勝が領して、吉祥院を常倫寺と改め、久志本氏菩提所とし、常勝亡父常倫居士をもって当寺中興の開基とした。
この常倫寺本堂内陣の奥に久志本家代々の位碑堂があり、その中央に金色の燦然とした阿弥陀如来像が祀られている。その左右に、それぞれ厨子に納められた久志本左京亮常勝夫妻の像がある。常勝の像は神官風に衣冠束帯をしたもので、いたって簡素な姿にみられる。厨子の内扉に「享保四己亥年七月二十五日、聴流堂知泉前左京亮度会常勝」と記され、像背には「徒五位下左京亮度会常勝公七十三歳卒」とある。夫人の齢昌院の像は法体に袈裟をつけた齢六十歳前後とみられ、ふくよかな顔に品位が備わり、美貌の女性であったことが知られる。厨子の内側に享保七壬寅八月五日、齢昌院殿秋光貞圓大姉」とある。齢昌院は夫常勝が死去すると直ちに髪を剃りおろして仏門に入り秋光貞圓と号した。よほどの篤信者であったことがうかがわれる。

久志本氏夫妻
廟所の常勝の石塔に「従五位下左京亮常勝神儀」とあるので、常勝の祖先以来伊勢神宮の神官度会氏を称していたことから神葬としたものであろう。常勝は万治3年(1660)家督をつぎ、貞享3年(1686)常憲院(将軍網吉)の御側医師を仰せつけられ、従五位下左官亮に叙任、以後たびたびの加増によりすべて2千石を知行した。

旗本久志本家歴代の墓所
享保5年(1720)7月常勝居士の一周忌にあたり、施主齢昌院より廟所にいたる照光坂の途中に新規井戸の造成の指示があり、このため7月5日より掘りはじめ同月24日にいたって成就した。この井戸掘の費用は齢昌院からの寄附によって賄われたので、井戸を「齢昌水」と名づけたという。
照光山上の廟所に、久志本氏最後の領主の墓が歴代の墓碑の末尾に連なって建っている。「盛廣院殿度会常懐居士、明治三十人年八月三十日、俗名久志本常懐」とあり、右側面に「旭村駒岡有志者建之」と旧領民による建立の旨を記している。明治維新によって食禄を失った旗本領主の運命には概して苛酷なものがあったようだが、こうした状況のなかで、旧領民たちによってかつての領主の遺徳を偲び墓塔が建てられたことに驚きと、その敬愛の情の深さを読みとることができる。
そう思うと、薄暗い本堂の内陣裏の位牌堂におかれた久志本氏夫妻のわびしげな像にも一条の光がさしたような気がした。
鶴見歴史の会相談役/大熊司
鶴見区文化協会「鶴翔」から
このページへのお問合せ
ページID:983-168-248