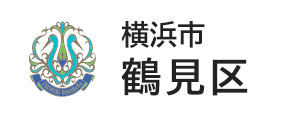ここから本文です。
第12回:菅沢町小史(その2)
最終更新日 2024年7月9日
江戸時代の暮らし
東海道の整備と助郷の苦しみ
天正18年(1590年)7月、この地方を支配していた北條氏が豊臣秀吉に滅ぼされた。関東八州を与えられた徳川家康は同年8月1日には江戸城へ入り、関東地方を支配した。慶長5年(1600年)の関ヶ原の勝戦後、家康は慶長8年(1603年)に江戸に幕府を開くと、全国支配の必要から主要な街道の整備をすすめ、以前はもっと山寄りにあった東海道を海寄りの道筋に決め、諸大名に命じて整備させた。
菅沢村は直接東海道の道筋にはあたらなかったが、街道の宿場に、人足、馬を常備し、大名行列が通るときには、彼らの大荷物を宿場から宿場へ運ぶ伝馬制による助郷役の制度で大きな影響を受けた。鶴見区域では市場村、矢向村、潮田村、菅沢村、江ケ崎村の5ヶ村が川崎宿の助郷役を課せられた。日当は支払われたが、お上からは出ず、結局村の負担になった。助郷役に参加したからといって年貢が免除になったわけではなく、また農繁期だからといって出ないわけにも行かず大変な負担となって村は疲弊した。
二ヶ領用水の恩恵
菅沢村をはじめ、潮田村、市場村、矢向村、江ケ崎村の鶴見川左岸の各村は、鶴見川に面しているが、鶴見川は上げ潮になると潮水が上がり灌漑用水には使えなかった。また多摩川下流と鶴見川下流との間(現在の川崎市の平地の大部分と鶴見区矢向、江ケ崎、市場地区)は多摩川の流れが何回か変わったので荒地、砂れきの河原が多く、農業の生産力は低かった。
家康は江戸に入って以来関東の経営上、街道の整備、水防上の理由による利根川の付け替え、水路の整備等を行って来たが、多摩川の沿岸が荒れているのに着目、ここに灌漑用水をひいて米の増産を計画した。家康の命を受けた小泉次大夫は慶長2年(1597年)に測量を開始、慶長4年から本格的に堀割り工事にかかり、慶長16年(1611年)に全ての工事が終わった。川崎領、稲毛領二つの領を潤すので二ヶ領用水と呼ばれている。二ヶ領用水の取り入れ口は多摩川の宿河原で、最初は太い流れから枝分かれし、最後は毛細血管のごとく各村々の田んぼを潤した。
菅沢村もこの用水の恩恵を受けた。菅沢村は流れの末端で3本の流れが鶴見川に注いでいた。昭和に入ってからはドブ川になってしまったが、多摩川の宿河原から取った水なので水質はよく、飲み水や洗い物などにも使われたという。
二ヶ領用水完成20年後に山王社(大山祇神社)が創建され、宝泉寺にある庚申塔が建立されている。これは二ヶ領用水によって、村の田んぼの生産力が上がり、人々の暮らしにゆとりが出たためとも考えられる。
海に面していた菅沢村
『新編武蔵風土記稿』の菅沢村の項に、「芽野・・・・・、芝原・・・・・、イツレモ海邊ニアリ」と明記されており、菅沢村は海に面していた、あるいは海に面していた土地を持っていたことがわかる。『鶴見区史』には、菅沢村は「江戸期はもちろん、近代に入ってもノリ生産に加わって磯付海辺村の姿をとどめる」と記されている。江戸時代、海の漁業権などは非常に厳しく、生麦村のように漁業を専業に行うことを許可された村落を「浦」、それ以外の海岸に面していた村を「磯付海辺村」といった。磯付海辺村は生麦浦の漁師のように自由に漁をすることはできないが械が立つまで(3尺まで)は漁場として小魚、貝類、藻などを捕ることが認められていた。菅沢村は神奈川あたりから大森村など18ヶ村の磯付海辺村の組合に入っていた磯付海辺村だった。
海に面していた土地はわずか1町歩余り(約1万m2=1ha)であるが、菅沢村はこの土地のおかげで磯付海辺村の権利を持ち、海で小魚、貝類、藻草を捕る権利を得た。そして明治に入って海苔の養殖を始めて大きな収入を得ることになった。現在この土地と思われるところは大工場が立ち並び、高速道路、産業道路上を自動車が走り、かつての面影は全くない。

図1:正保年中改定圖

図2:海浜に面していた江戸時代の菅沢村
(各種資料より推定図)
過去の大きな災害
天保の飢饉
江戸時代には「おおよそ30年の小飢、50年の大飢」といわれるように、周期的に飢饉に見舞われていた。特に享保、天明、天保の三大飢饉は被害が大きかったといわれている。中でもこの地方では天保の飢饉で大きな苦しみを受けた。天保4年(1833年)から天保10年(1839年)までの7年間、天候不順、台風などにより農作物は大きな被害を受けた。天保7年には長雨、低温、大風雨により大凶作となり、人口163人の菅沢村では101人の飢人を出した。高持百姓(裕福な大百姓)、役所、その他から援助を受け最低限生きている程度の米1日1~2合の支給を受けて生き延びた。この地方は幕府の直轄領でもあり、東海道の道筋でもあったので、東北地方のように何万人もの死者を出すということはなく、ひどい苦しみを受けたが直接飢餓のため餓死した人はいなかったといわれている。(『川崎史話中巻』)
風水害
江戸時代の記録を調べてみるとこの地方は10年に1回位の割合で大きな風水害を受けている。風水害には大きく分けて二つあり、一つは6月から7月の梅雨時期における長雨、および台風の大雨による鶴見川、多摩川の氾濫、浸水である。旧多摩川の川筋を通ってくる多摩川の水と鶴見川からの浸水とが合流して上流側から大洪水が押し寄せて大きな被害をもたらした。また鶴見川においては右岸(鶴見、生麦村)と左岸(矢向、市場、菅沢村)との間に堤防の高さ、その他について長い間利害の対立があり、抗争が続き、しばしばお上(幕府評定所)へ訴訟を起こし、天保13年(1843年)には鶴見村の名主が牢に入れられるという事件を起こしている。
もう一つの風水害は台風による強風と高潮である。昔は菅沢と潮田との間は一面の田んぼであり、風を遮るものがなかったことと、また海岸には堤防があったが、海岸の砂を盛り上げ、丸太の杭などで補強し、萱などを植えた程度のものであったため、台風の度に押し寄せる波浪にはひとたまりもなく崩れてしまい、南風が吹いた場合は海水が押し寄せ高潮となり、一面の海となって大きな被害をもたらしたことが記録に残っている。
この強風と、高潮に対する昔の人の恐怖心は大変なもので、私の家は菅沢でももっとも南側にあり、私が子どもの頃、父は台風が来ると、軒先が吹き上がらないよう(農家風のつくりで軒先が長かった)軒先に石を吊したり、雨戸を「かんぬき」という補強材で補強したりして、夜ほとんど一睡もしなかったのを憶えている。ある時、父にそんなに心配しなくても大丈夫ではないかという意味のことを言ったら「お前たちは台風の本当の恐ろしさを知らないからそんなことを言っているのだ、今にひどい目にあうぞ」とひどく叱られたのを憶えている。
明治40年と明治43年の大水害
いずれも二つの台風による大雨で、多摩川水源域で1000ミリ程度の降雨があり、多摩川の堤防が決壊、川崎はもちろん鶴見川左岸の低地を襲い、菅沢村も大被害を受けた。この水害は鶴見川からの浸水もあったが、主因は多摩川の堤防決壊による洪水であり、人々を驚かした。
大正6年の高潮
9月24日南方洋上で発生した台風は9月30日夜半、静岡、浜松の間を通過し、箱根の西側から丹沢、大宮、更に東北地方を縦断し、近畿以東に大被害をもたらした。なかでも東京湾一帯は折からの満潮と重なり、台風による南風で海の水位が通常より3.08メートル上昇し、デルタ地域の低地を襲い、典型的な高潮となった(当時の人々は津波だと言っていたそうだが、正確に言えば高潮)。菅沢村(当時は町田村)には海の方から水が押し寄せたので、人々は比較的高い土地に建っている家に命からがら避難したという。
「私の家(隠居屋さん)で川漁に使っていた舟も上流に流され、鶴見橋(現在の鶴見川橋)付近から市場の一里塚辺りまで流されてしまった。道が冠水しているうちに舟を川に戻すことが出来たので助かったが、恐ろしく大きな台風でしたよ」(『鶴見の古老が語る百話』)。

図3:現在の隠居屋さんの釣り船

図4:大正10年頃の鶴見川の氾濫
(左上に鶴見橋(現鶴見川橋)が見える)
関東大震災
大正12年(1933年)9月1日午前11時58分、相模湾を震源とするマグニチュード7.9の大震災が東京、横浜をはじめ関東地方一帯を襲い、東京、横浜では火災が発生し、菅沢辺りでも三日三晩赤い炎が見えたという。この結果、死者、行方不明者13万3000人を出す大災害となった。
菅沢(当時は橘樹郡潮田町の大字)は残念ながら公式の記録としては6ヶ村が合併した潮田町の記録しかないので詳細は判らないが、昔からの茅葺き屋根の家が30軒位あったと思われる。ほとんどが倒壊し、残ったのは2~3軒、90パーセントぐらいの家が地震で潰されてしまった。幸い東京、横浜のように火事は起きなかったので、人々はその後に起きた余震に脅えながら、潰された家の材料でバラックを作り、残った物置で夜露をしのいだという。
この地震は非常に強く、被害の範囲も広かったが同じ鶴見地区でも寺尾、末吉等丘陵の上の家は倒壊も少なく、被害も少なかった。これは明らかに地盤の違いによるもので、寺尾、末吉等の丘陵は地質学でいう下住吉層という長い間かかって出来た安定した地盤に対し、菅沢、市場、潮田のような低地は5000年ぐらい前までは海で、そこへ多摩川、鶴見川から流れてきた砂れき、砂泥が堆積してできた、地質学でいう沖積層であることの違いによるものである。このことは、この土地に住む者にとって頭の中に入れておくべきことで、家を建てる場合、あるいは防災対策を行う上で肝に銘じておくべきであろう。この地震を実際に経験し、その恐ろしさを語った人たちもほとんどいなくなってしまったが、この人たちは第二次大戦の空襲より大震災の方がその衝撃が大きく、恐ろしかったと語っていた。
参考文献
新編武蔵風土記稿
鶴見区史/鶴見区編集委員会・編
古老が語る鶴見の百話/古老が語る鶴見の百話刊行委員会・編
川崎史話/小塚光治・著
文責:鶴見歴史の会・岩澤清次郎
このページへのお問合せ
ページID:607-145-314