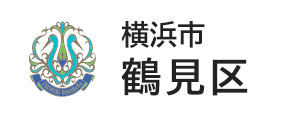ここから本文です。
第23回:總持寺今昔 観音像二題
最終更新日 2024年7月9日
濃く深い森にひとときのやすらぎを求めて訪れる人、御仏や伽藍を描く人、純粋な信仰心から本山に参詣する人、親しい友人や家族の墓参をする人、散歩する親子、著名人の墓地掃苔…。さまざまな人が、さまざまな思いで總持寺を逍遥している。
桜木観音菩薩像(桜木観音)

桜木観音菩薩像(正面)
日本一といわれるコンクリート製の仁王門(三門)をくぐると左側に桜木観音菩薩像(桜木観音)がある。この美しいブロンズ像は、昭和26年に桜木町駅構内で起きた電車の火災事故の犠牲者の冥福を祈って、昭和27年4月24日に建立された。八角形の基壇の上の八角形の台座に凛として立つ観音像。この美しい観音像は当時の彫刻界の権威、赤堀信平の自発的な申し出によって制作された。また「桜木観世音菩薩」の名号と103名の犠牲者の名前は鎌倉円覚寺管長朝比奈宗源の筆。台座後方の扇形の屏風には犠牲者たちの魂を天空にいざなうかのように楽を奏で、手を差し伸べる二体の天女像が線刻せされている。像建立の代表発起人は、当時の東京駅長と国鉄労組委員長。
手元に昭和30年代に観音像の正面から写した写真のコピー(左上)と今年の夏にやや下から仰ぐような角度で写した写真がある(右下)。同じ観音像であるはずなのに、見る角度、写す角度によってか、顔の表情や手の位置などに微妙な違いがある。風雪に晒されて半世紀、事故の犠牲者の無念の思い、遺族の苦しみや悲しみを一身に引き受け続けてきたためか、その表情に深みが増したようにも感じられる。50年前は樹木もなかった観音像のまわりに今は木々が生い茂り、背後には深い森が迫っている。しかし、何よりの違いは、創建当時の観音像は左手に宝珠を載せているが、現在の観音像の手に宝珠はない!?

桜木観音菩薩像
観音像建立時を知る人の話によれば、宝珠には事故の犠牲者103名の名前が刻まれていたのだという。宝珠が、いつ、どんな理由で御仏の手を離れたのかはわからないが、観音像は八角形の台座に立っている。八角形は生々流転の源である宇宙を表し、供養塔は死者の霊を弔うだけでなく、残された人や後の世に生きる人の幸せ、そして、不滅なる霊魂の再生など、さまざまな願いがこめられているという。
八角形いといえば、法隆寺夢殿。その夢殿の本尊は聖徳太子をモデルにしたといわれる国宝観音菩薩立像(救世観音・ぐぜかんのん)である。明治17年に岡倉天心とフェノロサによって全身を覆っていた白い布が解きほどかれるまで、長い間秘仏とされてきた救世観音も両の手で、すべての願いがかなうという宝珠を持っている。
桜木観音の制作者赤堀信平は、昭和22年に東京都北区の飛鳥中学校の校章のデザインを依頼され、飛鳥という文字から飛鳥時代を連想し、飛鳥時代の象徴ともいうべき法隆寺の天蓋にある「鳳凰」を研究して図案化したという。当然のことながら夢殿や救世観音にも魅了されたことは想像に難くない。仏教で国を治めようとした聖徳太子の一族はみな非業な死を遂げた。その太子の無念の思いを沈めるために建立された夢殿と救世観音……。
昭和27年に建立された桜木観音と八角形の台座には、聖徳太子伝説と夢殿救世観音につながる、制作者赤堀信平の深い思いが託されていた。桜木観音の御手に抱かれた103名の魂は、50年の歳月を経るなかで生まれ変わって新しい生命となって、今の時代を生きているのかも知れない…。
放光菩薩(ひかりかんのん)像

放光菩薩像(2代目)
大駐車場の奥の木立の中から参拝者をやさしく出迎えている放光観音像は2代目である。初代の放光観音像は、大正14年に当時帝国美術院会員・帝室技芸員で仏教美術に造詣の深い彫刻家新海竹太郎によって鋳造された。この像は、観音信仰に基づく身の丈三十三尺の美しい観音像だったという。
台座は法隆寺が日本最古の寺院建築であることを学問的に示した、日本最初の建築史家で平安神宮や築地本願寺などの設計で知られる伊東忠太の作品である。
放光観音像は、本山が能登から移転後15年ほど経った大正14年、本山としての寺容も整ったことと、大事業が滞りなく進んでいることを感謝して建てられたものだというが、伊東忠太設計による台座もまた六道に輪廻する衆生を救済する六観音を意味しているのではないだろうか。六角形の花崗岩の台座には勢至菩薩、観世音菩薩などの梵字が美しく配されている。放光観音像には、観世音菩薩の大慈悲によって大正12年の関東大震災の犠牲者の霊をも救済供養する願いも込められていたのではないかとも想われる。
放光観音像は龍王池のほとりに立っていた。丹塗りの橋、湖上に浮かぶ蓮の花、吹上台からの緑風、水面にうつる観音像は得も言えぬほどに美しく、龍王池のほとりはさながら極楽浄土の風情を漂わせていたという。が、諸行は無常なり。戦争の嵐は、龍王池の別天地に住まう美しい御仏までも奪っていった。

放光菩薩像(初代)
太平洋戦争のさなか、金属資源の不足により昭和16年には金属類回収(供出)が始まり、戦局の悪化にともない鉄びんや鍋、釜、指輪や火箸、仏具、タンスの取っ手、そして寺院の梵鐘や偉人の銅像なども鉄砲の弾や兵器に姿を変えていった。總持寺にも大梵鐘の供出命令がきたが、梵鐘があまりにも大きすぎ運び出すことが困難だったため、その身代わりとして龍王池のほとりに立つ放光観音像が供出されることになった。
昭和19年の春、全身を白い布で覆われた放光観音像は、僧侶たちが唱和する観音経と別れを惜しむ人々の涙に見送られて、この地を去っていったという。
鶴見高等女学校の卒業アルバムに新海竹太郎作の初代放光観音像が写っていた。女学生たちに見守られ、そして女学生たちを見守る、香気漂う池畔の観音像は、伝説にたがわぬ美しい御仏であった。
伊東忠太が制作した六角形の台座は主のいない空座であったが、昭和40年に交通安全の願いを込めて、日産自動車川又克二社長の寄進、山脇正邦作による2代目の放光観音像が再建された。
平成17年、總持寺の仏殿(大雄宝殿)、三松関、香積台、紫雲台、放光堂、鐘楼、三宝殿など国の登録文化財に登録された中に放光観音像台座も含まれている。今回指定された大僧堂もまた伊東忠太の設計である。また、總持寺墓地には浅野総一郎や田中新七の墓など、伊東忠太の作品も多い。伊東忠太自身も總持寺の、自ら設計した墓に眠っている。
このページへのお問合せ
ページID:687-898-277