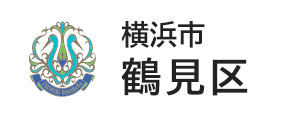ここから本文です。
第17回:末吉神社考
最終更新日 2024年7月9日
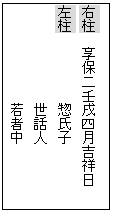
橘樹郡上末吉村昔ばなし

末吉神社
鶴見区上末吉4丁目のバス通りを入ったところに、末吉神社がある。この末吉神社は、昭和31年4月、古くから上末吉神社に鎮座した三島神社を中心に、付近の八幡神社、梶山神社を合祀して、末吉神社と改称した。入口に古色をおびた神明造りの石鳥居がある。
旧三島神社から移したものである。旧三島神社について『武蔵風土記』に「三島社字根畑ニアリ山ノ半腹二社ヲ建テ石階十九級ヲ設ク、例祭九月十九日村内円明寺持」とある。現在の末吉神社は祭神を天照皇太神としているが、明治初年までは大山祇命であった。
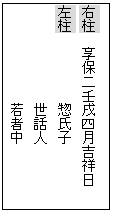
また氏子区域は、旧氏子が上末吉、下末吉で、現在は上末吉全域となっている。旧氏子に下末吉とあるのは、かつてその半数が三島神社を鎮守としていたことによるものである。これは口碑によれば氏子の三島神社への霊験のあつさを物語るものといわれている。また、末吉村が上・下二社に分かれた時期について『武蔵風土記』に、「此村古クハ上・下スベテ一村ナリシガ中古ニ分カレシト、正保ノモノヲミルニ未ダ分カレズ元禄ニ至リ上・下ノ二村ニ分カテリ」とあり、正保から元禄の間に分村が行われたものであろう。
鶴見区域では、東西北寺尾、馬場などの村が同じころ寺尾の分村によって生まれている。この時代、江戸近郊の幕府直轄領などに活発な郷村の分割が行われたことが知られる。
このことは一方で農村の開発が進んでいることを示すものであろう。建武2年(1335)の寺尾古図(県立金沢文庫蔵)に末吉領主三島東大夫とした書込みがあり、この三島東大夫は現静岡県の三島大社の神官をさしたものと思われる。
三島大社に聞いたところでは現在もこの三島東大夫、西大夫の二流社家があることがわかったのである。三島大社は古くは三島明神といい、源頼朝の崇敬があつく、その伊豆旗揚げに際し、当社に戦勝を祈願したことは史実によっても明らかである。
頼朝が鎌倉に幕府を開き、日ごろ崇敬する三島明神神官に所領を与えたことの記録はない。しかし、三島明神を軸として相模、駿豆、武蔵の地に創立された三島神社の数は多いのである。前記古図にみえる末吉領主三島東大夫の存在がたしかなものとして、その氏神三島神社が末吉に創建されたものと信じたい。

弁頼筆子塚
戦国時代の末吉村は、小田原北条氏治下の一寒村であったと思われる。鶴見地域の馬場村には諏訪三河守5代にわたる居城があった。また諏訪坂にも城主の居館もあり、城下町を形成した。
鶴見は鶴見川をひかえて東海道の宿駅として街道の要衝でもあった。
また、上末吉一帯は鎌倉時代、幕府軍と新田義貞軍との間で鶴見合戦が行われたところで、小さな村は戦火の中でその苦悩も大きかったにちがいない。
『小田原衆諸領役帳』に「間宮豊前守康俊三十五貫文、小机末吉」などとあり、小机は中世小机城のあったところで、大田道灌の小机城攻めは史実に名高い。
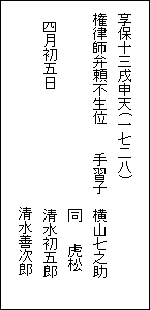
間宮氏は『小田原編年記』に「初代信冬伊豆田方郡間宮村に住して間宮氏を稱す」とある。また「六拾六貫文、江戸川崎」などとあり、永禄のころ、多摩川は川崎の南を流れ古市場から尻手、八丁畷あたりを流れていたものという。
今、川崎砂子の曹洞宗宗三寺には信冬の墓所があり、当時間宮氏の所領であったことが知られるのである。
三島神社(現末吉神社)別当の円明寺(上末吉1―8)は真言宗の寺で、末吉山東光院といい、本尊に七佛薬師の木造を安置した。今この円明寺跡には、江戸時代に寺子屋を開いて子弟を教導した僧弁頼の筆子塚がある。
この弁頼筆子塚は、横浜市域で2番目に古い筆子塚である。円明寺は明治6年廃寺となって、今わずかに墓地がその跡をとどめている。
鶴見歴史の会/大熊司
鶴見区文化協会「鶴翔」より
このページへのお問合せ
ページID:157-605-066