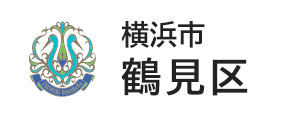ここから本文です。
第14回:鶴見の史跡と伝説
最終更新日 2024年7月9日
ニケ領用水
市場の「夫婦橋」の橋名板と「二ヶ領用水路地跡」の碑
市場上町六丁目のバス通りに面した熊谷酒店のブロック塀の礎石に「夫婦橋」と記された小さな橋名板が残されている。
江戸時代の東海道市場村の神奈川宿と川崎宿の境には大小2つの用水堀があった。潮田方面に流れるのが潮田堀、市場方面に流れるのが市場堀と呼ばれていた。夫婦橋はこの2つの用水堀にかけられていた大小二つの石橋の名前である。
2つの堀の本流は多摩川から引き入れられた二ヶ領用水で、きれいな水がどんどんと音を立てて流れていた。浅くもなく深くもない流れは、東海道を行き交う旅人たちが汗とほこりを洗い流すのに絶好の場所でもあった。
二ヶ領用水は、毎年のように洪水を繰り返す暴れ川多摩川の治水と新田開発のため、徳川家康の命を受けた用水奉行小泉次太夫によって開削された。慶長2年(1597)に測量を始め、その2年後に開削工事が始まった。多くの農民たちの協力をえながら進められた大工事、全長32キロメートルの用水路は測量開始から15年の歳月をかけて1611年(慶長16)に完成した。稲毛領37村、川崎領23村、計60村の水田2700町歩(199ヘクタール)に網の目のように張り巡らされた用水路、稲毛領と川崎領の二領を潤したので二ヶ領用水の名がつけられた。小泉次太夫は対岸の世田谷・六郷の六郷用水の工事も同時に着手、完成させたので、この2つの用水は「四ヶ領用水」とも呼ばれた。鶴見川を挟んで川崎寄りの市場・矢向地区は江戸時代には川崎領に属していたので、二ヶ領用水の恩恵を受けていた。
鶴見区域は、1927年(昭和2)に横浜市に合併し、潮田・市場・矢向地区にも水道が敷かれた。鶴見臨海部が埋め立てられ京浜工業地帯が形成されて、農地は宅地や工場用地に姿を変えた。二ヶ領用水は工業用水としても利用されたが、水道が普及し、農業用水としても生活用水としてもその役割を終えたとして埋め立てられて、そのほとんどが道路に変貌した。
「鶴見川の水は海水が逆流するので塩分を含んでいたため水田や生活用水には使えませんでした。二ヶ領用水のおかげで、このあたりの田んぼはうるおっていたのです。この用水で潅漑された田んぼの米はとてもおいしい米でした。江戸時代はこの流域でとれる米は稲毛米と呼ばれる良質米で、江戸城の寿司米だったそうです。戦後もきれいな水がどんどん音を立てて流れていて、用水堀の近くに住んでいた人たちは、この堀で野菜を洗ったり米をといだりしていました。工場や住宅が建って、田んぼや畑がなくなって、用水は埋められ道路になってしまいました」と、10年前に市場の古老が語っていた。いまはもうその姿を語り伝えてくれる人もほとんどいなくなってしまった。熊谷酒店前の交差点から京浜急行の線路の方に大小二つの道がYの字に分かれている道がわずかに往時の水路の名残をとどめている。
鶴見区矢向には「二ヶ領用水路地跡」の碑がある。この碑は、1972年(昭和47)に矢向地区の人々が埋め立てられた二ヶ領用水の跡地を国から払い下げを受けて、道路と緑地帯に整備して二ヶ領用水路に架けられていた石橋を再利用して建てたものである。
碑の正面には「二ヶ領用水路地跡」、裏面には「紀元二千五百五十年明治二十六年十一月、町田村矢向外下郷村々」と刻まれている。夫婦橋も矢向の石橋も共に明治時代にに架けかえられた橋である(図2参照)。
参考資料・「鶴見の史跡と伝説」

図2・矢向の二ヶ領用水路
このページへのお問合せ
ページID:564-616-536