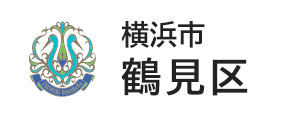ここから本文です。
第21回:手枕坂の碑
最終更新日 2024年7月9日

手枕坂の碑
手枕丹むすひし夢は昔しにて
さ免ゆくみ世の坂は此坂・黒川七十九翁
落ち葉ふる手枕坂や鐘の音・吉川六十八翁
曹洞宗大本山總持寺境内には、横浜開港前夜にこの地を訪れた外国人の足跡をいまに伝える「手枕坂の碑」がある。この碑は大正13年(1924)11月、鶴見村の戸長を務めていた黒川荘三とその友人吉川兼次郎によって旧手枕坂を記念して建てられたものである。手枕坂は、現在の場所ではなく、鐘楼や三宝殿がある双眸丘と現在の鶴見大学図書館の間辺りにあった坂道と伝えられている。関東大震災後の總持寺再建や戦時中の混乱、樹木の生育などが原因してか、所在不明となっていた碑が戦後になって地中より発見され、現在地に移された。鶴見神社の宮司を勤めた黒川荘三は、横浜開港前後の鶴見村のできごとや地誌、史蹟・名勝起源などを『千草』に書き残すなど民俗や郷土史の伝承・継承に大きな役割を果たした人物である。
吉川兼次郎は鶴見川鉄橋の架橋技師の齊藤精一郎に、当時はまだ珍しかった混和土(コンクリート)技法を学び、黒川荘三とともに鶴見の各所に郷土の歴史を伝える碑を残した人物である。味気なくなりがちなコンクリート製の標柱に色とりどりの小石を配するなど意匠を凝らした美しい碑が、後の世に生きる者を郷土史探訪の旅へと導いてくれる。總持寺の深い木立の中に静かにたたずむ「手枕坂の碑」の由来を思い、『千草』に「手枕坂起源」をたずねると、文明開化前後のもの騒がしき世のなかの悲喜こもごもがよみがえってくる。
―「嘉永七年(1854)甲寅年二月十六日神奈川青木町海岸より―
異人上陸せしは開闢以来の嚆矢なり。
……役人より異人上陸、江戸へ趣により先村々へ急達持回りをもって取締方および渡船及び船は一切隠し手筈を達す」と、黒船来航で上へ下への大騒ぎをしているときに、神奈川に上陸した乗組員が、江戸を目指して歩いてくるという知らせが、子安村の名主から鶴見村の名主に早飛脚で届けられた。その知らせを市場村名主へ送り届け、村中に触れ回ると、血気にはやる若者などは「容赦なく殴り殺せ」と殺気だつ。
ときはいまだ鎖国の時代。まさに開闢以来の晴天の霹靂。
「一大事!」と、村人たちは大いに驚き騒ぎ立てる。名主は村方年寄や百姓代を呼び集めて村の騒擾を取り鎮め、子安村から鶴見村に向って歩いてくる外国人を出迎えるために成願寺山(現在の總持寺境内)に向かう。
黒川荘三の父黒川四郎左衛門も成願寺山へ出かけ、南台の坂下道で外国人に出会った。赤ひげぼうぼうのいかめしい顔色に、黒の筒袖、黒の股引で黒の頭巾をかぶり、腰には剣のようの刀を紐にぶら下げ、黒色の靴をはいている、仰ぎ見るような大男。付添役人は羽織袴に帯刀。江戸へ行きたい一心で足早に歩く外国人について行けない。子安村年寄役の清右衛門は羽織・股引・鞋の軽装、風体剛毅者ということで「貴公何分同伴を頼む」と役人に言われて1人で外国人に随行していた。東寺尾村を通過し、外国人と清右衛門が鶴見村字成願寺台、南台の坂を降るとき、右の傍らのくさむらの中に墓石を見つけた外国人が同行していた清左衛門に何かべらべらと尋ねる。しかし何を言っているのかさっぱりわからない。清右衛門が戸惑っていると、外国人は墓石をさして目を閉じ、身振り手振りで土を掘り、埋めるまねをしたので、これは死者を葬るのかと尋ねているのだと推量して、そうだとうなずいて見せると、外国人もついに死者を埋葬している墓ということを理解して大いに喜んだ、ということで、「手枕坂」という名前がつけられた。
鶴見歴史の会・斎藤美枝
このページへのお問合せ
ページID:755-990-417