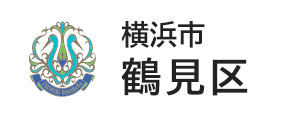ここから本文です。
第2回:植木発祥の地宗泉寺は、五百羅漢とエビネの寺
最終更新日 2024年7月9日
震災復興のために始めた植木栽培
大正12年(1923)の関東大震災後,横浜など壊滅状態になった市街地復興のために植木が必要になった。植木園芸組合をつくり,植木栽培にいち早く取り組んだのが上の宮の人々であった。
当時は,植木や園芸関係の仕事に対する課税基準がなく,植木への課税の枠もなかった時代で,上の宮の人たちは,「植木とは何だろう」「園芸とは何だろう」ということから考えた。最初は農業のなかの園芸部門であると考えたが,「園芸というものは,人間の一つの趣味である。趣味に課税するのはおかしい」ということで,土建業で許可をとった。
土建業を始めた当初は,庭をつくり,公園をつくるために必要な苗木は,埼玉県の安行村から取り寄せていたが,上の宮の宗泉寺の横井諦運住職も,とぼしい寺の収入をおぎない,生活の糧にと,境内の山林を耕して苗木を育てていた。境内地はさし木に適した赤土だった。
珍しい苗木も栽培していた宗泉寺の住職
菊名の蓮勝寺の住職にさし木づくりを習った横井住職は,「さし木なら何でもこの畑でつかないものはない」といいながら,育った苗木は上の宮の人たちにも分けてあげた。
川崎大師の植木市で買った苗木の増やし方も蓮勝寺の住職に教わった。上の宮の農家の人たちが最初に覚えたのは,サザンカとツバキだったが,横井住職は珍しい苗木も育てていた。横井住職から珍しい苗木を買って,ひと儲けをしようと思った人たちは,寺の境内に座り込んで値段の交渉をした。しかし,植木の値段は基準がないので交渉が難しい。
住職は元木の仕入れ値と手間賃を計算してソロバンをはじき,「お前はいくらで買うんだ」と聞くが,農家の人たちは答えられない。この苗を買って3年から5年育てたら,いくらで売れるのだろうと,考えた金額と,住職のソロバンとはなかなか合わなかった。しかし,各地の縁日で植木を商う露天商たちが,上の宮に植木を買いに来るようになり,植木も売れるようになった。
昭和5年ごろ,鶴見の庭師組合といっしょになって造園組合をつくり,市の公園をつくったり,まちの緑化のためにも貢献してきた。
地形をいかした親しまれる寺づくり
植木発祥の地といわれている宗泉寺は,現在,羅漢とエビネの寺として親しまれている。
平成元年,宗泉寺の横井久運住職は,地域に親しまれる寺づくりの一環として,起伏に富んだ地形を生かした境内を回遊式庭園に仕立てた。色とりどりの数十種類のエビネと,さまざまな表情,姿をした五百羅漢を見事に配し,シダレザクラ,サツキ,ボタンなど四季折々の花が楽しめる庭園が整いつつある。木立ちの間を流れる清流,竹林の茶室方正庵の風情も格別である。
寺へ至る参道のツツジや八重桜は,「さすが上の宮は植木発祥の地」と思わせる趣がある。

さまざまな表情をした羅漢像

10周年を記念して羅漢祭が行われた
「つるみ・このまち・このひと」から
このページへのお問合せ
ページID:985-383-531