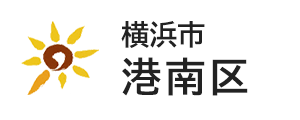ここから本文です。
申告漏れや申告時に誤りやすい事項について
よく見受けられるケースを抽出し、記載しています
最終更新日 2026年1月20日
申告時に誤りやすい事項について
シルバー人材センター配分金や個人年金と外国年金について
個人年金について
生命保険会社やJA等から支払われる個人年金は、課税所得となりますので申告が必要です。
確定申告書を提出しない場合は、市民税・県民税の申告が必須となります。
申告区分は雑所得の中の「その他の雑所得」となり、公的年金等とは別の区分で申告します。
支払元より送付される通知書(証明書)に収入金額、必要経費が記載されていますので、
市民税・県民税申告書へ内容を転記してください。
※申告書には通知書(証明書)の写しを必ず添付し、ご提出ください。
外国年金について
外国から支払われる外国年金は厳選徴収義務がないため、確定申告書を提出する必要があります。
少額等のため確定申告書の提出をされない場合は、市民税・県民税申告書の提出が必須となります。
シルバー人材センター配分金等について
シルバー人材センターの配分金は、雑所得の「業務」区分で申告する必要があります。
支払元より送付される通知書(証明書)に収入金額と、必要経費については「家内労働者等の
必要経費の特例」の説明書きがありますので、市民税・県民税申告書に転記のうえ提出してください。
※申告書には通知書(証明書)の写しを必ず添付し、ご提出ください。
なお、当該配分金で必要経費が65万円未満の場合、「家内労働者等の必要経費の特例」を
適用できる可能性がありますので、諸条件も含め下記リンク先を参照してください。
国税庁のページへアクセスします
配偶者控除と老人扶養(同居老親等)について
配偶者控除について
配偶者控除の適用を受ける場合、扶養親族等申告書や確定申告書等に配偶者の所得金額等を
記載する必要がありますが、誤って収入金額を記載しているケースが見受けられます。
正しく申告をすれば配偶者控除を受けることができ、収入が少なければ非課税に繋がるケースも
ありますので、手続き時の記載誤りにはご注意ください。
(補足)なお、育休手当(育児休業給付金)や失業手当は、税金の計算上は収入認定されません。
老人扶養(同居老親等)について
70歳以上の親族を扶養している場合は、老人扶養控除を申告することができます。
また、その親族が直系尊属で同居を常としている場合は、同居老親等として申告することで
さらに税額を減額することができます。
※ 老人ホームなどへ入所している場合は、同居を常としておらず、同居老親等として申告できません。
年金の源泉徴収票等には当該同居に係る項目がないため、市民税・県民税の税額計算へ反映されることはありません。
個別に市民税・県民税申告書を提出し、同居老親等の手続きをする必要があります。
ひとり親控除、寡婦控除について
寡婦控除やひとり親控除は、配偶者と(離別・死別・生死不明)となった場合に適用できる控除です。
税金の算出上大きな影響を与える控除となりますので、年末調整等での手続き漏れや、申告漏れにはご注意ください。
適用条件は、以下のとおりです。
ひとり親控除
原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない
一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(2)生計を一にする子がいること。
※この場合の子とは、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や
扶養親族になっていない子に限られる。
(3)合計所得金額が500万円以下であること。
寡婦控除
原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。
※事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の方がいる場合は、対象となりません。
(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる方で、合計所得金額が500万円以下の方
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の方で、合計所得金額が
500万円以下の方
※「夫」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。
社会保険料控除、寄附金控除、生命保険料控除について
社会保険料控除
社会保険料控除は、申告者自身が支払をしている社会保険料のみ申告することができますが、
よく見受けられる誤りとして、以下の1~4がありますので、ご注意ください。
1、配偶者の年金から特別徴収されている介護保険料を、申告者分として計上している。
⇒配偶者の年金から特別徴収され、申告者自身が支払いをしていないため、申告できません。
2、申告者の年金から源泉徴収されている社会保険料を、二重計上している。
正)年金からの特別徴収分 22万(うち、後期高齢者医療保険料15万、介護保険料7万)=22万
誤)年金からの特別徴収分 22万+後期高齢者利用保険料15万+介護保険料7万=44万
3、住民税(市民税・県民税)額を、社会保険料に計上している。
4、生命保険の介護医療保険料を、社会保険料控除に計上している。
⇒生命保険の介護医療保険料は、生命保険料控除として計算のうえ記載する必要があります。
※社会保険料控除の介護保険料を、生命保険の介護医療保険料として申告しているケースもあります
寄附金控除
ふるさと納税等の寄附をされた場合、寄附者の寄附金控除となり、申告者と寄附者は原則一致します。
※原則、寄附者として証明書等に記載されている方しか、寄附金控除の申告はできません。
ただし、一部例外もありますので、以下を参照してください。
例1:妻名義で寄附、寄附金の支払いも妻
⇒ 妻の寄附金控除とし申告(夫名義の申告では申告不可)
例2:妻名義で寄附、寄附金の支払いは夫名義のクレジットカードや口座振替
⇒ 夫名義での支払根拠資料を添付のうえ、夫の寄附金控除として申告可能
生命保険料控除・地震保険料控除
生命保険料控除や地震保険料控除は、支払金額そのものが控除となるものではありません。
計算式を活用し、支払金額から控除額を求めたうえで、申告する必要があります。
しかし、支払金額=控除額として確定申告に記載しているケースが散見されますので、ご注意ください。
※市民税・県民税申告書を提出する場合は、他の控除と同様に資料(保険会社からの証明書)の添付が必要です。
各保険料控除の計算式については、以下のリンク先を参照してください
国税庁のページへ
国税庁のページへ
横浜市財政局のページへ
このページへのお問合せ
ページID:384-997-160