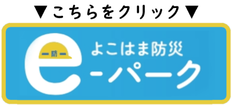ここから本文です。
ストーブ火災
最終更新日 2025年4月8日
ストーブを原因とする火災は12月から3月にかけて増加する傾向にあります。
過去の火災事例をもとに、ストーブ火災の危険性や対策を学びましょう。
ストーブ火災の月別件数(2013年~2022年)
ストーブ火災は死者発生率が高い!?
ストーブには、石油ストーブ、電気ストーブ、ガスストーブ、石油ファンヒーターなど、様々な種類のものがありますが、どの種類のものでも一度出火すると被害が大きくなりやすいのがストーブ火災の特徴です。
横浜市内では、過去10年間(2013年~2022年)で249件のストーブ火災が発生し、30名の尊い命が奪われています。
これは他の火災原因による死者発生率と比べて、非常に高い割合となっています。
主な出火原因別の火災件数と死者発生率
就寝中のストーブ火災に要注意
ストーブ火災の発生した件数を時間別にみると、ストーブ火災249件(うち1件は出火時間不明)のうち75件は、就寝時間帯である〈22時~5時台〉に発生しており、死者が発生した27件(※1件で複数の死者が発生した火災もあります。)のうち11件はこの時間帯に発生しています。
寝る前には、必ずストーブのスイッチは切るようにしましょう!
ストーブ火災の発生時間帯(2013年~2022年)
電気ストーブは安全⁉
ストーブ火災の出火経過をみると、電気ストーブに可燃物が接触して出火しているケースが多いことがわかります。
電気ストーブは、灯油等の燃料がいらず、換気などの手間もかからないことから、手軽で安全だと思われがちですが、使い方を誤れば火災になるおそれがあります。
ストーブを使用する際は、使い方を改めて確認し、適切に使用しましょう!
電気ストーブとその他のストーブの火災発生割合
どんなものに火がついてる?
洗濯物
〈ケース①〉ストーブの近くに干してあった洗濯物がストーブに落下し、一定時間が経過後、出火。
※ストーブと着火物が接触していなくても、ストーブからの熱が原因で火災になることもあります。
火災を防ぐポイント
ストーブの周りは常に整理整頓し、ストーブの上や近くに洗濯物を干すことは絶対にやめましょう。
布団
〈ケース②〉ストーブをつけたまま寝てしまい、寝返りを打った際に掛けぶとんがストーブに触れ出火。
※ふとんがストーブに接触した火災のほとんどが、電気ストーブから発生しています。
※掛けている布団に着火した場合、死傷者が発生する確率も非常に高くなっています。
火災を防ぐポイント
就寝時やその場を離れる時は、必ずスイッチを切り、プラグをコンセントから抜きましょう。
その他
灯油などの石油類
〈ケース③〉ストーブをつけたまま、カートリッジタンクに給油し、蓋の閉まりが不完全だったため、蓋がはずれ、灯油が燃焼筒にかかり出火。
〈ケース④〉石油ファンヒーターのカートリッジタンクに、誤ってガソリンを給油し点火。
その後、ガソリンが混入したカートリッジタンクの内圧が上がり、ガソリンがあふれ出て石油ファンヒーター本体の炎に引火し、出火。
火災を防ぐポイント
・ 給油時は必ずストーブを消火し、給油後は蓋がしっかり閉まっていることを確認しましょう。
・ 給油の際は、取扱説明書等に記載のある燃料の種類を確認しましょう。
スプレー缶などの可燃性ガス
〈ケース⑤〉ストーブの近くにいたゴキブリに殺虫剤スプレーを噴射したため、放射されたガスが石油ストーブの火に引火して燃え上がり、周囲にあった物に着火。
〈ケース⑥〉石油ファンヒーターの前に置かれたヘアスプレーが、温風により熱せられ破裂。その際、破裂したヘアスプレーのガスがファンヒーターの炎に引火。
火災を防ぐポイント
・ スプレー缶などを使用する際は、ストーブから十分離れ、十分な換気をしましょう。
・ ストーブの近くに、スプレー缶を置かないようにしましょう。
火災調査メールマガジン📧
防火防災を動画で学ぶ👀
このページへのお問合せ
ページID:620-784-995