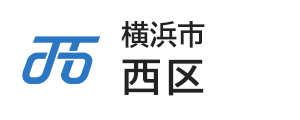最終更新日 2019年1月17日
ここから本文です。
西区歴史さんぽみち 旧東海道
昔、現在の横浜駅の一帯から、久保町方面にかけては、袖ヶ浦とよばれた内湾であった。旧東海道は、神奈川宿から海に沿って(現在の楠町から浅間町)保土ケ谷宿へ通じていた。あたりは静かな入り江に白帆が浮かぶなど、大変景色のよい所として有名であった。
江戸時代、街道沿いの宿と宿の間には、人足や馬の休憩場所としての立場(たてば)があった。神奈川宿と保土ケ谷宿の間の芝生村(しぼうむら・現浅間町)は、この立場として発展した村で、農場のほかに飯屋や酒、わらじの販売など商業も営まれていた。
勧行寺

南軽井沢9
文禄4年(1595)開山。本尊は大曼荼羅、一塔両尊。門を入ってすぐ左手に近藤内蔵助長裕の墓(供養塔)がある。彼は天然理心流という剣法の開祖で、新撰組の隊長として名を残した近藤勇はその4代目にあたるという。
また、横浜のエキゾチシズムを描いた横浜生まれの作家・北村透馬と劇作家の余志子夫人が眠る。境内には、名木古木指定のイチョウがある。
軽井沢の庚申塔

南軽井沢61
建立は、安永8年己亥(1779)2月吉日。塔の後ろに建つ碑には「この塔は道路拡張にも拘わらず西区唯一の建立当時の現地にあり保存のため建之昭和46年(後略)」とある。
この塔は主要地方道横浜生田線が三ツ沢へ上る右側の崖の中腹、関東自動車学校へ通じる階段の途中に建つ。
庚申(こうしん)の行事は、60日に一度まわってくる庚申(かのえさる)の日の夜に三尺(さんし)という虫が睡眠中に人体を抜け出し罪過を天帝に報告するので、この日は謹慎して眠らずに過ごすという道教の教えに基づく。わが国では平安時代のころからみられ、江戸時代には形を変え庶民に広まった。今では信仰は衰え、青面金剛像、日、月、鶏、三猿が刻まれた塔だけが残っている。
浅間神社

浅間町1-19-10
承歴4年(1080)富士浅間神社の分霊を祭ったものと伝えられている。祭神は、木花咲耶姫命(コノハナサクヤヒメノミコト)で旧芝生村(しぼうむら)鎮守。本殿2階建浅間造。社殿のある丘は、「袖摺山(そですりやま)」と呼ばれ、昔は山の下がすぐに波うち際であったという。
この丘の斜面には20基の横穴墓があり、そのうち開口したものが「富士の人穴」と呼ばれ、この中に安置されていた大日如来石像が、現在社殿横に置かれている。
追分

浅間町350付近
保土ケ谷区境の三叉路は、東海道でも芝生(しぼう)の追分(おいわけ)といって有名だった。八王子道の起点で甲州街道の八王子宿まで延びていたことから、東海道と甲州街道を結ぶ要路として賑わいを見せていた。開港後も絹などの輸送路として栄え、追分から八王子道に入ったところには、小さな川が流れ、石橋がかかっていて、評判のドブロク屋があった。その先には2体の古い地蔵があったという。
木村担乎先生終焉の地石碑

浅間車庫前公園
木村担乎は、帷子(かたびら)小学校長退職後、私費を投じ、![]() 徳(りんとく)小学校を建設した人。嘉永6年(1853)仙台藩士の子として生まれ、明治11年(1878)神奈川県の教師になり、後に帷子小学校の校長となった。大正6年(1917)、いろいろな理由で学校へ通えない子供たちのため浅間町に私設の小学校を建てた。「人間は生きている間が仕事」と一貫して教育者として力を尽くしたが、大正12年(1923)の関東大震災のため生涯を閉じた。木村先生の徳をしのぶ有志が浅間車庫前公園に碑を建てた。
徳(りんとく)小学校を建設した人。嘉永6年(1853)仙台藩士の子として生まれ、明治11年(1878)神奈川県の教師になり、後に帷子小学校の校長となった。大正6年(1917)、いろいろな理由で学校へ通えない子供たちのため浅間町に私設の小学校を建てた。「人間は生きている間が仕事」と一貫して教育者として力を尽くしたが、大正12年(1923)の関東大震災のため生涯を閉じた。木村先生の徳をしのぶ有志が浅間車庫前公園に碑を建てた。
洪福寺

浅間町5-385-3
寺伝では、開山は呑海(どんかい)といわれている。寛永13年(1636)袖摺山(そですりやま)薬師堂を当地に移したという。本尊薬師如来は、鎌倉権五郎景政の守り本尊と伝えられ、目洗薬師といわれている。
このページへのお問合せ
西区総務部地域振興課
電話:045-320-8389
電話:045-320-8389
ファクス:045-322-5063
ページID:484-741-453