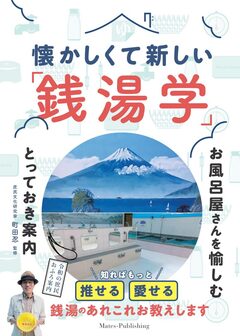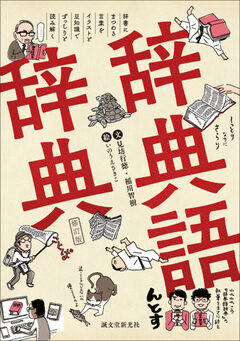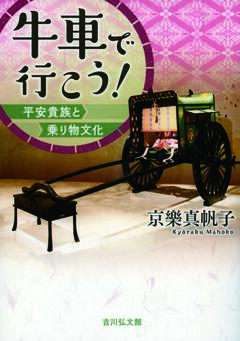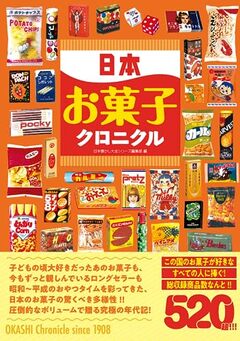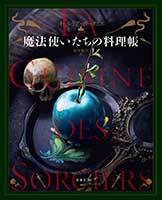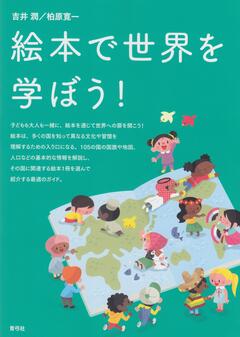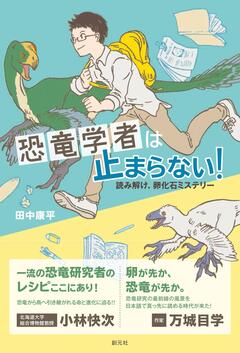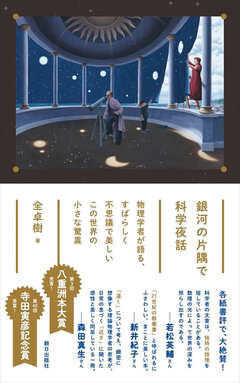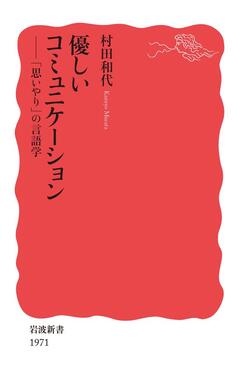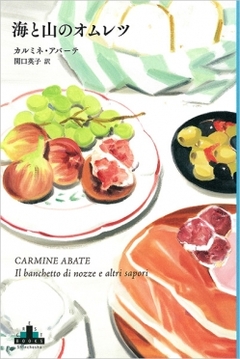- 横浜市トップページ
- くらし・手続き
- 市民協働・学び
- 図書館
- 図書館のおすすめの本
- 図書館の本棚から
ここから本文です。
図書館の本棚から
毎月23日は「市民の読書の日」、毎年11月は「市民の読書活動推進月間」です。横浜市立図書館が所蔵する本を、各図書館の司書がご紹介します。
最終更新日 2026年1月23日
画像をクリックすると、蔵書検索ページにジャンプします。横浜市立図書館での所蔵状況が分かります。
2月
タイトル:懐かしくて新しい「銭湯学」 お風呂屋さんを愉しむとっておき案内
著者名:三宮 麻由子/著
発行者:メイツ出版
出版年:2021年
身近な銭湯も、脱衣所や浴槽、釜場など分解して考える機会はあまりないのではないでしょうか。この本では、下駄箱、カランなど細かなアイテムから建物の種類まで銭湯の見どころを紹介しています。
また、銭湯の起源は○○時代だった…など銭湯の変遷の歴史も楽しめます。もちろん知識を深めるだけではなく、肌で味わいたいという気持ちにもしっかりこたえてくれます。第四章では全国の趣のある銭湯が紹介されています。本を読んで知識を深めて、実際の銭湯で体験してみるのも楽しいのではないでしょうか。
(本の紹介文は、金沢図書館が広報よこはま金沢区版2024年3月に掲載したものです。)
1月
タイトル:辞典語辞典 辞書にまつわる言葉をイラストと豆知識でずっしりと読み解く 修訂版
著者名:見坊行徳 /文、 稲川智樹 /文、 いのうえさきこ /絵
発行者:誠文堂新光社
出版年:2021年
辞書に詳しい人しか知らないような専門用語からこんな言葉が辞書に関わるの!?というものまで、681項目の言葉が紹介されています。中には小説やテレビ番組などの項目もあり、説明を読んでみると、どこでどのように辞書が登場したかが書かれていて、その内容の細かさに驚きました。巻末の総索引から気になる言葉のページを読んでもいいですし、開いてみたページの気になる言葉を読んでもいい、まさに辞書のように読める一冊です。
(本の紹介文は、旭図書館が広報よこはまあさひ区版2024年6月号に掲載したものです。)
12月
タイトル:牛車で行こう! 平安貴族と乗り物文化
著者名:京樂真帆子 /著
発行者:吉川弘文館
出版年:2017年
平安時代、中流以上の貴族が乗っていたという、牛に引かせる車「牛車(ぎっしゃ)」。本書では、牛車の種類や乗り降りの作法、また、平安貴族になったつもりで牛車に乗ってみるシミュレーションなどで、牛車とはどのような乗り物だったのかを説明しています。『源氏物語』や『枕草子』などの古典文学の引用や、絵巻物などからの図版も豊富に収録されています。牛車を通して、平安貴族の日常生活の一端が見えてくる1冊です。
(本の紹介文は、金沢図書館が広報よこはま金沢区版2024年1月号に掲載したものです。)
11月
タイトル:日本お菓子クロニクル
著者名:日本懐かし大全シリーズ編集部/編
発行者:辰巳出版
出版年:2023年
私たち日本人はずっと昔から、さまざまなお菓子を食べてきました。
お米を材料とした「せんべい」や「あられ」、甘い「キャンディ」や「チョコレート」、
洋風の「クッキー」や「ビスケット」、「ポテトチップス」を代表とするスナック類など…。
この本では明治から大正、昭和、平成と私たちに長く愛され、
普段普通に食べてきた日本生まれのお菓子達の歴史をパッケージと共に紹介しています。
懐かしのお菓子だけではなく、今でも人気のロングセラーも掲載されています。
皆さんが好きだったお菓子も、きっとこの本の中にありますよ。
(本の紹介文は、戸塚図書館が広報よこはま戸塚区版2024年12月に掲載したものです。)
10月
タイトル:魔法使いたちの料理帳
著者名:オーレリア・ボーポミエ/著、田中裕子/訳
発行者:原書房
出版年:2019年
仲間や敵、時には隣人として物語に登場する魔法使いたち。物語の中で彼らが作り、食べる料理…気になりませんか?ヒッポグリフの肉、闇の森のハーブ、オークの頭蓋骨のボウル、魔法で竜巻を起こしてかき混ぜる、など変わったレシピがたくさん出てきますが、一般人用の代案も用意されているので魔法が使えなくても作れます。物語の世界観を感じながら、お試しあれ!
(本の紹介文は、旭図書館が広報よこはまあさひ区版2022年5月号に掲載したものです。)
9月
タイトル:絵本で世界を学ぼう!
著者名:吉井潤 /著、柏原寛一 /著
発行者:青弓社
出版年:2020年
世界の105の国について、その国のことがわかる絵本、その国にゆかりのある作家の絵本を一冊ずつ紹介した本です。例えばノルウェーは『オーロラの国の子どもたち』、オーストラリアは『カンガルーには、なぜふくろがあるのか』という絵本を紹介しています。絵本を入り口に、世界の文化や習慣を学んでみませんか。
(本の紹介文は、磯子図書館が広報よこはま磯子区版2021年4月に掲載したものです。)
8月
タイトル:恐竜学者は止まらない! 読み解け、卵化石ミステリー
著者名:田中康平/著
発行者:創元社
出版年:2021年
恐竜学者と聞くと、恐竜の骨の化石を研究している人だと思うかもしれません。ですが、この本の著者は、恐竜は恐竜でも、骨ではなく卵の化石を研究する、卵化石研究者です。
卵化石には、恐竜の産卵、ふ化、子育ての謎を解く鍵が隠されています。体重が2トンもある巨大な恐竜は、どうして卵をつぶさずに温められたのでしょう?卵のお世話をする、イクメン恐竜もいたとか。
奥深い恐竜の卵の世界をのぞいてみてください。
(本の紹介文は、戸塚図書館が広報よこはま戸塚区版2023年2月に掲載したものです。)
7月
タイトル:銀河の片隅で科学夜話 物理学者が語る、すばらしく不思議で美しいこの世界の小さな驚異
著者名:全卓樹/著
発行者:朝日出版社
出版年:2020年
物理学者による科学エッセイ。「三人寄れば文殊の知恵」は正しいのか、真空発見のエピソード、彗星すいせいはどこからやってくるのか。日常生活の傍らに広がる世界と科学について、驚きと共にサラサラ読み進める22話。
(本の紹介文は、鶴見図書館が広報よこはま鶴見区版2023年11月号に掲載したものです。)
6月
タイトル:優しいコミュニケーションー「思いやり」の言語学
著者名:村田和代/著
発行者:岩波書店
出版年:2023年
仕事でもプライベートでも、雑談をするとき、どんなことを考えますか?人と人との関係構築に雑談は一役買っています。ではその役割はどんな形で相手にどのような影響を与えているでしょうか。社会言語学を専門とする著者が実際の事例や研究の成果を交えて易しく紹介しています。時と場所を選んだり、方言を使ったり、あるいはリモートで行われるコミュニケーションなど、普段の生活・仕事の中から見つかる言語学の奥深さに思わずうなります。
5月
タイトル:星空をつくる機械 プラネタリウム100年史
著者名:井上 毅/著
発行者:KADOKAWA
出版年:2023年
子どもの頃、遠足でプラネタリウムに行った思い出のある人もいらっしゃると思います。
1923年にドイツで誕生した近代プラネタリウムは、日本では「星を作る機械」と紹介されました。明石市立天文科学館の館長である著者が、古代ギリシャの天球儀から、最新の技術までを解説します。
プラネタリウムに魅せられた人々の手で国産機が誕生し発展していく道のりは、その情熱に圧倒されます。
最近は、枕を持参し、星空の下で説明を聞きながら気持ちよく眠る「熟睡プラ寝たリウム」という企画が人気とか。読むとプラネタリウムに足を運びたくなる1冊です。
(本の紹介文は、戸塚図書館が広報よこはま戸塚区版2024年4月に掲載したものです。)
4月
タイトル:私のことば体験
著者名:松居 直/著
発行者:福音館書店
出版年:2022年
4月23日は「子ども読書の日」。
本書は『ぐりとぐら』『おおきなかぶ』など多くの人気絵本を手掛けた児童書編集者・松居直氏の自伝です。母親に絵本を読んでもらった幼い頃のことばの体験が、後の仕事に生かされたことが伝わります。
月刊絵本「こどものとも」刊行の経緯や、絵本作家たちとの思い出なども語られます。
(本の紹介文は、磯子図書館が広報よこはま磯子区版2023年4月に掲載したものです。)
3月
タイトル:海と山のオムレツ
著者名:カルミネ・アバーテ/著、関口 英子/訳
発行者:新潮社
出版年:2020年
うちの雌鶏の卵、オリーブオイル、腸詰め(サルシッチャ)、赤玉葱、パセリをオムレツにして、焼きたてのパンに挟むと、祖母は僕を浜辺へ連れて行った。青空の下、オムレツにかぶりつくと、僕は幸福感に満たされ祖母に微笑んだ。そのすきに、カモメがオムレツをさらっていった――食の記憶は、人と場所に常に結びつく。過去も現在も、多分未来にも。
メニュー形式の章立てで作家の半生を振り返る短編集。
(本の紹介文は、旭図書館が広報よこはまあさひ区版2023年10月に掲載したものです。)
このページへのお問合せ
教育委員会事務局中央図書館企画運営課
電話:045-262-7334
電話:045-262-7334
ファクス:045-262-0052
ページID:461-358-467