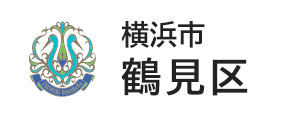ここから本文です。
第1回:幕末の動乱期の外国人殺傷事件・生麦事件(その1)
最終更新日 2024年11月7日
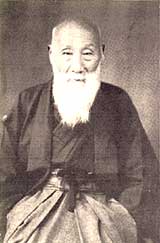
<写真は黒川荘三翁>
1862年、文久2年8月21日、旧東海道の一漁村生麦村で起きた英国人殺傷事件をいまに伝える「生麦事件碑」が横浜市鶴見区生麦一丁目、国道15号線と旧東海道の交流地点、キリンビール横浜工場の一角に建っている。
碑には、事件当時の世情とこの地で非業の死を遂げた英国商人リチャードソンの死を悼む歌が記されている。この碑は、橘樹郡区制の第三大区四小区の副戸長をしていた黒川荘三によって、1885年(明治16年)に建てられたものである。
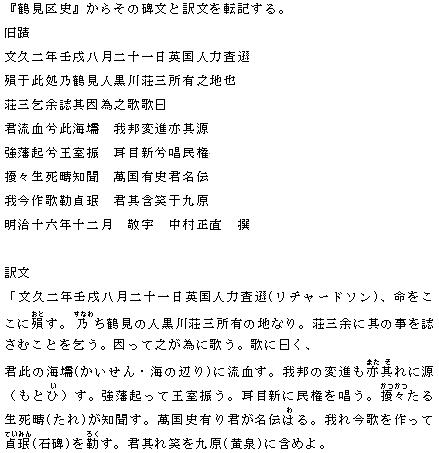
江戸時代に編纂された『新編武蔵風土記稿』に「東海道のかかる海沿いの地で、神奈川、川崎の二宿の間にあって神奈川へ一里、川崎へは一里半はなれており、江戸日本橋から六里の距離にある。子安郷に属し、安養寺の過去帳に、昔は貴志村(岸村とも書く)と称していたとある。また村名の起こりは徳川将軍が江戸入国のとき、生麦を刈り取って道に敷いたということから生麦というようになった」と記されてあるが、江戸時代、生麦は御菜八ヶ浦のひとつとして、江戸の将軍家に魚介類を献上していた。アサリやアカガイもたくさん獲れた。子安では貝の佃煮が名産だった。生麦の漁師たちは貝をむき、貝殻を道に敷いていた。貝の「生むき」から転じて「なまむぎ」になったのではないかとも言われている。白い貝殻が敷き詰められていたので、この辺りの道は貝殻道とも呼ばれていた……。
将軍さまが通るというので、暮らしを支える大事な麦、その麦を実りの前に刈り取って道に敷くほどの素朴な人情にあふれていた生麦。潮風が吹き渡る松並木と白い貝殻の道が続いていたひなびた漁村・生麦が歴史に登場するのは、いまから140年前の1862年のことである。文久2年8月21日の午後2時ごろに起きた薩摩藩による英国人殺傷事件という不幸な事件によって、生麦村の名前は歴史の1ページに記されることになった。

生麦事件之跡
文責「鶴見歴史の会」斉藤美枝
このページへのお問合せ
ページID:854-244-291