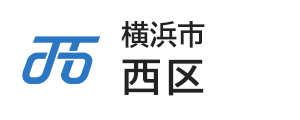ここから本文です。
ビル関連事業者向けノロウイルス情報
最終更新日 2019年3月6日
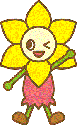
ノロウイルスは感染力が非常に強いため、ビルなどの人が多く集まる大規模施設内では感染が拡大する恐れがあります。
感染を広げないために、予防、拡大防止対策をとることが重要です。
ノロウイルスの基礎知識
【主な症状】吐き気、嘔吐、下痢
【発生時期】年間を通じて発生していますが、特に冬季に多いことが知られています。
【感染経路】ノロウイルスに感染した人の嘔吐物や糞便から感染が広がります。
施設内で嘔吐等があった際には
嘔吐物等には大量のノロウイルスが含まれています。嘔吐等があった際、ふき取りや消毒が徹底されていないと、乾燥した後ウイルスが空中を漂い、
口や鼻から人体に入り発症することがあります。施設内で嘔吐等があった場合は、ノロウイルス感染の可能性を考え適切な処理をする必要があります。
★嘔吐物処理方法★
【消毒薬の作り方】
アルコールはノロウイルスの消毒には効果がほとんどありません。 必ず、塩素系漂白剤(成分:次亜塩素酸ナトリウム)を使用します。
市販の塩素系漂白剤を用途に応じて希釈して用います。
| 希釈濃度 | 原液濃度 | 希釈 | 方法 | 使用する場所 |
|---|---|---|---|---|
0.1% | 1% | 10倍 | 原液10ml+水100ml | 嘔吐物や便が直接ついた場所・衣類 |
5% | 50倍 | 原液10ml+水500ml | ||
6% | 60倍 | 原液10ml+水600ml | ||
0.02% | 1% | 50倍 | 原液10ml+水500ml | 調理器具、床、トイレドアノブ、便座など (日常の清掃消毒に使用する場合) |
5% | 250倍 | 原液10ml+水2.5ℓ | ||
6% | 300倍 | 原液10ml+水3ℓ |
※消毒効果を保つため、原液は遮光のできる場所に保管してください。
※希釈した消毒液は、時間とともに消毒効果がなくなります。作り置きはせず、消毒時にその都度作成してください
【作業方法】
チラシはこちら→嘔吐物の処理、消毒方法(PDF:322KB)
動画はこちら→実践で学ぶ嘔吐物処理 - YouTube(外部サイト)(保土ケ谷区作成)
★換気、空調設備の管理★
嘔吐等があった際には、ウイルスが室内に滞留することがないよう換気を行います。大きく窓を開ける、換気設備を運転させるなどして新鮮な空気を取り入れるよう心がけます。
また、被害が拡大の原因となる可能性が高い場所(トイレ等)についても換気設備を運転させ空気の入れ替えを行います。
【有効な換気をするために】
1 室内の空気の流れをスムーズにするために、空気の入口と出口をできるだけ対角に2か所以上作りましょう。
(換気扇を使用する場合は、空気の入り口を作るため、なるべく換気扇から対角に近い場所に位置する窓を少し開けて運転しましょう。)
2 換気設備が有効に運転できる状態か定期的に点検を行いましょう。
(排気口のフィルターが目詰まりしていないか、排気口が塞いだり、空気の流れを阻害したりする障害物がないかなどを確認しましょう。)
3 平常時から換気時の空気の流れを確認しておきましょう。
感染拡大を防ぐためには
★嘔吐物等の処理情報を共有する★
嘔吐物等の処理があった際は、清掃担当者やテナントだけでなく、施設の所有者や管理者に連絡し、施設全体で情報を共有しましょう。
情報共有をすることで、施設内で感染があった際、原因が特定しやすくなります。原因特定が迅速にできると、感染拡大を防ぐための措置を早期に講じることができます。
★従業員への衛生教育★
清掃担当者やテナント担当者に対して、嘔吐物等の処理方法やノロウイルスの流行情報などについて周知を徹底しましょう。
(衛生講習会を開催する、嘔吐等発生時のマニュアルを作成し配布する、など)
現在の感染症流行情報などについては横浜市衛生研究所 感染症情報センターをご参照ください。
横浜市感染症情報センター(横浜市衛生研究所:横浜市感染症情報センター)
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
ページID:647-855-832