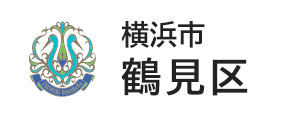ここから本文です。
第9回:100年以上も前にあった鶴見川バイパス計画(その2)
最終更新日 2024年11月7日
鶴見川を神奈川にバイパスする計画があった
1.天保の計画
1830年代に洪水の続く鶴見川を改善するために、幕府が計画したもので、詳細は不明。
「白幡村の農民が出した反対嘆願書や綱島池谷家に残る地図や資料により推測」(『港北百話』p221)すると、分水路は小机東部の大曲付近より篠原小谷口、白幡村の中程を通り、西子安村方面に抜けるルートだったようだ。「天保度新川掘割目論見測量手扣帖」という表紙だけが残っている。
2.明治3年の計画
明治になってから、南綱島と太尾の村民から「鶴見川通新川目見建白書」が神奈川県に提出されている。
池谷家に残る計画図では新川を作り、新川分岐点から太尾橋までは廃川し、農地に転用する計画だ。新川ルートは、「現在ある亀甲橋の少し下流から篠原坊ヶ谷、篠原池、六角橋溜池を通り神奈川宿の瀧の橋に至るもの」(『港北百話』p222)で、延長30町余(約3.3キロメートル)幅員10間(約18メートル)であった。太尾橋より下流を「鶴見川」とし、鶴見川本流の上流部を含めた新川の名称を「神奈川」とする二つの河川に分離してしまう案だ。
計画によれば、新川建設用地には6町歩(18,000坪)の土地を要するが、新たに田畑となる土地が新川分岐点から太尾橋までの間に21町6反歩(64,800坪)生まれるとの損得勘定である。
このほか、洪水での農民の悩みを軽減するだけではなく、公費での河川改修、自普請(農民が自力で行う工事)の減少が見込まれるほか、従来鳥山川から用水を取っていた右岸の大豆戸ほか数ヶ村は、新羽用水からの分水が可能になる。さらに、1730年の瀬達以降、堤外地(堤の水流に面した側の土地)へは竹木植えが禁じられていたが、維新以来桑の植え付けが奨励されており、植え付場所がなく困っているが、新川により余地が生まれる。また、下肥の運送にも便利であるし、海岸埋め立て用の土が新川で発生するなど、一石二鳥の内容である。しかし、県の処置は不明のまま、立ち消えになった。
3.明治20年の計画
中下流の村々からの願いを受けて、後に新田村村長となる笈川新兵衛は分水路計画の実現に尽力した。計画は「小机東部の大曲付近から鳥山の飛地を通り、篠原、六角橋を経て神奈川飯田横町の小川(現在の滝の川)へと行く経路(『港北百話』p224)で鶴見川をバイパスするものであった。
分水路は幅員8間(約14.5メートル)、深さ5尺(約1.5メートル)、総延長1里10町(約5キロメートル)の規模で、洪水の被害を減らすとともに、収量の低い田である下田の多い分水路周辺の水田を上田に変えることができるとしている。また、既存の鶴見川の流路を拡げ、堤防を強固にするには大幅な土地供出を要するため。かえって分水路を造った方が損得勘定からも得策としている。工事・用地費約22,245円を見積もり、明治20年に神奈川県知事に提案した。測量や設計まで進めつつあったこの計画も明治36年の笈川新兵衛の死により、後を継ぐ人もなく立ち消えとなってしまった。
むすび
新横浜の多目的遊水地と「小机千若雨水幹線」は、何百年も苦しんできた先人たちの苦労を、ようやく国、県、市などの行政側で受け止めて、過剰とも思える施設を実現してくれている。
先人の跡を学び、発想を変えること以外に、悩みから脱出できないことを私たちに教えてくれる。
参考文献
『鶴見川誌』竹内治利・編(神奈川文庫・1970年)
『港北百話』港北区老人クラブ連合会(1976年)
『鶴見川歴史散歩』瀬田秀人・編(横浜230CLUB新聞社・1998年)
『明日の利根川』山崎不二夫・編(農山漁村文化協会・1986年)
文責・サトウマコト
(鶴見歴史の会運営委員)
このページへのお問合せ
ページID:164-331-098