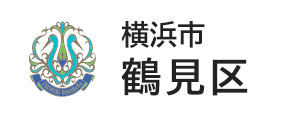ここから本文です。
第9回:100年以上も前にあった鶴見川バイパス計画(その1)
最終更新日 2024年11月7日
鶴見川と神奈川区
町田市に源を発する鶴見川は、青葉区、緑区、都筑区、港北区を通り、鶴見区で東京湾に注いでいる。一見、無関係に見える鶴見川と神奈川区が、実は知られざる縁があった。
鶴見川の治水安全度が上がった!
横浜市は10年の歳月をかけて、全長約7.9メートル、内径3.5~8.5メートルに及ぶ地下巨大トンネル「小机千若雨水幹線」を1996年に完成させた。60ミリの雨量が鶴見川流域にあった際、その一部の雨水を取り込んで地下に貯水するとともに、徐々にポンプアップして海に流すという鶴見川安全装置のひとつである。東神奈川駅から約5分の神奈川下水処理場にその出口がある。

また、現在、横浜国際総合競技場の一帯(約84万平方メートル)に、豪雨の際に雨水と鶴見川の水を一時的に貯めておくための「鶴見川多目的遊水地」を建設中である。総貯水容量39億リットルの水を貯えるので、鶴見川多目的遊水地にある建物は土台が高くなっており、水を貯められる構造にしてある。洪水が収まると、排水門から鶴見川に徐々に流す仕組みである。この事業は国土交通省により進められている。
昔から鶴見川は暴れ川で有名だった。最近までコンクリート固めの堤防と川ざらいで何とか対応してきたが、都市化率80%以上になり、雨が降るとほぼ全量が下水管から鶴見川に流れ込み、アッという間に水位が2メートルぐらい上がってしまう程の状況になってしまった。そこで、大きな池と地下の巨大パイプに一時的に水を貯めることが検討され、ようやく実現へと向かいつつあるわけである。
歴史をひもとくと、洪水で苦しんだ農民は、鶴見川の水を小机から岸根、六角橋を経由して神奈川の海へ流すことを考え、何回も建白してきたのであった。その歴史を振り返ってみたい。
洪水に悩まされ続けた川沿いの村々
鶴見川は、太尾橋から河口までの中下流都の高低差が少なく、日々潮が満干するので舟運に恵まれ、真水と海水の交わる下流部は漁にも恵まれていた。しかし、潮のため、川の水を農業用水に使用できず、右岸は谷戸に溜池をつくり、左岸は多摩川の水を二ヶ領用水として潮田、小田、渡田まで網の目のように配して、米作りをしていた。洪水が肥沃な土地を作り、果樹、野菜の産出にも恵まれていた。
その反面、洪水により大切な稲が冠水してしまい、年貢減免願の連続であった。昔から「太尾には嫁にやるな」と言い伝えがあったほどである。農家の納屋に平底舟が吊り下げられていたのは、つい最近までの話である。
水と川に恵まれぬ神奈川の村々
神奈川の村々は、山坂が多く、大地の上は水がないため田畑には不向きで、滝の川、入江川沿いのごく狭い地域でしか農業を営めなかった。
川の利用法については、瀬違(流れの経路を変更するもの)、分水路、用水などの様々な方式が早くより考案、実践されてきていたのだが、情報見聞の機会の少ない農民にとって、後述する新川や分水路計画は迷惑以外の何者でもなかったようで、鶴見川の水が分水嶺である岸根の丘を越えて流れることなく、今日に至っている。
このページへのお問合せ
ページID:138-254-169