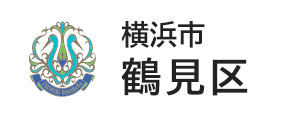ここから本文です。
第7回:シーボルトと熊茶屋(その1)
最終更新日 2024年11月7日
関口日記に見る熊茶屋の顛末
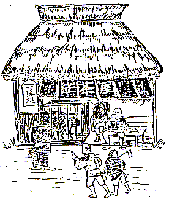
東海道生麦村の街道沿いには立場茶屋が軒を並べていたが、どの茶屋もあれこれ工夫を凝らし、客寄せに懸命であったようすがうかがわれる。文化・文政のころ、鶴見と生麦の境、生麦北町に、月の輪熊を飼いならし、店先につないで見せ物にしていた熊茶屋五右衛門の茶屋があった。この茶屋では、文化7年頃から飼っていた牝熊が芸達者だったので、人気を呼び繁昌していた。その後、文政7年ごろからやはり生麦の忠左衛門方で白熊(白子)を飼い始め、店の客寄せに利用しはじめた。
ちょうどそのころ、文政9年(1826年)、長崎のオランダ商館長に従って江戸に出たシーボルト(1796~1866年、ドイツ人、医師)は、その往復の道で、生麦のこの2頭の熊を見て、その著「江戸参府気候」に熊茶屋の熊について次のように記している。
「1826年(文政9年)4月9日、一頭のよく慣れた熊を見る。頭は小さくてとがり、頭のてっぺんにそって深く溝があり、鼻づらは短く、先が細くなっていてその両側は茶色味を帯びていた。この動物は長さ4フィート、無格好に太り、18才で捕らえられて17年経つ。よく慣れていていろいろな芸をした」
その後、シーボルトはオランダに帰国したが、1833年に発行された「日本動物誌」に、日本で見聞した動物について紹介し、その中で生麦村で見た熊のことを詳細に報告している。これは日本の「熊」について海外に紹介した最初であるといわれる。以下少し長文にわたるが、その一部を抜粋して記すことにする。
「日本動物誌」シーボルト著
「チベット熊(学名:ラルスース、チペタヌス)
この種類の熊は、インドの山地にごく一般に棲息しており、中国にもいるが、日本にもたくさん棲んでいる。日本では、クマまたはツキンシバ・クマ-三日月状の斑点をもつ熊(月の輪熊)の意である、-と呼ばれている。この熊は、この列島のそれぞれの島の山地一帯に広く棲息している。その習性はヨーロッパ種の熊の習性とほとんど同じである。すなわち、木に登り、冬季は自分の掘った穴の中に引きこもる。食料とするのは、果実、木の根等、植物性のものがもっとも普通である。これを捕らえたときには、さつまいも、煮た米その他の穀類あるいは澱粉質の果実などを与える。檻に入れられ、あるいは鎖につながれている若い熊がしばしば見られるが、これらは3~4才まではおとなしく扱いやすい。しかし、この時期を過ぎると、どう猛になり、手放さざるを得なくなる。日本の興行師はこれらの熊に芸をしこみ、人びとの集まる場所で見世物に供する。
シーボルト氏は、この国の首都を訪問したおりに、江戸から数里、川崎にほど近い生麦村で、18年前に捕らえられたというこの種類の熊を見た。その体長は1メートル30センチほどでいくつかの芸ができた。シーボルト氏はまた、江戸で(生麦の誤り)全身が真っ白な熊を見た。それは日本の北部で捕らえられた白子であった。この熊には、そら豆の莢その他が餌として与えられていた。日本人はこの熊の肉をひじょうに珍重し、皮は輸出する。脂肪はさまざまに利用され、高く売られる。肝は薬用に供される。
博物館に、比較に用いることのできるインド産のウルスース、チベタヌス(チベット熊)の個体がないので、日本のこの熊がインドの熊と全く同種であると断定することはできない。しかし、日本のこの熊の見事な2枚の皮とその頭蓋を見た限りでは、インドのチベタヌス(チベット熊)に関して描写されているところとの間に違いはまったく見られない。この対比較によれば、両者が同一種であることには、まったく疑問の余地がないとわれわれの目には見えた。」(大久保昭男氏翻訳)
このページへのお問合せ
ページID:371-661-549