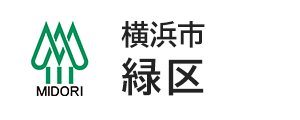ここから本文です。
地名の由来
最終更新日 2025年7月4日
原則として、横浜市市民局総務部住居表示課(現・市民局窓口サービス課)が平成8年12月に発行した「横浜の町名」を転載しています。
発行時から歳月が経ち、現状にそぐわない箇所もありますが、著作権の関係で本文は発行当時のものになっています。あらかじめご了承ください。
緑区は、昭和44年10月1日の行政区再編成により港北区を分割して新設したが、平成6年11月6日の行政区再編成により、一部の地域を青葉区・都筑区とし、現在の区域となった。区名は、一般の公募で、緑区・北区・川和区・都筑区・青葉区等の中から選定して、緑を美しく保存したいという願いを込めて決定した。横浜市の北西部に位置し、鶴見川と、その支流の恩田川に沿うように、東西に細長い地形となっている。緑区の中央部に近い三保・新治地区の樹林地は、横浜市内でも最大規模である。山林や公園の緑、農地などが緑区の面積に占める割合(緑被率)は、およそ52パーセントで、18区内中、第一位である。江戸時代に大山街道や中原街道、八王子街道が通じたが、区域全体としては農業地帯であった。明治41年に横浜鉄道(現横浜線)、昭和41年に東急田園都市線が開通した。昭和30年代から区画整理事業や公的団地開発が活発となり横浜線4駅を中心に住宅地が広がり、市街化が進んだ。緑区は、「こもれび踊るふれあいのまち 豊かな自然に恵まれ、いきいきと暮らし集えるまち」をまちづくりの目標として掲げている。そして、区内の緑や水といった自然の資源を生かした拠点を回廊で結ぶ「緑と水の回廊構想」を進めている。緑区の町名は、北八朔町、西八朔町、十日市場町など古くからの歴史的な町名に因むものが多い。また、土地区画整理事業の施行により、新しく設けた町には、霧が丘、竹山のように「丘」や「山」のつく町名やいぶき野のように植物に因む町名を付けている。緑区の町で、面積が一番広いのは長津田町(4.305平方キロメートル)で、面積が一番狭いのは竹山三丁目(0.094平方キロメートル)である。
西部
中部
東部
このページへのお問合せ
ページID:123-820-310