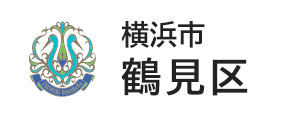ここから本文です。
第8回:なぞに包まれた中世の寺尾城(その2)
最終更新日 2024年11月7日
馬場稲荷社(寺尾稲荷)
寺尾城址の西山麓に寺尾稲荷が祀られている。現在は地名が馬場になったことから馬場稲荷と呼ばれているが、古くは寺尾稲荷と呼ばれていた。江戸時代には馬術上達がかなえられる稲荷として有名になり、江戸からの参詣者も多かった。それを物語る奉納絵馬・石碑類が多数残されている。正一位相国稲荷の位をもつこの寺尾稲荷は、『新編武蔵風土記稿』の「馬場村稲荷社」に、「正一位相国稲荷と号す。相国の文字いかなる故と云ことを知らず。馬術を学ぶ人当社に祈誓して大いに感応ある由。いづれの頃か紀伊殿厩を預かれるもの信仰して相国の号を与へしと云・・・・」とあり、江戸時代に紀州藩や江戸城の馬回り役から信仰されていたことを裏付けている。旧東海道鶴見村の東海道との分岐点(現鶴見図書館前)にある「寺尾稲荷道」の道標は3度も建て替えられている。
この寺尾稲荷が有名になったのは、寺尾城主諏訪右馬之助にまつわる伝説による。
昭和5年に刊行された『鶴見興隆誌』には、「ここはむかし寺尾城主諏訪右馬之助が馬場を設けた因縁の地。右馬之助は生来馬術が下手であった。一城の主として馬術が下手では千軍万馬のなかをかけめぐって、武勇をたてることはむずかしい。そこで城下の稲荷社に馬術上達の祈願をかけた。ある夜、夢に一人の老翁があらわれ、「われは、そなたが念願に及ぶ寺尾稲荷である。日ごろの熱心なそなたの願いに感じ、いまより馬術上達の加護を与えるであろう」といって消えた。右馬之助の喜びは大変なもので、まもなく馬術は練達し、北条氏康きかの十勇士の中に名を連ねるほか、相模衆の一家に加えられるまでになったという。それ以来、だれ言うともなく、寺尾城主諏訪右馬之助の馬術上達祈願の昔話が、ありがたや、ありがたやと広められ、武家の馬上安全、馬術上達の祈願をこめる者あとを絶たず・・・・」とある。第二次大戦中も輜重兵たちが武運長久を願って参詣に訪れていたという。
諏訪氏及び寺尾の名は武蔵各地に存在している。『新編武蔵風土記稿』の「入間郡寺尾村」には、「村内に諏訪馬之助居城せしなりと云へり。北条役帳に二百貫文寺尾諏訪三河守とあり、また小田原記に武州寺尾の住人諏訪馬之助とあり。されば彼諏訪当時この地を領せしこと知るべし。されど橘樹郡の支郷馬場村にも諏訪三河守が居城の跡ありて、彼人の馬場の旧跡なりといふ。また同郡西寺尾村建功寺の旧記に『村内白幡明神は永享七年寺尾の城主諏訪勧請す』とあり。また秩父郡寺尾村にも諏訪の旧跡ありといふ。諏訪が城跡四ヶ所まで寺尾と号するのも奇というべし」とある。
鶴見歴史の会では、入間郡の寺尾城跡も訪れ、検証を重ねたが、未だその関係を明らかにする資料にめぐりあっていない。
寺尾城の没落
永禄12年(1569年)10月、武田信玄は北条氏康が駿河の今川方へ加勢に出たあと守りが手薄になった小田原城の虚をついた。武田軍は碓氷峠を越え、江戸の葛西に入り、池上(東京都大田区)から平間(川崎市)を通り、稲毛十六郷を荒らし、鶴見・寺尾から片倉、神大寺(神奈川区)を筋違いに惟子(保土ケ谷区)に出て藤沢に進軍し、小田原城を攻撃した。武田軍が鶴見を通過したとき、寺尾城主諏訪右馬之助は駿河軍加勢のため小田原に招集されていた。城主不在の寺尾城にはわずかな兵しかいなかった。戦う威力のないのを見越した武田軍は、「城を焼かずに通り過ぎた」と、『北条記』には記されている。
前述の享保16年(1731年)に記録された建功寺『霊簿』には、「五代目馬之丞の時、天正三年(1575年)に諏訪発落」とある。永禄12年(1569年)から天正3年(1575年)までは6年の隔たりがあるが、武田軍通過後に寺尾城主諏訪右馬之助が寺尾城に戻ったという記録はない。城主不在のまま、寺尾の城も諏訪の館も朽ち果てていったと推察されている。
馬場一丁目にある曹洞宗建功寺は寺尾城主諏訪右馬之助の開基と言われている。建功寺の寺紋は諏訪氏の紋である諏訪梶である。
『横浜市史稿』によれば、建功寺について「相州愛甲郡東富岡村(現在の伊勢原市東富岡)の竜散寺の僧守聞和尚が当地に巡錫し、寺尾城主諏訪右馬之助の帰依を得、その外護によって一宇を建立した。これが当寺である」とあるが、建功寺『霊簿』に一部諏訪氏の記録が記されている以外、菩提寺としての記載はない。

数年前、鶴見区内に唯一残されていた戦国時代の遺構である堀、土塁、曲輪跡などの発掘調査が行なわれ、現在、その一部が殿山公園として整備され、地域の人々の憩いの場になっている。
参考文献『建功寺誌』『寺尾城百話』
文責:四元宏・齋藤美枝
このページへのお問合せ
ページID:205-224-554