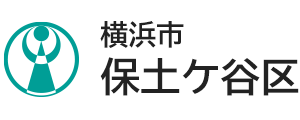ここから本文です。
幼児期の食生活
最終更新日 2025年7月4日
幼児期の食生活~楽しく食べる子どもに~
「食」は、子どもの健やかなこころとからだの発達に欠かせない大切なものです。こころもからだも元気に育てるため、バランスのとれた栄養素の摂取だけでなく、食事は楽しく、家族揃っての食卓を大切にしましょう。
よくある悩み(子どもの食事で困っていること)から
好き嫌いなく食べるための工夫
味覚が発達し、微妙な味の違いがわかり、好みが出てきたり、意思表示ができるようになると、急に今まで食べていたものを食べなくなることもありますが、子どもの好き嫌いは一過性のことが多いです。食事の基本は、からだを動かしてお腹がすいた状態で食事を迎えること、そして大人も一緒に食卓を囲み、楽しい雰囲気で食べることが大切です。
1.生活リズムをつけよう
偏食の予防にはおなかをすかせ、食卓につくことができるように、遊び、食事、睡眠などのリズムを整えることが大切です。
2.無理強いしないように
子どもにとって嫌いなものは味だけではなく、においや食感などさまざまな要因が考えられます。無理強いするとかえって食べなくなることもあるので、無理強いはせず、調理法を変えてみるなどの工夫をしてみましょう。
3.食べられたらたくさんほめよう
嫌いなものを細かく刻んだり、すりおろしたりして、料理に混ぜ込むだけでなく、旨味のある食材と一緒に調理したり、汁気の多い料理にしたりすると多少食べやすくなります。食べられたら褒めてあげると自信になり、食べる力を育てます。
4.大人が美味しそうにに食べて見せよう
家族が美味しそうにに食べている姿を見て、いつの間にか嫌いなものでも食べてくれることがあります。あせらずに見守り、根気よく励ましましょう。
5.いつもと違う盛り付け、雰囲気で楽しく食べよう
お弁当に入れたり、庭で食べてみたり…。苦手なものも好奇心を刺激して。産地見学に行ったり、栽培や調理に挑戦したり、それまでとは違う目で食材を見ることができる機会をつくり、興味を持たせましょう。
6.お子さんと一緒に「食」を楽しむ
食事は味だけでなく目でも食べると言われています。季節の味を取り入れて、材料に変化をつけたり、切り方も花形や動物に切ってみたり、そして時には食器も変えてみましょう。
7.調理の工夫を
にんじん
目先を変える(花型や星型など型抜きして)
ピーマンや玉ねぎなど
細かく刻んでオムレツやチャーハンに
トマト
皮をむいて食べやすく
煮込み料理に使用など
おにぎり

卵で巻いて

そぼろをまぶして

普通のおにぎりも醤油を付けて焼くだけでおいしくなります!
嫌いなものをおいしく食べる工夫
| 食品名 | 調理法 |
|---|---|
|
冷たくして |
魚 |
茹でてほぐして |
|
挽肉にして |
野菜 |
おろしや、みじん切り |
穀類 |
調理法を変えて (おにぎり、炒めご飯、丼物、むしパン、お好み焼、煮込みうどん、スパゲティミートソース) |
少食・食欲不振の時は
お子さんの体重や身長が伸び、元気であれば心配ありませんが、
気になるときには、原因を考えてみましょう。
こんなことはありませんか?

- 夜更かし等で、生活のリズムが乱れている。
- 食事やおやつ、甘い飲み物を不規則に与えている。
- 体を動かすことや、外遊びが少ない。
- 食事の無理強いをしている。
- テレビをつけながら食事をしている。
- 子どもだけで食べている。
栄養のバランスを考え、できるだけ食べやすいメニューを用意しましょう。
食べきれる量を与え、自信を持たせましょう。
外で元気に遊びましょう。
家族と一緒に食べましょう。ひとりぼっちでは食事も進みません。一緒に食事を楽しみましょう。
遊び食べ・むら食いについて

遊び食べは好奇心の現れの一つ、無理に妨げず、こんな事に注意して、楽しい食事の雰囲気をつくりましょう。
- 食事に集中させる雰囲気をつくりましょう。
- テレビは消し、おもちゃは片付けましょう。
- だらだら食いはやめ、30分程度で切り上げましょう。
- 食前に、飲み物などを与えないようにしましょう。
かむことがうまくいかない時は
1歳6か月頃の消化吸収について
奥歯で食べ物をかみつぶせるようになりますが、歯は生えそろっていませんし、消化能力も発育途上です。ご飯はやわらかめに、野菜などは一口大に切ってやわらかく煮たり、かみやすい形にしてあげましょう。
その半面、いままでとは異なった大きさや固さの食べ物へ少しずつ挑戦することが成長を促します。
こんな配慮をしてみましょう
- 口の中に入れる量を少量にして、食べきってから次に入れるようにしましょう。
- テーブルの上に水を置いて流し込む習慣をつけないようにしましょう。
- 子どもが一人だけで食事をすることがないよう、大人も一緒にお手本を見せてあげながら、食事をしましょう。

おやつについて
おやつも小さな食事です
まだ胃の小さな幼児にとって、おやつは食事の一部です。お昼・夕方の食事までは2時間以上あけ、次の食事に影響がないようにしましょう。
- エネルギーが高く、糖分や塩分の多いものはなるべく控えましょう。
- 菓子類だけでなく、甘い飲み物(ジュース類、乳酸菌飲料、スポーツドリンク等)も食事に影響を与えます。のどがかわいたら水やお茶類をあげましょう。
- 牛乳・果物などいろいろ組み合わせてあげましょう。
- 「栄養の補給」「水分の補給」「食べる楽しみ」とおやつの持つ役割は大切です。ただし、夕食後におやつをとることが習慣化している場合には改めましょう。
おやつの与え方も大切
子どもに与えるおやつをものごとの駆け引きに使ったり、お菓子でごまかしたりすることはやめましょう。
おやつは子どもにとっては小さな食事です。きちんとテーブルについて食べる習慣をつけましょう。
おやつは楽しい心の栄養
手づくりすることは楽しい時間です。手軽に混ぜるだけ、焼くだけの半加工品を使えばお手伝いもしたくなります。おやつをつくること、食べることはリラックスする時間でもあります。楽しく食べて大人も心にゆとりを持ちましょう。
おやつが多くなっていませんか?
食事をとらないからといって、次の食事まで待てずにおやつを食べていませんか?
子どもがおやつを欲しがって困るという方は次の点に注意しましょう。
- 時間を決めてあげましょう。
- 冷蔵庫にジュースやアイスの買い置きはしないようにしましょう。
- おやつのある場所の管理は大人がしましょう。
- 牛乳、果物、イオン飲料のとりすぎには気をつけましょう。
- 甘いお菓子ではなくおにぎりなどの食事をあげましょう。


このページへのお問合せ
保土ケ谷区福祉保健課健康づくり係
電話:045-334-6344
電話:045-334-6344
ファクス:045-333-6309
メールアドレス:ho-kenkou@city.yokohama.lg.jp
ページID:688-895-844